HSPという概念①
わざと悪い言い方をすると、昨今「ブーム」になっているのがHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン/Highly Sensitive Person)です。
視覚や聴覚などの感覚が敏感で、刺激を受けやすくそれにより社会的な困りごとを抱えている人達のことを指します。
アメリカの臨床心理学者エレイン・N・アーロンが1996年に出版した本の中で初めてこの言葉を使用しました。
日本では「繊細さん」と呼ばれることも多く、近年は様々な書籍が発売され、発達障害と結びついて有名な言葉になっています。
しかしながらHSPという単語は、精神医学や心理学の検証を受ける前に有名になってしまったきらいがあります(ちなみにアーロン氏は心理学者です)。
例えば最新のHSPに関する論文をCiNiiで調べてもなかなか出てきません。HSPの検索でひっかかる論文のほとんどがHeat Shock Protein(熱ショックタンパク質)についてのものです。

最新の論文は「HSPと発達障害は区別可能なのか?」という熊本大学教育学部紀要の論文になります。リンクはこちら。
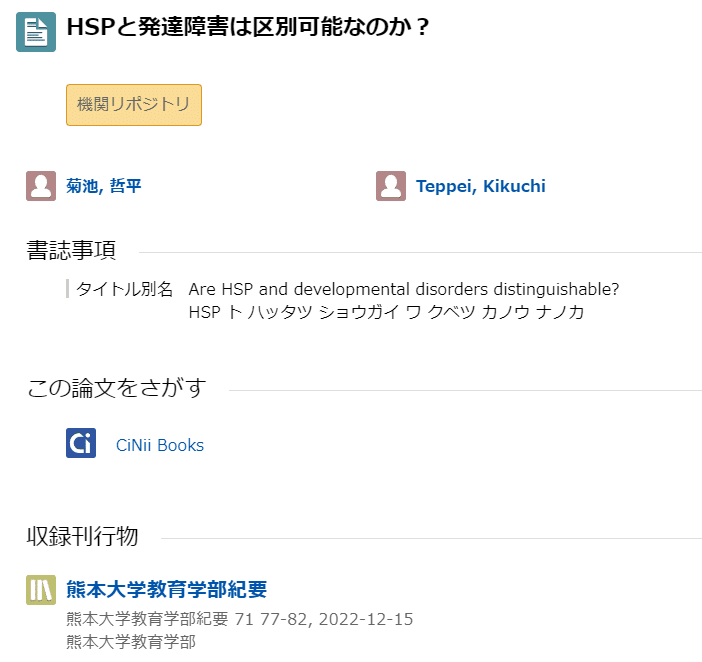
論文的にはこのような段階ですね。
金子書房から"HSPの心理学 : 科学的根拠 (エビデンス) から理解する「繊細さ」と「生きづらさ」"という書籍が出ていますが、こちらも一般書です。
このように学問的検証を十分受けないまま有名になってしまったHSPですが、学問的検証を受けていないからといって現実に困っている人がそこにはいるわけなので、当方でもクライエントからそういう主張があったら対応しないわけにはいかないです。
少し腰を落ち着けていろいろ考えるためにも、記事にしてまとめていこうと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
