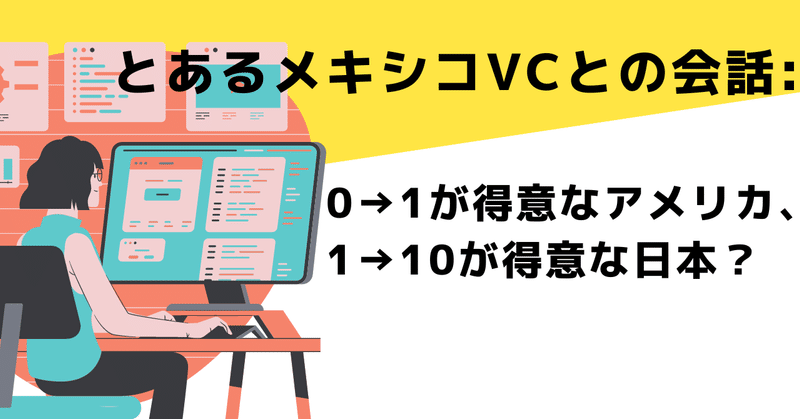
0→1が得意なアメリカ、1→10が得意な日本?とあるメキシコVCとの会話
注)本記事はJICAの公式見解ではなく、専門家個人の見解、所管です
先日、とあるメキシコのベンチャーキャピタル(VC)と話していて、興味深いディスカッションになりました。VCいわく、
「メキシコでは、結構皆すぐに事業を始めるので、スタートアップは多いように思う(質はおいといて)。だけど、スケールアップの段階になると行き詰まり、組織を大きくできないところが多い」
「アメリカは0→1が得意なように思う。我々もどちららかと言うとそうだ。日本は1→10が得意なように思う。トヨタがやっているカイゼンなんかはまさにそうなんじゃないか。日本はその観点でスタートアップへの教育支援なんかをやれると面白いんじゃないか。」
創業者(起業家)と経営者には全く違う素質が求められる?
創業者(0→1をやるひと)と経営者(1→10をやるひと)には全く違う素質が求められる、というのはよく言われる話です。例えば、グーグルは、創業者(ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリン)が0→1をやった後にプロ経営者のエリック・シュミットを呼んで1→10をやった、とみることができます。
が、国や文化ごとの特性を考えたことはあまりなかったので、ちょっと面白いなあと思いました。
確かに、アメリカでは、何か新しいチャレンジをすることが推奨される雰囲気がありそうだし、「とりあえずやってみよう!」という人が多い気がします。一方で、日本は今あるモノを少しずつ改善するのが得意な気がします。日本は、既存のモノを少しずつ改善して極限までクオリティを高めるのが得意です。
住み分けの話:どっちがいい悪いという話ではない
どっちがいい悪いという話ではないと思います。特性の問題で、スタートアップが0から10、さらに100になるには両方必要です。
日本においては、0→1をやれる人がイノベーターだ!と言われがちな気がしますが、0→1をやれる人は癖が強かったり、独創的すぎたり、自信家すぎたりして、大勢を率いて会社を大きくすることが難しい場合もあります。(もちろん、両方やれる場合も多々ある。FacebookのザッカーバーグやAmazonのベゾス、テスラのイーロン・マスクなどは、両方自分でやった人達でしょう)
少しずつの改善、例えば毎日1%の改善を毎日続けると、1年後には40倍近くの改善が得られる、というのはよく言われることです。(1.01の365乗)
逆に、自信家で自己肯定感が高すぎるようだと、0→1はできるけど1→10ができなかったりします。少しずつの改善は、少なからず自己否定(今日はここがいけなかったよね、今日はここをもっと改善できたよね、etc)を含むので、それができないからです。
だからスタートアップはオモシロい
こんな風に、いろんな特性を持った人が関わって、世の中の流れとともに成長する可能性があるのがスタートアップで、総合格闘技的な感覚があるなあと思っています。
真面目な人も必要、おちゃらけた人も必要、大胆な人も必要、細かい人も必要。
だからスタートアップはおもろいなあなんて思っています。
更にメキシコは、中南米中から人が集まってきたり、アメリカからも投資が来たりと、多様性の宝庫な感じでもあるので、これからのスタートアップシーンに期待です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
