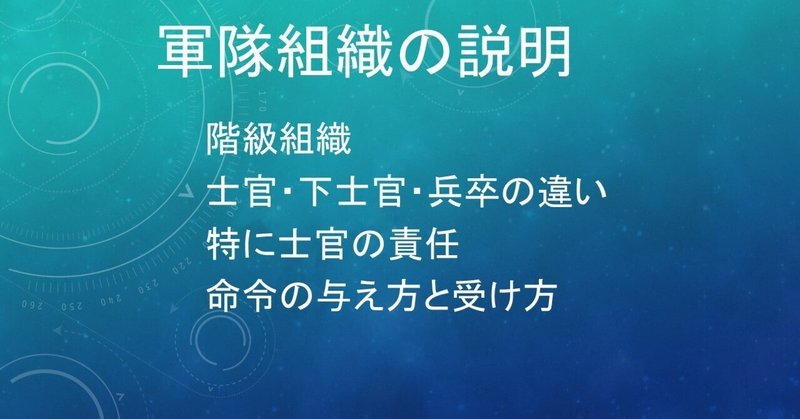
軍隊組織の説明
組織について議論するとき、一つの極端例として、軍隊組織を知っていると、色々と見通しがよくなります。特に欧米の組織論を学ぶときには、軍隊の基礎知識が必要です。

階級の必要性
まず軍隊には、階級があります。大きく分けると以下のようになります。
将官:大将・中将・少将 軍や師団・大隊の指揮
佐官:大佐・中佐・少佐 大隊の指揮
尉官:大尉・中尉・少尉 中隊から小隊の指揮
ここまでが士官
軍曹 分隊の指揮
伍長
ここまでが下士官
兵卒:上等兵・一等兵・二等兵
このような階級がありますが、その中でも
先任者優位
と言う原則もあります。
なぜこのように、序列にこだわるかというと
戦場では指揮系統を統一
の必要があるからです。付け加えると
戦場ではいつ誰が死ぬか解らない
指揮官死亡や負傷で指揮不能になれば
速やかに交代要員が立つ
必要があります。そこで混乱を起こさないように
優先順位を階級で決め
同じなら先に任官者を優先
という原則を決めています。
士官の責任
少尉より上の士官(将校ともいう)は、上位者の命令に対して反論したり、意見具申できます。しかし反論の場合には、代替え案を出す責任があります。なお、決定した命令に対しては
命令の前提条件が変化しない限り服従
する義務があります。なお、情勢の変化時には、上位者の指示を仰いで、適宜対応するのが原則ですが、連絡が取れない場合には、各自の判断で行動する責任があります。
士官には、大局的な視野で、総合的な判断を行う、訓練がされています。従って、上位者がいなくても自分の判断で行動する責任があります。
下士官の立場
下士官は、現場の指揮監督を行います。現状の任務遂行に対する意見具申と、現状対応での臨機処置が出来ますが、それ以上は求められていません。
アメリカのマスメディアが、日本の某首相を
K軍曹
と読んだのは
判断なし・意見無しのレベル
と揶揄ったのです。
兵卒の立場
ここでは、命令(号令)に従って、動くことだけが求められています。
命令の与え方
命令を与える場合には、以下の項目を明確にして指示します。
・ 背景となる状況認識
・ 行動方針(必要に応じてその行動の重要性の説明)
・ 活動の報告時期
・ 優先処理事項
・ 基本態度
・ 注意事項
なお、命令を出すときの一般原則は以下のとおりです。
(1)指揮官が実行できないことは命令しない、計画できないことは計画しない
(2)形容詞・副詞は使わない 例) 速やかに× → 何日の何時までに○
(3)後から出た命令は、前の命令を自動的に取り消す
(4)命令を受けるのは人間であると配慮する、また協力を受ける部隊にも配慮する
(5)完全な情報を求めて、決断時期を逃さず、欲しい情報の 1/4 で決断する
(6)大胆な案は、「最悪に対する代替と予備がある」ものである
以下は、特に士官レベルの命令の受け方対応の確認事項です。
(7)背景になる状況認識を伝える、この状況認識が間違っていた場合には、臨機応変に 対応することが必要で、そのために士官の階級がある
(8)戦力と時間・空間に過不足ないか検討し、指揮官に対して正しく取引の出来ない部 下は、指揮官として使ってはならない
注)勝利に自信のない命令を引き受けることは、勝利に自信のない命令を発することと同程 度の罪悪である。これを認識してないものは指揮官の資格はない。
なお、命令から、実行の詳細指示を抜き、目的だけを伝えると『訓令』です。例えば
「地球温暖化に対応せよ!」
が訓令である。
一方、背景などを抜いて、実行すべきことだけ命じるのは『号令』です。極端は
「突撃」
と一言です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

