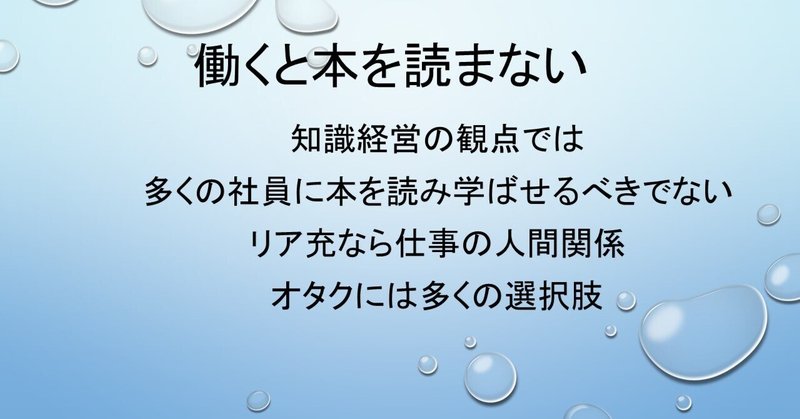
働くと本を読まない
働いている人は本を読まない、と言う趣旨の本が出ています。
私は、働いているときは、月に1万円以上を本に投資してきました。従って、この本の趣旨とは違う人間です。
しかしながら、「働いていると本が読めなくなる」状況は確かにあります。
この問題について、私が思う原因を考えて見ました。
一つの切り口は、「知識経営」の発想です。
ナレッジマネジメント - Wikipedia
つまり
働く人に適切な知識を経営側から与える
と言う発想です。私は、業務効率化の観点から言えば
各担当者が本を読んで調べる
状況は、経営的におかしいと思います。確かに、私はマイコンのソフトウエアの技術者として、当時の先端を切り開きました。そこでは色々な本を読み、調べる場合もありました。しかしこれを、多くの社員に求めるのは間違っています。
仕事に必要な知識は
仕事をさせる側から与える
が原則です。例えば、自動車のモーター制御のソフトウエアを作るからと言って、クラーク座標への変換などの基礎知識を学んで居ると、いくら時間があっても足りません。確かに
基礎知識を得るために本をじっくり読む
のは有効ですが、全ての人にこれを求めると、会社経営は成り立ちません。
さて、もう一つの切り口は
読書による仮想体験
の効果です。これに対しては
働くことでリアルな関係の充実
があります。仕事の関係者により、認められたり感謝されたりする満足は、読書の仮想体験より、実感のこもった喜びになります。確かに、仕事の苦しみもありますが、リアルな人間関係の力には、大きなモノがあります。
一方、こうした「リア充」に対して「オタク」という人達がいます。会社のリアル生活の他に、自分の世界を持っている人達です。しかしながら、彼らにとっては
多様なメデイア
特にゲームなどの充実で
読書は選択肢の一つ
なのです。
このように考えると
昭和の時代に比べると
本を読まなくなる
と言うには納得してしまいます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
