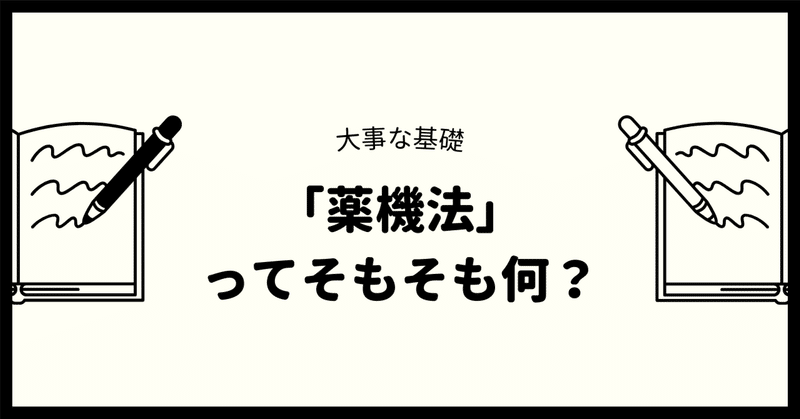
薬機法って何?全部読まないといけないの?
医療ライター・薬機法ライターなど美容健康業界で活躍している人は絶対に耳にしたことがあるルール「薬機法」。
日本の法律ということもあり、難しい内容が全部で91の条文に分かれ書かれており、どうやって勉強したらいいか悩む人も多いと思います。
参考:e-GOV法令検索 薬機法
勉強方法についての結論です!
難しい内容で書かれている量も多いのですが、全ての条文を読む必要はありません。丸暗記は不要で、必要な箇所のみ理解していれば大丈夫です!
※あくまでライターの人向けの話です。法律系の仕事をしている人向けではないことをご理解ください。

今回は医療ライター・薬機法ライターなどが理解しておくべき箇所のみを抜粋してみました。

そもそも薬機法とは?
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、「薬機法」や「医薬品医療機器等法」と略されます。
その名の通り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等について定めた法律です。
具体的には、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義・開発・承認・製造・販売・広告などに関するルールが定められた法律です。
「広告」とあるように、この部分がみなさんに一番関係があると思いますが、そもそもの目的や定義など知らないと表現できないこともありますので、順番に学んでいきましょう。
目的
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
医薬品等は国民全員の健康や命に直接関わります。
そのため、医薬品等が正しく使用されないことによる保健衛生上の危害の発生及び拡大を防ぐことも目的としています。
ここで注意して欲しいのが、医薬品等が正しく使用されないというのは、単に製造段階の不備や用法用量を守らないということだけではありません。
誇大広告や未承認医薬品(健康食品など)をあたかも医薬品のように表現・広告することも医薬品が正しく使用されなかったと判断されてしまいます。
この表現・広告するという部分が非常にややこしく、ライターの皆さんも苦労している部分かと思います。
薬事法との違いは?
薬機法というよりも「薬事法」と言った方が馴染みがある人もいるかもしれません。
薬事法の時だと「再生医療等製品」などがカバーできなかったとして2014年に法改正が行われ、名称も変更になりました。
名称が変わっとしても目的や誇大広告等に関する内容はほぼ変わっておらず、国民全員の健康・生命を守るためのルールであることにも変わりありません。

定義
薬機法に記載ある「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の定義はしっかり理解しておきましょう。
医薬品
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
定義にも記載あるとおり「疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的」であることが重要です。
医薬部外品
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
医薬品と比較して人体への作用が緩和なものを指します。
「厚生労働大臣が指定するもの」とは「指定医薬部外品」を指します。指定医薬部外品とは、医薬品販売の規制緩和に伴い、医薬品から医薬部外品へと移行された品目のことです。
指定医薬部外品は、告示(平成21年厚生労働省告示第25号)によって27品目が指定されています。(暗記は不要です)
化粧品
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
この定義からわかるように化粧品は人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変えるなどの目的で使用されるものでです。
医薬品と異なり「疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的」ではありません。
そのため、化粧品広告では「ニキビの治療」「シミ跡の治療」などの表現は基本的にはできないということがわかるかと思います。
(基本としているのはすごく上手く考えることで、表現することができなくはないからです)
医療機器
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
医療機器は疾病の診断、治療若しくは予防に使用される機器のことです。
(参考)健康食品
健康食品の広告で薬機法違反と判断された例を聞いたことがあると思います。しかし、薬機法の中で「健康食品」は定義されていません。
正確にいうと「健康食品」というものはどの法律でも定義されていません。
「健康に良いとされている食品」程度で大丈夫だと思います。

薬機法違反
ここでは主に広告表現に関する違反に関して解説します。
【考え方】
例えば健康食品などを医薬品として広告してしまう、医薬品等の誤った情報が発信されてしまうと、一般消費者の誤解を招いてしまいます。
その結果、間違った使い方をしたり、過度に効能効果を期待して、本来必要な治療を受けずに症状が悪化したりする可能性があります。
人々を健康にするはずが逆に健康被害を引き起こしてしまいます。
このような状況を防ぐためのルールがあるということです。

どんなことをしたら薬機法違反となるのか?
基本、嘘をつくことはいけない!ということですが具体的には
1、未承認医薬品を広告する
2、虚偽・誇大な表現で宣伝する
これらはNGということを覚えておきましょう。
1、未承認医薬品を広告する
「化粧品」を医薬品のように「シミが治ります!」などと表現する
「健康食品」を医薬品のように「高血圧にお悩みの方へ」などと表現する
このような場合、未承認医薬品の広告と判断されてしまう可能性があります。
2、虚偽・誇大な表現で宣伝する
効能効果、性能、安全性に関する虚偽・誇大な広告や、医師などが効果等を保証したと誤解される可能性のある広告はNGです。
具体的に薬機法には以下のような記載があります。
虚偽・誇大広告等の禁止(薬機法第66条)
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
特定疾病用医薬品等の広告の制限(薬機法第67条)
政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
承認前医薬品等の広告の禁止(薬機法第68条)
何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

具体的な罰則
薬機法に違反すると、行政処分や課徴金納付命令、刑事罰になる可能性があります。それぞれ具体的にどういうものかを紹介します。
1、行政処分
業務改善・業務停止命令、措置命令、許可・登録の取消などがあります。
この中で広告表現が関わる「措置命令」に関して解説します。
措置命令(薬機法第72条の5第1項)
虚偽・誇大広告等の禁止や承認前医薬品等の広告の禁止に違反した場合に措置命令を受ける可能性があります。
内容としては、違反と判断された広告の停止(中止)、違反広告の再発防止策の公示(公表)などが命じられます。
2、課徴金制度
薬機法第66条の「虚偽・誇大広告等の禁止」に違反した場合、課徴金納付命令を受けるおそれがあります。(67条、68条は対象外)
2021年(令和3年)の薬機法改正時に導入された比較的新しい制度です。
ざっくりいうと課徴金額は違反広告を行っていた期間中における、課徴金の対象商品の売上額×4.5%です。(売上が5,000万円未満の場合対象外などのルールあり)
課徴金制度ができる前の罰金額の最高額が200万円だったので、違反した場合高額な課徴金を支払わなければならない可能性があるため抑止力になることが期待されています。
3、刑事罰
悪質な薬機法違反の場合、懲役や罰金などの刑事罰が科せられる可能性があります。
薬機法第66条の虚偽・誇大広告等の禁止に違反した場合
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または両方を科せられる可能性があります。
それ以外にも違反内容次第で罰則が異なるので気になる方は法律を確認してみてください。
薬機法違反を防ぐためのポイント
最後に薬機法違反にならない、というより
薬機法などのルールをクリアした表現・広告を作成するためのポイントを紹介します!
1、美容健康業界広告が関わる法律・通知・ガイドラインを理解する
このnoteで薬機法の基礎基本をしっかり学び、厚生労働省が発行している「医薬品等適正広告基準」などガイドラインをしっかり理解しましょう。
薬粧連が発行している「化粧品等の適正広告ガイドライン」などの自主基準も必須なので必ずチェックしましょう。
また、日々様々な団体が発信している薬機法関連の情報やニュースも日々チェックし、情報収集することも重要です。
2、専門家に相談する
法律やガイドラインはそれ単体では完結せず、複数に内容がまたがっているものもあり非常に複雑です。わかりにくい表現や専門用語も多数あるので学ぶのに苦労します。
また、どれだけ学んでも自信が持てない、最後の判断に迷う、不安という声も聞きます。そのような不安がある場合は薬機法専門のコンサルティング会社や弁護士などの専門家に相談・依頼することもおすすめです。
私自身も月額3.3万円〜(平均的な業務内容の場合)で質問無制限のサービスも展開しておりますので、気になることあればまずは無料相談をしてみてください。
まとめ
薬機法は美容健康業界で仕事をしていく上で必須な法律です。
違反すると行政処分や課徴金納付命令、刑事罰につながることもあります。
正しく長期で活動するために、薬機法を含めた法律・ガイドライン・通知をしっかり理解しておきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
