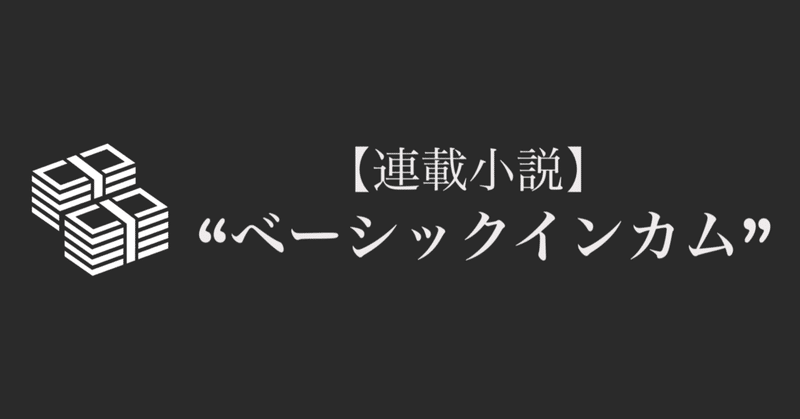
【連載小説】“ベーシックインカム“ 第2話
その日、A氏は帰りの電車を乗り過ごしてしまった。
酒に強いA氏は、酔って電車で寝落ちしたことすらない。ましてや今はシラフだ。
こんなことは入社以来初めてのことだった。
自宅の最寄り駅を出たA氏は、さっき見た動画の内容を頭の中で反芻していた。
「はい、みなさんこんにちは!」
動画の中のN氏は、動画配信者にありがちなやけに明るい調子で話し始めた。
動画の内容を一言で言えば「カツカツ層のみなさん、こっちへおいで!」といったところだろう。動画ではBI 層の生活がいかに素晴らしいかを、できるだけフラットな目線に見えるよう細心の注意を払いながら語っていた。
空き家や古いマンションを最新のインフラ設備でリノベーション。
「丁寧な暮らし」で人気の小売メーカーがタイアップした非常にシンプルで洗練された内装と家具家電。
おまけに政府からは引っ越し資金や祝金、免税、子供数に応した助成などさまざまな形で経済的支援が受けられるときている。まさに至れり尽せりだ。
ただしこれには条件があり、特典を享受できるのは政府が指定した期間、地域のBI層への移行を申請した世帯のみだという。
この財源はどこから出ているのか気にならないではないが、そんなことよりA氏は動画の内容に素直に惹かれた。
いや、正確には惹かれている自分に後から気づいた。
BI層の生活はA氏が思っていたほど質素なものでも地味なものでもなく、何よりその動画からは、何かしらのステイタスなイメージすら感じられた。
A氏は歩きながら考えた。
今も自分は週に数回、電車に乗って出社している。
全線で自動運転の導入が済んでからは、路線の大幅な増加により首都圏からは殺人的な満員電車はほとんどなくなった。とはいえ座ってゆったり通勤できるわけでもない。
通勤中はAIパートナーと会話しながらエンタメや仕事に関わるニュースをインプットする。
今や電車内の誰もがパートナーと常に会話しており、皆イヤホンはノイズキャンセリング仕様のため、昨年末には非イヤホンユーザー専用車ができた。もちろんA氏は乗ったことはない。
会社についてからも、仕事はパートナーと共に終わらせる。業務によっては自分がAIの秘書に回っていると錯覚する日もある。
そうやって仕事を終え、帰宅するのはいつも20時前。
正直、生成AIが民主化された10年前から彼の生活スタイルはあまり変わっていなかった。
時々ふと思う。なんのために生きているんだろう、と。
その度に彼はそれを考えないようにしていた。
考えたところで虚しくなるに決まっているからだ。
だがBI層の生活も悪くないと思えた今の彼にとって、その問いかけは今後避けては通れないもののように思えた。
「ただいま」
A氏は自宅の玄関の扉を開けた。
それはいつもより、なぜか重く感じられた。
・・・
翌日の午後、会社の商談ルームの前を通りがかったA氏は、中から聞こえてくる会話を耳にした瞬間、危うく手元のコーヒーを落としかけた。
部屋の中からは同期のTと、彼の上司の声が聞こえる。
Tは上司に退職願いを提出しているようだった。
夕方、A氏は仕事の合間を縫ってTを屋上に呼び出した。
「なんだよ?・・・ああ、あれか?ついに離婚か?」
屋上についたTは、いつものように挨拶代わりの冗談を言った。
「うん、まあそんなとこだ」
「なるほど」
Tは笑いながら紙巻タバコに火をつけた。
彼はA氏同様に、入社以来アンチ電子派を貫いていた。
二人が意気投合したのは、入社式後の飲み会で電子派に対し二人で論陣を張ったことがキカッケだった。あれからもう10年だ。
「おい!・・・で?なんだよ?」
A氏は我に帰った。隣でTが見つめている。
「すまん偶然だったんだけど、今日、商談ルームの前通った時、聞こえてきた」
「・・・ああ、そうか」
Tがゆっくりと煙を吐いた。彼はつぶやいた。
「まあ、そういうことだ」
「いつから考えてた?年末の飲み会では、全く・・・」
「2年ぐらい前かな。ちょうど大学の先輩がBIに移った時だわ」
「え、BI?」
A氏は驚いてTを見つめた。
「うん、、、え?」
Tも怪訝な顔でA氏を見つめ返す。
「お前、BI層に行くのか?」
「え、それを聞いたんじゃなかったのか?」
「いや、俺は退職の件だけで。通りすがっただけだったし。
っていうか、そうなのか?てっきり転職かと・・・」
それを聞いたTは、
「転職って、お前。もう俺たちホワイトカラーに残された仕事なんてないだろ」
ホワイトカラーって死語か、と言いながらTは乾いた笑いを返した。
「来月あきる野に新設されるBI特区に引っ越す。今度お前も来いよ」
「・・・奥さん、反対しなかったのか?」
「むしろ妻から提案してきた。うちの子、18まで病院通わないかんから」
「・・・」
A氏が黙っていると、Tから切り出してきた。
「お金は大丈夫だ。むしろそれもBI特区なら今よりも手厚く国が保障してくれる。
それに家族との時間も増える。それこそ時間は死ぬほど増える」
Tはそういうとタバコを灰皿に落とした。
彼の言葉と表情に迷いはなかった。
A氏はそう感じだ。こんなTを見るのは初めてのことだった。
ただ、A氏はその横顔に何か諦めの色のようなものも同時に感じていた。
ただそれをハッキリと自覚した訳ではなかった。
「ここでお前をタバコを吸うのも、多分最後だ」
「それは多分じゃないだろ」
雲間から真っ赤な夕日が見える。A氏の長く伸びた影がTのそれに重なった。
二人は笑いながら屋上を後にした。
(つづく)
第1話はこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

