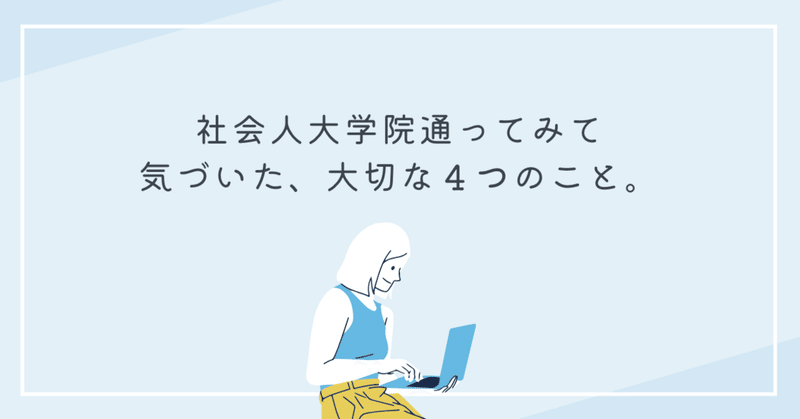
社会人大学院に通ってみて気づいた、大切な4つのこと。
立教大学大学院リーダーシップ開発コース(https://ldc.rikkyo.ac.jp/)に通って約4ヶ月が経ちました。この4ヶ月で私が気づいた「大切な4つのこと」について備忘録的に記そうと思います。
ちなみに、社会人になってなぜ大学院に行こうと思ったのかは、こちらのnoteをご覧ください◎
①「締め切りを自分でつくる」という意識
入学前は、「大学院と仕事の両立、やってやるぜ!」という気持ちでいました。実際できると思っていたし、そこにそんなに不安はありませんでした。
でも、いざ始まってみると、慣れない授業に、設立したての会社を経営していく、そのことで本当にいっぱいいっぱいでした。
特に入学してすこし経った5月は、自分の会社のことで考えるべきことが増えた時期でもあり、精神的に揺らぐこともありました。
切羽詰まりすぎた時は、会社も大学院ももう辞めてしまいたい…..と思ったことも正直あります。
でも、入学式の時に、この大学を選んだ理由でもある、中原淳先生が言っていた「どれほど大変でもしんどくても、自分たちで選んだ道ということを忘れないでほしい」と言う言葉が心に残っていて、会社をつくろうと決めたのも、大学院に通おうと決めたのも、この私だ、ということに改めて気付かされたと同時に、自分自身の時間の使い方を見直そう、と思いました。
それから私は日常の中で「締め切りを自分でつくる」ということを意識することにしました。具体的には、いつ大学院の課題を終わらせて、いつ課題図書を読み終えて、いつ大学院にまつわるnoteを書くのか、というスケジュールを引きました。
例えば、こんな感じです。
7/18 18:00 組織行動論課題終わらす
7/20 22:00 大学院note締め切り
8/2 20:00 ティール組織5章まで読み終える
なんとなく、課題をこの日にやろう、この日に本を読もう、というのではなく、いつまでに何を終わらすスケジュールで日々過ごすのか、を意識しました。特に「学び」に関しては終わりがないので、自分でいつ終わらすのか、を決めて取り組むことがとても重要だと感じています。
忙しいから本が読めない、とか忙しいから論文が読めない、と私も思っていましたが、そう思っているうちはきっとこの先もおんなじ理由でやらないんだろうなと。
大学院と仕事の両立を進める上で、「自分自身がどれだけその時間を確保したいと思っているか」で時間は作れるし、ちゃんとやれるということを学びました。
シンプルに、自分がその時にやるか、やらないか。
やると決めたなら締め切りを設けること。
これは今も大切にしながら日々を過ごしています。
ちなみにこのnoteも締め切りを決めて取り組んでいるので、仕上げられています。
②授業と実践を結びつけるための「振り返り」
最初の数ヶ月は授業と実践を結びつけることに苦労しました。
授業は「経営学概論」「組織行動論」「戦略的人的資本論」という興味深い授業なのですが、自分の現場となかなか結び付かない。
というのも私の会社のメンバーは3名で、まだ設立して半年ということもあり、部署なんてものも中長期計画なんてものもありません。授業や、授業内の議論では「人事」という部署がある前提で進みます。
「あなたの会社ではどうしている?」「どういう人事施策をしているの?」という質問に対して「私の会社にはまだ部署というものなくて….」という回答しかできませんでした。
ちなみに会社についてはこちらのnoteにまとめていますのでよろしければご覧ください◎
授業自体は面白いし興味深い。けれど、実践に結びつけるとなるとどうにも遠く感じる。
そこで大学院のメンバーと授業後に15分の簡単な振り返りを実施することにしました。
「今回の授業で実践に活かせそうだなと思ったことは?」
「集団凝集性ってなぜ起こるの?」
など、授業内容を理解できているか、と今回の授業を日常でどう活かせるかという視点での振り返りは、少しずつではありますが実践と結びついていく感覚がありました。
正直まだ100%授業内容と実践が結びついた!とは言えないですが、授業で学んだことを実践に活かすことができるかどうかは、振り返りが非常に重要なのではと思っています。
③仲間の「すごいところ」を吸収して真似してみる
大学院での醍醐味は、一緒に学び合う仲間の存在だとも思います。
私たちの学部は「リーダーシップ開発コース」というのもあると思いますが、授業中もグループワークが多く、授業でワークショップを作る授業もあります。様々なバックグラウンド、経験を持った仲間の視点から、いつも刺激を受けています。
ただ、ここで、「ほお〜すごいなあ」と感心するだけだと勿体無いので、吸収して真似してみる、ということを意識しています。
例えば、私はロジックで物事を説明することが苦手なので、ロジックで説明することが上手な人の話を積極的に聞いて、どういうステップでここまで辿り着いたのだろうと想像しながら議論に参加したり。この人だったらどういう視点で質問をするだろう、どんなステップでワークショップを進めていくだろう、と想像してその人になりきってみたり。
他にも、私たちの大学院ではお互いの提出した課題が閲覧可能なので、セグメントごとにまとめるのが上手な人の資料を見てまとめ方を学んだりもしています。
仲間の「すごい」と思ったところに触れて、吸収して、真似しながら学びを深めていくことも、大学院で学んだことです。
④なぜ、大学院で学びたいのかの「原点」を忘れない
大学院に4ヶ月通って、一番私が大切だと思ったのは、自分が大学院に通おうと思った「原点」をことあるごとに思い出し、アップデートすることだと思います。
例えば、大学院では課題を出されます。
自分に余裕がない状態だと「ああ、適当にちゃっとやって出してしまいたい」と思うことだってあります。(人間だもの…)
でも、自分はなんのために大学院に通うと決めて、どういう力を身につけたいのかを思い出すと、そこに「目的意識」が生まれます。
問いを立てるとしたら「なぜ、課題をやるのか?」
私の場合だと、自分で何かを始めたり、0→1で形にしていくことは得意なのですが、ロジックで物事を考えたり、理論やデータを使って事象を説明することは苦手です。なので、大学院では理論やデータなどを使って説明できる力を身につけたいと思っています。
そのために、課題に取り組むときに「この事象はどういう理論が当てはまるだろう?」「この課題はどのデータからいえるのか?」という視点を持つようにしています。自分の苦手なことなので、もちろん時間がかかりますし、考えてもわからん!となる時もありますが、課題を終わらせることが目的ではなく「自分の苦手な理論やデータ、ロジック力を身につけるため」に課題に取り組むようにしています。
もっと大きな視点で言うと、私個人のビジョンは「組織で活き活きと働くことのできる人を増やしたい」ということ。そのために必要な専門知識習得のために大学院に通って、組織の中で起こっている事象を理論やデータを使って整理する力が必要だと思っています。
あくまでも私にとって一番大切なのは「ビジョンとミッション」です。
個人のVMV(ビジョン、ミッション、バリュー)を整理するとこんな感じになります。
「自分の個人のビジョン、ミッションを達成するために、大学院に通って学んでいる」そのことを常に忘れないようにしています。

以上が、「私が社会人大学院に通ってみて気づいた、大切な4つのこと」です。まだ4ヶ月しか経っていないので、きっとまた残りの半年間で様々な気づきや学びがあると思います。
まず残りの半年の目標は、自分自身が組織開発や人材開発にまつわる理論やデータをしっかり扱えるようになることと、会社で新規事業を作るための準備を整えていくことです。毎日、できることをコツコツと積み重ねていくぞ。
今後も、定期的に大学院にまつわるnoteを更新していきますので、よければフォローしてください◎
そして、大学院に通っている方、これから通おうと思っている方、共にぜひ頑張っていきましょう。
ここまで読んでいただいてありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
