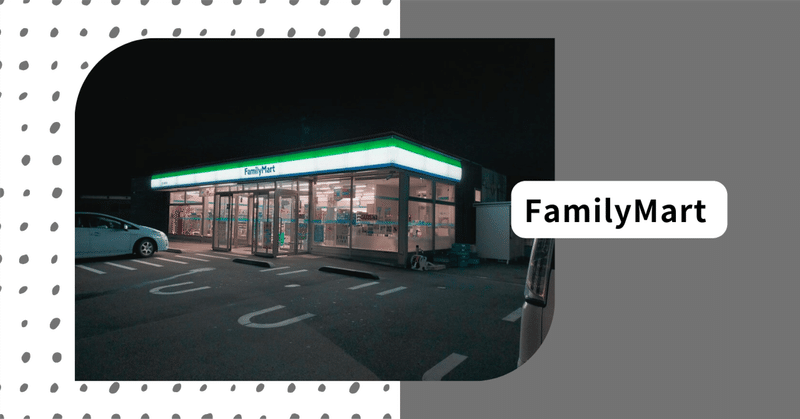
世の若者の常として時間なんて無限にあるものだと錯覚していた
大学時代、僕は実家からキャンパスまで通っていた。バスとJRと地下鉄を乗り継いで片道で二時間くらい掛かった。親の金で定期券を買っていたのでその膨大な交通費についてはあまり考えなかったが、時間がもったいないという感覚が当初は強くあった。毎日のように数時間をただの移動に費やすことで人生における貴重な学生時代を磨耗している気がした。
しかし、それにも次第に慣れていった。世の若者の常として時間なんて無限にあるものだと錯覚していたので、その価値を低く見積もっていたのだ。通学時間中、僕は音楽を聴いたり、小説を読んだり、スマホをぼんやりと眺めながら過ごした。講義がなくて早く帰れる時には、快速ではなく各駅停車の電車にあえて乗ったりもした。なんなら一旦逆方向の電車に乗って見知らぬ駅や街に行ってみることもあった。社会に出る前のモラトリアムである学生時代における、移動中というさらなるモラトリアムな時間を、どこかの時点から僕は楽しむようになっていたのだろう。
とはいえ、大学付近でアパートを借りて下宿している友達の家にはよく泊めてもらった。仲間内で集まって夜遅くまで飲むこともあれば、ただのビジネスホテル的に使わせてもらうこともしばしばあった。特に富山県出身のKのアパートには入り浸った。彼は希少価値の低い天然記念物みたいな男で、可愛げのある純朴な世間知らずのくせにどこか底意地が悪く、アダルトサイトの利用料の架空請求にビビって警察署に相談にいくような奴だった。講義終わりにアポも意味もなく彼のアパートにみんなでよく押しかけたし、僕は自分用にピンク色の歯ブラシを冗談半分で置いていた。他の奴がそれを見る度に「彼女できた?」と訊ねるのが仲間内での冗談だった。
ある冬の寒い夜、僕は遅くに彼のアパートを訪ねた。その時は事前に連絡をしていたのだけれど、Kはバイト先の飲み会に参加していて帰りが遅れていた。そんな訳で僕は外で一時間くらい待つことになった。二階建てのアパートの二階の廊下で、僕は眼下の住宅街の静寂に耳を澄ました。家と家の隙間から丁度見える片側一車線の道路を時折車が横切ると、冬の澄んだ冷たい空気にその残響が鋭く鳴った。道路の向こう側にあるコンビニの明かりの中では夜勤の学生っぽい店員が見えた。そんな景色をぼんやりと眺めていると、原付のチープな音が近づいてくるのが聴こえた。そしてその姿が道路に現れた瞬間、運転手はバランスを崩して転倒した。派手な音が辺りに響き渡った。運転手は路肩にうずくまり、コンビニで搬入作業をしていたトラックドライバーが「大丈夫か!」と叫んで近寄っていった。そこからの会話のやり取りは聞き取れなかったが、幸いにも重傷を負った訳ではなさそうだった。数分後にトラックドライバーは仕事に戻り、転んだ運転手はまた原付に跨ってその場を去っていった。しばらくすると、Kが暖かいペットボトルを二本持って帰ってきた。「ごめん、遅くなっちゃって。どっちがいい?」と彼は言った。一刻も早く帰るべきか何か暖かいものを買っていくべきか迷ったのだと、ヘラヘラ笑いながら説明した。僕は礼を言って飲み物を選び、部屋に入って熱いシャワーを浴びてからさっさと寝た。ついさっき一部始終を目撃した出来事については一切話さなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
