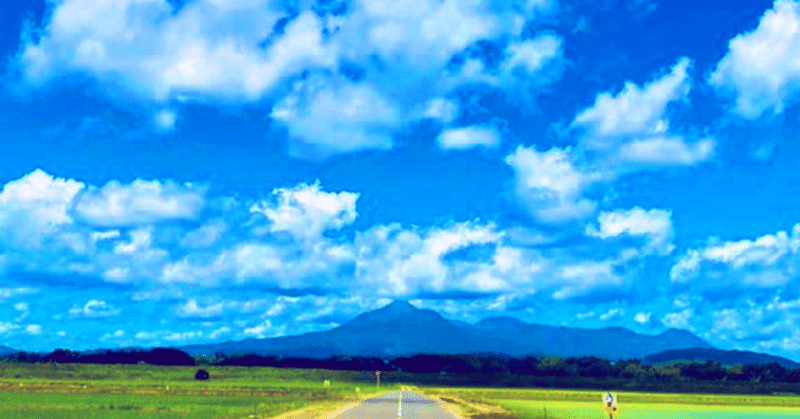
人生をどう生きるべきかーー答えは自分の中にある(と思う)
2年ほど前に鬼籍に入った石原慎太郎氏の「『私』という男の生涯」という本を読んだ。
この作品は死後に発刊されるものとして書き下ろされた本なのだという。それだけに氏が死に刻一刻と近づくなかでどのように死を眺めてきたのかをうかがい知れる本で、なかなか興味深かった。
本のはじめの方に「自分を忘却してしまって死ぬのだけは嫌だ。そんな風に終わる人生なんぞ、結局虚無そのものではないか。忘却は嫌だ。何もかも覚えたまま、それを抱えきって死にたい」という文章がある。
そもそも不帰の客となった方の心中を推察するというのは僭越ではあるが、おそらく氏にはニヒリズムみたいなモノに対する強烈な反発があったのだろうな、と思う。
生きている人間であれば、1度は死ぬことへの関心を抱くものだ。私自身も小さい頃、死ぬことへの漠然とした関心があった。
小学生の頃、伝記をよく手に取っていた。当時の私は偉人がどのような人生を送ったのか、どのような功績を残したのかには一切関心がなく、最後の方にある「死ぬシーン」を何度も読んでいた。
家庭科の先生には「図書館に行っては分厚い伝記を読んでいる」と勘違いされて褒められたこともあったが、実際のところ読んでいたのは死ぬところだけであり、ページ数にして10ページほどである。褒められていい気になり、「実はちゃんと読んでいない」という事実を伝えられなかった後悔は今も残る。
小学生向けの伝記では、死ぬシーンが非常に曖昧な描かれ方をしていることが多かったような記憶がある。それが当時の私にとって実に不満だった。
今でも私たちは死に向かってひた走っているのにも関わらず、実際のところ実体のあるものとして死を自覚する瞬間はまずないし、考えれば考えるほど死ぬことがよくわからなくなる。
気の小さい私なんかはそのうちおっかなくなって、死ぬことを考えることから距離を置いて、今をどう生きるのかということに意識を向けるようになる。
個人的に「どう生きるか」を真面目に考えるようになったのは、子供が生まれてからだと思う。ひとりのときにはダラダラと過ごしていたこともあって「まあこんな日々が延々と続くのだろう」と生きることに対して楽観的に構えていたが、幸運にも家庭を築くことになったいまになってなかなかそうはいかない。
人生の多くを仕事に費やすのも悪くはないが、それで家庭のことを一切顧みなかったり趣味もなかったりすれば、果たして充実した人生と言えるのだろうか。逆に、仕事以外にもさまざまなところに手を伸ばした方が良いものかと思いつつも、職人のように一つの世界に生きる「粋」のようなものも、己を掴んではなさないのも事実である。
職場で仕事をせよと命令されている時、確かにその仕事が己の知見を増やしているのはわかっても、そのように命令をされて生きることとは意志の喪失ではあるまいかという気にもなってくる。じゃあ自らの意志をもって仕事をするという話になったとき、一体全体その意志とは何だろうという気にもなる。いずれにせよ答えはない。
死の意味は死んでからわかるものなのだろうか。仮にそうだとすれば、生きている間には決して見つからぬ死というものの答えを人生の中で探し続ける我々に対し、死者がそれを我々に伝える術はない。
誰にでも生きることの果てに死があるのなら、生が多様なように死もまた多様であって、また答えはないのだろうし、そもそも答えを「外」に求めるのは、野暮なことなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
