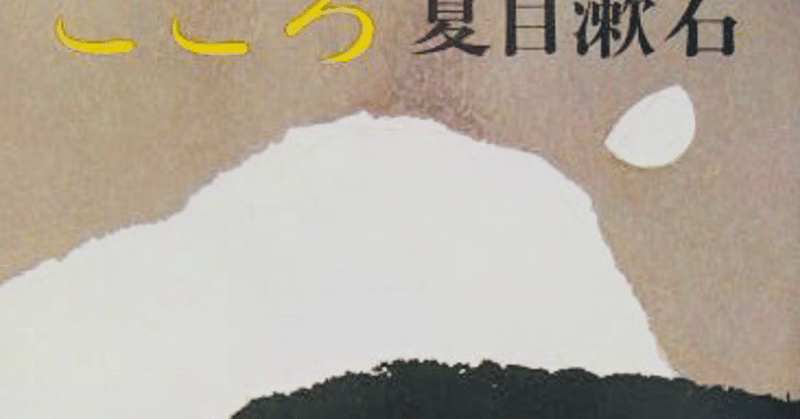
読書感想文②〜夏目漱石『こころ』を読んで〜
「私は死ぬ前にたった一人で好(い)いから、他(ひと)を信用して死にたいと思っている。あなたはそのたった一人になれますか。なってくれますか。」
「先生」が「私」に放ったこの言葉が鋭い矢のように自分の胸に刺さった。
自分自身、よく悩んできた。どれほど高尚な理想を掲げていても、現実とはいつも距離がある。どれほど人間の利他精神に心を打たれ、そんな風に生きて、死んでいきたいと切に願っても、気付けば自分のことばかり考えている。結局、自身の「エゴイズム」からは逃れられない。そう思い知らされると激しく自己嫌悪する。そんなことを幾度となく繰り返してきた。
そういうことに神経が研ぎ澄まされればされるほどに、苦しく、生きづらくなっていく。
先日、友人に誕生日プレゼントを贈った。かつて何度も自分を救ってくれた後輩の女の子だ。しかしプレゼントを梱包しながら思った。自分が本当にその人のことを想っているのか、それともその人に好かれたいからやっているのか。いい人だと思われたくてやっているんじゃないか。その人と親密になることで自分に便宜があるからやっているのではないか。下心がほんの少しでも入っているんじゃないか。綺麗にカモフラージュしているだけで、実はその心の内実は醜いものなんじゃないか、と。
そんなことを考えれば考えるほど、心の深淵に日々孤独が積み重なっていく。抜粋したセリフは、そんな風に「エゴイズム」によって孤独の淵にぎりぎりまで自分を追い詰めてしまった人間の心の叫びなのではないだろうか。主観だが、あのセリフは相手に向けて言っているようで、自分自身に言っていることのように思う。つまり、自分自身を一番信用していないことの裏返しだなのだと思う。学問で知識を幾重にも積み重ねてきた人間はどんどん高い位置から世界を見渡せるようになっていく。いずれ本当に美しいものが何なのかが見えてくる。そしてそれはいつだって、現実世界と折り合えない。いらないものを徹底的に削ぎ落として純化した理想的思想と俗世はあまりにも離れすぎている。ゆえに苦しい。理想をどれほど目指しても”我執”に抗えない侘しさ・寂しさ・虚しさ・悲しさ。夏目漱石はそれらを非常に繊細に感じていたはずだ。しかしそれが同時に人間存在の本質でもある。それらの究極体を文学の領域で、見事に表現しきったのがこの『こころ』という作品なのではないかと思う。
まだ封建制の名残が残っている明治時代に、物質的に満たされた近代社会において人間が苦悩するであろう「自我」問題をいち早くとらえていた夏目漱石の先見性には驚かされる。日本国内の純文学でも最高峰と名高い理由はここにもあるのかもしれない。
物語の終盤、「先生」は親友の「K」を出し抜いて「御嬢さん」を自分のものにした自分のエゴと自己の人間としての理想との間で板挟みになってしまう。最終的にはこのエゴを「人間の罪」と表現しているところに危うさを感じる。ここまで人間の我欲を昇華させてしまうと、キリスト教の「原罪」の考え方に近くなってくる。キリスト教においては、原罪の向こう側に「神様」という絶対的な存在を置き、自分を明け渡してしまうことで救われるという構造があるが、もちろんノンクリスチャンが「原罪」なんて背負ってしまうとただただ苦しい。最終的にそれが自殺によってしか解決できないと悟ってしまうのも無理はない。
だから、反対にこのエゴイズムを各人が自分で許し、むしろ認めていくことが重要なのではないかと思う。認め、引き受けながらも理想は目指し続ける。相手の欲も、そして自分の欲も。確かに人間には我欲はあるけれど、我欲だけで生きているわけではない。誰かのために真に一生懸命になることだってある。要はバランスの問題だ。
自分自身まだまだ着地点は見つけられていないけれど、ちょっとずつできればいいと思っている。
ちょっとずつ。そう、ちょっとずつだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
