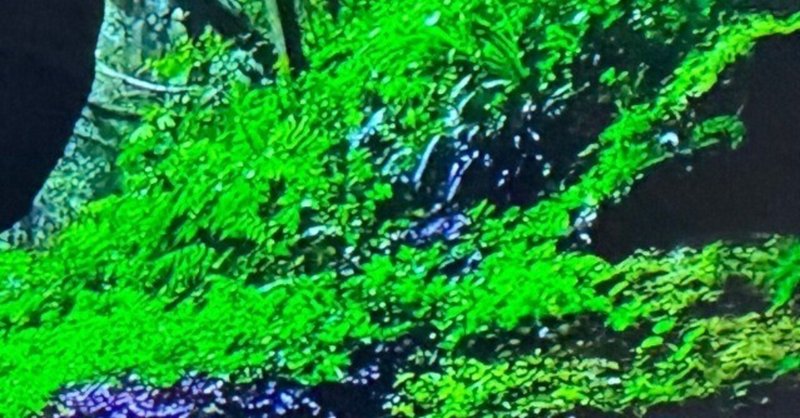
【小説】水族館オリジン 4
chapter IV: 町に出れば
崇くんがお休みのときは、二人で図書館の町まで出かけます。この時は崇くんの軽自動車に乗ってでかけました。動物学者ほどアクティブな生き物はいないとは崇くんの弁です。いつも動物を探し、動物の急にかけつけ動物に人生を捧ぐ、のだそうです。動物の病気は待ってはくれない、世の中はインディジョーンズのような考古学者をアクティブリサーチャーと思っているけれどとんでもない、遺物はもはや時をいそがない・・・そうです。すごくかっこよく聞こえますが、崇くんは動物じゃなくて、魚が専門です。私はふふん、と鼻で笑いながらきいています。
そんなわけで『アクティブな』水族館員の崇くんは取れるようになるとすぐに車の免許をとりました。それ以来ずっと軽に乗っています。私は免許をもっていないので、二人の休みのお出かけは必ず助手席です。小さな車はいつも綺麗に掃除されてどこもかしこもピカピカ。でもすこーしお魚のにおいがしますが、それは仕方ないことです。だから鼻が敏感な時は、できるだけ口で息をすることにします。そうでないと、おかげで実体のない匂いばかりが語りかけてくるようになってしまうから。
ここの映画館は、古い映画を一本だけかけている昔風の映画館です。昔は週末ごとに行列ができるくらいはやっていました。いまはお客が市内のシネマコンプレックスにすっかりお客を取られて静かです。
お客が減るのは日本中のどこでも同じです。が、ここは少し違います。大手のシネコンに負けない工夫で頑張っているのです。どんな手かというと、劇場前ロビーのカフェをおしゃれにしたのです。昔のまま、というより、わざわざ三十年まえのランプシェードや家具をレイアウトしたのです。それから映画会社の名前のついたカップアイス、噴水のようにオレンジジュースを噴き上げるガラス玉のジュースマシン、銀色の熱電灯が照らすアメリカンドッグ、赤いカーペットの床に、角を斜めにカットしたカウンター、一本足のスツールにソフトクリーム・・・。
一度に一本しかやらない映画館に、不思議と人が集まり、よく知ったストーリーにお決まりの反応をして楽しむ。そんな楽しみ方をおもしろがって『タナベネマ』と呼ばれるようになりました、地元だけで、ですけど。
今日も、二人で大好きなこの映画館へ来たのですが、用心していたにもかかわらず嗅覚につかまってしまいました。
いつものチケットのもぎりさんがにこやかにむかえてくれる入り口からシアターに入ると客席まで数メートルあります。以前はそこには立ち見の人が、立錐の余地もないくらい並んでスクリーンを見ていたそうです。立ち見も自由席も同じ値段ですが、入れ替えがないので大丈夫。座席のそばに立っていれば次の回には座れます。次まで待たなくても、途中で帰る人がいれば座ることができました。前回みられなかったところやもう一度見たいシーンまで居残るのはむかしは当たり前だったそうです。扉から席までの広いスペースはこの時の名残です、いまは立って見る人もなく、いつもガランドウですけれど。
そこを通ったとき、鼻のさきをくすぐるにおいがありました。いいにおいではありません。ハッキリしたにおいじゃないけれど嫌な感じの、近くの物を腐らせてしまう、そんな匂いです。
小さい時から死神のにおいと自分だけで呼んでいました。胃痛もちの人からこんなにおいがすることがあるけれど、死神のにおいは近くから人がいなくなっても、匂いは私の鼻の下から去りません。
どんな匂いがするかで人を判断してはいけないと自分をたしなめるのですが、
こんなにおいがする人は笑顔や言葉は感じ良くても、あとから印象を更新させられることがままあるので、信用しないことにしています。
さて、シアターに入ると予告編は始まっていました。照明が落とされうす明りの中でスクリーンの光が照らす輪郭だけが浮かんでいます。
座席までの立ち見の暗がりに、ほんとうはだれもいないのに、あのにおいがただよってきました。
そして鼻下に体温を感じたのです。
死人のにおいなのに体温をかんじたのです。
空気中に輪郭のない、匂いと体温だけを持った存在がいる、そんな感じです。
崇くんが手を引いて席まで連れて行ってくれます。
引っ張られるまま、フラフラついて行くと
空いている感覚に、さっきの存在がどんどん入り込んできて、
ぐんぐん大きく膨らんで、
勝手に私の中で背景と名前を持った生き物なりました。
やっと席にたどり着きました。
すわって自分を落ち着かせようとしましたが、
座面や肘置きを伝って頭の中にやってきて
映像が結ばれてしまいました。
きっと眠ってしまったのだと思います。
揺り動かされて目を開くと、劇場はもうあかるくなっていました。映画はとうに終っていました。
「寝ていたね」
崇くんは呆れ顔です。ごめんなさい。
説明しようとしましたが、申し訳なくてただうなずくだけにしました。いまは一日一回の上映ですから、座わりつづけていても見逃したところを見ることはできないので、出なくてはいけません。自分のじゃないみたいな足を無理に立たせ、崇くんの後ろをついてゆきます。
「せめてお茶だけでもしていこうよ」
崇くんがいうので、映画館がリニューアルオープンした時にできたカフェ・レストランに寄ることにしました。ここはこのまちに流れ着いた北のシェフが、上映中のリバイバル映画に合わせたメニューをだしてくれます。もぎりのお姉さんが返してくれた半券を見せなければ注文できません。映画を見た人限定のレストランなのです。私たちはクリームブリュレを頂きました。キャラメーゼされた表面をスプーンで壊すと本当に新しい自分が始められそうな気がします。
「それで、どんなひとだったの?」
やっぱり崇くんです。嗅覚にやられていたのに気づいていました。さっきまでの玉ねぎ色の遠慮がゆるゆると一枚ずつはがれていきました。私はうたたねの中で見たことを話すことにしました。
雪が降っていました。風景は四十年ぐらい前のこの映画館です。でもグレー一色です。私は大きなストールを頭かぶり雪の中で待っていました。ずっと待っていました。手も足もかじかんで感覚がありません。それよりもつらかったのは、待っている人がきっと来ないだろうという確信でした。場面はすぐに変わり、私はお葬式にいました。たくさんの人が動き回る中、言葉を交わす親しい人もなく、大きな和室の端っこに申し訳ない気持ちで座っていました。
私の存在にも気持にも関係なく式は始まり、親族が私の愛しい人の体を順繰りに清めてゆきます。葬儀社の人の取り仕切る中、奥さんと子供たちがあの人の体の横に体を沿えて静かに泣きました。とても長く美しく静謐な時間でした。
そして白木の箱におさめられます。葬儀社の係がとても丁寧に、
「お別れをなさりたい方はいらっしゃいますか」
と言いました。私はつよくつよくもう一度あの人の顔を見たい、あの細い指と高く太い鼻梁にさわりたいと思いました。でもその気持ちを呑みこむしかありませんでした。
誰にも知られてはいけない。
私の馬鹿な行動でこの美しい彼の最期の時間をけがしてはいけない。
そう思いました。
とても丁寧なやり方で、あの人は小さな箱におさめられました。もう息をしないあの人が本当のご遺体になってしまいました。つらくて、かなしくて、涙が出そうになりました。けれど押し戻しました。
小さな箱は船なのです。あの世の、あの人がこの世に来るまえのところへ戻るための小舟です。
船の縁は私と彼を隔絶するもの。あの人は細い一線を越えた向こうがわに私の一部を持って行ってしまいました。あの人へ向けた笑顔、あの人だけを思って眠った夜、あの人の瞳の中だけに居た私。これからどんな人に会っても一緒に生きることになっても、他の誰にも絶対に見せないあの人だけの私を棺桶の中につれていってしまいました。
わたしの体と心のあちこちに穴があきました。
怪訝な顔をされながらも、私は親族で満席のバスに乗せてもらいました。
そして町はずれの焼場の駐車場のかたすみで、
煙突から立ち上る白い煙にむかって手をふりました。
あの人が「いい子だったね」と手を振りかえしてくれました。
そんな気がしました。
これでおわりです。
このあと、わたしが別の人に嫁いだのかどうかわかりません。
でも「私」はもう亡くなったみたいです。
人の念は、想いの強い場所や物に残るといいます。「私」さんにとって、今日のこの映画館は、最愛だった人との最後の約束の場所だったのかもしれません。その念を私が汲んであげたことで幸せになってくれれば、それでいいです。
「そうだったのか。すてきな恋だね。
あなたは情が深いからきっと分かってくれるって思ったんじゃないかな、その人」
崇くんは本当にそう思っているみたいに言ってくれました。わたしの話を馬鹿にしないできいてくれました。そして優しい目で私をみてくれました。
ハロウィーンがすぎ、急に夜が長くなりました。スウィーツだけ頂くつもりが、すっかり遅くなりました。
リバイバルレストランの外にはもう、紫色の闇がおりてきていました。
私たちの全身が映るようになったお店の窓ガラスをとおして目を凝らすと、
遠くの水平線に動かないホタルがいるのが見えます。
その光ったり消えたりする様を数えていたら、白いものが落ちてきました。
雪でした。外海の風はときどき、せっかちな白いお客さんを連れてきます。
「ワインでも飲む?」
崇くんが財布の中を確認しながらいいました。
いいでしょう、早めのクリスマスディナーといきませんか?
「わりかんね」
はい、いいですよ。
私は、どうやったら乾いたアスファルトの上にうっすら積もった雪の上を解かさずに崇くんの軽が走れるかを考えながらうなずきました。
真鯛のポアレとホタテのムースが最高でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

