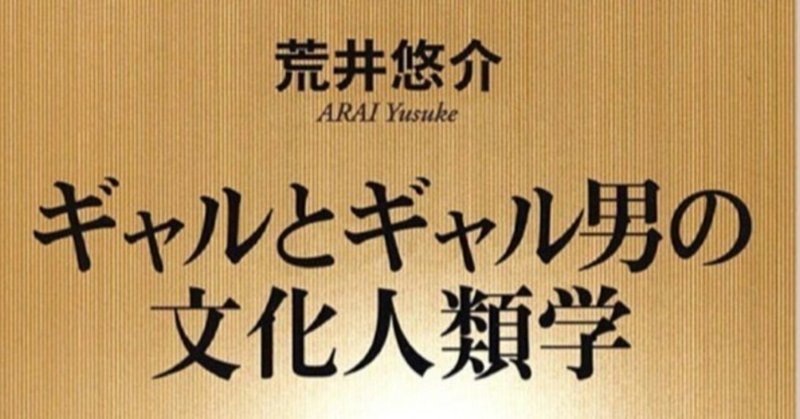
ほんのしょうかい:荒井悠介:『ギャルとギャル男の文化人類学』(新潮社)〈『思想の科学研究会 年報 最初の一滴』より〉
荒井悠介:『ギャルとギャル男の文化人類学』(新潮社)
言語論的転回以降、社会構築主義を多くの社会学者が意識するようになって、社会学の調査の方法は、おおきく様変わりしている。研究者が、研究対象を扱う場合、研究者の立ち位置というものが、研究に影響することが意識されるようになっているようである。
社会調査によって、なんらしかの考察の素材を手にすることができるのだが、論考の結果をニュートラルなものにするために、調査の採取については、その確かさを高める方向と、まずデーターを集めそのあとで研究者による影響をいかに消していくかという方向の大きくわけて二つにわかれているように思われる。構築主義の影響で、この後者の方向が強まっているが、『最強の社会調査入門』(ナカニシヤ出版)は、そのあたりの若手の研究者の苦労を、よく伝えてくれている。
荒井悠介氏は、2000年代初頭の渋谷を中心とした“イベサー”「ive.」に所属して活動し、代表までつとめた。この体験をもとにして書かれた一冊である。この“イベサー”というのは、「パーティ」や「イベント」の運営を中心に活動する大学生、もしくは高校生を中心とした様々な集団の総称ではあるが、活動拠点を大学に置き普通の学生を対象とした「イベント系サークル」とは異なり、繁華街、ストリートに活動拠点を置き、ある種の逸脱を自覚的に行っているギャルやギャルサー(ギャルサークル)を対象に活動をおこなっていた集団である。
この本は、著者の実体験がもとになっている。そういう意味では、研究者と対象が、ある意味同一であるという証拠としての強さをもっている。けれども、荒井氏は、この本では、そこに甘えることなく分析を丁寧に行っている。その繊細さがなければ、単なる体験報告に堕ちかねなかったかもしれない。
私は、このことを可能にしたのは、彼の誠実さであり、活動をしながらも自分の奥底にあった居心地の悪さの自覚であったように思っている。「居心地の悪さ」と表現したが、これは、言い換えれば、自我や自己認識、自由の選択、つまり己を問う行為に常につきまとうものなのである。
言語論的転回以降の、社会学と社会調査の問題に関しては、対象と、研究者と、研究によって明らかにしようとしているものとの関係そのものが問われているのだろう。これは、ある意味、「解釈」という行為や、「解釈学」というものが扱おうとしている分野であり、その座標に置き直すことが必要におもう。そのとき、自分を問い続けざるを得なかったこの本の独自性が、重要になると考えている。 (本間神一郎)
年報は研究会のWEBSITEから閲覧可能です。
最近、研究会のサイトは、引っ越しをしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
