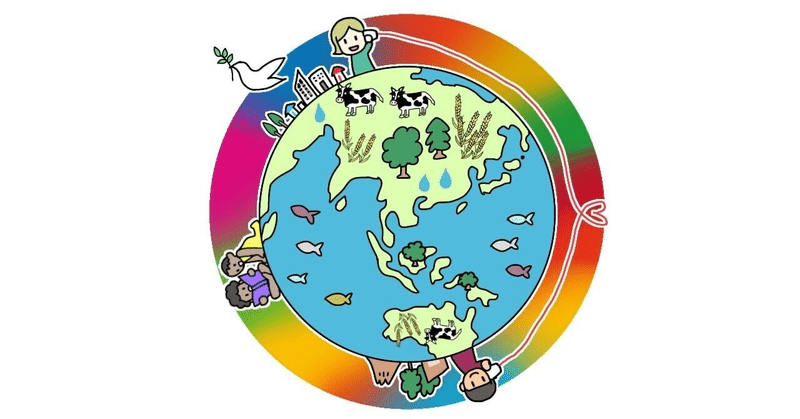
気象 第57回問1から「中層大気」とは12/18
第57回気象予報士試験一般
問1
中層大気の1月の月平均の気温や等圧面高度などについて述べた次の文(a)~(d)の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a)高度10~20km付近では経度平均した気温が最も低いのは赤道付近である。
(b)高度20~50km付近では高度が高いほど気温が高く、オゾンの数密度も大きい。
(c)高度70~90km付近における経度平均した気温は、大まかにみると、北極付近で最も高く、南極付近で最も低い。
(d)北半球の高度20~50km付近では、等圧面上の等高度線は北極を中心としたほぼ同心円状になっている。

この中層大気の気温に関する問題もよく出る。
第56回にも出題された、次の図は覚える必要あり、、
下の図と

この図も覚える

大気の温度は、
対流圏界面まで下がり、赤道上では熱で大気が膨れ、同じ高度では赤道上が一番温度が低い。
成層圏ではオゾン濃度ピークの25km付近まで同じで、そこからオゾンが熱を発生させ上昇していく。熱せられた大気はブリュワードブソン循環で北の極に冬過ぎに集まる。
中間圏では放射冷却で成層圏で温度の高い夏極上空が放射冷却で一番温度が低く他は一律に高くなる。
熱圏では一律に気温は高くなる。
もう一度、問題をみると、、、
問1
中層大気の1月の月平均の気温や等圧面高度などについて述べた次の文(a)~(d)の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a)高度10~20km付近では経度平均した気温が最も低いのは赤道付近である。
(b)高度20~50km付近では高度が高いほど気温が高く、オゾンの数密度も大きい。
(c)高度70~90km付近における経度平均した気温は、大まかにみると、北極付近で最も高く、南極付近で最も低い。
(d)北半球の高度20~50km付近では、等圧面上の等高度線は北極を中心としたほぼ同心円状になっている。
(a)はその通りで
正
(b)成層圏のオゾンは25km付近が一番多いので、オゾン数密度は高くなればなるほど大きいわけではないので、、
誤
(c)は中間圏はその通り
正
(d)は北極側は大きなプラネタリー波が出来る。
誤
よって答えは⓵
おはようございます。
ゆっくり眠られましたか?
こちら、雪です。
大雪になりそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
