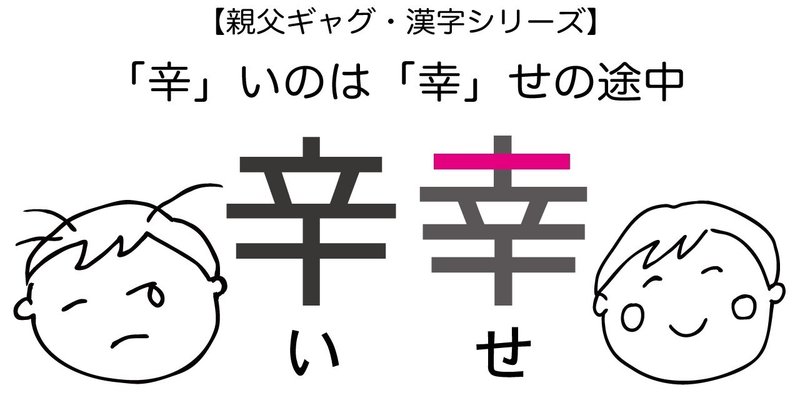
ライフサイクル・モデル
子育てと親父ギャグを五十音順のキーワードで綴ります。ラ行に入り、いよいよ終わりがみえてきました。
友人の数名から「本になるのですか?」と質問をいただきました。本当に有難いことです。今のところ、100日後にキャンペーンを開始する予定はございません。
本日は「ラ」で、ラッキーピエロの話しをしましょうかね。函館にあるハンバーガーチェーンで、オリジナルメニューがウマい。全国ご当地バーガー日本一に選ばれています。
ぼくがラッキーピエロに出会ったのは30年前、大学生のときに自転車で北海道旅行して函館のライダーハウスに立ち寄り・・・
と、ぼくの思い出話には興味ないと思われましたので、子育てに関わるテーマで「ライフサイクル・モデル理論」について書きます。
ライフサイクル・モデルは、精神分析家のエリク・H・エリクソンが提唱した、幸せに生きるための道標です。
乳幼児/幼児期/児童期/学童期/思春期・青年期/成人期/壮年期/老年期のステージに分け、それぞれのステージにおけるテーマを示しました。各ステージで乗り越えるべき課題があり、それらを解決できないと危機的な状態が訪れるといいます。
この理論のポイントは、ステージの順序が決まっており、とび級がないこと。乳児期を健全に過ごしてから、幼児期を健全に過ごすことができ、児童期、学童期へと続く課題をとばすことはできません。
マズローの欲求5段階説(生理的欲求/安全欲求/社会的欲求/承認欲求/自己実現欲求)とこの点は似ています。ただ、欲求段階説は曖昧なイメージで語られがちなのと、科学的に検証できていない欠点がありました。
エリクソンのライフサイクル・モデル理論は、年代ごとの課題と、乗り越えられなかったときに陥る危機状態が具体的に示されており、メッセージがより明確。
ぼくは、マズローよりエリクソンが好みです。昔、巨人にいた長身のピッチャー、ガリクソンも好きでした。
以下、ライフサイクル・モデル理論について、佐々木正美先生『あなたは人生に感謝ができますか?』を参照して記述します。佐々木先生は不朽の育児書『こどもへのまなざし』の著者です。
ライフサイクル・モデル理論における人生の8段階とテーマは次になります。
乳児期 「基本的信頼」の獲得。人を、自分を信じられるか
幼児期 「自律性」を身につけること。セルフ・コントロール
児童期 「自主性」、積極性、主体性、目的性をはぐくくむこと
学童期 「勤勉性」の基礎づくり。友達とのさまざまな共有経験
思春期・青年期 「アイデンティティ」の形成。自分を見出せるか
成人期 「親密性」をもつこと。家族や同僚とのむすびつき
壮年期 「世代性」を生きること。引継ぎと引き渡し
老年期 「人生の統合」人生に感謝ができるか
佐々木先生によれば、自分がどの時期にいると考えるかは年齢にかかわらず自由とのこと。
乳児期(0〜2歳)のテーマは「基本的信頼」を抱くこと。母親的な人から無条件に愛されることで、赤ちゃんは人を信じることができるようになります。
子どもが母親を信じられることを、心理学の用語で愛着形成(アタッチメント)といいます。いっぱい抱っこすることで愛着は育まれます。
幼児期(2〜4歳)のテーマは「自律性」を身につける。徐々にしつけを始める時期ですが、しつけは信頼感を育てたうえで行う。
イヤイヤ期の只中ですが、自分でできるようになるまで待つ。いつやるかを子どもに決めさせてあげることで、自律性が育ちます。
児童期(4〜7歳)のテーマは「自主性」をはぐくむこと。この時期に最も重要なのは遊び。遊びがさまざまな面で子どもを成長させます。
児童期の子どもは遊ぶのが仕事。できないことにも挑戦し、失敗から学ぶ。しっかり遊んで自主性、積極性、主体性、目的性が育まれます。
学童期(7〜12歳)のテーマは「勤勉性」の基礎づくり。勤勉性は勉強ではなく、友達と遊びあうなかで身につきます。小学生時代はとくに、違うタイプの友達が数多くいたほうがよい。
思春期・青年期(13〜22歳)のテーマは「アイデンティティ」。アイデンティは自己同一性と訳されます。自分はこういう人間なんだと知ることが課題になる。
自分を客観的にみつめる時期で、出かける前に鏡で外見をチェック。内面を映し出す鏡も必要で、価値観を共有できる仲間や、尊敬できる先生を求めます。
成人期(23〜35歳)のテーマは他者との「親密性」。家庭や職場で、親密な人間関係を築くことで生産性を高めます。成人期に親密な人間関係を築けないと孤立します。
又、エリクソンは人間関係を重視しますが、必要な人間関係はステージによって変わります。乳幼児期は母親、児童期や学童期は母親より友達。思春期・青年期は多くの友達より価値観を共有できる少数の仲間。成人期に職場の同僚や家族と新しい関係を築きます。
壮年期(36〜55歳)のテーマは「世代性」を生きる。前の世代から受け継いだものを、次の世代の人たちへ譲り渡す。上司になる年代であり、いつまでも「俺が俺が」と自分ファーストでいると停滞します。
老年期(56歳以上)のテーマは「人生の統合」。長寿社会になり、年齢はもっと後ろでよいかもしれません。
自分の人生を振り返って満足ができると、幸せに人生を終えることができる。最後に問われるのは「人生に感謝ができるか」。
以上、ざっくりですが、ライフサイクル・モデル理論の説明でした。
ちなみに、佐々木先生は「育児の主役はあくまでお母さん」という考え方があり、先生のシンパの方から「育児にお父さんは不要」と言われたことがありました。
『あなたは人生に感謝ができますか?』の本でも、次の記述がありました。
日本は男女共同参画社会になってきています。そのこと自体には、私は大賛成ですとても重要なことだと思っています。
だけど、お母さんとお父さんが育児を半分ずつ均等に分担しあうとか、お母さんが従来やっていた役割を一部お父さんが安易にやることに、私は不安や警戒心をもっています。そういうことをすすめるのは、赤ちゃんの心を知らない人ですよ。(P66)
その根拠になっているのが佐々木先生ご自身の子育て体験談で、エビデンスに基づいているわけではない。この点だけ残念だなーと思うのでした。
もっとも、わが家も主役は母親なのですが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
