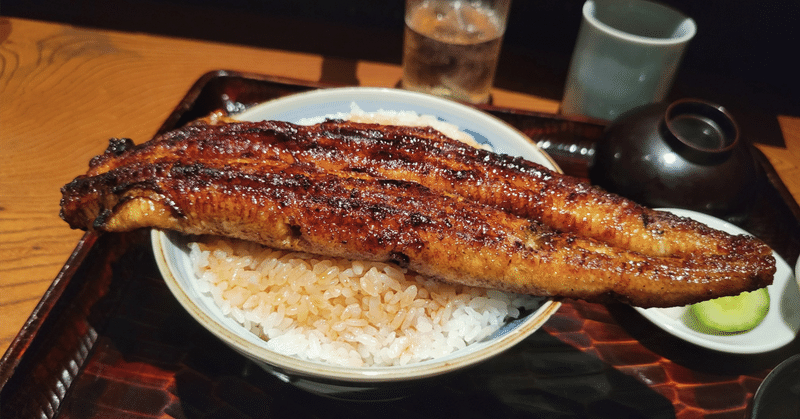
災いと芥川龍之介 第四章「訳が分からないよ」
この章の魅力:翻訳で翻弄
おれは沼のほとりを歩いてゐる。
Oh summer sunset、晩夏の黄昏、ひっそりと沼を閉ざす芦の匀が漂う中、枝蛙の色褪せた声が跳ねると、空に星は瞬き、秋がかすかに目を醒ます。夢現の「おれ」はいつまでも独りで沼のほとりを歩きながら、水底から絶え絶えに漂ってくる曲に耳を傾ける。
おれは沼のほとりを歩いてゐる。
水底から漂ってくるのはInvitation au Voyageの曲。「おれ」は水底に咲く「スマトラの忘れな艸の花」に憧れ、
困憊を重ねたおれ自身を名残りなく浸す事が出来たら――
と思う。このままほとりで「待つて」いても仕方がないが、
見れば幸、芦の中から半ば沼へさし出てゐる、年経た柳が一株ある。あすこから沼へ飛びこみさへすれば、造作なく水の底にある世界へ行かれるのに違ひない。
おれはとうとうその柳の上から、思ひ切つて沼へ身を投げた。
身を投げるとその拍子に芦は喋り立てて、水は何かを呟く。そして青い水底に「おれ」は沈んでいく。
おれの死骸は沼の底の滑な泥に横はつてゐる。死骸の周囲にはどこを見ても、まつ青な水があるばかりであつた。この水の下にこそ不思議な世界があると思つたのは、やはりおれの迷だつたのであらうか。事によるとInvitation au Voyageの曲も、この沼の精が悪戯に、おれの耳を欺してゐたのかも知れない。
不思議な世界はいつまで経っても姿を顕さない。「おれ」は沼の精に欺されたと思いだした。が、そう思っていると種子には命が宿りはじめる。
が、さう思つてゐる内に、何やら細い茎が一すぢ、おれの死骸の口の中から、すらすらと長く伸び始めた。さうしてそれが頭の上の水面へやつと届いたと思ふと、忽ち白い睡蓮の花が、丈の高い芦に囲まれた、藻の匀のする沼の中に、的皪と鮮な莟を破つた。
そうして暗澹たる沼に白い莟を破った「玉のやうな」睡蓮の花をじっと仰ぎ見ながら、「おれの死骸」は不思議な世界にいつまでも横たわり続けるのだった。
be deceivedからbe conceivedに至る睡蓮water lily開花の顛末は、無論、夏目先生の『夢十夜』第一夜からの着想である。そちらでは男が、死別した女と百年を経て再逢できると信じて待っている。待ち続けて男が挫けそうになったところで、白百合white lilyに成って逢いに来る(聖)女の姿があったはず。
(…)自分は女に欺されたのではなかろうかと思い出した。
すると石の下から斜に自分の方へ向いて青い茎が伸びて来た。見る間に長くなって丁度自分の胸のあたりまで来て留まった。と思うと、すらりと揺ぐ茎の頂に、心持首を傾けていた細長い一輪の蕾が、ふっくらと瓣を開いた。
暗い世にたった一つ輝く星のような夢の短編とも読めるが……
そも、『寒山拾得』は第「六」夜の続きで、件の橋は夢中に架かる浪漫派の橋であった。
運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいると云う評判だから、散歩ながら行ってみると(…)
久しぶりに漱石先生の所へ行つたら、先生は書斎のまん中に坐つて、腕組みをしながら、何か考へてゐた。「先生、どうしました」と云ふと「今、護国寺の三門で、運慶が仁王を刻んでゐるのを見て来た所だよ」と云ふ返事があつた。この忙しい世の中に、運慶なんぞどうでも好いと思つたから、浮かない先生をつかまへて、トルストイとか、ドストエフスキイとか云ふ名前のはいる、六づかしい議論を少しやつた。
このあと帰路に就き寒山拾得に遭遇している。夜の影は『沼』にまで延び、いや、第一夜の夢にダイナマイトの在処を認めることなど……
年上の友人の事です。
私が何か話をすると必ず「私ならこうする」と言います。
こんな夢を見た。
腕組をして枕元に坐っていると、仰向に寝た女が、静かな声でもう死にますと云う。
女は息絶え、男と再逢を誓う。男は女を待ち続け、願いは神秘的に成就する。そこに不穏な影が無いわけではない。まずもってこれは男の見た夢だろう。
な……そこで、その病人の処に死神が行く。行って、最初ァ病人の足元に座ってる。それで念力ィかけて、病人を弱らせる。早く病人を弱らせて、あの世に送るのが腕のいい死神というこった。俺なんぞ……ま、いいか。で、病人が、もういい、終わった、となると、死神のルールでその病人の枕元ン処に座るんだがな(…)
殺意!枕元で男がする腕組の含意をそう解釈る落語家がいる。
「あーあァ、嫌だ/\。嫌だなァ。働く気にもならねえ。何てえ嬶ァだ、あ奴は。亭主の顔を見りゃ"働きが悪い"の"収入が少ねえ"、果ては"能無し亭主野郎"とまで言やがった。子供もガキだい。兄妹揃って母親ァに味方きやがって肩ァ持って、父親ェ眺めてやがる。とても長屋にゃァ居られねえ。叩き出そうったって下手ァすりゃァ、当方が出されちまいそうだし、何ィ言い出すか判んねえし、寝首ィ掻かれるかも知れねえ。長屋ィ帰らなきゃァ仕事場に怒鳴り込んできやがるし、仲間にゃみっともなくて見せられる絵じゃねえし、仕事に行きたくねえし、帰る処もねえし、何で生きてるんだか判らねえ……。
死んじまおうかなァ……」
「死んだほうがいいよ」
「死んでやろう」
「そうしなよ」
「死のう」
「死ねよ」
「死のう……」
「そうだい」
「……? ……誰だ、え? 何か言ってる奴ァ」
「俺だよ」
「えっ、おっ、居やがった。お前か……、今、何か言った奴ァ。"俺が死にてえ"ったら"死ねよ""そうしな"ってなことを言った奴ァ」[引用符原文ママ]
「そうだい」
「何だ、お前は」
「死神だよ」
夢の中では腕組をして一丁前の男も、落語の国ではお誂え通りに参らない。家での威厳を失い他所での体面も保てなくなった男の口から希死念慮が零れると、死神は夢の裡での女の心の中を明かすかのような木霊echoを放ち始める。
「死のう」
「死ねよ」
「死のう……」
……
「もう死にます」
「そうかね、もう死ぬのかね」
「死にますとも」
「死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね」
「でも、死ぬんですもの、仕方がないわ」
……
これはふしぎ! 何たる主客転倒の妙! 男の命が危ぶまれ、夢の裡が垣間見えてくる。「もう死にます」と女は言えど、そこには主語が無い。死にます、死にますと言いながら誰が死ぬのか判然とさせないでいる女。男もまた。何者かに緘口を強いられているような、これは気色悪い夢。
詳細に引用する。二人の発言の主語欠落に留意すること。
腕組をして枕元に坐っていると、仰向に寝た女が、静かな声でもう死にますと云う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜実顔をその中に横たえている。真白な頬の底に暖かい血の色が程よく差して、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。然し女は静かな声で、もう死にますと判然云った。自分も確にこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込む様にして聞いてみた。死にますとも、と云いながら、女はぱっちりと眼を開けた。
もう死にます。そうかね、もう死ぬのかね。主語は消されている。「(…)消えると死ぬよ、消えるよ、消えるよ、死ぬよ」。その最中、女の鏡照日の眼が開いて事態を搔き乱す。
大きな潤のある眼で、長い睫に包まれた中は、只一面に真黒であった。その真黒な眸の奥に、自分の姿が鮮に浮かんでいる。
女を見下ろす男の姿が女の眸に映ると、男が女の眸に映る自分の姿を見ているのか、女を見ているのか判然しない。
自分は透き徹る程深く見えるこの黒眼の色沢を眺めて、これでも死ぬのかと思った。
「これ」が何を指すのか、判然と思い描こうとも叶わず、主語は忌避され、さて死ぬのは女か男か……。像はぶれて、理由も無く死を告げられて心許なくなってきた男がつれない女に縋り付く姿まで見えてしまう。女の眼居の含みもまた違ってくる。
それで、ねんごろに枕の傍へ口を付けて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね、と又聞き返した。すると女は黒い眼を眠そうに睜たまま、やっぱり静かな声で、でも、死ぬんですもの、仕方がないわと云った。
その後も主語が判然と書かれずに曖昧のままでもよい、しかし何者かが女を殺さないで居られない。
「百年、私の墓の傍に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」
自分は只待っていると答えた。すると、黒い眸のなかに鮮に見えた自分の姿が、ぼうっと崩れて来た。静かな水が動いて写る影を乱した様に、流れ出したと思ったら、女の眼がぱちりと閉じた。長い睫の間から涙が頬へ垂れた。――もう死んでいた。
男は暁の星を待ち続ける。そして、百年経って、会いましょう。けれども、第一夜の夢で死んでしまうのは、男でも女でもよかったはず。
結論、暫く会わない、で通しています。
というように、女には女の言い分があったはず。しかし、「百年、私の墓の傍に」……、取って付けたような「私の」という一言でケリがついてしまう。これが女自らの意志で発せられた言葉だと、誰が信じるか。御前が見たのはこんな夢ではない。
「そうかァ……。で、女の死神も居るのか」
「居ねえ、女の死神なんて気味がワルイや」
「そうかな……。(…)」
この女々しい死神は何だ?
夢は意気地なく語られたにすぎない。そしてこの語り口は、芥川氏の『寒山拾得』における「道具屋」の一言が、橋上に漂う六〇年代の気配を断ち切ってしまう所に受け継がれていた(なので、第一夜の夢の前半の剣呑さを改めて問うてよいわけです。次章のテーマ)。
Lis blancを見ながら前半における主語の欠落には眼を向けない、なんて、虚しい。では主語を補えば不味いかというとそうでもなく、
私が何か話をすると必ず「私ならこうする」と言います。
と、判然と「私」と記したマンダリン氏の文章が果たして同様の曖昧さに見舞われていたように必ずしも興味を損なわない。
The dreamer sits at the bedside of a woman who says she is dying.
あるいは本編の英訳、
The woman lying on her back said quietly that she was going to die.
もなかなかいい風。Sheがheを内包しているから。
But the woman said quietly and clearly that she was going to die.
もたまらない不気味さを湛えている。「判然clearly」としないのが面白い。けれども「第一夜」は一人称の夢なので、どうしても
I began to think she would indeed die, (...).
など興覚めの一文が出てきてしまう。I が夢の邪魔をしている。He began to think(...). 三人称の夢をこそ、見たい。この点the dreamerを主語に置くWikipediaの紹介文あたりが一番そこに近いように感じられるが、どうだろう。
英訳でなく邦訳で、というのが芥川氏のやり方で、「おれ」を『沼』に沈めたのは炯眼というほかない。夢の裡で男が死ぬのが判然と見えている。それだけに一人称の選択は注目されてよい。「おれ」よりも中性的な「私」とか「自分」の方が滋味深まる気がするところ、その選択の動機は何処にあったのか。
おれは沼のほとりを歩いてゐる。
おれは散歩を続けながらも、云ひやうのない疲労と倦怠とが、重たくおれの心の上にのしかかつてゐるのを感じてゐた。
『東洋の秋』と『沼』の二作が「おれ」のメランコリックな歩行を書いた同時期の作であることを思えば、「第三夜」の夢を歩きなおしてみたくもなるもの。
明治四十一年、七月二十八日の『東京朝日新聞』に現れた「盲目」は、青坊主ではないが、同年十二月の『深川の唄』にも見える。それが芥川氏の眼に留まらなかったはずはない。
阿呆陀羅経のとなりには塵埃で灰色になった頭髪をぼうぼう生した盲目の男が、三味線を抱えて小さく身をかがめながら蹲踞んでいた。
さして年老っているというでもない。無論明治になってから生れた人であろう。自分は何の理由もなく、かの男は生れついての盲目ではないような気がした。(…) けれども、江戸伝来の趣味性は九州の足軽風情が経営した俗悪蕪雑な「明治」と一致する事が出来ず、家産を失うと共に盲目になった。
三味線の音を耳に、「あきイ――の夜 」へゆく「おれ」の歩みであったと思しい。『蜜柑』は過去を尋め行く「第三夜」を典拠としていた。舞台は冬であったけれども、「走つてゐる方向が逆になつたやうな錯覚」と符号していて面白い気がする。
以下、「第三夜」の夢の回想。
六つになる子供を負ってる。たしかに自分の子である。
自分が御前の眼はいつ潰れたのかいと聞くと、(…)
自分は我子ながら少し怖くなった。
自分は黙って森を目標にあるいて行った。
自分は股の根に立って、ちょっと休んだ。
自分はちょっと躊躇した。
自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。
自分はますます足を早めた。
その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照して、寸分の事実も洩らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうして盲目である。自分はたまらなくなった。
自分は覚えず留った。
自分はこの言葉を聞くや否や、今から百年前文化五年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で、一人の盲目を殺したと云う自覚が、忽然として頭の中に起った。
「御前がおれを殺したのは今からちょうど百年前だね」
おれは人殺であったんだなと始めて気がついた途端に、背中の子が急に石地蔵のように重くなった。
人殺の一人称! 杉の根の処で「自分」が「おれ」に殺されたその瞬刻が分かるだろう。
(第四章 おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
