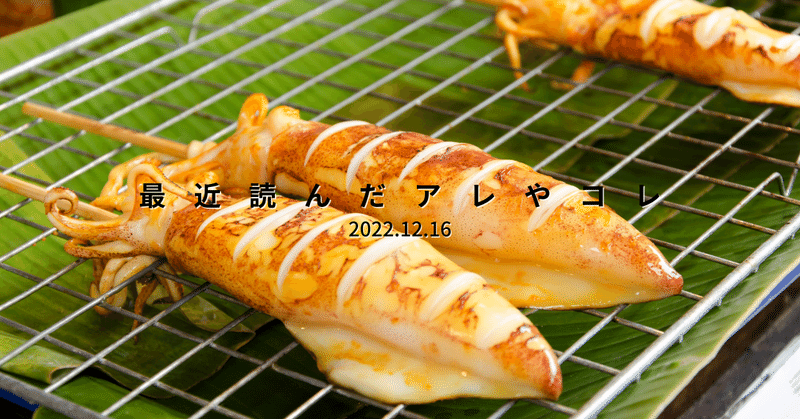
最近読んだアレやコレ(2022.12.16)
最近はポケモンで遊んでいました。紅の方。マップ上のゴースのアイコンが画面上に浮かんで消えないというおそるべき霊障に阻まれながらも、我が主人公くんは無事に青春し、気がつけば除霊も終えていた。我がパートナーのワニくんの歌が成仏の一助となったことは想像に難くありません。「ポケモン勝負」を軸にして全ての要素が美しく噛み合っていた盾の方が私は好きですが、未踏をアギャアギャ走りまわってぽんぽんボールを投げまくる本作も大変愉快な体験でした。「今、自分は冒険している」という実感が凄いよね……。デザインではマフィティフが好きですね。「ああ、こういう犬いるわぁ~!」という実在性もいいし、そこにオラチフからの進化という文脈、そしてあのあくどい笑みが加わることで、「ああ、そういうポケモンなのね」とコンセプトへの理解が鮮やかに立ち上がるのが気持ちいい。
■■■
魔眼の匣の殺人/今村昌弘
絶対の予言をもたらす魔眼が告げたのは、死者の数。閉鎖環境下で進行する「定員の決まった連続殺人」は、推理と真相を必然的に歪めてゆく。オカルトを1つ核にして組み立てられたシリーズ第2作であり、前作『屍人荘の殺人』よりもさらに堂々と、遮蔽物なく「推理小説の第一義のおもしろさ」を屹立させたその態度にはほれぼれしてしまいます。「未来が見える魔眼がある」……「では、それがあるならどんな動機が生まれるか」「どんな手法が生まれるか」「探偵はどう行動するか」「謎解きはどう組み立てうるか」……示された前提条件に対し、読者の頭に真っ先に思い浮かぶ当たり前の発想が、全てハイレベルな実践となって真正面から打ち返される心地よさ、小気味よさ。引け目や気後れが微塵もない。探偵と語り手の関係性を通じて語られるおなじみの「探偵はつらいよ」問題についても、この事件と真相から得られるものが過不足なく語られていて、特殊設定ミステリとしてのプレーンさに異物を混ぜることはありません。推理小説という筋金入りの頭でっかちをたっぷり描きながらも、その「でっかち」を綴る小説全体は均整がとれている。なんと気持ちのいい推理小説なんでしょう。スカッとするぜ。
兇人邸の殺人/今村昌弘
『魔眼の匣の殺人』がとてもおもしろかったので、まだ文庫が出てないのにkindleで買ってしまいました。シリーズ第3弾。序盤で描かれる「推理小説にありがちな曰く付きの館に、完全武装して攻め入る」という絵面のハジケぶりにケラケラ笑ってしまったし、そこから肩をすかすようにモンスターパニックが始まるジャンルハックぶりもたまらなく愉快です。「犯人は本当に狂科学者に作られたモンスターなのか……?」で、マジでモンスターが登場して登場人物を殺しまくるの悪い冗談すぎる。あらかたのおふざけが済んだ後に、それらを真顔で見つめ直し、粛々と推理小説を組み立ててゆくお行儀のよさもおもしろい。ここまでふざけた後にでも「推理小説」をまっすぐやれるものなんだ。というか、謎解きのクソ真面目さに関しては、本作はシリーズ内でも群を抜いてる気がします。ケレン味に溢れた装飾は、パズルの駒を塗り分けるように淡々とラベリングされ整理されてゆく。登場人物たちを通じて描写される息詰まる攻防と、生存者とモンスターの駒の動きを机上でぱちぱち動かしてゆく無味無臭のギャップの妙。変則的な「安楽椅子探偵」の趣向もユニークで、それが生む探偵のドラマも味付けが濃すぎず、のど越しよく食える。おもしろかったです。次作が楽しみ。
地球人類最後の事件/浦賀和宏
〈松浦純菜・八木剛士〉シリーズ、その8。復讐というカタルシスを終えてなお、残便のようにずるずるねとねと繰り返し繰り返しくすぶり続ける主人公・八木剛士の怨みと呪いが、ようやく1つの決着点を迎える巻なわけですが、どこまでも内側に向けて自分勝手に自己中心的に言い訳と責任転嫁と性欲と暴力衝動を塗り固めたその果てが、読者に心地よいもののはずはなく。この物語の全てを強姦し尽くし、虐殺し尽くそうとしているように、主人公を中心とした世界に存在するあらゆる出来事とあらゆるキャラクターに対し、不快感と忌避感をもたらす描写がなされます。読者をふるい落とすのですらない、読者に暴力を奮うように、露悪を越えた激怒をもって、ただひたすらに執拗に、呪詛が文字の形をとってゆきます。この物語は誰に対して語られているものなのか。いや、読者の存在なんておそらく最初から眼中になく、ついに今回、その周辺視野に我々が捕えられたのが悲しき不幸だったというだけでしょう。目にとまる全てに汚物と精液を吐き散らす『世界でいちばん醜い子供』は、これまで間接的に飛沫をかけていた読み手にすら、区別なく攻撃を加えるに至った。全てを拒絶し内燃し続けるこの物語は、もはや物語なのかすらよくわからないほどに、ぐずぐずに崩れ煮えている。あらゆる評価軸は全て焼き溶けた。ただ、熱と力だけがここに込められている。
生まれ来る子供たちのために/浦賀和宏
〈松浦純菜・八木剛士〉シリーズ、最終巻。『生まれ来る子供たちのために』という急に綺麗なことを言い始めた題に鼻白みながらめくったら、「知ったことか。俺は自分さえ良ければ、それでいいんだ」というエピグラフが飛んできて読者の鼻骨を陥没させる。まさにそういう最終巻であり、そういうシリーズであり、そういうキャラクターだったと思います。もはや物語なのかすらよくわからないほどに、ぐずぐずに崩れ煮えたこの小説は、結局、何を物語り、誰に物語っていたのか。読み終えたらそんなことどうでもよくなってしまったというのが正直なところです。9冊かけて書かれたストーリーは、おそらく2、3冊程度でまとめるべきものだったもののように思います。しかし、書かれた文字の全てが「八木剛士」という子供そのものであり、「松浦純菜」という子供そのものであったことは疑いようがありません。顎を外され、喉を裂かれ、2人の子供を生きたまま飲み込まされたこの陰惨な読書体験に対し、「おもしろさ」や「好き嫌い」の尺度をあてる気には私にはなれません。「〈松浦純菜・八木剛士〉シリーズを読む」ということは何だったのかと尋ねられた時、どう答えるべきなのか。私は「傷つけられた」が最適のように思います。つけられた傷は、痕に残る。こんな小説が書かれ、読んでしまったということを忘れるのは難しい。その語彙は、私の中では「特別」と似た意味を持っています。読み終わって、しまったなあ……。
