
2-2 あらかじめ回避された悲劇 ジョン・ディクスン・カー『三つの棺』

ジョン・ディクスン・カー『三つの棺』The Three Coffins(The Hollow Man) 1935
ジョン・ディクスン・カー John Dickson Carr(1906-77)
カーはクイーンと並ぶ黄金期の巨匠だが、作品傾向はともあれ、その作家的姿勢には対照的なものがある。結論からいってしまえば、カーはイギリスに移住したことによってアメリカ作家に課せられる「重荷」をあらかじめ回避した。カーの創作において、道徳的命題は余計な事柄だった。
パリを舞台にして最初の作品を書いたとき、カーの脳裏にあったのは先人ポーだけだったろう。しかしポーの時代とは比較にならないほど、パリはアメリカの知的な青年にとって身近な都会になっていた。カーは精神的亡命者ではないし、根無し草〈デラシネ〉志向でもない。彼の作品世界はイギリス社会という堅固な土壌を必要としていた。
『三つの棺』は不可能犯罪を語る上での指標的な名作だ。結末がわかっていても再読に足る作品のリストをつくっても高位にあがるだろう。複雑な解決の仕組みを理解するために三読は必要かもしれない。二件の殺人は、どちらも別種の密室状況で起こる。一つは、拳銃を撃った犯人が部屋から消失し、もう一つは、最初から姿の見えない犯人が路上で拳銃を撃って殺人を犯した、というもの。この小説は『うつろな男』というタイトルも持っていた。消えた犯人、もともと消えていた犯人は「うつろな男」だった。
地中の棺から脱け出すマジックや悪魔学の講義が重要な背景に使われる。探偵役による「密室講義」が後半に置かれていることでも名高い。ミステリのなかでミステリを論じるという「自己言及性」の早い作例だ。カーの人物たちは、自分らが作中人物であることを自覚しているばかりでなく、進んで口にする。これは「読者への挑戦状」にも増して、ミステリ空間のゲーム性を強く意識させる。モラルが入りこむ余地はない。
人間は機械トリックを成立させるための道具だ。人体が『エジプト十字架の謎』のようにT字型死体のオブジェとして使われるなら、掛け金をかける紐のような小道具として役立つのも当然だった。うつろな男、がらんどうの男なら、それも可能だ。カーの人間観は他のミステリ作家よりもはるかにラディカルに非人間的だ。ヒューマニズムはカーの世界においてはまったく無意味だ。外界からの強い切断がなくては、こうしたワンダーランドは成立しない。
徹底した切断はいかにして可能だったのか。謎が小説内ですべて解決されているにもかかわらず、カーの世界は謎に満ちている。
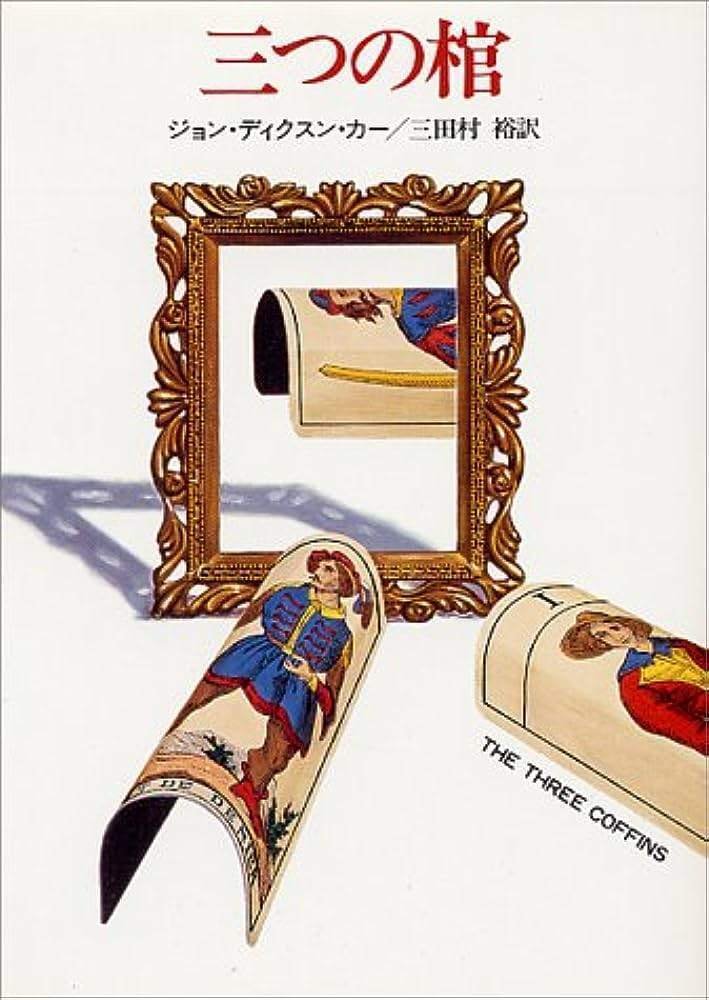
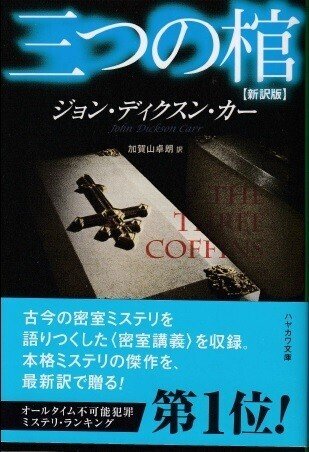
他に
『魔棺殺人事件』 伴大矩訳 日本公論社 1936
『三つの棺』 村崎敏郎訳 早川書房HPB 1955
タイトルにふさわしく、三回の改訳・新訳。その都度、マニアからの詳細な論評があった。長大にして複雑な解決編は、それ自体、高度なミステリ感応力を要求していた。
余談だが、ナボコフは、薦められて読んだ『ユダの窓』について、たった一語のネタバラシともども毒舌の蒼い焔を吐きかけている。E・ウィルソン夫妻とナボコフ夫妻の交友が濃密だったころ、彼らの話題に新作ミステリの評判がしばしばあがっただろうことは、黄金期の勢いを傍証する充分な文献たりうる。E・ウィルソンの名をミステリ界においてのみ「不朽」にしたところの駄文「誰がアクロイドを殺そうが知ったことか」は、彼の学識や批評眼の鋭さのみにとどまらない、ジャーナリストとしての処世や小説や戯曲でも成功した器用さを勘案してみれば、ミステリ実作に挑戦してみた結果(プランを練った段階だけだったにせよ)から来る「恨み節」を行間に洩れださせていると読めなくもない。
ーー以上は、『ナボコフ=ウィルソン往復書簡集 1940-1971』を散読した印象からの発想だから、精密な考証とはおのずと別のものである。
この本からの引用は、もう一箇所あるのだが、それはしかるべき回にあつかわれる予定。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
