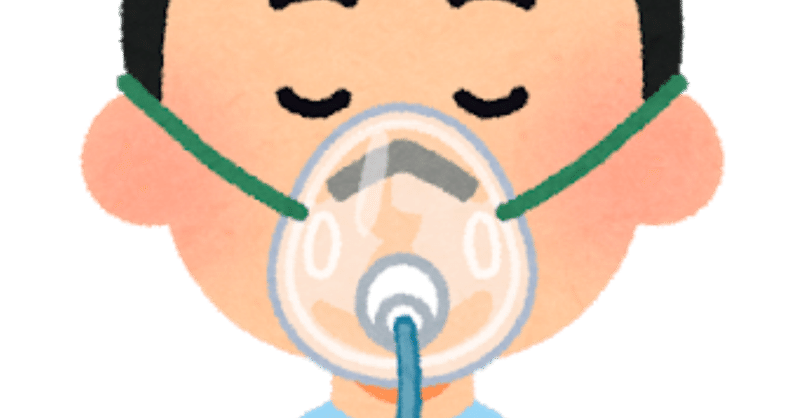
【看護過程】COPD患者のアセスメント(役割)
男子看護学生の鳩ぽっぽです
以前、アセスメントのポイントという記事を書きましたが、それでは分かりづらいと思いましたので、具体例を書いていきたいと思います。
アセスメントは最初から完璧に書くのは難しいです。自分のスタイルができるまでは、基本のアセスメントを真似して書くべきです。
そのテンプレとなるアセスメントをここでは紹介できればと思います。
今シリーズはCOPD患者のアセスメントの事例を紹介します。
※ここにでてくるアセスメントは全て架空の事例です。
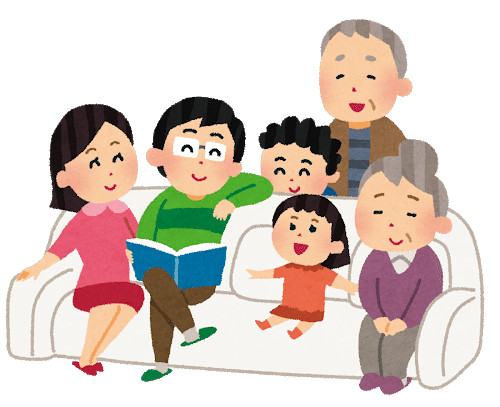
役割・関係
※この事例は架空の人物です
()は情報、太文字はアセスメントです
老年期の社会的関係の変化によって、高齢者の社会的な役割の変化が生じる。家族関係では、例えば親子関係は、子どもが親の言うことを聞いていたそれ以前の状況から、むしろ親が子供が言うことを聞かねばならない場面が増える。社会的には、職業的な役割を喪失する場合も多い。また、身体の虚弱化によって、家庭内でも社会的にも、役割が減っていく傾向がある。どのような役割を果たすことに価値を感じるかということは、個人によって異なるが、役割の変化を「役割の喪失」ととらえてることによって心理的な喪失感を感じる場合がある。このような心理的な喪失感は意欲の低下、不安感の増大などの心理的な不適応を招く大きな要因となる。老年期に応じた役割の獲得ということが老年期の生活上の大きな課題の一つである。
Aさんは(家庭では夫)という役割、社会的には(町内会役員)という役割を担っている。以前は(会社勤め)、(子育てをしていた)ことから、会社員や父親という役割を担っていたが、定年や子供の自立、その後、(孫の送り迎えなど)の祖父としての役割を果たすようにもなり、役割の変化が大きく起こっている。これらの役割の変化に適応できており、家庭内でも社会でも役割を果たしている。
役割緊張とはなんらかの原因で役割遂行(望ましい役割を果たす行動)が困難になり、行為者の心理と相互作用そのものに緊張が生じることをいう。その役割を十分に取得していないとき、精神的に不安定で役割を遂行する力がないとき、あるいはその役割をこなす客観的条件がないときに役割緊張が生じる。役割葛藤とは、同一人物に期待される役割と役割が矛盾する状況のことをいう。入院することで本来の役割を果たせなくなるため役割緊張になったり、職業人の役割と病人の役割は矛盾するため、役割葛藤に悩むことになる。
Aさんは現在(入院中)であることから、家庭内・社会的役割を果たすことができていない状態である。そのため、役割緊張や役割葛藤が生じている状態であると考えられる。
パーソンズは病人にも役割があると考えており、特徴を次のように挙げている。病人は通常の役割を果たすことを免除される、病人は病気であること自体には責任が無いとされる、病人は病気の状態を望ましくないと認識し、回復を試みる義務がある、病人は医師に専門的援助を求め、医師に協力する義務がある。
Aさんは新たに患者という役割を有しており、(疾患や治療への理解)、(積極的な治療への取り組み)、(治療に対しての意見や意思を医療職に伝える)など、現在の状態から回復しようとし、医療職に協力する姿勢をみせていることから、患者としての役割を果たしていると言える。また、実習においては(学生に対して協力的な姿勢や知識を教えようとする姿勢が見られることから)、教育者としての役割を有し、果たそうとしていることが考えられる。
家族関係は発達段階に応じて変化し、老年期においては、親や配偶者との死別、子どもの独立、孫の誕生・成長、子どもとの再同居などがある。また、社会的関係性については、老年期になると希薄となる傾向にあり、会社や地域での関わりがなく、高齢者うつや孤独死へとつながる可能性が高まる。
Aさんは家族内では夫、地域では町内会役員の役割を有しており、これを果たす上で関係を持っている。子供とは、(孫)を通じて関係性を持っており、子育ての中で三世代のつながりを有している。その中でも妻とのつながりは強く、(長く一緒に過ごしてきた)、(困難を共に乗り越えてきた)ことから、特別な関係であることが言える。病院においても、(妻が週5回面会)に来ており、その関係は繋がっている状態である。家族との関係性は良好である。
また、病院にて患者としての役割を果たしていることから、医療者との関係性は良好である。しかし、(個室入院)で、(COPDにより移動が自立していない)ことから、他の患者との関係は持っておらず、限られた関係性の中にいる状態である。孤独感を感じるリスクはある。
キーパーソンは息子であり、関係性は良好である。また、疾患や治療に対しては(自宅に戻れるようにしたい)、と理解しており、受容できている状態にある。
経済状況について、Aさんは(年金暮らし)であり、(節約しながら)生活している。酸素療法を自宅でも続けてきていることから、介護保険などを活用してできていることが考えられ、問題はないと考えられる。
結論
・家庭内では妻、家族間では祖父、社会的には町内会役員の役割を有している
・入院によって役割を果たせず、役割緊張や役割葛藤が生じている
・患者としての役割は果たせている
・実習において、教育者としての役割を新たに有し、果たそうとしている
・家族、社会と関係を持てている
・病院内では医療者以外との関係はなく、孤独感を感じるリスクがある
・キーパーソンを始め、家族は疾患や治療の受容ができている
・経済的問題はない

まとめ
今回はここまでです。
役割関係はさまざまな役割や関係が出てきますが、大きな流れとして、"それらの役割や関係が入院していることによって妨げられている"というアセスメントになります。そして、新たに得る患者という役割を果たせているか、という視点もアセスメントに必要です。
高齢者は特にそうですが、役割や関係など社会的環境が大きく変化することで健康に与える影響は計り知れないものがあります。
私たちは病院が職場のため、職業人という役割でいれますが、患者は全く異なる役割を有しなければならないのです。
これを患者の立場に立って考えられるかがこのアセスメントで問われるところだと思います。
=================
アセスメントのポイント(役割)はこちら→https://note.mu/810poppo/n/n3cb3c9ff9e56
鳩ぽっぽの経歴はこちら→https://note.mu/810poppo/n/n59147f8e4b2f
ツイッターもやってます!フォローはこちらから!→https://mobile.twitter.com/810ppo
=================
最後に、記事を最後まで読んでいただきありがとうございます!もし、ご意見やご質問、改善点、ご希望のテーマがごさいましたら、よろしくお願いいたします。フィードバックしてよりよくしていきたいと思っております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
