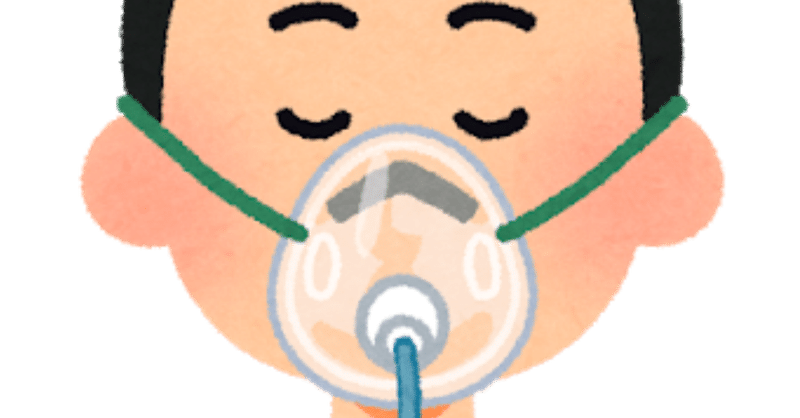
【看護過程】COPD患者のアセスメント(栄養)
男子看護学生の鳩ぽっぽです
以前、アセスメントのポイントという記事を書きましたが、それでは分かりづらいと思いましたので、具体例を書いていきたいと思います。
アセスメントは最初から完璧に書くのは難しいです。自分のスタイルができるまでは、基本のアセスメントを真似して書くべきです。
そのテンプレとなるアセスメントをここでは紹介できればと思います。
今シリーズはCOPD患者のアセスメントの事例を紹介します。
※ここにでてくるアセスメントは全て架空の事例です。

アセスメントの書き方
復習として、アセスメントの基本的な書き方を紹介します。
基本の形は「一般論→その人のアセスメント」という流れです。
最初に一般論を書き、その一般論を基に、その人はどのような状態なのかを書いていきます。
これを各項目ごと(アセスメントのポイント)に行なっていきます。

見づらくて大変申し訳ございません
ただ、大まかな流れはこのような形になります。一般論→アセスメント→一般論→アセスメント…
場合によっては、アセスメントに一般論をつける必要がないこともあります(教員がスルー、自身の体力的に無理、もう分かりきっていること)が、できる限りこの形にした方が後からわかりやすいと思います。

COPD患者の栄養・代謝
※この事例は架空のものです
()が情報、太文字がアセスメント
老年期男性に必要なエネルギーは、以下の通りである。50〜69歳の場合、身体活動レベルに応じてⅠ:2100kcal、Ⅱ:2450kcal、Ⅲ:2800kcalが一日の必要エネルギー量とされる。
※身体活動レベル
Ⅰ(低い):生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
Ⅱ(普通):座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買物・家事・軽いスポーツ等のいずれかを含む場合
Ⅲ(高い):移動や立位の多い仕事への従事者。あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている場合
Aさんは老年期前期であり、身体活動レベルはⅠであるため、1日に必要なエネルギー量は2100kcalである。現在、(普通食1600kcal)を三食、(毎食完食)していることから、1日の総摂取カロリーは4800kcalであり、必要エネルギー量を上回っている。
BMIは身長と体重の比率によるエネルギーの摂取量及び消費量のバランスの維持を示す指標に用いられるものである。50〜69歳の適正BMIは20.0~24.9の範囲である。
AさんのBMIは(19)であり、やせの部類に入る。また、(血液データより、赤血球数と総タンパク、アルブミン)の量が少なく、エネルギー、タンパク質が不足していることがうかがえる。これはCOPDによる息切れやそれに伴う呼吸筋の過剰な収縮弛緩によってエネルギーが大量に消費されていることが原因と思われる。また、(Na値も低く)、電解質のバランスが悪いことが言え、エネルギー不足、タンパク質不足も踏まえて、低栄養のリスクが高い状態である。これに対して、Aさんは(間食をする)などして、不足を補おうとしている。
食事の機能について以下の通りである老年期の生理機能の変化には嚥下機能の低下、咀嚼機能の低下がある。これにより、誤嚥などを引き起こすことがあり、誤嚥性肺炎のリスクがある。また、身体機能の衰えから、食物を運び込む能力が低下したり、認知機能の衰えから、食事を認識できないなどの問題が発生する。
Aさんは(老年期)であるが、(嚥下機能)や(義歯がないことから)咀嚼機能に問題はない。また、加齢に伴う認知機能の低下も問題ないレベルであり、食事の認識ができている。しかし、加齢変化による身体機能の低下とCOPDの労作時の息切れによって食事動作に支障をきたしている。対処として、口すぼめ呼吸や休憩を挟んでおり、自立して食事はとれている。
成人の1日に排出される水分量は、尿として1000~1500mL、不感蒸泄として約900mL、糞便中の水分(約200mL)などがある。老年期の場合、成人よりも水分保持能が低いため、これよりも多いことが考えられる。
Aさんは(毎食カップ一杯300ml)、食事のお吸い物約200ml×3、その他食事から300ml程度を摂取している。合計で1800mlであり、代謝水300mlを合わせると、水分のインアウトバランスが取れていることが考えられる。脱水の症状は見られないが、(Na値が低いことから)脱水のリスクは存在する。
食事が進まない症状になる原因には、様々あり、食道や胃・腸のように直接食べたものが通る場所の病気だけでなく、消化器の病気、慢性腎不全・うっ血性心不全・慢性閉塞性肺疾患(COPD)など腎臓・心臓・呼吸器の病気、脳血管障害などの脳や神経の病気、甲状腺機能低下症などのホルモンの病気、関節リウマチなどの膠原病、糖尿病、さまざまな感染症(結核や肺炎など)、悪性腫瘍(がん)など、体のあらゆる部位の病気によって、食事が進まない症状になることがある。また、心理的なストレスが長く続いたり、葛藤が解決されないままでいたりすると、食欲不振となることがある。
Aさんは(食欲があり)、(食事を楽しみにしている)ことから、食欲不振の状態にはないことが言える。しかし、COPDによる(食事時の強い息切れ)によって食欲が低下するリスクがある。
結論
・年齢相応のエネルギーは取れている
・COPDによってエネルギー不足が生じている
・やせの状態であり、低栄養のリスクが高い
・現在、間食をとることでエネルギー不足を改善しようとしている
・水分のインアウトバランスは取れているが、脱水リスクは存在する
・COPDの労作時の呼吸苦によって食事動作に支障をきたしているが、現在は自立している
・COPDの呼吸苦によって食欲不振となるリスクがある
まとめ
今回はここまでです。
栄養に関してはエネルギー量だの水分のインアウトだのBMIだの、計算することが多い場所です。また、正確な情報が収集できていないと、不足気味であったり、正しい値が出てこなくなります。
できる限り正確な情報収集を心がけましょう。
また、今回は体重変化などを入れていませんが、経時的に変化を見ることで得られるアセスメントもあるため、是非着目してみてください。
=================
アセスメントのポイント(栄養)はこちら→https://note.mu/810poppo/n/n023b7eba4c57
鳩ぽっぽの経歴はこちら→https://note.mu/810poppo/n/n59147f8e4b2f
ツイッターもやってます!フォローはこちらから!→https://mobile.twitter.com/810ppo
=================
最後に、記事を最後まで読んでいただきありがとうございます!もし、ご意見やご質問、改善点、ご希望のテーマがごさいましたら、よろしくお願いいたします。フィードバックしてよりよくしていきたいと思っております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
