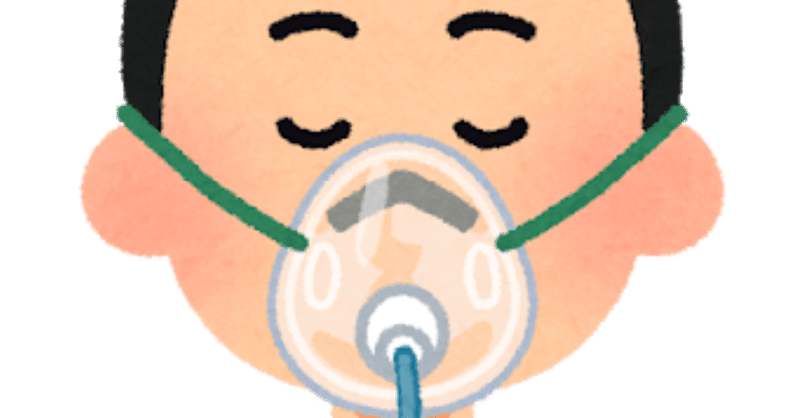
【看護過程】COPD患者のアセスメント(認知)
男子看護学生の鳩ぽっぽです
以前、アセスメントのポイントという記事を書きましたが、それでは分かりづらいと思いましたので、具体例を書いていきたいと思います。
アセスメントは最初から完璧に書くのは難しいです。自分のスタイルができるまでは、基本のアセスメントを真似して書くべきです。
そのテンプレとなるアセスメントをここでは紹介できればと思います。
今シリーズはCOPD患者のアセスメントの事例を紹介します。
※ここにでてくるアセスメントは全て架空の事例です。
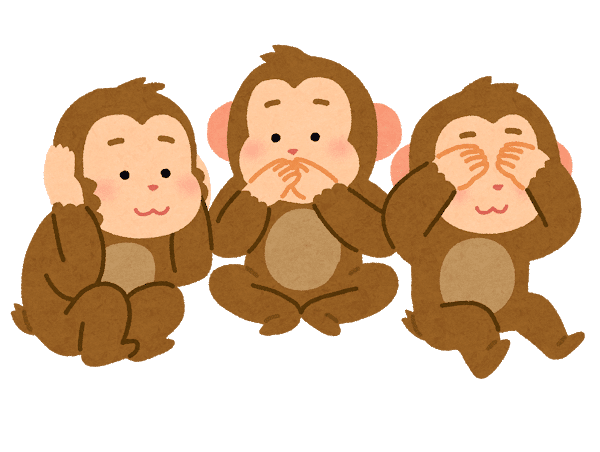
認知・知覚
※この事例は架空の人物です
()情報、太文字アセスメントです
認知とは理解、判断、論理などの知的機能のことを言い、五感(視る、聴く、触る、嗅ぐ、味わう)を通じて外部から入ってきた情報から、物事や自分の置かれている状況を認識する、言葉を自由に操る、計算する、学習する、何かを記憶する、問題解決のために深く考えるなどといった、人の知的機能を総称した概念である。老年期の認知機能は個人差が大きく、また、分類別でも差があるが一般的に低下がみられる。種類には記憶、遂行、言語理解、判断能力がある。
Aさんは(老年期)であることから、認知機能の低下が考えられる。しかし、(認知症がないこと)、(スムーズにコミュニケーションがとれること)、(治療について理解し、望ましい行動がとれていること)から、低下の度合いは著しくないことが言え、認知機能が維持されていると考えられる。Aさん自身の予防行動として、(計算ドリルを毎日解いている)ことが影響している可能性がある。
記憶には種類があり、まず、短期記憶と長期記憶に分かれる。短期記憶は短時間、短期間のみ記憶されるものであり長期記憶は長期間記憶されるものである。長期記憶にはエピソード記憶、意味記憶、手続き記憶などがある。エピソード記憶は思い出であり、過去の出来事の記憶である。意味記憶は知識であり、一般的な常識や覚えた知識が該当する。手続き記憶は物の使い方の記憶であり、箸の持ち方や電車の乗り方などが該当する。この中で最も残りやすいのが手続き記憶で、次にエピソード記憶、最後に意味記憶である。
一般的に加齢変化によってこれらの記憶力は低下するが、今まで覚えていたエピソード記憶や手続き記憶は残りやすい、特徴がある。
Aさんは(老年期)であり、(物事を一瞬忘れる)など記憶力が低下していることが考えられる。しかし、(過去の自分の話をしたり)、(知識を披露したり)、(自身の治療について適切な行動を覚えている)など、長期記憶は保持されており、記憶力が十分にあることが考えられる。
また、(治療内容を覚え、)(治療への意見を述べたり)、(いつ、どこかが言える)など、理解力、見当識もあることが言え、意思決定能力を有していることが考えられる。
老年期の加齢変化には感覚機能の低下が挙げられる。感覚機能は視力、聴力、味覚、嗅覚、体性感覚の低下がある。
Aさんは(老年期)であり、(眼鏡の着用)、(小さな声が聞こえない)、(味が薄く感じられる)など、感覚機能が低下していることが考えられる。しかし、(スムーズにコミュニケーションがとれている)ことや(眼鏡の着用によって物が見えている)ことから、日常生活に大きな支障をきたすものではない。
また、疾患による疼痛や痺れに関しても特にない。
結論
・認知機能は維持されている
・長期記憶は保持されている
・理解力を有しており、見当識は正常
・意思決定能力を有している
・感覚機能は低下しているが、大きな問題はない
・疼痛、痺れなどの異常知覚はない
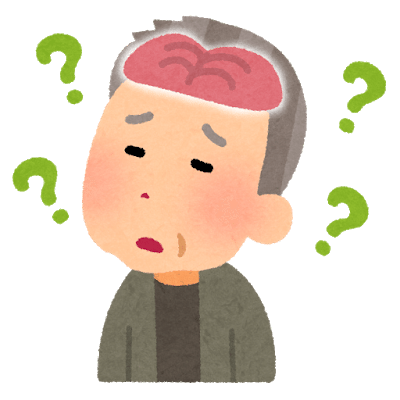
まとめ
今回はここまでです。
少しずつ少なくなってきたと思いますが、項目が少なくなるにつれて、全体の分量も少なくなっていきます。
今回は認知機能と感覚に大別できますが、認知機能にも種類があるのがポイントです。
これらは人によって大きく変わるため、アセスメントの項目では一般論とは正反対のことを言うこともあります。
以上の点を踏まえて、アセスメントを進めてみて下さい。
=================
アセスメントのポイント(認知)はこちら→https://note.mu/810poppo/n/n7f77a17b9350
鳩ぽっぽの経歴はこちら→https://note.mu/810poppo/n/n59147f8e4b2f
ツイッターもやってます!フォローはこちらから!→https://mobile.twitter.com/810ppo
=================
最後に、記事を最後まで読んでいただきありがとうございます!もし、ご意見やご質問、改善点、ご希望のテーマがごさいましたら、よろしくお願いいたします。フィードバックしてよりよくしていきたいと思っております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
