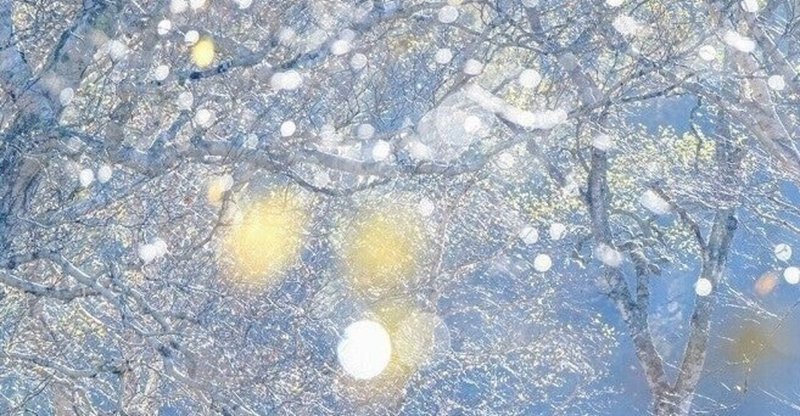
【小説】花のように泡のように
うっすら色のついた唇が、別のひとみたいだと思った。
カウンターに並んで座っていると、細い肩と首筋のあたりから、降り積もった雪の匂いがする。この灰色の街にはない、彼女の故郷の匂いだ。
「わたしもお酒が飲めますよ、先輩」
帰省の間に誕生日を迎え成人式に出席してきた彼女は、得意気な顔でレモンサワーのグラスを僕のジョッキにカチっと合わせた。おおっぴらに居酒屋で摂取するアルコールに、耳たぶがほんのり赤い。首元に光るシルバーのネックレスが、色づいた肌に映える。
「あれ、式で、着物はきたの」
「振袖ですか?」
まあ一応と、関心なさそうに彼女は呟きながら軟骨のから揚げを口にした。彼女に骨まで食べられる鶏は前世で大変徳を積んだに違いない。
小柄な彼女に似合うのは、どんな柄の振袖だろう。派手すぎず、でもたくさんの花が散りばめられていて、春が芽吹くような淡い色をまとった彼女を想像する。
「友だちには会えた?」
「仲良しの子と、少しだけ」
口についた油をぬぐったナプキンに、かすかに色が移る。薄い桜の花びらのような唇を見つめていると、彼女が本当に大人になってしまった現実が隣にあると気づいて、胸の奥がチリチリと焦げた。
成人式の会場で同級生を見つけてはしゃぐ彼女。標準語にはないイントネーションで話す彼女。もしかしたら、僕の知っている笑顔で、僕の知らない彼に駆け寄ったのかもしれない。
「幸せそうだ」
僕のつぶやきに、彼女は目を細める。それから、頬杖をついて僕の顔を覗き込むように笑った。挑発でも憐みでもない、幼稚園児をあやすような、つややかに湿った黒い瞳。この瞳になら、僕は吸い込まれてもいい。
彼女は僕の大学の後輩で、五日前にハタチになったばかりで、地元に婚約者がいた。そして困ったことに、僕の好きなひとだった。
***
彼女と出会ったのも、今日みたいに街が冷たい色に染まる冬だった。
僕が働いている本屋に、新しくアルバイトとして入ってきたのが彼女だった。
大学から歩いて五分。目抜き通りを横に逸れ、木造の建屋をリフォームしたこの店は、品揃えの良さで人気があった。ベストセラーはもちろん、構内の生協とは違う書籍のラインナップに惚れて通い詰める学生も少なくなく、僕もその一人だった。ただし、仕送りを受ける学生に金はない。読みたい本のタイトルと値段とに睨めっこしていた大学一年の僕の目に飛び込んできたのが、「アルバイト募集」の張り紙だ。
その翌週に緑色のエプロンをつけた僕は、本好きだからといって本屋で働く適性があるわけではないと気づく。カバーを素早くかける手先の器用さ、お客さんのうろ覚えのタイトルから本を探す記憶力、重い本や雑誌を棚に品出しする体力、どれも僕には揃っていなかった。唯一あったのが、ただ続ける忍耐力だ。
倉庫作業で背中と腕が筋肉痛になっても、仕事場に来るのが嫌になることはなかった。お客さんに本を探すのが遅いと怒られても、自分の無能さを呪うことはなかった。けれど人を待たせるのは申し訳ないから、部屋の壁にフロア図を貼った。
人によっては僕の姿を見て、鈍感とか、楽天的すぎるとか言うのかもしれない。ただ僕は、時間が流れて毎日が積み重なっていくのなら、状況は変わっていくのだろうと思っていた。そうやって気づくと、多くのアルバイトのメンツは入れ替わっていて、バイト歴二年目に入る頃には僕の胸には色の違うバッチがついていた。
ある日バックヤードで雑誌のビニール掛けをしている僕のところに、店長が「今日からスタートするバイトさん」と彼女を連れてきた。「この人バイトリーダーだから、なんでも聞いて」と言い残して去っていく。
髪を後ろでひとつに結わえ、糊の利いたエプロンをつけた彼女は、小声で「よろしくお願いします」と頭を下げた。緊張できゅっと体を固くしている。その割には、長いまつげに縁どられた涼しげな瞳でまっすぐに僕を見る。
「冬が、似合いそうな……」
僕の口から出た言葉に、彼女は素直に怪訝そうな顔をした。僕は動揺を表に出さないように「苗字ですね」と付け加えた。彼女の胸には、『白椿』と書かれたバッチがついていた。
初対面で変な奴と思われなかったのは、単純に僕が仕事ができたからだ。
店には、夕方になるとひっきりなしにお客さんがやって来る。一般の文芸書はもちろんのこと、おとぎ話に出てくるお菓子のレシピを記載した『おとぎの国お菓子辞典』、スウェーデン・ストックホルムの旧市街地での日々を記した明治の文豪のエッセイ『ガムラスタンの猫と夏』、マンガに登場する実在しない本のタイトルを延々としるした『じつは、ない』など、質問をすいすいさばいていく僕の隣で、彼女は一言一句聞き逃さないように大きく目を見開いてメモをとる。
うっかり常連さんにつかまってフロアに戻ると、彼女はちょうどお客さんから声をかけられていた。小柄なおばあさんにあわせて、固い表情のまま身をかがめる。子ども、お弁当という単語が僕の耳にも届く。彼女は手の中のメモを一瞥してから、うんと頷いたあと、先ほど僕がお客さんを案内した趣味実用書のコーナーに向かっていく。彼女とおばあさんの歩幅にあわせて、僕もさりげなくゆっくりと後を追った。
閉店時間になりレジ締め作業をしている僕のところに、彼女がやってきて「今日はありがとうございました」と頭をさげた。声は最初聞いたときよりも、はっきりと通るようになっていた。
「初日、がんばったね、接客」
僕の言葉に、疲れていた彼女の表情がパッと明るくなった。わからない作業には不安の色を隠さない彼女だけれど、飲み込みはとても早かった。何より一度教えたことは、ほとんど忘れない。
「僕なんかより、ずっと筋がいい」
彼女は、一瞬、目をぱちくりさせてから、笑った。そうか、これが彼女の接客用じゃない笑顔なんだと思った。音のない本屋の片隅に、儚い花が咲いていた。
ほどかれた長い髪が、自動ドアの向こうに消える。彼女と入れ違いに、まっさらな冬の空気が流れ込んできて僕の胸をくすぐった。やっぱり、続けていると物事は変わってゆく。ほんの少しだけ、思いがけない方に。
***
現代労働組合論や英文学原典講読の授業で居眠りばかりしてしまう僕は、社員に間違われるくらいバイトに精を出していた。だから自然と、彼女がシフトに入る日は僕もいた。
彼女の口から出た好きな作家の本で未読のものがあれば、積極的に手にとった。そして彼女も同じことをした。二人で品出しをしながら、不意にでた僕の発言にくすくすと笑う彼女との距離を、ただのバイト仲間に保っておくほうが難しい。そんな気も、必要も、まったくないと思っていた。だって僕らは、完璧に若いただの男女だったのだから。
彼女が僕の部屋にきたのは、バレンタインの日だった。「いつも、ありがとうございます」と控えめな字で書かれたカードと、青いリボンでラッピングされた小箱を、閉店後のレジの中で渡された。お礼に読みたがっていた本をあげるよ僕は言って、バイト帰りに店から徒歩十分の僕のアパートに彼女を誘った。
とっぷりと暮れた外はまだまだ寒くて、彼女はマフラーをぐるぐると巻く。自転車を押す僕と同じ速度で歩く彼女が、さえずるように笑う度に隠れた口元から白い息が漏れて夜の住宅街に溶けた。見上げると満月が僕らの後をついてきている。僕は、彼女の形のよい唇を無性に見つめたくなった。
コンビニで買った缶ビールとリンゴジュースを、楕円のローテーブルに並べる。肩が触れる距離に座ると、寒さで固まった互いの身体が、ゆっくりとほどけていくみたいだった。
彼女は子どもみたいにポテチの袋を開けた。「お酒、飲んだことない」と僕の缶ビールを一口なめて苦い苦いと騒いでいたから、僕はリンゴジュースを喉の奥に流し込んで、体を右隣に傾けて彼女の唇にキスをした。
苦くて甘いねとクスクス笑い合って、狭いシングルベッドに二人で潜り込んだ。彼女の肌は、白くて、やわらかくて、あたたかかった。
しっとりと汗ばんだ、彼女の華奢な指を、いっぽんいっぽん丁寧に舐めているとき彼女が言った。
「わたし、婚約者がいるの」
灯りを消した冬の部屋が、一瞬、夜空に放り出されたみたいに静かになる。それからすぐに、静けさの片隅から悲痛な叫び声が聞こえてきて、耳の奥で鳴り響いた。でも僕は、ぼくの思ったことを口にした。
「うん。好きだよ」
彼女の左手の薬指を甘噛みする。少しだけ、震えていた。僕らは不完全なひとりのまま、二人で一つになることを選んだ。
その夜、あたたかなベッドのなかで、僕は冷たい夢を見た。
台所から聞こえる包丁の音とカレーの匂い。玄関にランドセルを放って、僕は母のもとに駆け寄る。エプロンの裾を引っ張り、僕は何かを言う。止まる包丁の音。母の口元がかすかにふるえている。僕は心配になって、同じ言葉を繰り返す。僕の手を振り払い、こちらに向き直った母が、口を開く。
「どうして、あなたはそんなにやさしくないの」
そして鍋が噴きこぼれる。
目を開けると暗闇だった。とっさに動かした手に、長い髪の毛が触れる。
忘れても繰り返し思い出される夢のなかで、小学生の僕が何を言ったのか、さっぱりと覚えていなかった。しばらくしてから両親は離婚した。僕は知らない町に引っ越した。一人になった教室で、僕は黙々と本を読んだ。教室の後ろにある学級文庫はもちろん、図書室の年齢相応の本棚を制覇し高学年むけの棚に手を伸ばす頃、「その本、おもしろい?」と前の席の男の子に声をかけられた。僕は、新しい苗字で呼ばれてもすぐに反応できるようになっていた。
もしかしたら僕の一言が離婚の引き金になってしまったのかと、布団をかぶって寝れない夜もあったけれど、成人してから聞いた事の顛末は、母と祖母の確執や、見えないところでひび割れていた父との亀裂で、たとえ僕が僕じゃなかったとしても、離婚は避けられなかったのだと腹落ちするものだった。
ただ、僕の記憶にある母の言葉だけ響く台所を思い出すとき、母の記憶には、きっと僕の言葉だけしかないのだろうと思う。
どこまで行っても途方もなく長く思える人生の中で、僕が忘れてしまう言葉と忘れられない言葉は、どちらが重いのだろう。言葉は受け取った人に、しこりのように残る。
澄んだ光がもうすぐ外の世界を照らす冬の明け方に、僕は、ベッドのなかのぬくもりを抱きしめる。
***
僕らは二人でいるとき、たまに彼女の身の上を想像して遊んだ。
「実家が執事のいるようなお金持ちで、箸も持たない深層の令嬢」
「いまどき、マンガですらない設定ですよ」
「隣の家に幼馴染がいて、夜中にベランダ越しに会話する」
「おとなりまで、車で十五分かかる田舎なんです」
僕の口から出るデタラメのなかで、玄関を開けると突進してくるハスキー犬を室内飼いしている空想が、彼女のいちばんのお気に入りだった。
バイトが終わると、二人で並んで僕のアパートに帰った。手をつなげるからという理由で、自転車はめったに使わなくなった。彼女が好きなポテトチップスはのりしおで、アイスクリームはバニラ。目玉焼きには醤油で、トーストにはイチゴジャム。
本屋からアパートまでの道の、だれかの家の梅の蕾が膨らみ始めてから、ゆっくりと夜の空気が緩んでいって僕らは順調に日々を重ねた。やがて春がきて川べりで花見をしたり、長雨に辟易しながら彼女が足の爪を塗るのを眺めたりした。そして大学の試験が全て終わって、水着や浴衣の単語が学食に飛び交うころ、彼女が言った。
「ちょっと帰省してきますね」
夏休みがはじまったというのに、僕にはバイトしかやることがなかった。クーラーの効いた店内で、せっせと品出しをする。新刊コーナーで大輪の花火が描かれた表紙が目に留まった。彼女が好きだと言っていた作家の新作だった。僕は、二冊買った。
彼女はきっちり二週間で戻ってきた。お土産だといって、笹団子をくれた。ずっしりした笹団子の山は僕には多すぎたし、あんこの甘さは冷たい麦茶には合わなかった。もちもちと咀嚼する彼女の横顔を眺めるうちに、浴衣を着たのかどうか、聞きそびれてしまった。
バイトもなく彼女との予定も合わなかった日、僕は大学に向かった。図書館はいつだって静かで好きだ。それに、クーラーもちゃんと効いている。卒論で必要な本を見繕ったあと、自販機で缶コーヒーを買って中庭に出た。そこで、彼女を見つけた。
彼女は藤の木の下のベンチに座っていた。僕からは後ろ姿しか見えない。けれども結った髪からのぞく、白くて細いうなじは、たしかに彼女だったし、耳元に当てているスマホの猫のケースも、彼女であることの証明だった。
課題でもやりに来たのだろうかと、僕はベンチに近づいた。あと数歩の距離で、彼女の声が耳に届いた。
「しょうちゃん」
やわらかくて丸い、僕の名前を呼ぶときと同じ響きで、彼女は知らない名前を呼んでいた。僕は息を止めて、ゆっくりと後ずさりする。なるべく足音を立てないように図書館に戻り、リュックをとって自転車置き場に向かう。日差しが僕の背中を刺す。
聞いたことのない、彼女の方言訛りが耳に残っている。
たった一言に、僕が知らない彼女のこれまでが詰まっているような気がした。スマホのむこうの相手に話しかける笑顔が想像できてしまう僕は、ペダルを力いっぱい踏んだ。
彼女の婚約者のことは、何も知らない。どんな人かも、どんな関係かも。いつ結婚することになっているのかも。聞けば、きっと彼女は答えてくれたと思う。けれど、僕らのあいだにその情報は必要のないものだった。僕は、聞かずに彼女と続ける世界を選んだ。
アパートのドアを開けると、蒸し暑い空気が僕を包んだ。機械的にエアコンのスイッチを入れ、シングルベッドに仰向けに寝転がる。室外機の音と、セミの鳴く声が耳にまとわりつく。どれだけ目を閉じて息を潜めても、僕の胸の内が静かになってくれない。じわじわと傾いていく夕陽を感じながらじっとうずくまる。やがて、ドアベルが鳴った。開けると、胸元に紙袋を抱え、腕にビニール袋を下げた彼女がいた。
「メンチカツ買ってきました」
紙袋からは、香ばしい脂の匂いが漂ってくる。控えめに見積もっても、二人前には多すぎる量が入っていると思う。
「……なんで?」
「おいしそうだったし、好きかなと思って」
「……そっちは?」
「ビールとジンジャエール!」
袋のなかで缶がぶつかる音が、僕の胸を鳴らす。
厳しい夏の日差しはもう姿を潜め、空は濃い青に染まっていた。電気をつけなくても、彼女がいる玄関は明るかった。
僕らは、冷蔵庫で干からびそうになっていたキャベツを見つけ、救出するぞと叫びながら千切りにして、熱々のメンチカツをつまみ食いした。なんなら、台所に立ちながらビールとジンジャエールも飲んだ。キャベツを皿に敷いてメンチカツを盛り付けて、なんか嘘みたいだねと笑いながらむしゃむしゃと食べた。
それからシャワーを浴びて、シーツを変えたばかりのシングルベッドにもぐりこんだ。 うっすら湿った鎖骨からは、石鹸の香りがする。僕は鼻先を押し付けてめいっぱい肺に吸い込みながら、やっぱり彼女にはハスキー犬が似合うと思った。
「親の借金」とか「家のしきたり」とか、どちらかといえばあまりよくない方の彼女の身の上を考えたことはある。でも何度繰り返そうと、今日みたいに小さな口でメンチカツにかぶりつく姿や、僕の手にすべてを委ねるように肌を染めてよろこぶ体には、好都合なハッピーエンドを創り出す不幸なシナリオは似つかわしくなかった。
彼女が僕を呼ぶ声は、深くてあたたかく、雪のようにはかなく消えてしまいそうで、しんしんと包み込む静けさがあった。切ない吐息が鼓膜に触れる瞬間に名前をつけるなら、「愛」がよかった。その静けさが、たとえ僕ではない男の名前を呼ぶ声に含まれていたとしても、だ。
いつの間にか眠ってしまった彼女の髪をなでながら、彼女が実家の玄関を開けてハスキー犬に飛びつかれる幸せを願った。目を閉じると、遠くでヒグラシの鳴く声が聞こえる。二人でいる季節がまた、ひとつ過ぎようとしていた。
***
レジの店員さんに、ごちそうさまでしたと感じの良い挨拶をして、彼女は水色のマフラーを巻く。見たことのない模様のやつだ。首元に光っていた、僕がクリスマスに贈ったネックレスの星が、あたたかそうな毛糸で隠れてしまう。
この街の冬だって、十分に寒い。店を出た途端、冷たい空気が頬刺す。ネオンがやけに眩しい夜を酔っぱらいのサラリーマンたちが通り過ぎていく。春が来たら、僕もあの一団に仲間入りをする。ネクタイ似合わないですねと、彼女は笑うだろうか。その朝まで、彼女は隣にいてくれるだろうか。
半歩後ろにいた彼女が、跳ねるように僕のコートのポケットに手を突っ込んできた。細くてならかな指先を、僕は絡めとる。
「日本酒を買ってきました」
体重を僕に預けて、彼女が言う。
「お土産?」
「そう。あと、ゆべし」
「ゆべし?」
「うん、甘いの。日本酒に合うんだって」
「ふうん」
僕はゆべし、と、もう一度口に出してみる。少しだけ愉快になるような気がした。
「おじいちゃんが好きだったの」
「ゆべしを?」
「うん、なにかあるとね、日本酒と一緒に飲んでたの。だから」
レモンサワーの分だけ、彼女の足取りは夢見心地だ。歩くスピードを、ゆっくりにする。長いまつげが、夜風に震えている。
「一緒に、飲みましょうね。先輩」
彼女の指が強い意思を持って僕の手を抱きしめた。
吸い込んだ冬の空気に胸を刺されたようになって、声が固まる。僕と結びついたものが、彼女のなかに増えていく。恋人であれば、過ごした時間の分だけ思い出が増える、そんな当たり前の話だと思っていた。でもきっと、彼女の中に降り積もっていく景色は違う。いつか溶けてしまうものとして、それでも消えないように、傷跡ではない印を、残そうとしている。
「あ」
彼女がネオンの看板を見上げたのにつられて、僕も夜空を仰ぎみた。灰色の雲に覆われた狭い空から、ちらちらと粒が舞い落ちてくる。
「きれい」
形を保てなくなった雪の欠片が、彼女の手のひらですうっと崩れて消える。
「こんなふうに、降るの? 住んでいた場所にも」
僕が尋ねると、はじめて会ったときのように、彼女は大きな目でまっすぐに僕を見た。
「ううん、もっと大きくて湿っていて、こんなに軽くないの。部屋の窓から見える田んぼが、遠くのほうまで真っ白でぜんぶが眠っているみたいなの。でも、雪の降る音だけが、聞こえてる気がするの」
僕の頭のなかに、机に参考書を広げホットミルクをすする今よりも少し幼い彼女が浮かんでくる。冬は、好き? と尋ねたら、彼女はどうでしょう? と、もう一度夜の空を見上げた。
「青くてピンと空が晴れた日にね、風が吹くと積もった雪が舞ってきらきらするの。そういう、冬だけの光を見ると、なんだっけ、おばあちゃんから聞いた言葉が、ぴったりだなあって……」
風花、と僕は思う。
もっともっと幼い彼女が、子犬のハスキー犬と道端の雪に足跡をつける姿がよぎって、僕は言葉を探す。つないでいくための言葉を、どうしようもなく探す。
「でも、春は、やっぱりうれしい」
すとんと、僕の肩と手に彼女の体重が落ちてきた。
髪の毛とマフラーに、雪の結晶がきらめいている。そのいくつかを僕は指先で払って、ゆき、と言った。うん、と彼女が頷く。もう一度、好きと愛をつぶやくのと同じリズムで、「ゆき」と口にしてみる。そうやって僕は、何度も彼女の名前を呼ぶ。
灰色の街の隙間埋めるように、粉雪が降り注ぐ。アスファルトを覆った白は、朝陽に照らされて泡のように消えるだろう。
肩にもたれかかる彼女のマフラーの隙間から、息が白くなって漏れた。僕は顔を近づける。マフラーをずらすと、彼女の形のよい唇がほほ笑んでいる。
まぶたの裏に、はらはらと変わっていく夜を焼きつける。街は静かに音を失っていく。散る花のような雪に包まれて、僕らは、ポケットのなかでつないだ手を離せずにいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
