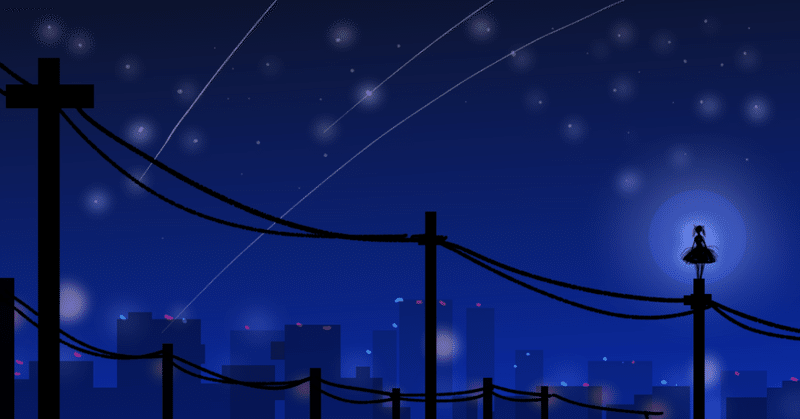
海のむこうの小さな街のシアターにて
小さな仕事部屋で、窓の外の風にゆれる巨木の枝を見ながらパソコンに向かっていると、自分が異国にいることを忘れそうになる。
私はニュージーランドに暮らしていて、夫は日本人で、娘はこの国で生まれて育つ6歳の小学1年生。
親の私が知る感覚とは、異なる社会で育つ彼女。
娘が小学校に入学する前、私は彼女が「新しい環境になじめるのかな」と心配していた。いまのところ、親の不安はどこ吹く風で、娘は毎日笑顔で過ごしている。
靴を履いて登校したのに、なぜか帰りは裸足で教室から飛び出してくる娘。神経質な私や夫では与えられない、この社会の「ゆるさ」が、彼女の持つ好奇心や冒険心をうまく伸ばしてくれているのかなと思う。
*
先月末、娘の学芸会を観に行った。
娘の小学校では2年に1回、全校生徒で行う学芸会を開催するのが習わしになっている。200人弱の生徒数という小規模校だからこその成せる技だ。
この学芸会のスタイルが、私の知っているものとはだいぶ違った。あまりにも「違う点」が多すぎたので、一覧にしてみよう。
・学芸会の開催場所は街のミュージカルシアター(400人収容、2階席あり)
・観劇チケットは有料、1枚$13(約1,000円)
・平日の夕方6時~7時半の公演
・まさかの2日間開催
・衣装、小道具、舞台装置、音楽、振り付け等、膨大な数の親がボランティアでお手伝い
・シアター内の売店でアルコールを購入して呑みながら観劇できる
200名の生徒の親だけでなく、親せき、祖父母、中学生以上の兄弟、親の友人が連れ立って観にくるものだから、当日のシアターは町おこしレベルで賑わっていた。
もちろん、私と夫も2日分のチケットを購入し、娘の「はじめての舞台」を見るべくいそいそと出かけた。
*
歴史あるアール・デコ建築のシアターには、座り心地が快適とはいえない赤い座席が並んでいる。身長の低い娘の姿がよく見えるようにと、3列目の真ん中に座り、幕が上がるのを待つ。
演目は、ディズニー映画のパロディ。ミュージカルスタイルで、主要キャストを演じるのは、校内オーディションを勝ち抜い5年生と6年生。高学年の子ほどソロダンスや見せ場があり、低学年の子はグループダンスだ。
娘の出番は2回。事前に、ペンギンの踊りだと娘から聞いていたが、詳細は定かではない。
開幕時間を数分すぎて赤い幕がするすると上がる。驚いたのは、その演技レベルの高さ……ではなく、観ている親のテンションだった。
まず、拍手が多い。ちょっとした歌があれば拍手が沸き起こる。それから、客席の歓声。出演者が多いグループダンスほど、我が子の勇姿に沸いている大人も増えるから、歓声が大きくなる。
ピュー!と口笛が聞こえたかと思えば、フッフー!とライブ張りに叫ぶ親。
子どもたちのダンスやセリフは、けして上手とはいえない。むしろリズムも手足の角度も不揃いだ。でも、笑顔で懸命に踊る子どもたちの姿に、観客席のあちらこちらで拍手と声援があがる。
なんだろう、とっても楽しい。
開始5分で、娘が躍る1年生のグループが登場した。みな、ペンギンの帽子をかぶり、衣装までお揃いだ。舞台の端っこで見つけた娘の姿は、相変わらず一番小さい。『ベイビーシャーク』の音楽にのせて、ペンギンたちが躍る。その姿は、愛らしさそのものでしかない。
湧き立つ親の歓声。子どもたちの動きにあわせて大きくなる拍手。雰囲気につられ、私もつい「フッフー!!!」と声をあげてしまった。スマホの動画にテンションの狂った自分の声が入ってしまい、ちょっと恥ずかしい。
数分のダンスが終わり、舞台が暗転して子どもたちが袖に引っ込んでいく。
「娘ちゃん、暗いとこ怖くないんだね」
となりに座る夫が、なんだか親バカですねとしか言いようのない感想をもらした。
そうか。この、どうしようもなく劇場を包むキラキラとした空気は、きっとこの場にいる大人たちが抱く愛だ。
子どもの成長を眺める、2年に1度の晴れ舞台。あんなに大きくなってと、心の涙腺を潤ませながら見ている大人が、ここにどれだけいるのだろう。
たとえ失敗しても、リズムが合わなくても、絶対に子どもの笑顔に惜しみない拍手を送るのだと、強く優しい想いが劇場を包んでいた。
終幕5分前になって、娘のグループが再登場。衣装を変え、黒Tシャツと黒ズボンにビビットピンクのスカート。Mark Ronsonの『Uptown Funk』にのせて、自信満々の笑顔で娘がリズムを踏む。
洋楽をほとんど聞かないけれど、この曲なら一生忘れられないプレイリストに入れてもいい。親の目に強烈に届く可愛さに胸をときめかせ、学芸会は盛大な拍手に包まれ終わった。
*
一度シアターを出て、裏口から子どもたちが待つ舞台裏に娘を迎えにいく。中に入ると、すっかり着替えを終えた娘が、頬を上気させて友だちと遊んでいた。
声をかけ、ぎゅっとハグをして、よくがんばったねえ、上手だったねえ、可愛かったよと、思いつく限りの称賛をかけてワシャワシャと娘の顔をなでる。
娘は、褒め言葉が自分に浴びせられるのを知っていた、という自信に満ちた目で笑い、さらに頬を赤くさせた。
ああ、この表情をみたことがある。
誰かが、自分の力でなにかを成し遂げたとき。心のなかに、ゆるぎない自信の種を芽吹かせたとき。人は、輝いているとしか言い表せない、とてもよい顔をする。
この日、はじめて娘は見せてくれた。親の手を離れた場所で、成長するということ。この先、もっともっと、学校から先生から友だちから、かけがえのないものを得て、娘がそれを心の栄養にして育つということ。親の側だけではなく、社会のなかで大きくなるということ。
6年の月日のなかで、娘が外とつながり、少しずつ広げていった彼女の居場所を、私たち親に見せてくれた日だった。
楽屋の扉から外にでると、辺りはすっかり暗くなっていて、南半球の初春の冷たい空気が興奮しきった子どもたちを優しくなでる。私と夫の手を握り、見慣れない夜にジャンプする娘の姿から、どれだけ特別な一日だったかを知る。
私は、エンドロールで舞台の袖から袖へと走りぬけていった子どもたちの姿を、思い浮かべていた。
全校生徒、200名ちょっと。この国で生まれた子も、そうでない子もいる。きっと、数か月滞在するだけの留学生もいる。どこから来たなんてルーツはわからない。
どの子も、みんな笑顔だった。その笑顔に、私たち大人は、大きく手を鳴らし続けた。赤い幕が下りるまで。
小さな街の夜を照らすシアターから、ひとり、またひとりと、あたたかな家へと帰っていく。けして消えない、いつかふと思い出されるような幸せの種を胸に。
今宵、間違いなくシアターは、この街のなかで愛というものに満ちた場所のひとつだった。続く2日目の公演が、おなじくらいの喜びと笑顔に包まれていたことは、言うまでも、ない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
