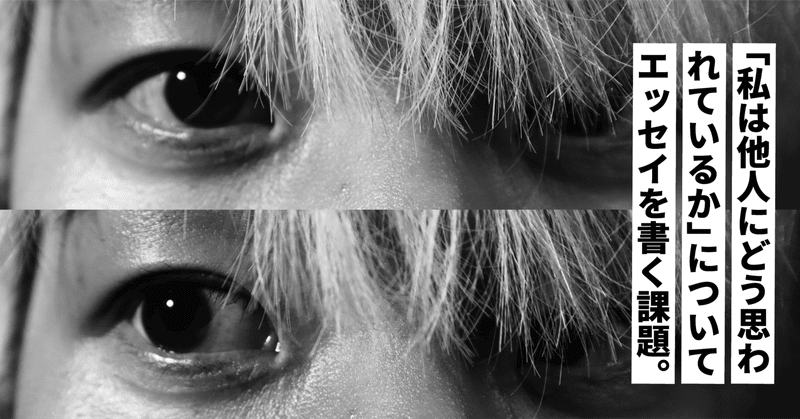
「私は他人にどう思われているか」について、エッセイを書く課題。
僕は一般大を辞めて三浪したのち今の美大に通っているのですが、美大といっても絵を描いたりなどしているばかりではなく、外国語の授業もあれば体育もありますし、普通に課題のレポートを出したりもしているわけです。3年生になったら就活なんかもするわけです。しんどいですね。
で、そんな美大での課題の話です。この課題は、絵でも彫刻でもなく、文章を書く課題でした。それもレポートではなくエッセイです。
エッセイのテーマは「私は他人にどう思われているか」
字数は約5000字。条件は、そのことについて自分の周りの5人以上に取材をすること。対象は、家族・友人・恋人はもちろん、長らく会っていない人や、バーでたまたま出会った人などでも可。つまり誰でもOK、とのことです。あなたなら誰に取材して、どんな構成で書いてみるだろうか?
そして、その文章を自分のポートレート(自分が写った写真)と組み合わせ、雑誌のようにページをレイアウトする、というものです。そうなってくると美大っぽいですね。何百枚も写真を撮りました。文章を書くよりそっちの方が疲れました。

同じ課題に取り組んだ学生が10人ほどおり、最終的には全員分をまとめて、こんな感じで一つの書籍として印刷・製本しました。その作業は他の学生がやってくれたんですが、すげー綺麗ですよね。売ればいいのに。
とはいえ、特に外部に向けて公開・販売されることはないまま、課題はこれで終了しました。まあそもそも学校の課題ってそういうもんですよね。
ただ、ちょっともったいないな?
ということで、この書籍内で僕が関わった部分をこのnoteに残します。作品というのは人に見せてこそ完成でしょう。
最終的にこの授業で僕が得た評価は、5段階中最高の"秀"で、また原稿に対しては教授からこんな感じでハッピーなお褒めの言葉をいただいたりもしました。嬉しいですねえ。

さてこの文章は、作者の家原 流太と他に4人の人物が登場し、いくつかの短い章に分かれた構成となっています。ちなみに僕以外の4人の名前は仮名です。
「まなざしに棲む」という題名をつけました。最後まで読むことで完成する文章です。お付き合いいただければ幸いです。


甲斐崚二
「一年の七組におもろいやつがいる」
生徒会のひとつ下の後輩がそう言ってきた。おもろいって、いったいなんだ。会話のセンスが良いのか、見世物としての面白さなのか。高校生の使う"面白い"という表現は、場合によっては嘲笑じみたニュアンスを含むことがあるから、少し慎重になってしまう。その「おもろい」一年生は家原というらしい。
八月の下旬、あと数日で学園祭が始まる。空調の届かない廊下はじっとりと暑く、窓の外の明るさを反射してきらきらと光っている。教室を覗くと生徒たちが窮屈そうに作業をしているのがうかがえた。
俺は生徒会の業務で、一年生の準備の様子をビデオに撮って回っていた。見慣れない上級生が教室に入ってくるのはやはり緊張するようで、毎回少し警戒されてしまう。一年生は体育祭で各組のテーマカラーを使った巨大なパネルを描くことになっており、七組の代表が家原だった。
家原にカメラを向ける。
「ええと、まだ全然できてないんですけど、白組です。これから白塗ってきます。クジャク描いてます。それでええと、すごく清潔で美しい、なんか綺麗な絵になる予定です、はい。どうなるかわかんねえんだけど、でも良い絵にします。楽しみにしててください」
レンズに向かう家原は、なんというか、くねくねしている。体の動きの話だ。話しながら体の軸が左右に揺れたり、首が動いたりと落ち着かない。
だけど、きらきらしている。
堂々としていると言い換えてもいい。自分たちが描いた絵を待っていてくれと、臆さず伝えようとしている。おもろいとは、そういう意味か。この学校にはこういう人はあまりいない。
「生徒会入りなよ」
気づけば俺は声をかけていた。たぶん、向いてるから。
灰色の校舎の中で、生徒会室は少しだけ色づいているように見える。クラスの中でねじれの位置にいるような人たちが集まる、贅沢で滑稽で、自由なホームだった。俺や、恐らく家原のような、クラスで馴染めない奴らの逃げ場でもあったかもしれない。
モノクロの制服と頭髪が一様に課されるように、島根という閉鎖的なこの街の、さらに閉鎖的なこの学校で俺たちは、常にはみ出さないことが求められる。やりたいことをやろうとすると目立つ。目立つと、出る杭を打たれる。
生徒間で噂されるくらいならまだいいが、先生たちに目をつけられると厄介だ。彼らは時に学校の評判と生徒の一元管理のために、こちらを矯正しようとする。役者の仕事をしたいことは、この学校では人には言えない。東京の事務所に所属していることも言うべきではない。
しかし家原はずっと、偽るまいと抗っているように見える。それで後ろ指を指されても、気にしてないって顔をしながら、しっかり傷ついて何かになりたがっている。しかしその何かがなんなのか、まだ本人もわからないのだろう。
「そういえばさ」
放課後の生徒会室で、家原が振り返ってこちらを見て、聞いてくる。
「甲斐さんって、高校出たらどうするの」
一瞬迷って、「どうすんだろうね」と答えた。本当は、ある。家原を信用してないわけじゃない。
俺たちは似ている。はみ出せないのにはみ出したくて、見下すくせに馬鹿にはなりきれない。そのうち最終下校時刻になり、生徒会室の明かりが消える。

三鷹駿吾
いつかこいつとは仲違いする予感があったけど、そのときが来たのかもしれない。前はもっと、普通に友達でいられたはずなのに。
高校一年生のクラスは早進度コースで、真面目で静かな雰囲気に満ちていた。休み時間でも球技大会でも、誰とも喋らずに英単語帳ばかり読んでいるやつばかりだった。たぶんこいつらは俺よりも、将来のこととか、人生のことについて真剣に考えているのだろう。けれどそういう人たちを見ていると、なんだか可哀想に思う。そんな学校生活の何が楽しいのだろう。
家原はクラスで唯一の同じ中学校出身者だった。真面目な空気に上手く馴染めない同士という共通点もあって、休み時間に話したり、一緒に帰ることが多かった。二人で学校をサボった日もあったし、夏休みになれば、深夜に自転車を何キロも漕いで、真っ暗なスーパーの駐車場に集まったりなんかした。そうしているうちは、成績や将来みたいなことについて考える必要がない。目の前の瞬間が面白ければそれで良かった。やりたいことも、なりたい姿もないけれど、こういう時間がいつまでも続いてくれればいいと思った。あの頃はたぶん、ちゃんと楽しかった。
だけど最近イライラすんだよな。きっかけは高校二年生、こいつと一緒に生徒会に入ってからだ。

「お前さ、頼むからもうちょっとちゃんと仕事やってくれよ。」
家原のその口調が、俺をさらにイライラさせる。ああ、鬱陶しい。
家原が生徒会長になると、俺も役員に誘われた。"生徒会"という響きはなんとなく格好良く思えたし、部活をサボる口実にでも使えたら儲けものだった。
しかし、学園祭が近づくとぐんと忙しくなり、やる気のない人たちは生徒会室に集まらず、結果一部の数人に業務が集中するようになった。そして、メンバーのなかでも仲の良かった俺に、仕事をするように家原は何度も頼んできた。
「いや、部活あんだってこっちも。そんな毎日毎日行けるわけねえじゃん。ていうか俺以外にも働いてないやつおるくない? あいつらにはなんも言わんの?」
俺はもうイライラを隠そうともしない。ちゃんと与えられた作業はこなしているはずなのだから、文句を言われる筋合いはない。それで仕事が回っていないのであれば、それはこいつの責任だ。
「呼んだって来ねえじゃんあいつら。俺もやってんだから、頼むよ。このままじゃ間に合わないんだって」
呼んだって来ないとか、呼んでから言えよ。結局お前は俺が一番誘いやすいから声をかけてきてるんだろうが。
ひとりで頑張るぶんにはともかく、リーダーを張れるほどこいつは人の使い方が上手くない。昔から追い込まれると周りが見えなくなるし、協調性と客観性が足りていない。自分の考え方や感性が正しいと信じ込んでいるのだろうな、と思う。第一こいつは、どうして学園祭なんかにそんなに必死になるんだろう。それがなんになるのか。
一度考え出すと、次々といくらでも嫌な部分が思い浮かんでくる。変な部分に真面目で、冗談が通じないところ。俺の話し方や態度を指摘してくるところ。ツイッターに痛々しい長文ばかり書いているところ。目立ちたがりのくせに、周りなんて気にしてませんって顔をするところ。
前はもっと、普通に友達でいられたはずなのに。変わったのは、家原か、俺か。たぶん両方だ。俺たちだけじゃない。周りも丸ごと、だんだんと変わっていく。誰だって昔のままじゃいられない。
高校二年生になってから少しずつ、進路、志望校、人生、そういうことについて考えることを求められるようになった。目の前のことを楽しむだけじゃ、もうダメなんだろう。だからって別に、どうする気もない。
ところで家原は、将来とかについてどう考えているんだろうか。まあそれも、どうでもいいんだけど。
イライラする。何より、そんなことを考えている自分にイライラする。

中村青
静岡大学に来るのは入試以来だ。試験のときの緊張感と違って、日の当たるキャンパスは穏やかな充実感に満ちている。今日はオリエンテーションを兼ねた新入生歓迎会で、同じ学科の十人の新入生と初めて会う日でもあった。最初にしくじらないようにしなくちゃ、と慎重になる。
「島根から来ました。鳥取の隣の島根ね」
低い声で喋る流太くんという男子は、服装や振る舞いがなんだか大人っぽく見える。大学は高校とは違うなあと、修学旅行の男子のダサかった私服を思い出す。
「浪人とかしてた?」誰かが尋ねた。
「してねえよ」流太くんが答えた。
昼からはなぜか自動車学校の説明会があり、百人を超える学生がぎゅうぎゅうと教室に集まっていた。自動車に関するクイズに正解するとお菓子をもらえる、という企画らしい。教習所の職員の人がお菓子の大袋をいくつか掲げた。あのお兄さん結構イケメンかも。
「助手席にブレーキがついている教習車を開発したのは、静岡県の県知事である。マルかバツか」
教習所の車には助手席にブレーキが付いていることさえ知らなかったのだから、そんなのわかるわけがない。「わかんないねー」と隣の女の子が言ってくる。ねー。
すると近くにいた流太くんがスッと手を挙げる。そして、平然と正解した。
「そんなこと知ってたの?」
「だって、わざわざそうやって聞いてくるってことはマルってことでしょ」
うわあ。そりゃたしかにそうだけど、それ言っちゃうんだ? ていうかこの人の声よく通るなあ。教室みんなに聞こえてそう。
でもその言い方には目立ってやろうと意気がる様子はなくて、ただただ淡々と、そう思ったからそう言っただけみたいだった。
景品のカントリーマアムの大袋を、流太くんが私たちに手渡してくる。
「山分けしようぜ」
私は高校で人を信用できなくなっていた。人には裏と表があること、みんな誰かの噂が好きなこと、上手く生きるためにはしくじってはいけないことを知った。高校という世界は息苦しく、大学もきっとその延長が続くのだろうと思っていた。
けど、この人にならなにを言ってもよさそう。どうしてか流太は、そう思える人だった。東京藝大を目指すと言い出し、大学を休学して居なくなるまでの四ヶ月間、流太はずっと堂々としたままだったから。純粋で、裏表がなかったから。というよりはむしろ、全面的に裏側だったのかもしれない。
ただ異性の友達って、周りの目が厄介。「そこ二人セットなのなんで?」と聞かれることもよくあった。同性ならそんなことにならないのに、どうして異性というだけでとやかく言われるのだろう。
いっそ流太が女の子になればいいのに。そしたら全部解決する。うん、女の子に生まれてくればよかったのに。そういうとこは気が利かないなあ。
でも流太なら誰かに悪い噂をされても、たいして気にしないんだろうな。「知らねえよ」なんて言って。

西宮千暖
「驚く顔が見たかったから」
大学一年生の四月、誕生日プレゼントを渡してくれた流太は、そう言って嬉しそうに笑った。受け取った袋のなかを見ると、二十個以上のじゃがりこが詰まっている。たしかに好きとは話したけど、まさかこんなにいっぱいだとは思わない。
素敵な人だな。初めはそういう小さな呟きだったと思う。一緒の美術予備校に通っていた時期もあったから、存在は知っていた。髪が白いし背も高いし、なんとなく怖い印象があったけれど、大学に入ってちゃんと話してみると、全然そんなことはなかった。二歳年上だったこともあり、大人びて見えた。
それから半年が経ち、金木犀の匂いがし始める頃、いつの間にかその呟きは無視できないほどに大きくなって、私の心を私以上に振り回すようになってしまった。制作のこととか、考えなければいけないことがほかにあるはずなのに、この人の重力が私を自由にしてくれない。
私は流太が好き、なのだろう。けれどその好きが、どういう種類のものかわからない。こんな感情に今までなったことがなかった。私はこの人をどう思っているのだろう。この人と、どうあることを望んでいるのだろう。

「暖ちゃんはどんなときに寂しくなるの」
「え。うーん、いつだろう……」
今がまさにそうだよ、と思わず口に出しそうになる。一人でいるときも、二人でいるときもおんなじ寂しさがあるなんて、思いもしなかった。
少し寒くなり始めた帰り道を、二人で並んで歩いていた。少しでも一緒にいられるように、ゆっくりと時間をかけて進む。それに合わせて流太も、歩幅を狭めてくれる。
まだ十七時過ぎなのに、空は深い藍色に染まりつつあった。道の左右に高く木が立ち並んでいるせいで、わずかな光も枝葉によって遮られ、流太の顔はよく見えない。けれど近くにいると、金木犀に混じって流太の匂いがする。声が、鮮明に聞こえる。
「寂しそうな人っていいよな。寂しそうな人が好きなんだ。ふと見たときの横顔に寂しさを感じると、なんかどきっとするんだよね。あ、この人は生きてるんだ、って。普段はそんな気配を全く見せずに笑っていても、この人のなかにもちゃんと痛みや悲しみはあるんだって気づく。そういう瞬間が愛しい」
流太は丁寧に話している。生きている。
この人は、いつも真剣に言葉を探していると思う。たぶん誰に対しても同じように、相手の話をしっかりと聞いて、体力を使って向き合おうとするんだろう。
でも、それで生きづらそうだなと思うこともある。そうやってたくさん考えるのは疲れるだろうし、必ずしも相手が流太と同じくらい、真剣に向き合ってくれるわけではないだろうから。流太のそういうところに救われる人は大勢いるはずだけど、素通りしてしまう人も多いはずだ。
「わかる、気がする。その感覚。でもそういうとき私は、目の前のその寂しそうな人の力になれるのか、なれないのか、どっちなんだろうって考えると思う。自分本位な考え方だし、力になれたとしても、ひょっとしたら迷惑になるかもしれないけど。その人が必要としているのは、別の人かもしれないけど」
私はちゃんと向き合いたいよ。
たぶん流太よりも真剣に、流太に向き合いたいと思っているよ。
流太の寂しさにも、ちゃんと気づいてあげたいから。できれば力になりたいから。ひょっとしたら、迷惑になるかもしれないけど。流太が一緒にいたいのは、私じゃないかもしれないけど。そんなことを思いながら流太の長い前髪を見ていると、なんだか泣きそうな気持ちになってしまう。冷えた指先を温めようと、袖の内側をぎゅっと掴む。
私はこの人をどう思っているのだろう。話をしながら歩き続け、流太の言葉と思考のひとつひとつが胸の中に入り込んで私と混ざり合うたび、その答えが明確なものになろうとしていく。
並木道を抜けて、わずかにあたりが明るくなる。金木犀の匂いはもうしなかった。

家原流太
東京でも、島根でも静岡でも、空はどこまでも遠く透明に広がっていて、その巨大さがなんだか恐ろしい。日の沈む上野公園の空の端では、青色と赤色が濁ることなく繋がっている。
あんなふうに自然に、僕も人と繋がれたらいいのに、と思う。
高校生から大学生、浪人生を経てまた大学生と、歳を重ねるにつれて、人と関わるのがだんだんと苦手になっていった。なにを話せばいいかわからず、上手く笑うこともできず、会話のなかでただ黙っていることが増えた。少なくとも高校生の頃はそんなことはなかったはずなのに。大人になって知ることが増えるたび、考えなくてもいいことを考え出して動けなくなってしまう。
他人の目なんて気にしないと振る舞うくせに、内心では人の顔色ばかり伺って怯えている。友達と一緒にいられることが嬉しくてたまらないのに、全員どうしようもなく嫌いになる日がある。一体なんなんだ、僕は。
だから尋ねてみたのだった。巨大な空の下のどこかで同じく生きている、僕のことを教えてくれたあの人たちの顔が浮かぶ。
甲斐崚二。このあいだの舞台はとても良かったよ。以前よりもさらに表現力が増していたし、きらきらしていて、堂々としていて、格好良かった。舞台の上やカメラの向こうのあなたは、生徒会室にいるよりもずっと鮮やかに色を放っている。いつも僕の一歩先で、真っ直ぐに芸術に向き合うあなたの人生に、どれだけ勇気をもらったことか。僕はあなたのようになりたかった。
三鷹駿吾。当時はごめんな。でもお互い様だとも思うよな? お互い子どもだったんだ。なあ、ちゃんと覚えているよ。あんなふうに斜に構えていたお前が、大学に入ってから俳優を目指して大阪に出て、そして挫折した、あのとき。お前は苦しかったと思うんだけど、その歩みと痛みは僕の目には光のようだったよ。それを見られて嬉しかった。もう大丈夫だよな。二人とも変わったんだから。
中村青。元気にしてますか。もしかしたらあなたは、僕が一緒にいてくれている、と思っていたかもしれないけれど、それは逆なんだ。あなたが一緒にいてくれたことに、僕がたくさん助けられたんだ。藝大を目指して僕が壊れていた頃、何度も励ましてくれてありがとう。仕事が苦しければ、僕にならなんでも言ってくれよ。なんにもできないかもしれないけれど、できることを教えてくれよ。
西宮千暖。振り返ればさまざまな偶然と、出会いと別れと、挫折と奇跡の連続のおかげで、僕はどうにかここまで生きてきた。そうして辛うじて辿り着いたこの世界の真ん中に、あなたが立っていたんだ。あなたが優しくしてくれるたび、それに甘えている自分のずるさが嫌になる。僕にとって一番大切なものが、あなただと言い切れない自分が嫌になる。いつか僕のせいで全部壊れてしまうんじゃないかって、時々たまらなく恐ろしくなる。それでも僕はあなたが好きだ。
あなたたちのそのまなざしのなかで、僕も知らない僕が輝きながら生きていた。いったいそいつは誰なのだと、問いただしたくなるほどに。
だけど嬉しかった。そんなふうにありたいと心から思う。
なんだ、ちゃんと繋がれているじゃないか。あなたのまなざしに棲む僕に、いつか僕も追いつきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
