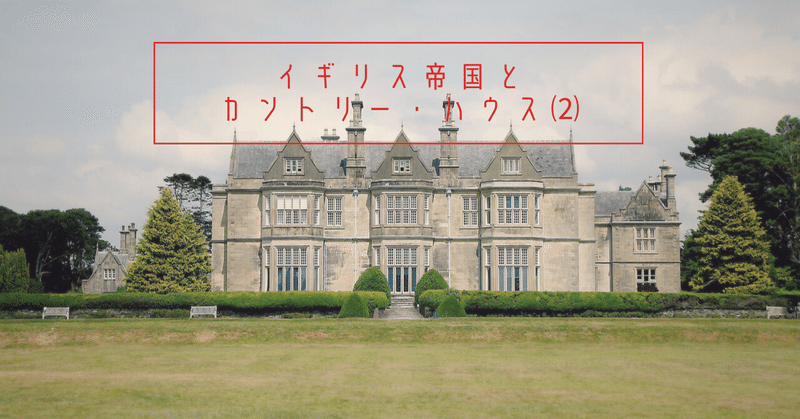
イギリス帝国とカントリー・ハウス⑵
前回↓
前回からどえらい間が空いてしまったが、今回は予告通り、カントリー・ハウスの文化とイギリス帝国の繁栄との関係を主に見ていこう。
それから、カントリー・ハウスが衰退していく過程と、現在数多くの地所を保全し、一般公開しているナショナル・トラストについても触れようと思う。
相変わらず大学の講義ノートをベースにしているため、「ソースが示されていない箇所は、講義で聞きかじったんだな」と思って読んでほしい。
なんか間違ってたらめんご🙏
イギリス帝国とカントリー・ハウスの文化
前回ちらっと触れたように、カントリー・ハウスの文化は、イギリス帝国の覇権と商業ネットワークの掌握に裏づけられている。
例えば、カントリー・ハウスで用いられた家具の材質の変化は、これを示す一例であるといえそうだ。
16世紀から18世紀の初頭まで、イギリスでは家具の材質としてオーク・ニレ・トネリコ・クリの木・クルミの木など、イギリス固有の木材が用いられてきた。
これがマホガニー・黒檀・サテンウッド・キングウッドなどに変わっていったのは、イギリスの植民地が拡大し、新たな木材が流入してきた後のことだったである。
また、カントリー・ハウスで供される食べ物を生産するキッチンガーデンでは、南国から持ち込まれたエキゾチックな果物が栽培されていた。
具体的にはメロンや桃、イチジクやルバーブなどが挙げられる。
(他にも、オレンジやレモンを栽培するthe orangeryみたいな施設もあったよ!)
これは、キッチンガーデンが温度管理を行える設備を備えていたからこそ可能になったことである。
加えてキッチンガーデンには、「キュウリをまっすぐに育てるためだけに使うカバー」のような、極めて用途の限定された道具が多数取り揃えられてもいた。
(「一つで〇〇役!」みたいなのとは無縁の世界やね)
この意味で、キッチンガーデンは「カントリー・ハウスの食糧生産を担うべく効率化された農園」というよりは、「食糧生産の過程すら贅沢化された、カントリー・ハウスという階級システムの象徴」であるといえそうだ。
実際、これは野菜や果物に限った話ではない。
カントリー・ハウスでは、シカ肉やキジ肉、ウサギ肉のシチュー(jugged hare)といった食肉すらも、往々にして敷地内で狩ったものだったのである。
普通、食肉を効率的に得ようと思ったら、狩りなんかせずに家畜を飼うよね?
そこをわざわざ狩ってくるということは、カントリー・ハウスでの饗宴は、「あえてそうしている」類の儀礼的なものだったということなんだろう。
そして──繰り返しにはなるが──このようなカントリー・ハウスの贅沢極まる文化を支えたのは、イギリス帝国の覇権と商業ネットワークだったのである。
イギリス帝国の覇権(=生産・流通・金融が特に強いこと)こそが植民地からの収奪を可能にし、強力な流通網でもってイギリス本国に集められた各地の文物がカントリー・ハウスでの生活を彩ったのだから。
「イギリスといえば」でお馴染みアフタヌーンティーの習慣なんかも、イギリスの覇権・広大な植民地・世界的な流通網が相まって初めて生まれたものだしね。
それは、西のカリブ海植民地からやってきた砂糖と、東の中国ならびにインドからやってきた紅茶が合わさって生まれた文化だったのだから。交易網が強くなきゃできねーべ。
やがてこのアフタヌーンティーの文化は、上流階級から一般市民、果ては労働者階級にまで伝わっていき、イギリスの文化に"snobs"な色彩を加えることとなる。
(「イギリス人のsnobbism」みたいなことは、ニーチェの『善悪の彼岸』とかでも語られているんだけど、その話までし始めると収拾がつかなくなるからやめておこう)
他にもタバコだの衣服だの、海外植民地から持ち込まれてカントリー・ハウスの文化に取り込まれていったものは枚挙にいとまがないが、ここでは割愛する。
(気になったら各々で調べてみてね!)
カントリー・ハウスの衰退
カントリー・ハウスが急激に衰退していったのは、アメリカからの安価な穀物の流入によって地価の下落や地代収入の減少が起こり、大不況となった1870年代以降のことである。
前回も触れた通り、イギリスにおける支配階級の権力は土地に裏打ちされたものだった。
そのため、地価や地代収入が下がることは、彼らにとっては大打撃だったのだろう。
とはいえ、それ以前からイギリスの繁栄には陰りが見え始めていたといえそうだ。
というのも、大不況以前の1850-60年代にはすでに、急速に工業化を遂げたアメリカとドイツが世界市場への進出を始めていたからである。
そしてイギリスは、産業分野におけるこうした新興の国々との競争に少しずつ敗れつつあったのだ。
加えて19世紀後半には、海外投資からの利子・配当金に収入を依存するような新興階級が、新たにイギリスの支配階級へと組み込まれていった。
大不況の起こった1870年代以降にもなると、「カントリー・ハウスの所有」は支配階級の必須条件ではなくなっていったのである。
(まあ、それでも「支配階級といえば、旧来からの土地持ち貴族・ジェントリ」という文化的イメージはそう変わらなかったんだけどね)
(大不況のちょっと前まで、ハイ・ファーミングの発展で地代収入はウハウハだったらしいし)
とかくイギリスは、19世紀後半を通じて「世界の工場(=生産)」から「世界の銀行(=金融)」へと変容していった。
(↑こういう話は、ウォーラーステインの「世界システム論」なんかを踏まえると面白いかもしれない)
金利生活国家と呼ばれたのも、この時代のイギリスであろう。
イギリス経済は、大不況の十数年前──広大な土地を所有する貴族やジェントリが繁栄を謳歌した時代──にはすでに、爛熟期にさしかかっていたのかもしれないね。わからんけども。
何はともあれ面白いのは、イギリス国内におけるカントリー・ハウスの衰退期とイギリス帝国の斜陽が、時期的に重なっているということだ。
カントリー・ハウスというシステムは、つくづくイギリス帝国の縮図だったのだろうと思う。
さて、1870年代以降、これまでの生活を維持するだけの十分な地代収入を得ることができなくなったイギリス上流階級の子弟は、家に「箔」がつくことを望むアメリカの富裕者の娘と結婚するようになる。
(1870-1914年の間に、300人ほどのアメリカ人の富裕者の娘が、爵位を持つイギリス貴族の子弟と結婚したらしい)
(まあ、アメリカの富裕者の娘と結婚したのは次男以降が多かったから、爵位や遺産を継げる可能性は低かったんだけどね。イギリス貴族は長男子相続制だし)
イギリス側は富を求め、アメリカ側は爵位や箔を求める結婚。
「海外から」新しい富を流入させた結婚。
イギリスが覇権国家にのし上がる前の歴史的過程をも踏まえて、実にイギリス的だと個人的には思う。
ナショナル・トラスト
ナショナル・トラスト公式サイト↓
さて、「カントリー・ハウスの話をしていたはずが、なんでいきなりナショナル・トラストの話に?」と思っただろうか?
その話をするためにも、まずは「ナショナル・トラストとは何なのか」について見ていこう。
ナショナル・トラストは1895年、国民の利益のために美しい景観や建築物の保全することを目的として設立された民間団体である。
まあ、ナショナル・トラストの「ナショナル」は「国民の」って意味だしね。
「美しい建築物を保全している」とある通り、この団体は現在、数多くのカントリー・ハウスを所有し、一般に向けて公開している。
(公式サイトのVisit→Place types→Houses & buildingsを見てみると、色んなカントリー・ハウスが出てくるよ!)
また、設立者の一人であるオクタヴィア・ヒルは、当時のロンドンの汚さやそこで暮らす労働者たちの様子にショックを受け、「全ての人間が、美しい場所へ行く機会を与えられるべきだ」と主張した人物でもあった。
ナショナル・トラスト自体の理念も、概ね彼女のこうした考えに即しているといって良いだろう。
つまりナショナル・トラストは、「歴史的価値のあるものとして保全され、全ての人に向けて開かれるべき美しい場所」の中に「カントリー・ハウス」が含まれていると考えている……というわけだ。
考えてみれば、これってかなりパターナリスティックじゃなかろうか?
前回も話した通り、カントリー・ハウスとは単なる大邸宅ではなく、家父長→その他の家族、上流階級→労働者階級、イギリス帝国→植民地という三重の支配/被支配関係を象徴する、階級システムの装置であった。
当然ながら、オクタヴィア・ヒルの生きた時代においても、カントリー・ハウスはロンドンの労働者たちにとって「ぜひ訪れたい美しい場所」というだけでなく「自分たち労働者階級を抑圧するシステムの象徴」でもあったはずだ。
それをナショナル・トラストは保全することにしたのである。しかも「(労働者階級を含む)国民の利益のため」という名目で。
そうすることで、人々の愛国心や「古き良き時代」へのノスタルジアを喚起しようとしたのであった。なんというかさぁ……
加えていえば、ナショナル・トラストは民間団体だ。
オクタヴィア・ヒルらの裕福な私人によって設立され、運営されてきたのである。
そう、ナショナル・トラストは「国民の利益のため」を理念に掲げているが、政府によって運営されているのではない。
要するに、国民のためと言いつつも、実際に国民の合意を得ながら地所の保全を行っているわけではないのだ。
裕福な私人の設立した民間団体が、労働者階級を含む国民のためという大義名分のもと、彼らの同意を得ることなく「カントリー・ハウス」という階級システムの遺産を保全する。
しかもナショナル・トラストの保全のやり方には、歴史的建造物に対する彼らの価値観や商業的価値という「ノイズ」が入り込む余地が生じてしまう。
本当に「ベストな」やり方で歴史的建造物を保全しようとするのならば、「その建造物には商業的な価値があるか(=観光客を多く呼び込めるか)」といった判断からは離れたところで保全が行われなければならないのだ。
本来なら、観光客が来ようが来まいが、歴史的建造物は歴史的建造物であるというだけで保全されるに足る価値があると考えねばなるまい。
ただ、そのためには、国家との協力が必要になってくるといえそうだ。
まあ、「小さな政府」が叫ばれる時代では、結局「商業」の力借りずして遺産の保全を行っていくのは、ほぼ不可能なんだろうけどね……
だいぶ嫌な言い方をしたが──これはまさにパターナリズムの一種である。
ナショナル・トラストはある意味、イギリスの階級システムの延長線上にある存在なのだ。
とはいえ、それは必ずしも守旧的なものではない。
というのも、前回ちらっと触れた通り、本来であれば上流階級は労働(=ビジネス)を嫌うからだ。
そもそも「ナショナル・トラストがカントリー・ハウスを買い取り、保全し、一般に向けて開いている」という状況自体、カントリー・ハウスの元の持ち主が没落し、金持ちとはいえ上流階級ではない一般民衆が力を持つようになったことを示している。
実際、ナショナル・トラストが設立された時期は、権力の象徴としてのカントリー・ハウスが衰退しながらも、それとは対照的に一般民衆の政治的プレゼンスが高まった時期と一致するのである。
この点でナショナル・トラストは、カントリー・ハウスが象徴するような伝統的な権力の系譜に沿って人々の「国民意識」を喚起しようとしつつも、多分に新しい市民的価値観(=地所の価値を商業的な観点から判断する価値観)を備えていたといえそうだ。
カントリー・ハウスを「保全する」ナショナル・トラストの存在自体が、カントリー・ハウスというシステムの衰退を示唆していたというのは、何とも皮肉なことだよな。
今後調べたいこと
前回と今回のnoteは、ケイン&ホプキンスの「ジェントルマン資本主義論」をベースにしているといえる。
とはいえ、「イギリス帝国」というものを包括的に考える際には、「本国の」「ジェントルマン」以外の視点も必要だと思うんだよね。
そういうわけで、今後もレーニンやホブソンの古典的帝国主義論、ギャラハー&ロビンソンの「自由貿易帝国主義論」、ウォーラーステインの「世界システム論」などに触れつつ、イギリス帝国についてもっと理解を深めたいと思っている。
また、歴史学からは脱線するが、イギリス人の精神性を現代思想の観点から追っていくのも楽しそうだ。
さて、イギリスについて知れば知るほど、「私はイギリスのことを何も知らない」ということが分かってくるが、それでもやはりイギリス史は面白い。
(ところどころブリカスなところも含めてね🤟)
参考文献(一部)
川北稔『砂糖の世界史』(岩波書店、1996年)
マーク・ジルアード著、森静子・ヒューズ訳『英国のカントリー・ハウス〈上〉貴族の生活と建築の歴史』(星雲社、1989年)
マーク・ジルアード著、森静子・ヒューズ訳『英国のカントリー・ハウス〈下〉貴族の生活と建築の歴史』(星雲社、1989年)
水野祥子「環境保護運動の結社 : ナショナル・トラスト」川北稔編『結社のイギリス史 : クラブから帝国まで』(山川出版、2005年)
村岡健次、木畑洋一編『世界歴史大系 イギリス史3 ─近現代─』(山川出版、1991年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
