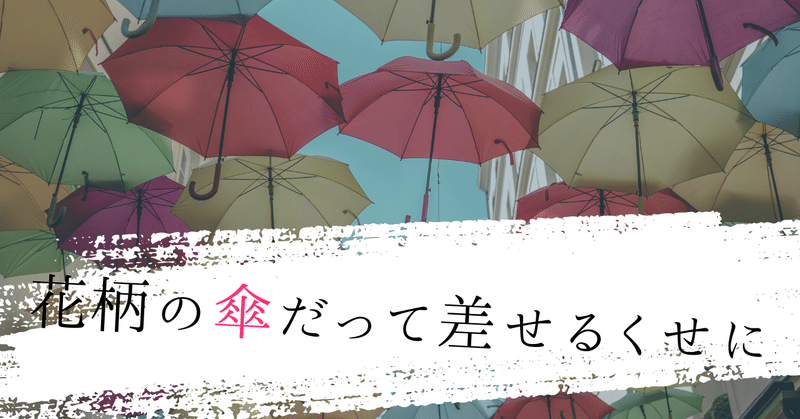
【短編小説】花柄の傘だって差せるくせに
なんかねー、「男性が女性に向ける羨望と失望」的なものが書きたかったんですけど、途中からちょっとわけが分からなくなりました。話があちこちに飛びすぎなんだよ。
まあ戯言です。主語がややデカなんですけど、気にしないで雰囲気で読んでね。
東京に戻ってみると、あいにくの雨だった。
運悪くかばんの中に折りたたみ傘もなかったため、俺は駅ナカのコンビニでビニール傘を買ってから、雑踏の中へと出ていった。
張りのある厚いビニールに雨が当たって、ボツボツという質量のある音が頭上で響く。高くはない、しかし安くもない革靴とスーツのズボンの裾に雨粒が跳ねる。少し強い風が吹くと、脇にぶら下げたかばんにも雨染みがついた。
ああ、憂鬱だ──傘を差しても結局はこうやって濡れるんだからさ。
そんなことを考えながら人を避けて歩いていると、ふと、ビニール越しの白みがかった視界に一本の傘がよぎる。雨と高層ビルからなる淀んだ灰色の景色の中で、それは実に鮮烈な赤だった。より正確にいえば、その傘には、真っ白な地に大きな赤い花がいくつか描かれていたのであった。
他意はなかったが、俺はなんとなく傘の持ち主を目で追う。
それは、暗めの茶髪をボブカットにした若い女だった。あまりたくさんの荷物は入らないであろう手提げかばんを持って、信号待ちの間、所在なげに自分の爪を眺めている。
「あー……」
気づけばため息が漏れていた。それから、そんな自分に驚いた。
…今、俺は何を考えていたのだろう? 何か、どうしようもない疲れがどっと押し寄せたのが分かる。だが、その正体がいまいち掴めずにいるのだ。
そうこうしている間に信号が変わった。件の彼女は、いつの間にか雑踏の中に消えていた。ひょっとすると、大通りに居並ぶ商業ビルの一つに入ったのかもしれない。
疲れ目をごまかすために数度まばたきをしてから、俺は大通りの一本向こうにあるオフィスへと歩いていった。
その途中で、俺と同じような出で立ちをした何人かの男とすれ違う。黒い傘、ネイビーの傘、ビニール傘。晩夏のこの蒸し暑さだというのに、みな一様にスーツを着て(よくてクールビズだ)、重そうなビジネスバッグを下げている。
彼らと何度かすれ違ううちに、俺には先ほど感じた疲れの正体が段々と分かってきた。それは、おそらく羨望だった。
──今のは語弊があったかもしれないが、俺は別に「女性」になりたいわけではない。花柄の傘を差したいわけでも、湿気に負けないよう髪をセットしたいわけでも、小さな軽いかばんを持ちたいわけでも、爪をぴかぴかに磨いておきたいわけでもない。
ぴしっとスーツを着て、革かばんを提げ、胸を張って雨の中を早足で歩いていく男。それが今の俺の姿だ。自分で言うのもなんだが、中々様になっていると思わないか?
今の自分に大きな不満はない、つもりである。仕事が多少きついが、金はあるし自由もある。少なくとも、欲しいと思ったものを誰にも気兼ねせず気軽に買えるような自由はな。俺はなんだかんだ「決められたレール」の上を歩くのが上手くて、そんな自分を少なからず気に入ってもいる。これは本音だ。
そんなことを考えている間に、オフィスビルのエレベーターが来た。中に乗り込んで26階のボタンと閉ボタンを押すと、ガラス張りのエレベーターの銀色の扉が静かに閉まる。
やがてガラスの個室が上昇を始める。中にいるのは俺一人だ。重力に従って雨が降るのに逆らいながら、ぐんぐんとコンクリートで固められた灰色の地上から遠ざかっていく。
──だから、この「羨望」は自己憐憫とは無関係である。俺は自分が哀れだから「女が羨ましい」などと言っているのではないのだ。
それに、誰かに憐れまれるのだって真っ平ごめんだ。だって、そうだろう? 憐れみはかくも自尊心を削るじゃないか。それは冷めつつある湯船に似ている。生ぬるく、だるく、緩やかに体力を奪ってゆく。
12階。いつだって、まっすぐに努力して自分の地位を勝ち取ってきた。そのことを誇りに思っている。
自分で生きる道を自分で切り開いてきた、これからもそうだという自負だけが、人間を尊厳ある一個人にしてくれるのだ。
14階。いいや、俺は幸運だったのだろう。努力ができることも、それが報われる程度には才能があったことも、俺が出しうる「結果」を評価してくれる社会に生きていることも、全ては一種の幸運である。
それにひょっとしたら、俺が男だということもその一部なのかもしれない。女が生まれながらに堕とされる地獄があったとして、その有様など俺には知りようもないからだ。
18階。ともあれ「自分は運がいい」と思っておいた方が幸せなのに相違はない。
そして俺は幸せな人種だ。つまり、概ねそういう牧歌的な人生観を持ったまま、ここまで生きてこられた幸運な男なのである。
しかし、だ──俺は地上を見下ろす。オフィス街なので人通りはまばらだが、時折、黒や紺の無地の傘、ビニール傘が通りかかる。足取りは疲れからか鈍重、そうでなければ、追われているようなせかせか歩きだ。あれは多分、日夜働く男たちなのだろうな。
どうにも、さっき見た鮮やかな傘の女とは似ても似つかない。いや、「女たちの通り」とは全くもって様子が違う。たくさんの女たちが歩く大通りをこんな風に上から見たら、きっとさぞ鮮やかなのだろう。急ぎもせず、かといって鈍くもなく、もっとワルツのように傘が行き交うのだろう。その光景を何気なく「美しい」と評することさえ、許されるのかもしれない。
俺はきっと、その優美さが羨ましいのだ。そして、彼女たちに優美であることを許している、この世界が厭なのだ。
彼女たちに「働かずにいられて、いいご身分ですね」などと言うつもりはない。それはおそらく的はずれな文句だ。女性の「社会進出」──言い換えると「資本主義の価値観に即した労働への動員」は、ここ数十年でずいぶん進んだことだろうから。
今日見かけた女たちの何割かは、俺たちと同じように働いているに違いない。ただその見かけに、男たちにはない「余白」があるというだけだ。自由に好きな傘を差していようが、結局は彼女たちだって一労働者なのである。
23階。それに、たとえ大通りの女性たちが有閑階級であるにしろ、いつかはその特権も消えてなくなってしまう定めにあろう。おそらくだがね。というのも、今我々が生きている世界は、とかく有閑の特権階級を嫌うからだ。
それが良いことなのか、悪いことなのか、俺には分からない。ただ一つ言えるのは、それは「男性性」の最終的な勝利──あるいは消滅なのだろうということである。概念とは「これは自分と異なる」といえる「他者」がいて、初めて成立するものだからだ。この世に生きている者たちが皆「男性」になってしまったら、「男性である」という現象そのものが消え去るというわけだな。
そうなったら、彼女たちはもはや、カラフルな花柄の傘を差さないのだろうか? 俺たちと同じように、おおむね似たりよったりの色味の傘(そして柄は大体無地)か、ビニール傘だけを差して歩くようになるのだろうか?
今以上に、堅苦しいスーツを着るようになるのか? 出かけるときも手ぶらか、大きな書類かばんばかりを持ち歩くようになるのだろうか? ──思うに、男たちがかばんを持ち歩きたがらないのは、彼らに「かばんは重くてかさばるし、仕事がらみで堅苦しい」という印象があるからなんじゃないかと、いい加減な推理をしているのだが。
不意に、チンという軽い音がして扉が開いた。どうやら、考え事をしているうちに26階に着いてしまったようだ。俺は革靴で柔らかい絨毯を踏む。
これからしなければならないことは、何々、交通費の精算に報告書の作成、それから社内会議もあるのか……はあ、ずいぶんと忙しいな。こんなことがあと何十年も続くかと思うと、少しうんざりしてしまう。とはいえ、暮らしていくためには仕方のないことなのだろう。
オフィスの扉を開けると、まず黒いカーペットの敷かれた床が目に入った。入り口のところに肩身が狭そうに置かれた傘立てには、ビニール傘、ビニール傘、黒い傘、ビニール傘、紺の傘、それから申し訳程度にパステルグリーンの傘。どれも乱雑に詰め込まれている。俺もその中に畳んだビニール傘を突っ込んで、中に入っていった。
そこでは、黒いカーペットの上に並んだ白いデスクに向かって、数名の社員が作業をしていた。カタカタとキーボードを叩く音と、おそらくオンライン会議か面談でも行っているのだろう、控えめな話し声が聞こえてくる。俺が挨拶をすると、近くにいた人は手を止めて申し訳程度の微笑を浮かべ、「おかえり」とやさしい声で言うのだった。
数日ぶりのオフィスを見回しながら、俺は、白黒の室内に散った色彩の、雑然とした感じに驚いた。デスクの上にバラバラに置かれたボールペンや付箋の色。社員のかばんやら水筒やらの色。部屋の隅に置かれたホワイトボードのマーカーの色。
まるで早朝の繁華街と、そこの締め切られたシャッターに描かれた落書きのようだ、と思った。白む空の下で夜のカラクリの全貌が暴かれるときの、あの身も蓋もない光景である。白みがかった灰色の、のっぺりとした感じ。薄汚い色の無秩序。要するに、このオフィスには色彩の天才がないのだ。いや、ここに限った話ではなく、あまねくオフィスにはささやかな「素敵な趣味」というものが存在しないらしい。
「素敵な趣味」というのは、あの花柄の傘の彼女がよく知っているもののことだ。つまり、やれ定例会議だの、記帳だの、誰も本気で受け取りやしないおべんちゃらだの、そういう足取り重く面倒くさい規則から逃れた、軽やかで無意味な優美さのことである。識別される、しかし無意味なものは、その内に一抹の「よさ」を隠し持っているものだ。
オフィスも仕事も俺たちも、そういうものを本来的に知らない。無意味だからだ。無意味は本来無価値ではないのだが、ビジネスの世界においては例外である。あそこじゃ、売上やら純利益やらを伸ばす上で役に立たないものには価値を認めないからな。だから俺たちはこれまで、些細な心地よい無意味というものを知る必要さえなかったのだろう。
とはいえ、世の中はずいぶん儀式めいてきた。生活はロールプレイらしくなってきた。遊びとか思い出とか体験とか、形の残らない「コト」を愛するようになったのだ。無意味を無意味であるというだけで切り捨ててきたこれまでのやり方じゃ、もう「時代遅れ」なのだともいえる。
そういうわけで、ビジネスは無意味の領域にすらその貪婪な食指を伸ばし始めた。そうしないと売上が伸びず、経済成長もしないからだ。だってもう、売れる「モノ」のフロンティアなんてたかがしれている。
ああ、それにしたって滑稽だよな、「意味」の手段が「無意味」だなんてさ!
そうはいっても、無意味の側も無意味の側だろう。もう少し、ビジネスの侵略に噛みついたっていいだろうに。いいや、噛みつかないことこそ「無意味」の定義なのかもしれないな。
思えば、傘の鮮やかな色柄も、メッセージの隅に描かれたちょっとしたイラストも、弁当の彩りも、語る言葉を持たないじゃないか。意味するところを持たないじゃないか。
だから、容易に侵略されてしまうのだろう。それという自覚もなく忘れられていくのだろう。素人のイラストはメッセンジャーアプリのスタンプで代用できるし、弁当は宅食サービスでどうとでもなる。傘の柄だって、きっとみんなどうでもいいと思っている。これまで、ビジネスにも社会的義務にも侵されていない純粋な「無意味」という甘美を特権的に享受してきた女たちですら、おそらくどうでもいいと思っているのだ。
俺は「特権」が急速に消えていくのを見てきた。あんただってそうだろう? 今じゃ多様性の世の中だ。
きっと、今俺が花柄の傘を差したって、それを表立って咎めるヤツは一人もいないだろう。何なら、俺が花柄の傘を差すことで、「傘が売れる」という経済的効果と「多様性の促進」という倫理的効果が相まって一挙両得、喜ばれすらするかもしれないな。
要は「堂々と花柄の傘を差す」という「特権」は名目上なくなりつつあって、表面的には万人に開かれようとしているってわけだ。
しかも、それをビジネスが後押ししている。自分が「後援」だということを隠そうともせずに、公然と後押ししているんだ。「資本の力でみんなが特権を享受できるようにしよう。そして私は、そこで生まれる需要のために働こう」ってね。
元来、特権とビジネスとは犬猿の仲だったろうに──今日になって手を結んだんだな。まあ、ビジネスの側が自分の利益のために、勝手に後援を買って出ただけのような気もするが。
俺だって、あんただって、この巨大な運動の中の一部なんだ。そのにおいを嗅ぎつけて「こんなもの、所詮は金儲けのための紛い物さ」と言ってみたとて、どうしてもビジネスのプレートは倫理の奥に、深く深く潜り込んでいくんだ。
誰にも止めようがない。いつか反動で大地震が起こるかもしれない。しかしどうしようもない。起こりうる、だがあまりにも巨大すぎて想像力すら及ばない報いを、俺たちは待ち続けているのかもしれない。
とにかくだ──少なくとも形式的には──万人に対して平等に開かれているビジネスの主導によって、特権が特権でなくなったら、こういう論理が成り立つようになるだろう。
つまり「やりたいのならやればいい。なぜなら、それは万人に対して開かれているのだから」という論理である。
そこから更に進んで「やりたいというのにやれないのは、その人物の意志の強さの問題だ。要するに、意志が弱いから、あるいは結局のところ遅れた考えを持っているから、行動に移せないのだ」という論理さえも導き出されるかもしれない。
思えば「昨今、男らしさが窒息している」というのはある意味嘘っぱちであって、実のところ、現状は社会が「女装」したにすぎないのだろう。「自由になったのだからやればいい。もっとも、それをできる力があるならだが。やるもやらないも自己責任だ」という価値観は、まさにその典型例じゃないか。ものを識別して意味づけする精神性も。
つまるところ、社会が「女性」化したような見せかけをとっていたとしても、その内実は極めて「男性」的──いやむしろ、「女装」によって「男性性」への警戒感が解かれているのを背景に、一層激しく「男性」となってきているのかもしれない、と思料する。
とはいえ、それも当然のことである。というのも、人間社会の営みとは弥縫だからだ。かつて男性中心主義的に築かれた社会システムは、多少の改修を経ても、少なくともしばらくの間は男性的であり続けるだろう。いや、違う人間の「違い」を明確にしておかなければ気が済まないという点で、社会とはそもそも「男性」でしかありえなかったのかもしれない。
大体、全てをぶち壊してまた一から、なんてことはそうそうないし、ぶち壊すのが必ずしも正しいことだとは、俺だって思っちゃいないんだ。
だが、ぶち壊すべきだという建前はあるだろう? 社会の変遷は弥縫でしかないのに、それが劇的な改革であると信じ込まなければいけない。
だってほら、今この瞬間にも、社会のほつれたところからこぼれ落ちた犠牲者たちの怨嗟の声が響き渡っている。「貴方たちの声が拾われることは、当分ありません。長い時間をかけて変わっていく社会の、当代の犠牲者のまま死ね」だなんて口が裂けても言えないだろう? 「今にも革命が起きて、救われるさ」と言うしかない。
もしくは、それよりも更に高次のレイヤーで「革命など起こらない、ということをみんな分かっていて、あえてそれを明言しない──フリをする。いや、仄めかしはするけど」みたいな遊びをしているのか。
とにかくメタ、メタ、メタの上のメタは、どこまで行っても遊戯的だ。「社会を良くするためにSDGsやら何やらを推し進める必要があるんだ」「結局それも建前でしょ? 本当は自分のため、金儲けのためにそういうポーズをとっているだけじゃん」「とかいって利己的なフリをしているけど、内心人間それだけじゃない、今のままじゃいけないって分かってるよね?」「そう言って分かった気になってるけど、社会なんか変えられるわけないじゃん。結局『一人勝ち』を目指すのが一番合理的なんだよ」──レイヤーが上がるたびに反転する、偽善と偽悪の「戯れ」だ。この問答の果てに、実際に何かが変わるわけじゃないからな。
とにかく俺は、「男性」的なビジネスの世界に呑み込まれて特権が消えつつ、「消えつつあるように見える」という事実自体もある種の戯れ、虚像であると知ってしまっていて、板挟みになっているのである。
「男性だって、好きにメイクしたり花柄の傘を差したりすればいいじゃん。多様性の世の中なんだから」と嘯かれたら、こう言わざるを得ない。「できるわけねーだろ」と。
「特権はなくなった。誰もが自由で平等だ」という言葉が頭の中で反転するたびに「自由というのはあくまで建前で、特権は実質的になくなっていない。それでもやりたきゃ自己責任。それであんたが周りからどう思われるかなんて知らねーよ」という嘲笑がちらつく。
あるいは、自分にはない特権を見せつけられて苦しむフリをしながら、俺もまた、自分が知らず知らずのうちに享受している特権に酔いしれ、戯れているだけなのかもしれないと思う。
罪悪感は革かばんになって、右手にノートパソコンと書類の、人を焦らせるような重みを伝えている。
特権意識は革靴を履いた早足になって、通路を進む一歩ごとに音高く自身の存在を主張する。
被害者意識は晩夏の湿気をたっぷり吸ったスーツになって、うんざりするような質感で汗ばんだ肌に貼りついてくる。
そして、大して役に立たない高踏は薄く曇ったビニール傘になって、生ぬるい雨を受けながらビル街を一層濁ったように見せている。
頭の中で、傘のあの巨大な赤が迫ってくる。オフィスのいたるところに散った矮小な赤が明滅する。
「女たちの通り」で、女たちがワルツを踊っている。傘が回る。壁掛け時計の針も回る。時間は客観的な空間に置き換える形で可視化されたのだった。特権が謳歌され、社内会議の時間が近づく。
針がカチカチ鳴る、キーボードがカタカタ鳴る、静かな話し声がオフィスに不規則なテンポを生む。俺はデスクにつく。少し離れた席の女性社員は、わずかに疲れの滲んだ顔で社内面談を始めようとしていた。
ああ、この女は、花柄の傘だって差せるくせに。
これは羨望なのか、失望なのか。
分からないが、とかく、俺たちは同じオフィスに押し込められて仕事をしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
