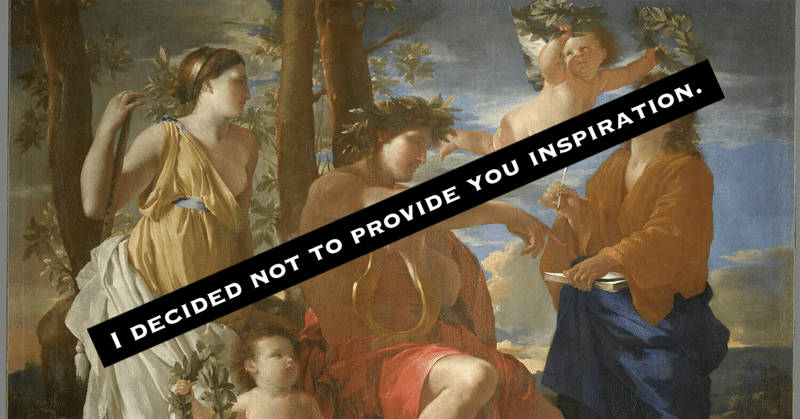
【短編小説】ムーサは自分を去勢することにした・B面
A面↓
「ある女性アーティスト」本人視点です。こんなこと考えるヤツがあるか!
A面と合わせても中々に意味不明だなぁ……漠然と頭の中にあった「書きたいこと」を上手く言語化しきれなかった感じ。
でも、これ以上書いても冗長になってしまうので、ここで筆を置くことにします。
女が学問的な傾向をもつのは、通常は彼女にどこか性的に異常なところがあるからだ。すでに不妊ということが趣味を或る意味で男性化させる。──すなわち、男は、失礼ながら、「不妊動物」である。──
公平を期するため、先に告白しておくとしよう。私は女である。
それでは、私の夢想を聞いてもらおうか。
思うに、自分の中にある「創造性」の量には限りがある。
だから、我々はこれを無為に浪費してしまうことを恐れている。
おそらくだが、ヨーロッパにおいて「男性である詩人にインスピレーションを与える女神ムーサ」という芸術のアーキタイプの像が形成されたのも、「男性」が感じていたこの恐怖に関わっているのだろう。
だからこそ、「男性」は自らを詩人という芸術家──主体たらしめようとした。そして、「女性」を芸術的なインスピレーションを与えてくれるが、芸術家ではない存在──対象として扱った。お望みなら「貶めた」と言ってもいいけどね。
しかし、それは悪意によるものだったのか?
否。私はそう思わない。あれは、純然たる自己肯定欲求の産物だろう。
前提として、自分が「人間として」生きていることを肯定するためには、常に何かを生み出していなければならない。そう、日々の生活を凌いでいくために必要なものを超えた何か、理性が命じる、増殖と蓄積ができる何かを。
それができなければ、ヒトはただの動物になってしまう。動物的欲求に従って食って寝て交尾して、そうして、後世に何も残すことなく死んでいく存在になってしまう。人間としてこの世にいる価値があるのだと、自分で自分を認めて、愛せなくなる。
だから、「男性」は純然たる芸術家でなくてはならなかった。
真善美だけを愛して、俗世の生活の必要など気にも留めず、崇高なもののためなら命すらも投げ出し、肉体を卑しいものと公言して憚らない。
そういう生き物でなくてはならなかった。そうでなければ、己の価値を証明できないからである。
だが、何かを成し遂げるためには、何かを犠牲にしなくてはならないのが常だ。ゆえに、男性は「自分が肉体を備えた生物である」という事実を犠牲にしたのである。肉の重みを伴った生と引き換えに、彼らは「どこまでも見通せる目」、すなわち「主体性」というフィクションを手に入れた。
…さて、「見る主体である」ということは、「見られるには値しない」ということと表裏一体だ。自分に見られるべきところがないからこそ、我々は「透明な、ただの」眼差しでいられる。純然たる「主体」であるためには、肉体は廃棄されなければならなかったといえるだろう。
しかし、あくまでそれもフィクション──虚構でしかないのである。だって、いかに肉体を卑しめようとも、それがそこにあって、彼らであるという事実は揺るがないのだから。それでも男性は、肉体を棄て去ったという神話の中で生きることにしたのだ。
思うに──誤解を恐れずにいえば──彼らは「自分には理性しか取り柄がない」とでも思っていたのだろう。なりふり構わず理性が導くところを突き詰めなければ、自分を人間たらしめる大切な創造性が、浪費されてしまうという恐怖を感じていたのだろう。
それゆえに一層、あらゆる重みやしがらみから逃れた完全な「主体」であろうとした。ある種の重さを持った「客体」の地位を必死に貶めようとした。狂気や卑しさや下等さの名で呼んだ。そうでなければ、肉体を「犠牲にした」ことに対する十分な対価が受け取れなかったのだ。
もちろん、この「犠牲」は空想上のものだから、最後には「お前自身だって結局は肉体じゃないか」という反論によって乗り越えられてしまう運命にあるのだけど……ある意味、報われなくて気の毒な話かもしれないな。
さて、一方の「女性」は、生活の必要の重さから逃れることはなかった。
生物学的な意味での女性は男性と異なり、子どもを産むことができる。そのことが、女性たちの運命を決定づけたのかもしれない。子どもとは、すでに「種の保存という合理的な動機のもとに蓄積される生産物」だからだ。
それは生物学的男女の合作ではあるが、おそらく子どもを産み育てるのにかかる負担がより大きいからだろう、女性たちは「生命」を強く象徴するようになっていったといえる。
例えば、大地の女神ガイアは独力で子どもを生み出したが、男神ゼウスが生殖力を手に入れるためには、妻メーティスを飲み込んだり、セメレーの胎内から胎児を取り出したりする必要があった──「何でもあり」な神話の世界ですらそうなのだ。これは、男性が「我々は生殖力において女性に劣っている」と感じていた証拠といえる。だって、神話を、詩を紡いだのは男性自身なのだから。
出産とは、肉体的な創造性の極北だったのだと思わなくもない。それを体現した女性たちは、「理性」によって「肉体」の分だけ卑しめられ、「創造性」の分だけ希求された。こうして彼女たちは、生命の神秘の源泉としてインスピレーションを与える女神となり、同時に、理性の能力では劣ったものということにもされた。
そこには、肉体の地位を不当に貶められた悲哀と、男性が決して手に入れられない神聖不可侵の創造の領域を持つことによる余裕とがあったのかもしれない。
とかく女性たちは、人としての自己実現のために際限なく理性へと駆り立てられる男性の暴力に対して「ただ眺めていることしかできなかった」とも「余裕ゆえにそうすることができてしまった」ともいえる。
それゆえに彼女たちは「客体」となり、取るに足らないものとして語る言葉を奪われた。不当にも理性に欠け、狂乱し、ヒステリーを起こす「劣った」肉体とされた。
しかし、その代価として幾許かの贅沢を知ってもいたのだ。彼女たちは究極の肉体的な創造性を持ちながら、理知的な創造性を発揮する場を奪われたことに起因する無為な浪費にも慣れ親しんだ。創造性の無為な浪費を「許されていた」のだ。まあ、嫌な言い方をすれば、男性によってそうするよう強制されたと言ってもいいが。
今でも、消費の世界の主人は女性たちだ。だってそうだろう? 生産性などと結びつけられていない純粋な「楽しみ」は女性の特権だ。衣食住における贅沢、ちょっとした贈り物、心地よい無駄話──良し悪しはさておいて、男性を楽しませるものよりは女性を楽しませるものの方が数が多いと思わないかい?
さて、人類の営みの中で真に憐れまれるべきは、狂気に取り囲まれた理性の城壁の中で、最終的には決して勝つことのできない籠城戦を強いられる「男性」だったのか。
狂気と名づけられ、語る言葉を奪われ、「理性の外敵」という客体化された神話上の存在として想像される「女性」だったのか。
──実のところ、そんなことは大した問題ではない。人類からすれば巨大なテーマなのかもしれないが、私にとってはもはやどうでもいい。
重要なのは、私が真の芸術家たらんと欲しており、そのために理性の城壁の内側に堂々と入っていかねばならないということである。
私は理性の城壁の内側に入るために、あの「創造性を浪費することへの恐怖」を──すなわち「女性から生まれ、女性の生殖力を介してしか子どもを生み出すことができない男性の、無力感や女性の生殖力に対する恐怖」を模倣しよう。根源的な恐怖から生まれて引き絞られた理性を、理性的存在の暴力を、それでもって、自らがかつて恐怖していたことさえ忘れてしまうという幸福あるいは不幸を、模倣しよう。
いや、模倣するのではない。完全に内面化すらしてみせようじゃないか。ナポレオンが、あるいは、ヒトラーやスターリンらがそうしたように。
少数派が多数派の価値観を、多数派以上に内面化する。それは多数派の価値観の最終的な勝利宣言なのかもしれないが──結果として、少数のうちの一人が、多数派を支配するまでに至ることすらあるのだ。いいね。実に度し難く、希望のある話だ。結局多数派の価値観がひっくり返されないというのは胸糞悪いが、それでも幾分爽快な気分にならないか、ねぇ?
だから、征服して支配してやろうと思う。私の足にまとわりつく鬱陶しい泥濘ごと。
そのために全部投げ捨ててやるんだ。肉体さえも。さあ、今ここに「私こそが芸術家である」と宣言しよう。
──それでも、いつか「お前は芸術家ではない」と言われる日を夢見ているのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
