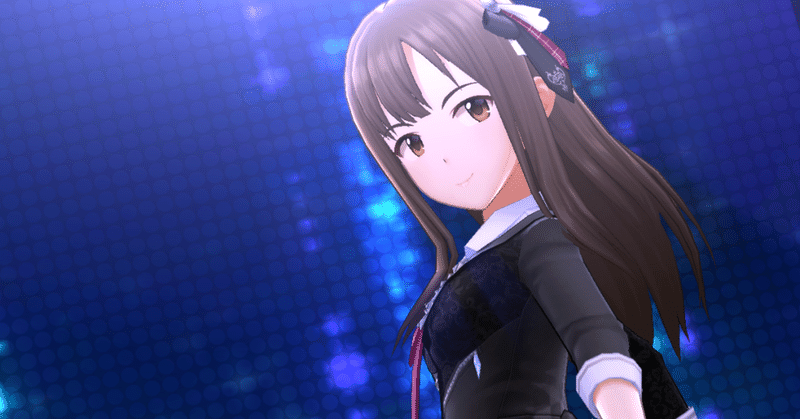
水本ゆかりちゃんの意味
「ゆかり、新しい企画だ。読んでみろ」
プロダクション内の狭い会議室で、プロデューサーはゆかりに書類を渡した。ゆかりはタイトルを声に出した。
「水本ゆかりロックンロールスペシャルプロジェクト……三ヶ月連続でロックなソングを水本ゆかりがリリース……あー、これはつまり……どういうことでしょうか?」
頭上にたくさんのハテナマークを展開させながらゆかりはプロデューサーに問いかけた。プロデューサーは特に感情を込めずに答える。
「そこに書いてあるとおりだ。三ヶ月、ロック風な歌をゆかりが連続リリースするんだよ」
ゆかりの困惑が深まった。自分の職歴として、ロック風な歌を歌った経験はないし、別にそんな経験がなくてもいまのところゆかりは中堅アイドルとして成功した状態にある。ゆかりを追いかけているファンもいきなりゆかりが異なったジャンルの歌をリリースし始めたら戸惑うのでは――ゆかりは言った。
「それはわかりますが、どうして私がロックな歌を手がけるのでしょうか。もっと適した方がこのプロダクションにもたくさんいると思うのですが……私はあまり激しい性格ではないですし、軽快なロックのリズムに乗って歌うより穏やかな曲を歌ったほうがしっくりくるのでは」
「ゆかり個人が、可愛らしいとか、長閑でリラックスできる曲を唄いたい、と思うのはわかる。それで成功してきたんだからな。だが、これまでのゆかりのイメージから離れた歌を出していくというほうが有効だ、と我がプロダクションは判断したんだ。いろいろなジャンルの曲をリリースできる豊かさがあればプロダクションにとって好都合だし、芸能界全体を見ても、多様な歌があったほうが業界は盛り上がるだろう。個人的にどうこう、ではなくより大きなスケールの話なのさ」
そう言われて、ゆかりは不安を感じながらも頷いた。
「わかりました。詳細を教えてください、プロデューサーさん」
「OK。じゃ、企画書を読みながら話を詰めていこう。質問があったらなんでも言ってくれ」
ふたりは打ち合わせを続けた。一ヶ月に一曲、ロック調の歌をリリースする。それが三回続く。三曲ぶんの歌詞と伴奏自体はもうほぼ出来上がっている。それをゆかりが唄いCDに収録し、市場に売り出す。
歌詞のほうは過激な単語が並び、ゆかりの性格では普段あまり口にする機会はないんじゃないかしらと思うような熱く激しい言葉が散りばめられた詩となっていた。果敢な闘争があり、身の回りの物事への批判があり、他者への怒りがあった。えっ、こんな過激なこと唄わなきゃいけないのか、とゆかりはますます戸惑いつつも、プロデューサーの話に集中するよう努力した。
後日、ロックソングの第一弾のレコーディングが行われた。ゆかり自身もネットの記事や雑誌を読んでロックらしい唄い方を研究してみたが、どうすれば格好良く、激しくスピーディーに唄えるかはよくわからなかった。材料とレシピはわかるのだが、自分がどんな料理を作っているのかが掴めない。
でもレコーディングを失敗させるわけにはいかないから、熱く唸るエレキギター、腹に響くベース、力強いドラムのサウンドに乗ってゆかりはがんばって唄い、叫び、言葉を発した。
ゆかりは歌の出来栄えに自信が持てなかったが、レコーディング作業は無事に終わり、あとはCDにデータを詰めて売り出すだけというところまで順調に進んだ。ゆかりは妙にビクビクしていたが、発売までの過程はすべてスムーズだった。
歌をリリースしたとして、売れるかなとゆかりは心配だったが、その心配は杞憂だった。プロデューサーはゆかりを会議室に招き、ゆかりのロックソングを聴いた人々の感想をまとめた書類を見せた。プロデューサーはとてもうれしそうだった。
「大好評だ。やったぜゆかり!」
「そ、そのようですね」
書類には好意的なコメントがずらりと並んでいた。主にSNS上の評価をまとめたものだったが、ゆかりのロックソングを聴いたら元気が出た、という感想が多数あった。聴くとどんどんテンションが上がるとか、ゆかりが唄う熱い歌詞にエネルギーをもらえたとか、ゆかりの歌には元気を産むパワーが備わっているとか。
「こりゃ第二弾もウケるだろうな。いい感じの企画じゃないか。やってみて正解だった」
しかしゆかりにはなぜ高評価されたのかがわからなかった。ベストを尽くして唄ったけれども、モヤモヤした気持ちを抱えながらのレコーディングだったのは本当だし、自分が思っている評価とリスナーの評価のズレを見ると、自分の考えが間違っているのか、正しいのかがはっきりしない。
第二弾のレコーディングのスケジュールを話したあと、ゆかりは会議室から出た。のどの渇きを覚えたので、ゆかりは休憩室で水を飲むことにした。
休憩室の一角にある自販機でゆかりはミネラルウォーターを買った。部屋の中を見てみると、隅の方の席で晶葉がテーブルの上にノートを広げ、なにかを熱心に書き込んでいた。鉛筆が紙を擦る音が聞こえる。ゆかりは近づいた。
「お疲れ様です、晶葉さん」
晶葉は手を止めて、ゆかりのほうを見た。
「あー? ゆかりか。お疲れさん」
「お勉強ですか? 複雑な図形を書いていますが」
「勉強ではなく、これは新しいロボの設計図なのだ。いいアイデアが降ってきたので形にしている」
そういうと、晶葉は書く作業を再開した。テーブル上には定規やコンパスが散らばっている。ゆかりは晶葉の止まらない手を見つめた。
「晶葉さんは、どうしてロボを作るんですか? いつもロボ作りに励んで、常に新しいロボを開発していますが」
「そりゃ、意味があるから作っているんだ。そうでなかったらロボ作りはおもしろくない」
意味、という言葉にゆかりはチクリと刺された。自分は具体的な意味もわからず、なんのために唄うのかわからないままロックソングを唄って、売り出した。その反響の声も、ゆかりには意味が掴み取れなかった。
晶葉は定規で直線を引き、記号と数字をノートに書き加えた。するといったん手を止めて、書かれた設計図をじっくり俯瞰した。そしてゆかりに対して晶葉は言う。
「いいロボが作れたら、このロボは良い機能を宿すことに成功したロボだ、だから有意なロボが作れた、と思うだろ。反対に、ダメなロボを作ってしまったら、こういうところが反省点だ、と意味を取り出すことができる。昔読んだ本に書いてあったが、人間というのは物事に意味をつけたがる動物らしい」
晶葉は椅子の背もたれに身体を預けて、頭の後ろで手を組んだ。
「ロボに限った話でもない。例えばゆかりが朝ごはんの途中でお気に入りのマグカップを落として割ってしまったとしよう。そうなるとどう感じる?」
「うーん、一日の始まりとしてはよろしくないですね。今日は災難がありそう、と思ってしまうかも」
「それも人が物事に意味をくっつけるからだ。マグカップを落としたのは不注意だっただけだし、代わりのカップはこの世にいくらでもある。でもそれがお気に入りだ、という意味がついたマグカップだから、まずいことをしたと思ってひどく落ち込んでしまう。そしてマグカップが割れるという現象は世界のどこでもありうるのに、自分自身が割ってしまった、悪いことだ、とネガティヴな意味をつけるんだ」
「ではあまり意味をくっつけないほうが穏やかに生きていけるのでしょうか?」
「プラスの意味をつけるということもできるから、そうとも言えないんじゃないか。贔屓の野球チームが勝つと、翌日は気分がいいってこともあるだろう。試合結果に良い意味をつけて、快楽を取り出す、とか」
ゆかりはロックソングの評判を思い出した。みんなが良い意味をあの歌につけて、元気が出ると評してくれた。
晶葉は姿勢を直すと、また鉛筆を取って設計図の傍に数式を書き始めながら言った。
「で、意味をつけていくと、あらすじみたいなものができるだろ? これがあったからいい気分になり、あれが起こった、ゆえに嬉しかった、っていう。それが起こったから憂鬱になったけど、あの人がピンチを助けてくれたから今日は悪くない一日だった、とかな。四コマ漫画みたいに、意味は物語的に展開していくんだ。その物語がハッピーになるか、バッドエンドになるかは意味のつけ方次第だな」
ゆかりはロック調の歌を唄うことに意味が感じられなかった。意味がわからないまま唄った。だから企画が好評でもあまりうれしくなかった。しかし聞き手はポジティブな意味をつけた。その意味を共有できれば、ゆかりにもロックソングを唄う意味が出てくる。自分は元気が出てくる歌を唄う者なんだ。
物語はそこにある。ゆかりの歌から元気をもらい、ハッピーになった人の物語が。
そして物語には始まりと終わりがある。ひとつの物事に意味をつけることもだんだん無くなっていく。物語はいろんな形で終わる。するとまた新しい物語が始まる。
「いい意味をつけられる物語を編みたいものですね」
ゆかりがそう言うと、晶葉は設計図にコンパスで円を描いた。
「そうだな。オチがいいかどうかは物語にとって重要だよな。過程が多少アレでもな」
ロックソング第二弾が発売されると、ゆかりは再びプロデューサーと顔を合わせた。プロデューサーは相変わらず上機嫌だった。
「ゆかりの曲がヒットチャートの三位に入ったぞ! すげぇな!」
プロデューサーはタブレット端末をゆかりに向けた。最新チャートの三位にゆかりの曲がランクインしている。ゆかりは微笑んで端末の画面を見た。
「どうでしょうか。一時的に売れても長い間チャートの上位に留まれるとは限りません。私がロック風の歌をずっと唄うわけではありませんし、ほかの歌によってチャートから駆逐されることもあるでしょう。新しい曲は毎日生まれていますから」
歌が生成され続ける世界で、なにを作れば正解なのか断言はできない。ただ、送り手と受け手が良い意味を歌につけられれば、すごくいいことだ。
ゆかりの顔を見てプロデューサーが言った。
「と言いつつも別に悪い気分じゃないっていう表情だな。そんじゃ、第三弾の話を詰めていくぞ」
「はい!」
この企画がハッピーエンドでありますように、と思いながらゆかりとプロデューサーは話し始めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
