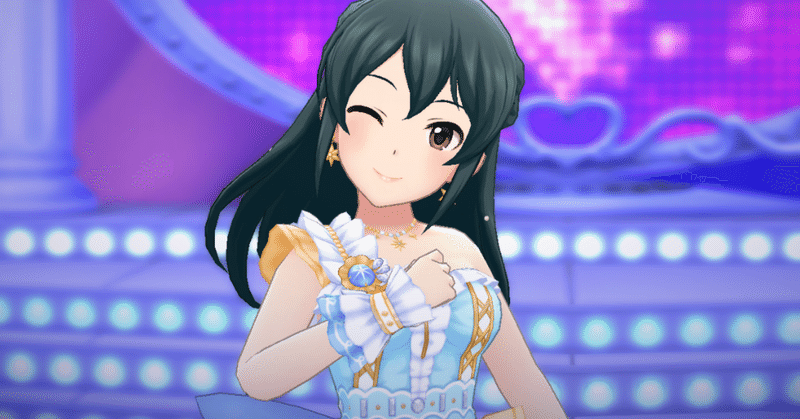
大石泉ちゃんの傑作
このところヒットチャートが騒がしい。というのも「ついに出た! これがこのアイドルの最高傑作なのだァー!」と評されるような曲がドカドカリリースされているからだ。それぞれのアイドルがこれまで発表してきた曲と比べても特に優れた傑作を世に送り出し、チャートの上位を総なめした。
泉はそんな業界の様子を見ながら、私には最高傑作なんてないな、と思うのだった。泉はそこそこ評価されているアイドルだし、落ちこぼれというわけでもないけれど、最高傑作なんていう曲は発表できていない。
傑作をリリースしたアイドルにはブーストがかかるというかオーラが付くというか、「あの曲を発表した人ですか! すげぇな!」という評判がくっついて仕事は多く回ってくるし金も稼げるし名声も得られる。泉は別に金銭や栄光を無性に求めていたわけではなかったけれども、やっぱり自分にとってこれが最高のものだな、と思える曲があったほうが、楽しいはずだとも考えるのだった。
とはいえ具体的にどうしたらサイコーの曲を作っていけるかはよくわからない。そうこうしているうちに「今度はこのアイドルが最高傑作を発表したぞ発表したぞ発表したぞ発表したぞうわあああああああああああああああ!」という評判がくっついた曲が複数リリースされ、チャートはより騒がしくなった。
「我がプロダクションも負けてはいられません」と打ち合わせの席で泉のプロデューサーは言った。「傑作と呼ばれる曲揃いのチャートに一石を投じるプロジェクトを始めましょう」
泉はプロデューサーから渡されたプロジェクトの概要が書かれた書類を読んだ。
「ファンからのリクエストに応じて歌を作っていくというプロジェクトなのね」
プロデューサーは頷いた。
「出発点としては、大石さんが過去に唄った曲をアレンジしてリリースしていきます。そこでまず我々のほうで曲をアレンジするチームを設置し、ファンのみなさんからインターネット上でリクエスト案を募集します。その案をもとに曲をアレンジしていきます」
「私もそのアレンジチームに入るって書いてあるね」と泉。
「大石さん本人が唄うのですから、あなたがいないといかんのです。ファンのみなさんの意見を組み込むことで優れた曲を作り、チャートに切り込んでいくのがこのプロジェクトの狙いです。軌道に乗れば、過去作のアレンジではなくまったく新しい曲をリクエストをもとに作っていくことを見込んでいます」
この方法で傑作と言われるものを生み出せるだろうか? 泉は少し不審に思ったが、プロデューサーのことは信頼しているし、それなりにおもしろそうだし、ファンの声に応えてがんばる企画というのにはやりがいを感じる。
「うん、わかった。やってみるよ」
泉が企画書から顔を上げると、プロデューサーは微笑んだ。
「まずはアレンジチームとも話し合う場を作りましょう。参加するメンバーはこういうメンツになっていまして」
そんなふうにふたりは話を詰めていった。
もしファンからリクエストが来なかったらこの企画はそもそも始まらないのだが、プロジェクトの開始後、泉を含めたアレンジチームのもとにはファンから大量のリクエストが寄せられた。「この静かな曲にあえて疾走感をつけてみたらきっとカッコいいと思います」「情熱的なラブソングをいっそ演歌っぽくやってみたらどうですか?」「この曲をエイトビートにこだわってアレンジしてくれ」「インダストリアルメタルとかに挑戦するのもありなのでは」「泉ちゃんのシャウトが聴きたい! 歌詞を叫ぶアレンジをやってください!」「デビュー曲をいまの泉ちゃんがアレンジしてもう一度歌い直すのはどうでしょう?」「マイナーだけどこの曲が好きだから、これをアレンジしてメジャーに昇華させて欲しいです」などなど。大雑把な注文が多かったがアレンジチームは丁寧にリクエストを分析し、曲を調整していった。
泉も調整作業中にがんばってアイデアを出し、チームのほかのメンバーの話を聞き、唄った。そうして仕上がりは上々だと思える曲がたくさんできた。もしかしたらこれは傑作レベルか、それに近いんじゃないかと思える輝きのある曲も生まれた。リクエストによってアレンジされた曲は次々とリリースされていった。
そしてヒットチャートの中に泉の曲の名が現れ始めた。「これが大石泉の最高傑作なのでは!?」という文言がつくことはなかったが、「大石泉の実力はかなりのものだ!」と、泉を高く評価するコメントが巷に広がるようになった。
名声が集まると、泉たちのプロジェクトは予定していたとおり既にある曲のアレンジではなくリクエストをもとに曲を作り上げていくというフェイズに移行した。アレンジチームはデザインチームという名前になり、メンバーも増えた。
リクエストはますますたくさん集まった。泉を主人公にした物語を生成するように、「泉ちゃんにはジャズっぽい曲も似合うのでは」「俺が考える泉ちゃんの理想の歌はこういうのだ」「ちょっとエッチな歌詞の曲も聴いてみたいです」「重厚な雰囲気の曲もいいんじゃないか」とファンから曲の原型となる意見が集い、デザインチームはより注意深くそれらのリクエストを検討・分析し、ファンの声を取り入れ、質の高い曲を作り続けていった。
そうした努力を重ね、泉の人気は上昇傾向に乗った。泉は率直に言ってうれしかった。チャートの上位に入ることも珍しくなくなった。メディアへの露出も増えたしライブの動員数も大きくなった。このまま人気アイドルとして活動できるとしたら素敵だなと思いながら泉はリクエストに応え、唄った。
しかし泉は徐々に疑問を持ち始めた。人気が上がったとはいえ、最高傑作と呼ばれる曲は未だリリースできずにいるのだった。せっかくがんばっているのに、これが大石泉の決定版! というものを持てないのは少し歯痒かった。ほかのアイドルが傑作と言われた曲を作る中で泉は作れない。かなりの人気を得たぶん、なぜがんばっても自分が特筆すべき評価をもらえないのかが気になった。リクエストに耳を傾けて曲を作るというモデルには限界があるのか、と思い始めた。
ある日、久川颯というアイドルがリリースした曲がヒットチャートの一位になった。中堅アイドルとして活動していた颯だったが、今回は異例となるヒット曲を生み出し、「久川颯の最高傑作きたる! これは凄い曲だ!」とアイドル業界は大騒ぎになった。
泉も颯の曲を聴いてみた。颯の歌声は伸び伸びと元気よく、美しかった。曲のリズムはシンプルだし、歌詞もありふれた内容だったが聴いていてとても心地良く、いい気分になる。これが傑作というものなんだ、と泉は感じ、同時に自分はこんなふうな曲は作れないのか、とも思った。泉は、こんなときはプロデューサーに相談してみようと決心した。
事務所に赴き、プロデューサーのオフィスに入ると、泉は思っていることをプロデューサーに話し始めた。
「プロデューサー、私の評価はもう上がらないのかな。リクエストから歌を作るプロジェクトでいい結果を出せたけど、これ以上の成功は見込めないと思うんだ……」
プロデューサーは不思議そうな顔つきだった。
「私も大石さんは今回のプロジェクトでいい結果を出していると思います。そして、もっと成功するのではないかと感じていますが」
泉はそれを聞いて少し戸惑う。プロデューサーは違う見方をしている。ならば自分の見方を言おう。
「実はリクエストに応え続けるの、ちょっとしんどいの。がんばって考えて話し合って、良いものが作れるっていうのはうれしいよ。でも最高のものは作れないんだ。そう考えていると、リクエストに従っている意味がわからなくなって……」
それがここまでプロジェクトに参加してきた泉の本音だった。リクエストに応えれば良い歌を作れるというのは確かなこと。でも最高に良いものは作れない。リクエストは集まってくるけれども、泉は最高の一品にまとめられない。それでもまたリクエストはやって来る。泉はまた最高ではない歌を作る。そのサイクルがキツいと感じ始めていた。
一瞬だけ、プロデューサーの目つきが鋭くなる。
「今回のプロジェクトを通して、大石さんが創造してきたものはたくさんあります。いずれプロジェクトに区切りがついてデザインチームが解散したあとも、大石さんは限りなく多くの曲を創造するでしょう。それこそが最高のものを作るというチャレンジではないでしょうか」
「作ること自体が、いいことなの……?」
「創造し続けること、無限に曲を作ること、大石さんにはそれができると私は思っています。私は最高傑作と評される唯一の作品を作るのがアイドルのすべてだとは思いません。価値のある作品を常に創造し続けること、それがアイドルの良い仕事だと思います」
泉はプロデューサーの声を聞きながら考える。たったひとつの輝きを灯すのではなく、無限に灯りをつけていくこと。最高はただひとつの解ではないこと。それが答えだったのだ。泉は言った。
「じゃあ、最高傑作のバリエーションがいっぱいあってもいいのかな。最高傑作に代入できる値はいくらでもある、っていうか」
「はい。そのいくらでもある値を作るのが創造というものだと思います。イメージは無限に追い求められますよ。もちろん、ひとつの曲に収めるためには割り切りも必要ですが、創造に限界はない。別な形でイメージを表していけば、大石さんが生み出すものは限りないものになると思います」
泉は肩から力が抜けるのを感じて、苦笑した。
「最高傑作は特定のひとつだけじゃない、って考えればよかったのね」
「ひとつ、ふたつ、と数えられるものではないのでしょう」
プロデューサーはそう言って、深く頷いた。
リクエストを元に曲を作るプロジェクトもあと一曲で終わろうとしていた。泉は最後だからとチームの中で積極的に意見を出し、リクエストを深く考察し、イメージを膨らませた。
そして出来上がった曲を、泉は好きになった。これ、けっこういけるんじゃないの、と思った。プロデューサーにもその曲を聴いてもらうと、良い出来栄えだからこの曲のプロモーションビデオを作ってみよう、という話になった。すると泉は晴れ晴れとした気分になリ、この曲を最高傑作に代入しよう、と決めた。
するとそんな気分のまま、次はどんな曲がいいかなと考え始める自分がいた。自分はアイドルなんだな、と泉は思い、アイデアを練り、創造し始めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
