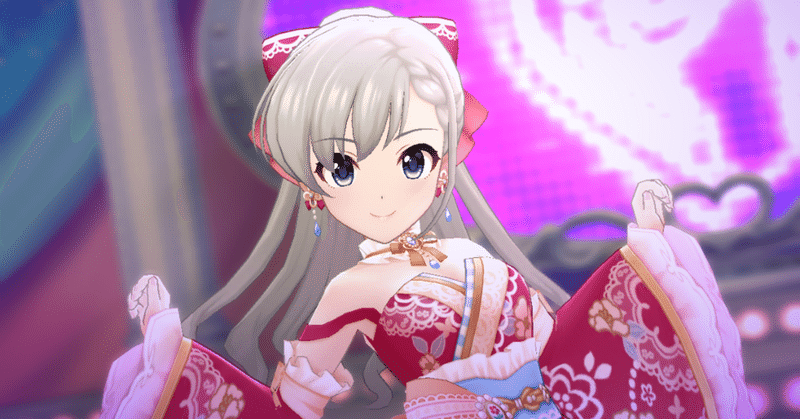
久川颯ちゃんのスロットル
これといって特技のないアイドルは淘汰されていくのだろうか。颯はスマホの画面に映るヒットチャートを見ながらそんなことを考えた。
チャートの上位はデビューしたてのアイドルたちが手がけた曲で賑わっている。まだアイドルとして経験の浅い子たちがチャートに名前を連ねるのは、どの子たちもしっかりとした特技を持っているからだった。しかしそれぞれの特技は、世界史マニアであるとか、美しい水彩画が描けるとか、表計算ソフトを使いこなせるとか、一見アイドル活動とはあまり関係がなさそうなものと思われた。
だがそんな特技でも、周りに対して自分を十二分にアピールできるツールとして機能した。デビューしたての子たちはメディアに登場するたびに自分の得意分野を語り、自信を持って特技を示していった。するとメディアを見る側は「あの子は特定の分野に詳しいからもっといろいろな話を聞きたい」「あの子のスキルを真似したい」「あの子が得意な技術を披露するところをたくさん見たい」と受け取り、デビュー間もないアイドルたちの人気はだんだんと上昇していった。
颯はそんなアイドルたちの活躍を眺めて、自分はどうしたらいいかわからなくなっていた。颯がイメージするアイドル像と直接関係のなさそうな特技でも、積極的に使っていけば周囲に強い影響を与えられる。ならば自分も、と颯は思うのだが颯には特別な技術や知識がない。では久川颯というアイドルは徐々に萎びて、活力を失っていくのだろうか。
颯は自分のプロデューサーに相談してみることにした。プロデューサーに時間を作ってもらうよう頼み、事務所内の一室で向かい合って座った。
「ねえPちゃん」と颯は切り出した。「はー、特技がないよね。どうしたら、みんなの人気を引き寄せる特技が身につくかな」
プロデューサーはそれを聞いて「うーむ」と唸ったあとで言った。
「特技がないことは悪いことじゃないと思うよ。だから特技を持てる者でない自分は劣っている! って考える必要はないんじゃないかな」
「Pちゃんは、はーが特技を持ってなくても、気にしない?」
と颯は聞いた。プロデューサーは頷いた。
「特殊な技能を持たずとも、颯はそこそこ成功した。これは基本的な能力が高水準にあるということだろう。だから、特別な力がなくても次のステップに颯は進んでいけるよ」
プロデューサーは颯を元気づけるように言った。いまの話の内容は颯にもよく理解できるものだった。
だが、基本スキルを習得していくだけでいいんだろうか、と颯は不安に思う。なにかスペシャルな能力を得る機会は、自分に訪れないのか。
週末の土曜日、颯はとあるライブハウスに足を運んだ。そこで近ごろ人気を集めている新人アイドルのライブが開催されるのだった。
それほど大きくないライブハウスの中には大勢のお客さんが集まっていた。主役となる新人アイドルは手品が得意で、ステージ上で手品を披露するスタイルが話題となっていた。
やがて開演を迎え、ステージにアイドルが登場し挨拶をした。
「みなさん、今日は私のライブに来てくれてありがとう。超楽しい時間をみなさんと一緒に過ごせたらいいなって思います。それじゃ、始めましょう!」
その言葉を受けて歓声が上がる。そして歌が始まった。颯はライブハウスを揺らすリズムを感じながらアイドルの歌を聞き、ダンスを見る。なかなかレベルの高い動きに見える。一方で、自分でもあれくらいのことはできるんじゃないかなとも思う。
一曲目が終わり、二曲目も終わったところでアイドルは「ちょっと手品をやります!」と言ってトランプのカードの束を手に持った。歓声があがる。アイドルは慣れた手つきでカードをシャッフルしたあと、束の一番上のカードを観客側に見せた。スペードの3だった。
「スペードの3ですね。このカードは目立ちたがりな子です」
そう言ってスペードの3を束に戻すと、新人アイドルは再びカードをシャッフルし始めた。目にも止まらぬ超高速のシャッフルだった。アイドルの手の中でカードが凄まじい勢いで回転し、ぐるぐると舞い踊り、現実のものとは思えないスピードでシャッフルが続いた。やがてアイドルは手を止めた。
「いっぱいシャッフルしましたね。では、一番上のカードはどうなっているでしょうか?」
束の一番上をめくるアイドル。めくれたのはスペードの3だった。
「おっ、さっきと同じカードが一番上に来ました! 目立ちたがりですね。二番目はどうでしょう?」
アイドルはもう一枚カードをめくった。現れたのはまたしてもスペードの3。さらにもう一枚めくる。次もスペードの3。次の次もスペードの3だった。さらにめくっていくと、現れるカードはすべてスペードの3になっていた。
「不思議ですね! 全部スペードの3になっちゃいました! どんだけ自己主張激しいんだよ。じゃ、次はこうします。ほいっ」
と言ってアイドルはカードの束を頭上に放り投げた。観客の視線も上にあがる。アイドルはひらひら雪のように落ちてくるカードを踊るような美しい動きで一枚残らず捕まえ、カードの束が再びアイドルの手の中に収まった。
「さて、カードを見てみましょう」とアイドルは束をめくった。「一番上は――ハートの3ですね」
アイドルはさらに次のカードをめくる。次もハートの3、さらにその次もハートの3。めくってあらわれる全カードがハートの3に変貌していた。
「これまた不思議です! ハートの3以外はどこかに行っちゃいましたね。スペードの3になにがあったんでしょう? みなさん、考えてみてください。さて、今回の手品はこれで終わりです。次回はもっと不思議なことを起こそうと思ってます!」
それを聞いて観客は拍手をアイドルに送った。颯も拍手した。アイドルはニッコリ笑った。
「ありがとうございます。さあ、次の曲にいきましょう!」
再び音楽が流れ始めた。観客は手品を見せられてよりテンションが上がったらしく、先程より大きな歓声が起こり、アイドルのほうもパワーを上げて歌っているようだった。
このアイドルが歌と踊りのスキルを向上させ、さらに手品のテクニックも向上させていったらどうなるだろうと颯は思った。歌うこと、ダンスを踊ることという基礎を固めた上でさらにレベルの高い特技を加えたら、颯に勝ち目はあると言えるか。
数週間経ち、事務所でプロデューサーは颯に企画書を手渡した。書類の一番上には「アイドルパフォーマンスマラソン」と大きなフォントで書いてある。
颯は聞いた。「パフォーマンスマラソンってなに?」
「テレビの特番だ。だいたい四〇人のアイドルを集めて、数分間、それぞれのアイドルになにかしらやってもらう。歌を唄うのでもいいし、シャドーボクシングをしてもいい。そういうパフォーマンスを陸上競技のマラソンの長さに合わせた約42分の間連続してやって、視聴者を楽しませようという企画だよ」
「はーの出番は……」颯は企画書を読んだ。「1分と4秒か」
颯はその時間を使って良い結果を出さねばならないことになる。企画にほかのアイドルが多数参加していることを考えると、半端な出来のパフォーマンスではほかのアイドルに比べ霞んでしまうし、制限時間内に印象を残さないと視聴者の関心を刺激できないだろう。1分4秒で颯はなにかを成し遂げなければならない。
プロデューサーが言った。
「この番組が収録されるのはちょっと先の話になる」
颯は書類をめくってスケジュールを確認した。確かに日程には余裕がある。
「それまでにどんなパフォーマンスをやるか考えていこう」とプロデューサー。
「ん、わかった。考えてみるよ」
颯は頷いた。心の中には不安がたくさんあった。
颯は日々のタスクをこなしつつ、マラソン用アイデアを練った。1分4秒の内に自分がなにをするかといえば、歌って踊るんだと思う。けれども何度も読み返した企画書に記されていた出演アイドルたちは、みんな個性的な特技を持っている者ばかりだった。当然、特技を駆使してアピールしてくるだろう。
その状況下でなにをやるか。思いっきり早口で歌う。1分ちょっとの間、歌もダンスも同じパターンをひたすら繰り返す。変な顔でダンスをする。などなど考えてみたがアイデアはまとまらない。
こういうとき、どうしたらいいか――颯は友達に相談することにした。
颯が喫茶店の席についてジュースを飲んでいると、喫茶店の入り口のドアが開き、のあが姿を見せた。颯は手を振って言った。
「のあさん、こっちだよ」
「颯……」
のあは静かに歩み寄ってくると、颯の向かいに座った。
「落ち着いた雰囲気の喫茶店ね……」
「いい感じでしょ。はー時々ひとりでここに来るんだ」
のあはアイスコーヒーを注文し、飲み物が来るまでふたりは軽くお喋りをした。やがてアイスコーヒーが運ばれてくると、のあは颯に聞いた。
「私に相談したいことがあるそうね……なにか困っているのかしら……」
「ええと、特技がないのに欲しいときって、どうしたらいいんだろう。それを知りたいんだけど、わからなくて、困ってる」
「特技……? 颯はそれを求めているのね」
「うん。はー、一個くらいは特技があったほうがいいんじゃないかって思うんだけど」
「そう……でも……なぜ他人に対して効果的な特技となりうるようなおもしろい行為をすると人は関心を持ってくれるのかしら……?」
「それは――なんでだろう」颯は首をかしげた。
のあはアイスコーヒーを口に運んでから言った。
「それはきっと、時間を支払っているからね……」
「時間を支払う?」
颯はきょとんとした。のあは続ける。
「つまり、楽しい、おもしろい、この人はすごい、と感じるとき、私たちはそれを感じている間の時間を消費しているということ……」
「それは」と颯。「おもしろいことに出会って楽しいなって思っているそのときに流れている時間を、使ってるってことか」
のあは小さく頷いた。
「時間というものは貯めておいたり増殖させたりできない、有限のものだわ……常に進んでいき、巻き戻すことも不可能……だからこそ有意義に使いたいと誰もが思う……尺が2時間の映画を見たとして、その映画がつまらなければ2時間を有意義に使えなかった、無駄に時間を使ってしまった……と嘆くでしょう……ゆえに時間はできるだけ満足いく支払い方をしたいと思う……おもしろいものに人の関心が集まるのは、楽しく時間を消費できそうだな、と考えるから」
であれば、自分はマラソンの中の1分4秒という時間を、見ている側が有意義なものとして思うように仕上げなくてはならない、ということだなと颯は思った。
しかし、いったい、どうすれば?
のあが言った。「颯は……他人におもしろいアイドルだなと、思われたいのかしら……」
「うん。でも、はーには特技とかないし……」
颯はうつむいてぼそぼそとつぶやいた。のあは数秒間黙ったあとに言った。
「特技がなければ、作ればいいんじゃない?」
「えっ? はーが自分で、特技を作る?」
「私ならそうするわ……」
特技がないと悩んでいるのなら、それを作ってしまえばいい。シンプルな回答をのあは述べた。そう考えると簡単な話のように聞こえる。そこになければそこに作り出せばいい。のあはさらに言った。
「私は颯の歌声を聞いたりダンスを見るのが好きだわ……それをさらに改良して、あなたが特技と呼べるレベルまで鍛えてみたら、颯の欲しいものが手に入ると思う……」
「そっか……はーの武器って言ったら、やっぱり基本スキルだもんね。それを特技にしちゃえばいいんだ。特技は作れるんだ」
歌とダンスはあっても特技がないのであれば、歌とダンスを特技にしてみればいいのだと颯は気づかされた。心が徐々に熱を帯びてくる。
すると、のあはおもむろにスマホを取り出し、画面をタップしてから颯に向けた。「最近見つけた、こういう動画がある……」
颯は画面に注目する。
「『スーパーヴォーカルトレーニング講座』っていう動画? 『ヴォーカロイドみたいに高いオクターブの声を出せるようになろう!』『声を解剖して自在に操ろう!』『歌と脳と身体の関係を知ろう!』か。ふむふむ……この動画で教えているトレーニングをやると、歌声がとんでもないことになるのか」
「ええ……かなりきついトレーニングだけれど……颯の歌をレベルアップさせてひとつの『技』に持っていきたいのならやってみてもいいと思う。私もまだこの動画で紹介されているメニューをすべてやったわけではないけど……ちなみにスーパーダンストレーニング講座という動画もある……」
「ありがとう、のあさん。チェックしてみるよ」
颯の悩みはほとんどなくなっていた。自分にこれといって特技がないのなら作ってみればいい。特技を作ることにトライしよう。納得いくまで。颯はそう思った。
アイドルパフォーマンスマラソンの収録日がやって来た。颯は控え室で出番を待っていた。数十分ほど経ったころ、プロデューサーが控え室に入ってきて言った。
「もうすぐ出番だ、颯。準備してくれ」
「はい。はーのパワーを炸裂させるよ~!」
颯とプロデューサーは控え室を出た。スタジオまでの通路を歩きながらプロデューサーが言った。
「颯の歌唱力がここまで伸びるとは予想していなかった。音の高低も、響き方も、歌詞の発音もすごくきれいになったよ。ダンスだってかっこいい動きもかわいい仕草も使いこなせるようになった。今回のパフォーマンスでもインパクトのあることができるんじゃないか?」
「うん、きっとできる。見ている側に有意義な時間を過ごして欲しいから、はーはがんばるよ」
パフォーマンスをどうするかについては、1分4秒の間に颯が普通に歌い普通に踊るのを完璧にやろう、ということになった。レベルは高く、内容はシンプルでわかりやすく。終わるときもきれいにオチをつけて、好印象をそっと残す。颯がパワー全開でぶちかませば、1分4秒を支払って損はないと受け手は思ってくれるだろう。
もうすぐスタジオに着く。颯はちょっと緊張していた。自分もまた、自分のパフォーマンスをおこなう時間を消費している。その時間を満喫して、自分もがんばったな、と思えるひとときにしよう。
スタジオに着いた。颯の特技を見せるときが来た。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
