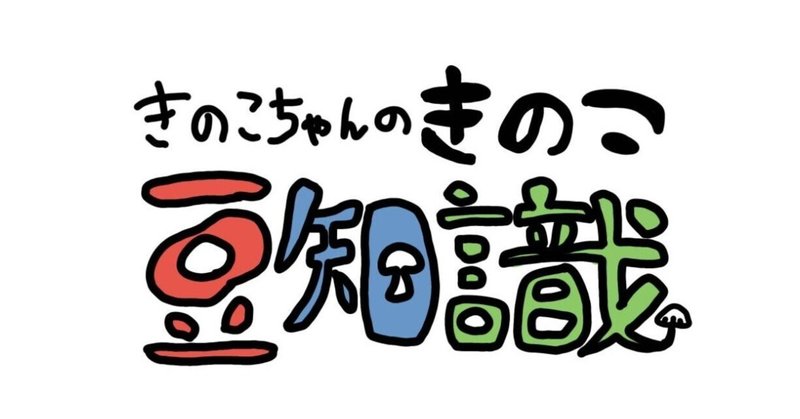
オウギタケ(扇茸)Gomphidius roseus
時期
夏から秋(福岡県では5月~6月頃、10月~11月頃の二度観察することができます。)
発生環境
アカマツやクロマツなどのマツ林地上に発生します。

特徴
【傘】
明るい赤褐色でややまんじゅう型をしています。幼菌の頃は紅色が鮮やかですが、傘が開き、時間が経つと色は褪せてしまいます。傘の表面は湿気がある時はぬめりがあり、乾燥するとややツヤがあります。



【ヒダ】
やや垂生しやや疎。はじめは白色ですが、古くなると黒っぽくなります。

【ツバ】
不明瞭で消失しやすい。成熟するとツバの上に黒色の胞子が降り積もっている姿を観察できることもあります

【柄】
柄は全体的に白っぽくやわらかい繊維状ですが、根元は黄色くなっています。古くなった個体ではふわふわ感はなくなり、淡黄土色になります。

名前の由来
ヒダが扇のように強く垂生している姿が「扇子」に似ていることからこの名前がついたといわれています。
きのこ探しとくっつきむし
アミタケやオウギタケを探して松の林に入ると、場所によってはハイゴケが松葉のすき間から顔を出していて、その隙間からはいろいろな植物が生えています。
ハイゴケは水分を含んでいて、クッションのようにふわふわしているから湿気が大好きなきのこたちにとっては住みやすい場所のひとつなのです。
「あ、アミタケがあった!」
声を上げてアミタケの元へ。正真正銘の「アミタケ」の姿に感動する私ですが、、その場にしゃがんだ時にチクっと痛みを感じました。
足元を見てみると、ズボンには小さな矢が刺さっているかのようにたくさんの植物の種がついていたのです。
「くっつきむし」とは一言にまとめられている言葉で服にくっつく植物の事を指しています。それらはたくさんの種類が知られています。今回、私が出会ったくっつきむしの正体は「ササクサ」と呼ばれるイネ科の植物であることが分かりました。

【参考書・文献】
山渓カラー名鑑日本のきのこ(山と渓谷社)
小学館NEO きのこ(小学館)
しっかり見わけ観察を楽しむきのこ図鑑(ナツメ社)
きのこの語源・方言事典(山と渓谷社)
写真:岩間杏美
注)きのこ豆知識は毎月2回更新をします。(第1、第2金曜日に更新を予定していますが、臨時休載、更新の変更などもあるかもしれないので、その際はご了承ください)
過去掲載一覧表
【あ行】
アミタケ(網茸)
オウギタケ(扇茸)◆今はこの記事をみています
【た行】
ツバキキンカクチャワンタケ(椿菌核茶碗茸)
【な行】
ニセマツカサシメジ(偽松毬占地)
【は行】
ヒラタケ(平茸)
【ま行】
マツカサキノコモドキ(松笠茸擬)
マツカサタケ(松毬茸)
ミドリコケビョウタケ(緑苔鋲茸)
【番外編】
きのこの暮らし
きのこの役割
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
