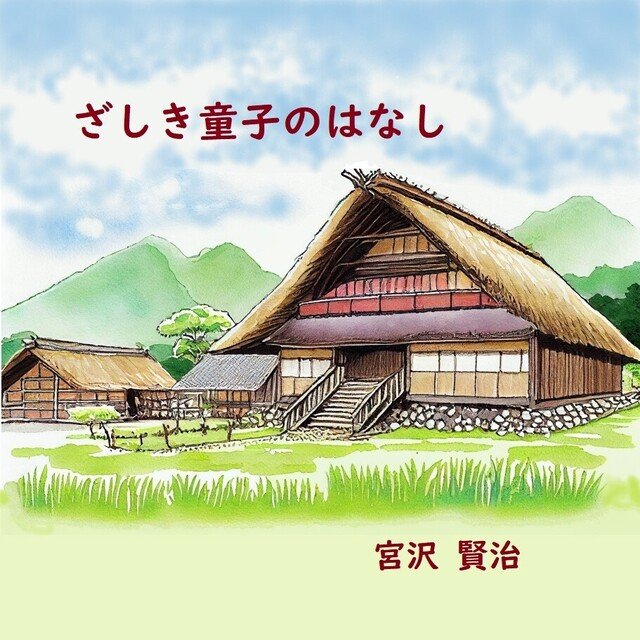
ざしき童子のはなし
宮沢賢治
00:00 | 00:00
青空文庫より、
宮沢賢治の「ざしき童子のはなし」
を読みました。
《ふわっとあらすじ》
私の地方に伝わるざしき童子の話です。
四つの話を聞きました。
一つ目。
明るい昼間、
子供が二人で庭で遊んでいました。
みな出払って誰もいないはずなのに
どこかの部屋から
ざわっざわっと箒の音がしました。
子供たちはこっそり見に行きましたが
どこにも誰もいませんでした。
なんの音かいろいろ考えてみましたが
やっぱり箒の音のようでした。
もう一度見に行ってみましたが
ただ明るい光が一面に降り注いでいるだけで
やっぱり誰もいませんでした。
二つ目。
あるお家にご馳走に呼ばれた子供たちが
輪になって「大道めぐり」で遊んでいる。
十人の子供たちが両手をつないで丸くなり
ぐるぐる回っておりました。
すると、
いつの間にか10人が11人になりました。
みんな知った顔で、同じ顔はないのに
どう数えても11人おりました。
大人が出てきて、
「増えた一人がざしき童子だぞ」と
言いました。
子供たちは、
自分だけは絶対ざしき童子ではない、と
目を見張ってきちんと座っておりました。
三つ目。
ある大きな本家では八月の初めに
如来様のお祭りを行います。
お祭りには分家の子供もみんな
呼ぶのでしたが、ある年、一人の子供が
はしかにかかってしまいました。
その子が治るまでお祭りは延期されました。
他の子供たちは、お祭りが延びたり
お見舞い品で鉛の兎を持っていかれたりして
まったく面白くありませんでした。
その子は九月によくなり、やっと
子供たちがみんな呼ばれました。
はしかにかかっていた子が来ると
他の子たちは意地悪をして
みんな隠れて覗いていました。
座敷に入ってきたその子の顔色は蒼く
ひどくやせ細っていました。
「ざしき童子だ」と一人の子が叫ぶと
みんな慌てて逃げ出しました。
四つ目。
北上川の渡し守から聞いた話です。
八月十七日の晩のことだ。
小屋で寝ていたら、
「おおい、おおい」と
呼ぶものがあるのに気が付いた。
おらは急いで船を出した。
向こう岸につくとそこにいたのは
紋付に刀を差し袴を着た綺麗な子だ。
たった一人で船に乗ると言った。
舟が真ん中あたりにきたころ
「お前さんは今からどこへ行く、
どこから来た」と聞いたらば、
「笹田のうちにいたけれど、
飽きたから他へ行くよ」と答えた。
「どこへいくね」と聞くと
「更木の斎藤へ行くよ」といった。
夢のようだがきっと本当だ。
そのあと笹田が落ちぶれて
更木の斎藤が立派になったから。
《語句解説》
座敷童子:ざしきわらし。
旧家に出没するとされた子供の妖怪。
岩手県の北上盆地を中心とする東北地方に伝承される。
箕:米などの穀物の選別の際に殻や塵を取り除くための容器。
大道めぐり:10人がお互いに両手をつないで丸くなり、
ぐるぐる回る子供の遊戯。
かごめかごめなどのような遊び。
お振舞い:冠婚葬祭などで客をご馳走でもてなすこと。
鉛の兎:鉛の人形は当時の子供の玩具。
紋付:家紋をつけた礼装用の和服。
白緒の草履:白い鼻緒の草履
袴:和服の一種で下半身衣である。
上下二部で成り立っている衣服の下衣で、
股(また)があり両足をそれぞれ通してつける衣を
「はかま」といい、股のないものを裳(も)という。
~・~・~・~・~・~・~
音声配信アプリstand.fmにて、
「しんいち情報局(仮)」の
「朗読しんいち」を
担当させていただいています。
しんいち情報局(仮)
広島県福山市新市町の情報をお届け!
https://stand.fm/channels/623f0c287cd2c74328e40149
宮沢賢治の「ざしき童子のはなし」
を読みました。
《ふわっとあらすじ》
私の地方に伝わるざしき童子の話です。
四つの話を聞きました。
一つ目。
明るい昼間、
子供が二人で庭で遊んでいました。
みな出払って誰もいないはずなのに
どこかの部屋から
ざわっざわっと箒の音がしました。
子供たちはこっそり見に行きましたが
どこにも誰もいませんでした。
なんの音かいろいろ考えてみましたが
やっぱり箒の音のようでした。
もう一度見に行ってみましたが
ただ明るい光が一面に降り注いでいるだけで
やっぱり誰もいませんでした。
二つ目。
あるお家にご馳走に呼ばれた子供たちが
輪になって「大道めぐり」で遊んでいる。
十人の子供たちが両手をつないで丸くなり
ぐるぐる回っておりました。
すると、
いつの間にか10人が11人になりました。
みんな知った顔で、同じ顔はないのに
どう数えても11人おりました。
大人が出てきて、
「増えた一人がざしき童子だぞ」と
言いました。
子供たちは、
自分だけは絶対ざしき童子ではない、と
目を見張ってきちんと座っておりました。
三つ目。
ある大きな本家では八月の初めに
如来様のお祭りを行います。
お祭りには分家の子供もみんな
呼ぶのでしたが、ある年、一人の子供が
はしかにかかってしまいました。
その子が治るまでお祭りは延期されました。
他の子供たちは、お祭りが延びたり
お見舞い品で鉛の兎を持っていかれたりして
まったく面白くありませんでした。
その子は九月によくなり、やっと
子供たちがみんな呼ばれました。
はしかにかかっていた子が来ると
他の子たちは意地悪をして
みんな隠れて覗いていました。
座敷に入ってきたその子の顔色は蒼く
ひどくやせ細っていました。
「ざしき童子だ」と一人の子が叫ぶと
みんな慌てて逃げ出しました。
四つ目。
北上川の渡し守から聞いた話です。
八月十七日の晩のことだ。
小屋で寝ていたら、
「おおい、おおい」と
呼ぶものがあるのに気が付いた。
おらは急いで船を出した。
向こう岸につくとそこにいたのは
紋付に刀を差し袴を着た綺麗な子だ。
たった一人で船に乗ると言った。
舟が真ん中あたりにきたころ
「お前さんは今からどこへ行く、
どこから来た」と聞いたらば、
「笹田のうちにいたけれど、
飽きたから他へ行くよ」と答えた。
「どこへいくね」と聞くと
「更木の斎藤へ行くよ」といった。
夢のようだがきっと本当だ。
そのあと笹田が落ちぶれて
更木の斎藤が立派になったから。
《語句解説》
座敷童子:ざしきわらし。
旧家に出没するとされた子供の妖怪。
岩手県の北上盆地を中心とする東北地方に伝承される。
箕:米などの穀物の選別の際に殻や塵を取り除くための容器。
大道めぐり:10人がお互いに両手をつないで丸くなり、
ぐるぐる回る子供の遊戯。
かごめかごめなどのような遊び。
お振舞い:冠婚葬祭などで客をご馳走でもてなすこと。
鉛の兎:鉛の人形は当時の子供の玩具。
紋付:家紋をつけた礼装用の和服。
白緒の草履:白い鼻緒の草履
袴:和服の一種で下半身衣である。
上下二部で成り立っている衣服の下衣で、
股(また)があり両足をそれぞれ通してつける衣を
「はかま」といい、股のないものを裳(も)という。
~・~・~・~・~・~・~
音声配信アプリstand.fmにて、
「しんいち情報局(仮)」の
「朗読しんいち」を
担当させていただいています。
しんいち情報局(仮)
広島県福山市新市町の情報をお届け!
https://stand.fm/channels/623f0c287cd2c74328e40149
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
