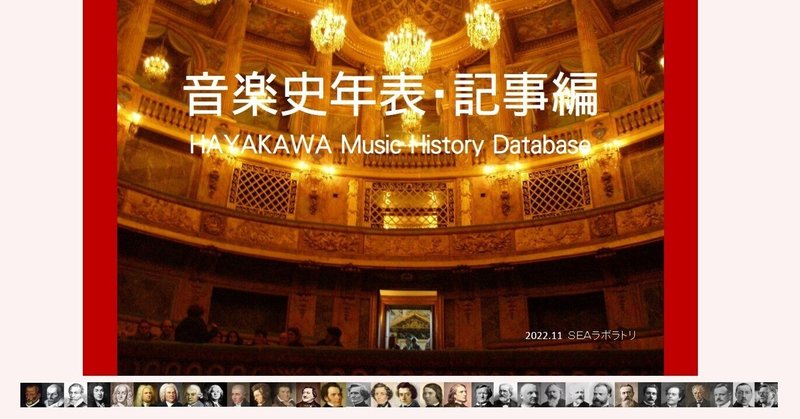
音楽史年表記事編13.教程書となったフックスの対位法理論
1725年、オペラの序曲がシンフォニーとして単独で演奏されるようになるこの時期に、ウィーンの皇帝カール6世の宮廷楽長フックスは、複数の旋律を重ね合わせる技法である対位法を理論書として出版しました。フックスの厳格対位法理論はその後、多くの作曲家の教程書として使用されます。
一方、セバスティアン・バッハは北ドイツを訪問し、ブクステフーデのフーガなどの対位法によるオルガン音楽の影響を受けました。カトリック圏、プロテスタント圏いずれの対位法も、フランドルのポリフォニーを起源とし、カトリック圏ではウィーン楽派のフックスが、プロテスタント圏ではセバスティアン・バッハがその大家となりました。

古典派のハイドン、クリスティアン・バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、いずれもフックスの厳格対位法を学んでいます。
ハイドンはウィーンの宮廷合唱団を声変わりで退団した後、独学でフックスの対位法理論、エマヌエル・バッハのソナタ形式理論を習得します。苦学して音楽の基礎を身に付けたハイドンは、エステルハージ侯爵家の楽長として当代随一の音楽家に上りつめます。
クリスティアン・バッハはセバスティアン・バッハの末子ですが、15歳で父をなくしており、父からの音楽教育は十分ではなかったように思われます。クリスティアン・バッハはイタリアへ渡りミラノでマルティーニ師からフックスの対位法を学ぶなどイタリア音楽を習得し、その後イギリスへ渡ります。
モーツァルトはおそらくロンドンでクリスティアン・バッハに紹介されたものと思われますが、イタリアへ渡り、ボローニャでマルティーニ師から古様式の教会旋法とフックスの対位法を学びました。その後、モーツァルトはウィーンでスヴィーテン男爵のもとでバッハの音楽を知り、大きな影響を受けました。
ベートーヴェンはライプツィヒ大学で学んだネーフェからセバスティアン・バッハの平均律クラヴィーア曲集を学び、その後ハイドンの推薦でウィーンに音楽留学しますが多忙なハイドンからの教育は十分ではなく、ハイドンに隠れてシェンクや当時ウィーンの対位法の大家といわれていたアルブレヒツベルガーからフックスの厳格対位法を学んでいます。
【音楽史年表より】
1725年、フックス(65)
ウィーンの宮廷楽長フックス、ラテン語の古典対位法教程書である「グラドゥス・マド・パルナッスム」を発表する。モーツァルトはイタリアのマルティーニ師のもとでこの教程を学ぶ。ベートーヴェンもこの教程で対位法を学ぶ。また、J・S・バッハもこの教本を蔵書していたといわれる。(1)
1770年3/25、モーツァルト(14)
モーツァルト、パラヴィッチーニ=チェントゥリオーニ伯爵の邸で、イタリア随一の音楽理論家・作曲家として尊敬を集めていた老大家ジャンバッティスタ・マルティーニ師と知り合い、二度にわたってフーガ作曲の指導を受ける。(2)
1770年10/9、モーツァルト(14)
ボローニャの町に戻ったモーツァルトは前回の滞在のときと同様マルティーニ師のもとに通い、伝統的な古様式を集中的に学ぶ。そして、一通りの勉強を終了したモーツァルトはマルティーニ師の計らいで名誉あるボローニャの音楽協会・アカデミア・フィラルモニカの入会試験を10/9に受け入会が認められる。(2)
1781年2/15、ベートーヴェン(10)
クリスティアン・ゴットロープ・ネーフェがボン宮廷オルガン奏者に就任する。この頃からベートーヴェンはネーフェに師事して、クラヴィーア、オルガンなどを学ぶ。ネーフェはベートーヴェンに最初に大バッハの平均律クラヴィーア曲集を教材として与える。(3)
1792年12月、ベートーヴェン(21)
ベートーヴェンに対するハイドンのレッスンが始まる。しかし、目前に迫ったロンドン行きの仕事に忙殺されていたためか、ハイドンはあまり身を入れて指導を行わなかったらしい。翌年ベートーヴェンは別の作曲家ヨーハン・シェンクから数ヶ月間ひそかに対位法を学んでいたという。また、94年ハイドンがロンドンへ出発すると、ベートーヴェンは作曲家のヨーハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーに対位法を学んでおり、この良心的な教育者はハイドンよりはるかに詳細に注意深い指導を行ったとされる。(4)
【参考文献】
1.ブノワ他著・岡田朋子訳・西洋音楽史年表(白水社)
2.モーツァルト事典(東京書籍)
3.ベートーヴェン事典(東京書籍)
4.青木やよひ著・ベートーヴェンの生涯(平凡社)
SEAラボラトリ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
