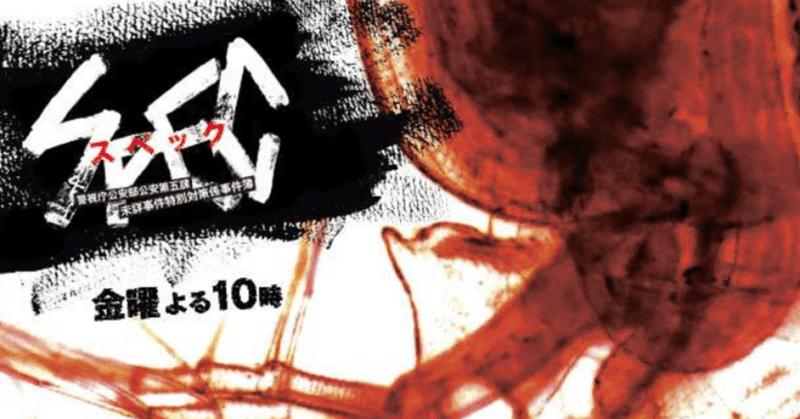
2010年のSPEC論。
第6回、無人のマンションの部屋に、サイレンの音が重なった瞬間、私はSPECを唯物論的に理解した。
理解したというのは正確ではない。どうやら実在しているらしい、という気配を、しかし曖昧にではなく明瞭に、淡くではなく濃密に、ただ感じたのである。把握する能力はないし、またその必要もないと思った。物事を手中におさめるのではなく、あるがままのフォルムを漫然と浴びればそれでいいのではないかと、ぼんやり知覚したのである。
ある容疑者の死を仄めかすあのサイレンは、同時に仕組まれ隠蔽された何かを指し示すサインでもあったはずだ。それは警告というような大仰なものではなく、軽い目配せのようなものである。目的が明確になってはいない、契機そのものが横たわっているような風情がそこにはあった。 物語的な必然でもなく、演出上の野心でもなく。非常にぶっきらぼうではあるが、きわめて精度の高いなにものかが、あの音には潜んでいる。
すべての言葉は比喩である。そんな言葉を残したのは、どこの誰だっただろう。思い出せない。思い出せないが、「言葉には素があり、言葉は、言葉の素にかたちを与えただけにすぎない」と言ったのは、糸井重里である。
つまり、あらゆる事物、事象はそもそも名前を有していたわけではなく、たまたまそれに「ふさわしい」と思われる呼び名を「あてがわれた」にすぎない。大切なのは、言葉ではない。言葉の向こう側にある素である。言葉から、その素を感じ取ることが、大切なのである。
こうして記してしまうと、随分当たり前のことでしかないような気もするが、こうしたことを、概念ではなく、具体的な現象を享受することによって認識する機会はなかなかなく、糸井の言説を私はついつい忘れがちなのである。だが、そのことを忘れていいと思っているわけではなく、ごく稀に、もののはずみで思い出すこともある。そうしたとき、不確かなのだが、奇妙な懐かしさとともに訪れる「手ごたえのようなもの」がある。そして、私は思うのだ。この瞬間を味わうために、思い出しては忘れる、忘れては思い出すという行為を、無意識に繰り返しているのではないか、と。
こうした書き方は、結論を先延ばしにする、単なる時間稼ぎに思う方も少なくないだろう。だが、いま書かれているこの文章がもし弛緩しているとしたら、それは意図的に選ばれた文体が作用しているからではなく、正直であろうとした結果にすぎず、正直であることがいかに思考をゆっくり運んでいくかという自分なりの発見がトレースされているだけなのだ。
『SPEC』で起こっている出来事は、確かに緊迫している。もはや一歩も退くことのできない時点にまで、事態は進行しているだろう。そう、それが人間にとって、幸か不幸かは関係なく、文明が無慈悲なまでに容赦なく進化するように。
映像の筆致は基本的に引き締まっている。点在するファクターもヴァラエティに富んでいる。ところが、なぜなのか、私は神経を集中させたり、アンテナを張りめぐらせたりするよりも、ただ無為に安堵してしまうのだ。いったい、そこでは、何がもたらされているのか。
いくら本題から逃げていると揶揄されようが、あえて明記しておきたい。これから綴られていくことを、どうか鵜呑みにしないでほしい。言葉の意味ではなく、言葉の素を感じてほしい。いや、もっと直裁に言えば、あなたの脳で、私が書き散らかした言葉のようなものたちを、まさぐってほしい。言葉とは、多くの場合、そのひとの身体の残骸である。拾い集めて、組み立て直すのは、いま、読んでいるあなたの仕事なのである。
人間の進化ということを考えるならば、私たちは類人猿だった時代に戻ることはできない。もはや、いまから、四足歩行のいきものに還ることは、現実的に不可能なのである。振り返ることが必要なときもあるだろう。しかしながら、帰ることは許されていない。立ち止まりながらでもいいから、一歩ずつ、いや半歩ずつでも進んでいくしかないのである。二足歩行のいきものとして。
どのような卵のなかにいるかは定かではないが、私たちは結局のところ自分自身を「孵らせる」ことしかできない。前述したように、それが正しい意味での更新である保障はどこにもない。改悪であったり、退化である場合も、充分ありえる。だが、それをやめることはできないし、やめるわけにはいかないのである。
かつて、私は超能力者を極端に進化した人間だと考えていた。彼ら、彼女らは、独自に、自分自身の能力を更新してきたのだと。
しかし『SPEC』は、まったく別の思考に導く。
彼ら、彼女らは、進化したのではない。進化をやめたのだ。意識的に。つまり、進化しないという道を、強固に選び取ったのが、超能力者たちなのである。言うなれば、旧人類だ。脳を10パーセントしか使っていない人間が進化して、残りの90パーセントを活用してしまっている人間が進化を止めているというパラドックス。
『SPEC』に登場する超能力者たちが全能の神でないことは明らかである。ある者は私利私欲に走り、ある者は復讐を遂行し、ある者は世間に向かって自己を主張してみたりする。彼らは、間抜けというより、単に幼い。その突出した能力に反比例するかのように、精神年齢はひどく子供じみている。超能力者だから、社会に適応できないのではない。社会に適応することを拒んでいるから、超能力者なのである。すなわち、能力と精神年齢は反比例してるのではなく、実は正比例している。
彼ら、彼女らは、能力が突出しているからこそ、幼いのである。
超能力者たちは基本的に、たったひとつの能力だけが突出しているにすぎない。そして悲しいことに、そのたったひとつの能力を有効に活用するには、世界は複雑すぎるのだ。だから、悲劇が起こる。『SPEC』はその悲劇を描いている。
世界は単一に形成されてはいない。つまり、世界は超能力者のたったひとつの能力に対応するわけにはいかないし、対応することはできないのである。たとえば、誰もが千里眼を有しているような世界があるとすれば、おそらくこのような悲劇は起こらない。千里眼を有した私たちは、一定のルールの下、優劣を競い合うだろう。また、いずれの能力が勝っているか否かだけではなく、その能力をいかに世界のために最大限に役立てることができるかについて模索し、それぞれに実践し、それぞれの成果を提示するだろう。もちろん、千里眼を駆使した犯罪行為がなくなることはないだろうが、誰もが千里眼を有しているのだとしたら、そこで誇示されるものは僅かなはずで、多くのひとびとは経済活動や芸術活動に結びつけるはずだ。千里眼をビジネスチャンスとして、あるいはアーティスティックなインスピレーションとして受けとるだろう。その結果、ほとんどの人間は心身ともにアスリート的な人生を送ることになるだろう。生きることがスポーツにようになれば、宗教も薬物もいらなくなるかもしれない。
しかし混沌を失ったその世界ほどつまらない世界はないだろう。悲劇のない世界は絶対につまらない。これは暴言以外のなにものでもないが、平和こそが人間を、人間の能力を堕落させるはずなのだ。
かくして世界は複雑でありつづける。
超能力者たちそれぞれの能力を受け入れることができない世界もまた未熟である。そして、世界が今後、成熟していく見込みはどこにもない。だが、それでも、私たちは生きるのである。
私たちは超能力者ではない。だが、私たちはとるにたらないそれぞれ固有の能力を使って、世界のために何かしようとする。極論を言えば、殺人も暴動も戦争も、それはすべて、世界のために何かしようとした結果だ。確かにそれは間違っている。人を殺めてはいけない。暴力を振るってはいけない。大量殺戮は絶対に許されない。
しかし、それでも私たちは、私たちの能力を、行使するべきなのだ。
私たちは世界のために何かをしようとする。世界は私たちのために何もしてはくれないだろう。それでも私たちは世界のために何かをしようとする。
あるひとが『SPEC』を作り、あるひとが『SPEC magazine』を作り、あるひとがそこで書き、あるひとがそれを読む。
世界は単一ではない。私たちも単一ではない。無数の差異に満ちた世界を、無数の差異を抱えた私たちは生きている。
そして私たちはSPECを行使する。誰かが死に、誰かが生まれる。それでも人間のSPECはケイゾクする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
