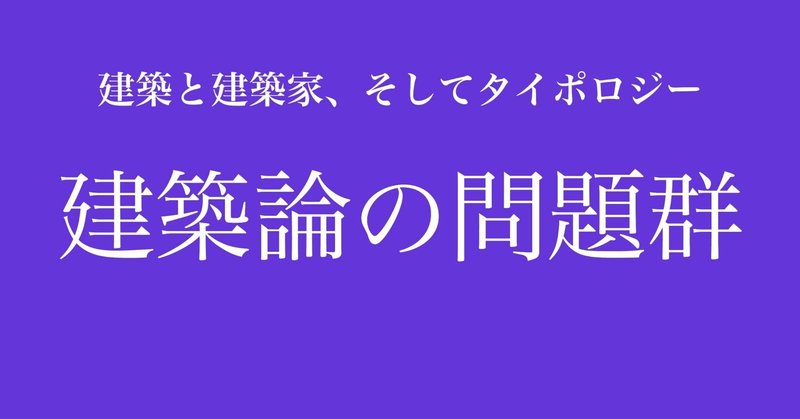
建築論の問題群03〈建築の社会性〉 建築と建築家、そしてタイポロジー
奥山信一(東京工業大学 教授)
建築学分野で一般的に社会性とはどのような内容で議論されているのであろうか。たとえば日本建築学会の地球環境委員会のHPでは、「建築物の社会性」を、建築が個人の所有対象にとどまらず、社会の財産としての性格を有するとし、安全かつ健康で快適であること、資源を浪費せず持続可能性が高いこと、周囲の環境及び社会インフラと適合していること、人々が大切にしたいと思う魅力を有すること、などが要求項目として列記されている。つまり、ここでの建築の社会性とは、原則として<眼の前に現象する社会>を前提にしている。社会とは、人間の集団が生み出す技術や経済の制度であるので、日々更新される制度と長い時間その場所に立ち尽くす建築物との関係を取り結ぶ手立てに向けた眼差しは大切な事象である。しかし、建築の現代性とともに、その普遍的な問題を扱う建築論・建築意匠論分野にとって、この時間とともに常に推移する<眼の前に現象する社会>に局限した思考の眼差しは、必ずしも有益な議論の場を提供するものとは思えない。
1)第2回研究会の振り返り
2019年の3月に「建築デザインにおける社会性を巡って」と題した本委員会主催の「建築論の問題群:第2回公開研究会」が法政大学で開催された。Covid-19の命名も未だなく、坂本一成、妹島和世、ヨコミゾマコト、青井哲人といった多彩なパネラーの顔ぶれも作用して、会場となった階段教室には文字通り立錐の余地もなく、熱気が充満した空間での議論の場であったことを懐かしく思う。個々のパネラーの主張内容とディスカッションの概要に関しては、本委員会によるnote記事「建築論の問題群」に掲載している連続研究会報告を参照いただきたいが、要約すると、社会性とは、個々の建築的トピックに内在する概念ではなく、私たちの胸中に巣食う想念であり、また建築家という存在と建築物双方の水準において検討を要する概念で、個と集団との関係図式として、それら双方は社会という人間集団の中で共有されることで成立するタイポロジーを介在させることで、ひとつの問題群として把握可能であるというのが私の見解であった。建築家も建築物もすべて個と集団の関係図式の反映である社会の内に存在せざるをえないので、すべての建築的言語は<社会性>という評価座標において検討可能であり、<社会性>とはそうした相対的な概念として位置付けざるをえないことが、当時の議論を通して推論された。
そこで以下では、前2回のラウンドテーブルでのテーマであった、「形態論」と「自律性と他律性」を題材に、建築物を設計する建築家にとって<社会性>をどのように想定すべきかを素描してみたい。
2)「形態論」における社会性
香山壽夫は『建築形態の構造』において、建築の形態論が対象とするのは形態そのものであり、形態の外在的条件ではなく、建築を形作る個々の要素の内在的条件を考えるものであるとしながら、そうした形態論が創作に有効なものとなるには「形態を構成する要素の特質を説明する要素論的段階から、その要素間の構成関係を説明する構成論的段階に進むことになる」と論じている。つまり形態論は空間論や領域論などともに、建築のファンダメンタルな概念の存在形式を問うものであり(What is 論)、それに対して構成論とは、そうした概念を創作に運用するための操作の形式としての方法論である(How is 論)と位置付けていると解釈できる。確かに、構成論の基本は「部分と全体の関係図式」でしかなく、それ自体は抽象的な意味しか持ちえず、そこに何らかの具体的な単位を規定しうる概念(形態、空間、領域・・・)が介在することで、形態構成、空間構成、領域構成などの生き生きとした建築の意匠論の水準に移行できるものであった。
そうした意匠論は、原則として個々の建築家に固有のものであって構わないが、次第にそれぞれの地域や集団で共有され、様式化されていくことで有名無名を問わず建築の歴史が形作られていったと考えることができる。その様式化されたものを私たちはタイプと呼び、そのタイプを見出す考え方をタイポロジーという。タイプが形成されるということは、その集団(社会)が時間の経過の中でその方法論(例えば形態構成論)を少なからず共有したと考えるならば、そこに<社会性>が発生したと位置付けることが可能であろう。言い換えれば、個々の建築家固有の方法から集団が共有する方法(タイプ)へのグラデーションが、建築の意匠論の<社会性>を測る指標となるということである。
J.サマーソンが『古典主義建築の系譜』で、「私は建築をひとつの言語のように扱って話を進めたいと思う。」とし、古典主義建築を構成する個々の要素とその組み合わせによる全体の表現を、いつしか定式として「ひとつの言葉のように結晶した」と論じているのは、単語と文法によって意味を発生させる言語の中に、建築との相同性を見出していたのである。言語はその集団の中で共有されているからこそ意味伝達が可能なのであり、またそこから新たな意味を生み出す変化が生じる土壌も用意されている。それは建築にとどまらず、人間の文明における<社会性>の根底をなす考え方と言えるのではないか。市原出を中心として編纂された『建築/かたちことば』の序文で香山壽夫は以下のように述べている。
「建築は、・・・人と人の心をつなぐ、ひとつの言葉であった。・・・一般言語と同じく、建築様式も、ひとつの文化集団の内において保存され、世代から世代へと伝達されていく。・・・その伝達の過程で、その形式は、豊かにされ、洗練されていく。・・・構成要素(一般言語における単語)と構成法(一般言語における構文法)が整理されていく。建築において「様式」とは、このように整えられた建築様式のことである、と言っていいであろう。」
ここには、個々の建築家の意匠論が共有されることで社会性を獲得していく様子が、ヒトが人類へと歩む過程で培ってきた言語との関係で端的に綴られている。
3)「自律性と他律性」における社会性
建築の空間や構造は建築物の内在的な仕組みであることから、それらは自律的な概念であり、それに対して建築物の背景となる歴史や環境は個々の建築物の範囲を超えて、当該の建築物を設計する建築家にとってはコントロール不能であることから、それらは他律的な概念であると、建築に纏わる言語を自律と他律の双方に振り分けることは可能かつ妥当なように思える。しかしそれは本当に可能であるか? 言い換えれば、辞書的な意味ではなく、建築という社会的な産物において、自律性と他律性は、はたして対立概念と言えるのであろうか。
たとえば、ある特定の建築物の空間を構想している時に、その空間は実体としてひとつの建築物を構成する内在的な要素であるが、その空間の相貌が、たとえばモダニズムの空間と共振していたとしたら、このような歴史的パースペクティブを背負った空間は、ひとつの建築に内在し、自律しているといえるであろうか。また建築の背景となる歴史に思いを馳せている時に、多くの人々に共有された歴史観ではなく、その建築家独自の極めてユニークな歴史観が構築されていたとしたら、それは他律的な問題として処理できるであろうか。そうしたことを以下に、自律性と他律性の代表的事例と目される古典主義と文脈主義(コンテクスチュアリズム)を題材に考えてみたい。
古典主義は、古代ギリシアおよびローマを範として、厳格な規則に従って構想された15世紀以降の様式建築であるので、その規則の体系は、原則として建築物の内側に閉じた自律的世界の内にあるといえる。しかし、それが当時の西欧社会の文化的基盤として広く共有されていたとするならば、実体としては自律的な体系であったとしても、様式というタイプを形成しているという側面では他律性を備えていたと考えることも可能であろう。そして、その共有されたタイプの規則を前提にした上で、個々の建築家が更なる創意を巡らすことで新たな自律的スタイルに移行し、それが再度共有されることで次なるタイプへと展開していく過程が、先に引いたJ.サマーソンの『古典主義建築の系譜』では論じられている。
また文脈主義(コンテクスチュアリズム)は、建築が立地する地域の文化的および実体的環境、時には記憶といった時間概念を背負った非実体的な環境も含めて、そうした環境要素をデザインの根拠とする方法といえる。環境とは建築物の外側に存在する、建築家が手出しできないものであるから、一般的には他律的なものと考えられるが、しかし、無数に存在する環境要素の中から何を選択しデザインの方法論とするかといった解釈論には多様性が十分介在し、それが特定の建築家独自の方法論として構想された場合は、その建築家の内側に閉じた自律性を保持していると判断することも可能であろう。ちなみに、冒頭で紹介した研究会でのパネラーのひとりであった妹島和世は、具体的な設計に際して、常にその土地の情報を観察し、地域の保有する歴史や文化を建築によって引き出すことを目指していると述べた。しかし彼女の場合は地域の素材や文化的背景を直截に反映すること、つまりサイトスペシフィックな方法を忌避している。むしろ自分の設計した建築が立ち上がった時に、その場の環境が再発見されることが主眼であるという。設計姿勢の導入では文脈主義といえるが、その後の設計プロセスでは極めて独自性を保持した方法論で展開され、未だ見ぬ空間が提出されてきたことは、妹島和世の建築を一度でも経験した輩には自明のことと思う。つまり文脈主義といえども、多くの建築家によって共有される以前の段階では、注目する対象それ自体は他律性に依拠したとしても、方法論としては個々の建築家の内面で形成された自律的な世界と考えることができるのである。
このように推論すると、古典主義でも文脈主義でも、それらは自律性と他律性のどちらかに押し込めることはできず、双方の間を揺れ動く概念であることがわかる。つまり、自律性と他律性は辞書的には対義語であるが、建築という社会的な産物を論じる場合には、それら両者は人々に共有される度合いによって測らねばならない相対的な判断基準の中に位置づくと考えられるのである。
いまここでは、古典主義と文脈主義を題材に論じてきたが、同様な推論はすべての建築的言語においても可能であろう。すべての建築的言語は、社会という集団によって共有された他律性のフレームの中に一旦放り込まれていて、そのフレームの中に辛うじて自律的な世界をそれぞれの言語が保っている概念図式を思い描いていただきたい。
しかし、この他律性のフレームの内側で漂う自律性とは一体どのようなものであろうか。建築がその発生段階から既に社会的存在であるという状況を受け入れた時点で、その自律性は、住まい手ならばプライベートな記憶の中に存在すると同様に、意匠論としては作者である建築家の内面に根差すとしか考えられない。それは、建築家個人の意識のなかで構想される説明根拠が、強靭な創作言語として成立した時にのみ浮上すると暫定せざるをえないのである。私たちの生活の基盤である社会という他律で形成された世界と、オリジナリティを求める建築家個人の意識との関係図式が、建築の意匠論における<社会性>という相対的な概念を誘導すると考えられるのである。
4)建築家は原則として自律的な個であるとしたら
これまでの議論で、建築における社会性とは原則として他律的なる世界に位置づくものであることが想定されたのであるが、こうした社会性(他律性)との関係からみた、建築家の自律性の極端な二つの形式を考えてみたい。ひとつは、社会性(他律性)の仮面を纏った自律性であり(【A】)、もうひとつは、自律性に内在する社会性(他律性)である(【B】)。
【A】:建築家の通常の設計作業は、たとえどんなに小さな建築であったとしても、さまざまな関係者(クライアント、スタッフ、構造家、設備家など・・・)との協働で成立しているといえる。主任デザイナーである建築家が徹頭徹尾細かな指示を与える場合もあり、上記の関係者とのディスカッションの中で方向性を探る場合もあるが、建築家が単独ですべての作業を成すということは完全なるセルフビルトでない限り論理的にはあり得ない。つまり、程度の差こそあれ、建築が地上に建ち上がるプロセスは協働作業なのである。しかし、この協働作業が終了し、<作品>として世に送り出される時点で、創作的言語と共に建築家の名が刻印される。こうしたプロセスを、冒頭で紹介した研究会のパネラーのひとりであった青井哲人は「切断」による社会性と断定し、そこでの創作的言語も良し悪しの判断抜きに「虚構」であると暫定した。
【B】:時代の趨勢に流されず、自身が信じる独自の理論と方法論を鍛え上げ、そしてその実現に邁進する建築家がいたとする。一般にそうした稀有な存在を孤高の建築家と呼ぶことがある。そしてそのほとんどは、社会という得体の知れない蠢きのなかに埋没し、時代の風にかき消されてしまうのが通例である。しかし、こうした極めて自己の内面に閉じて活動する建築家が、社会の総体ではなく、ごく限られた人々からの賛同を得て、それが大きな波のうねりとなって社会を動かす瞬間がある。理論も方法論も、その内側には社会との接点は皆無であったとしても、すでに述べたように社会の欲望とは時の流れに伴って常に変質する宿命にあるので、そうした社会の変化が当の建築家の不動の活動に寄り添ってくるのか、あるいは建築家が社会の流れを予見していたのか、おそらくその両者が介在することで現象する稀な状況かもしれない。
ここで述べた【A】と【B】の二つは、建築家の活動が<社会性>を獲得する極端なケースのように見えるかもしれない。しかし、多様な価値観がさまざまな媒体で私たちの身の回りを包み込み、一瞬個々の自由な欲望が許される状況であるとの錯覚を覚えながら、実はホワイトノイズのように正体不明な規制によって活動を制御されてしまう現代の後期消費社会では、【A】のケースは社会的に成功する建築家の典型と言えるかもしれない。それに対して【B】は、近現代も含めた歴史上にいくつかの輝かしい事例を指摘できるかもしれないが、社会の構成員すべてに等価に情報が流布され、それらが増幅されることで各自が受け取る情報の真偽さえ判断するのが困難な現代の高度情報社会では、特異な建築家に自らの夢を託す個性が成立する基盤は限りなく希薄であるといえる。しかし、社会的実践を超えた水準で建築デザインを構想する建築家の存在に一縷の望みを託すためには、【B】で述べたほど極端ではなくても、やはり建築家は自律した<個>であるという地点に立ち返って、その可能性を考えてみたい。
5)建築家が自律した個として社会性に接近していく図式とは
中心に社会と密着した領域があり、その中心から同心円状にいくつもの輪が広がっていく図式を想定していただきたい。中心の社会と密着した領域は太陽、その周りの同心円状の輪は惑星の軌道と、太陽系をアナロジーとしてイメージしていただいてもいいかもしれない。中心から次第に社会性が薄まっていく図式で、それぞれの軌道を回る惑星は、自律した個としての建築家である。中心の太陽(社会性)の内側は、社会のさまざまな制度で完全に規定された世界で、そこではもはや自律した建築家が存在することはできず、その表面との距離が、先に【B】で述べた論理と実践の独自性の度合いを示している。
たとえば、水星に位置する建築家は、自律性を辛うじて保ちながらも、社会的言語の多くを受け入れて活動し、冥王星の軌道上に乗る建築家は、わずかな社会性の引力のもとで、自律性の光彩を放っている。しかし、この構図のままでは【B】で述べた孤高の建築家が多くの賛同を勝ち得る状況を説明できない。社会性の度合いが安定し切っているからである。
現実の宇宙では、恒星を中心とする惑星は、自らの軌道をドラスティックに外れて運行することはないが、ここで提案した図式は物理学の法則に左右されない社会の仕組みであるので、中心の太陽(社会性)もその周りを巡る惑星(建築家)も、それぞれの質量(社会性の内容、あるいは自律した方法論の内容)がその時々の状況で変化可能な性質を含み込んでいる。だから惑星(建築家)は時に自らの軌道を外れて、太陽(社会性)に向かって突き進むことが可能である。そのまま太陽(社会性)の引力に負けて、その内部に突入してしまうと、太陽の熱(社会性の強度)で自律性の意志は燃え尽きてしまうであろう。運よく太陽(社会性)の表面付近を掠め、再び自らの軌道に生還できた時のみ、孤高の建築家は自律性を保持したままで、社会性を獲得することになる。また新種の建築家は、あたかも彗星のごとく、太陽(社会性)を一つの焦点とする長楕円での運行から周期的に太陽(社会性)のエネルギーを吸収して、自律性を保持しつつ社会における生産的な活動を続けることができるかもしれない。
いずれにしても、個として自律した建築家が社会性を纏う可能性は、上記のような活動軌跡の意識的な選択でしかありえないと考える。
6)批評性としての社会性
最後に、これまで述べてきた、個として自律した建築家が備えるべき社会性の内容(上記の図式における太陽のエネルギーの源泉)についてまとめてみたい。
先に2)で、何らかの建築的概念(形態論、空間論など:What is論)と操作の方法(構成論:How is論)が結合することで個々の建築家の意匠論が確立され、それが集団の方法へと共有されたタイポロジーの形成へのグラデーションが社会性を測る指標になると述べた。しかしそこで形成されるタイプは類型(ステレオタイプ)であって、そこへの接近は必ずしも創造的な社会性を生み出すとは言えない。美学的な水準を除けば、極めて安定した既知の建築的価値しか得ることはできないからである。それがそれぞれの地域文化に根ざした歴史的なタイプの場合はまだしも、消費社会の構図の中で形成された類型(ステレオタイプ)である場合は、一時の商業的な欲望が結晶した価値を生み出すかもしれないが、いずれ時間の推移の中で通俗性という泡沫に帰してしまうからである。
実は、個々の建築家の方法が共有され、集団の方法へと向かう図式には、時間の流れを遡るもう一つのベクトルが存在している。
高度な技術がどれほど進歩し、それにどれほど私たちの身体が順応していったとしても、生物学的な私たちの身体能力は、太古の昔からほとんど変化していないと言われている。ホモ・サピエンス以前の旧人と比べても、どれほどの変化があるのか不明であるとの指摘もある(『身ぶりと言葉』、A.L.グーラン)。そうした気が遠くなるような長い時間を遡及した時点で、私たち人類が共有していた空間や形の型、一般に祖型(アーキタイプ)と呼ばれるタイプもまた、現代社会で想定されるタイポロジーの中に含めることは可能であろう。ただ、そこに耽溺することは、アナクロニズムに埋没することにもなりかねない。歴史学あるいは先史学とは、過去の出来事を事実として把握することに主眼が置かれたものではない。どれほど有益な資料に出会ったとしても、それらは膨大な当時の現実世界のほんの一握りの欠片を示しているに過ぎないから、精緻な推論の先にあるのは可能性への期待の域を出ないからである。それでも私たちが過去へ眼差しを注ぎ続けるのは、生身の人間の歩みを軽々と乗り越えていく技術の発展への危惧を照らし出してくれるからではないか。だから、祖型(アーキタイプ)への眼差しは、今という時間を生きる実践的建築家にとって不可欠であるが、それを次なる時代を切り開く創造的な世界へと展開するためには、おそらく、類型(ステレオタイプ)に対する批評精神が後方支援するのではないかと思う。なぜならば類型(ステレオタイプ)といえども、必ずしもそのすべてが陳腐なものとは限らず、またそれぞれの時代を刻む類型(ステレオタイプ)も当然存在するので、実は祖型(アーキタイプ)と類型(ステレオタイプ)は、長い時間の流れの中では同じ建築的地平のそれぞれの時点を刻む建築型といえるからである。そうした考え方がタイポロジーという思考方法を、単なる分類学から一線を画す生産的な創造の方法へと導き、意匠論としての<社会性>を浮かび上がらせるのではないかと思う。
奥山信一
東京工業大学教授。1986年東京工業大学工学部建築学科卒業/1992年同大学博士課程単位取得満期修了後、同大学図学教室助手/1994年博士学位取得/1995年同大学助教授、2007年准教授を経て、2011年より現職
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
