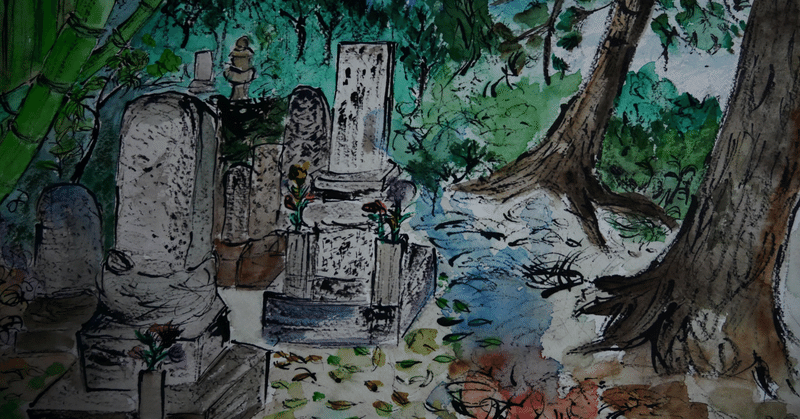
無意識な交わり 1
川沿いの遊歩道にある古びた木製ベンチの上に置き忘れられた、カバーがはだけて真っ裸の文庫本は、昨夜の雨に濡れて、今にも溶けてベンチに吸収されてしまいそうなほどくたびれてはいるが、純潔な少女が無数の触手に身体中を舐め回されるのに抗うかのように、腐った木と一体化することを拒み、なんとか文庫本としての形態を保とうとする姿からはどこかエロティックな感じを受ける、人気のない静かな昼下がり。青年はその文庫本に触れることはせず、鼻の先を近づけるようにして凝視し、雨にさらされて滲んだ表紙の文字から、その文庫本がどうやら官能小説であるということが分かると、よく晴れた日の昼下がりに、この場所に座り、背中を丸くして文庫本のページをこそこそとめくる、くたびれた背広姿の中年男性の姿が無意識に頭の中に浮かび上がった。時折、冬の気配を感じさせるような少々冷たい風が吹き、川沿いに広がる萌黄色の草草をサラサラと靡かせるが、あくまで日光は暖かく、出掛けにとってつけたように羽織ってきたアウターはサウナスーツのように熱いので、青年はアウターを脱ぐと、半袖tシャツ姿で再び中腰になり、まるで池の中をスコープで覗くかのごとく頭を下げると、しばらくは動く気配もなく、じっと文庫本を見つめた。その間、青年の頭のなかでは相変わらず妄想上の中年男性が官能小説を読んでおり、時折、退屈そうな顔をしてオンボロのママチャリを漕ぐ中年女性などが目の前を通り過ぎると、そそくさと懐に文庫本を隠すなどして、なんとか自分が官能小説を読んでいることを周りの人に悟られないようにする姿は、まさしく不審者のそれであったが、青年の関心は中年男性のそのような滑稽な様ではなく、どうしてその時間にその格好でそのような本を読んでいるのかということであり、中年男性の置かれている状況やそこに至る経緯を想像せずにはいられない。そんなことをあれこれと考え、妄想によって空白を埋めると、中年男性の置かれている状況を概ね把握した青年はそこから男という生き物が背負った悲しき運命を勝手に知った気になり、自分で創り出した妄想にひとり涙を堪えたりもする一方で、そんな青年の阿呆らしい一人相撲を側から退屈そうな顔で眺めている野良猫は所憚らず大きなあくびをしたのだが、青年はそれに気がついていないし、野良猫もまた青年の頭の中で繰り広げられている妄想世界のことなど知る由もない。
なにかを思い出したのように顔を上げると、青年は裸の文庫本をそのままに、再び川沿いを上流に向かって歩き始めた。川といっても多摩川のように雄大なものなどではなく、草むらの間をチョロチョロと流れるような可愛らしい小川であって、多摩川が竜の姿に喩えられるならば、この愛らしき小川はさしづめ草むらに隠れてコッソリコッソリと進む蛇のようであり、雄大な川がその堂々とした流れのなかに湛えている、ともすれば平然と人を飲み込み殺してしまうのではないかといったような恐ろしさなど、この小川からは全くもって感じられない。
しばらく進むと、遊歩道沿いに民家が所狭しと立ち並び、道の脇には沢山のプランターが乱雑に置かれていて、そのなかには綺麗な赤や黄色の花を咲かせているものもあれば、虫に食われて葉がボロボロになった植物などもあり、また、遊歩道に面した、錆びついた柵で申し訳程度に仕切られている狭いベランダには、くたびれた死にかけの水色のボクサーパンツや、黄ばんだ白色のタンクトップなどが干されており、その洗濯物の隣には大きさ1メートル程度の信楽焼きの狸の置物が首を傾げながらこちらを睨みつけている。まん丸の目の丁度中心に真っ黒なビー玉のような瞳がついていて、その目は怒っているようでもあり、何も考えていないようでもあり、とにかく薄気味の悪いもので、青年はその狸からすぐに目を逸らしたのだが、それと同時に青年は、あの中年男性もこの大きな狸を見たのだろうか、見たとしたらどう感じたのだろうか、と思うのだった。(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
