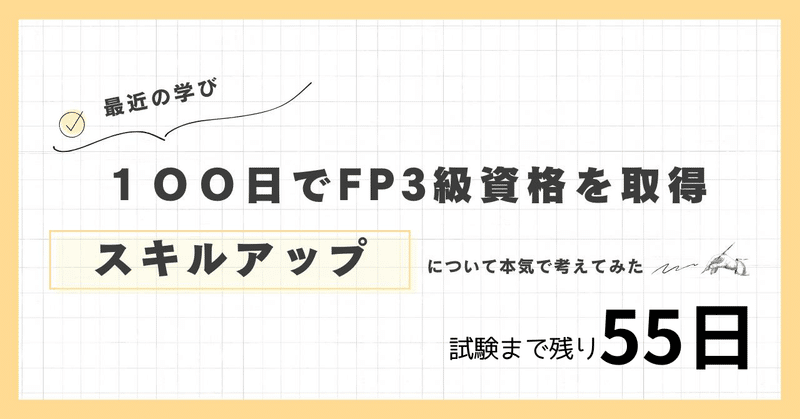
46日目:相続税
46日目は相続税について学んでいきます。
1.相続税の基本
1️⃣相続税とは
相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる税金です。相続税は、相続人ごとに課税されます。相続税の対象となる財産は、不動産、預貯金、株式、生命保険金、死亡退職金などです。相続税の対象から除外される財産は、被相続人の借金、葬儀費用、相続人が喪主となって支払った相続税などです。
2️⃣相続税の計算の流れ
相続税の計算の流れは、以下のステップになります。
個人の課税価格を計算する
相続人が相続する財産の価額から、借金や葬儀費用などの控除額を差し引いたものです。
相続税の総額を計算する
個人の課税価格の合計額から、遺産にかかる基礎控除額を差し引いたものです。基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えたものです。
課税遺産総額を、各相続人の法定相続分で案分し、相続税の税率を適用して税額を求めます。税率は、取得金額に応じて10%から55%までの7段階に分かれています。税額には、速算控除額を差し引きます。
各相続人の税額の合計が、相続税の総額になります。
個人の納付税額を計算する
相続税の総額を、実際の案分割合で分配します。
分配された税額に、相続税額の加算や税額控除を適用します。加算は、兄弟姉妹等の相続人がいる場合に行われます。控除は、配偶者や障害者等の相続人がいる場合に行われます。
加算や控除を反映した税額が、個人の納付税額になります。
2.Step1 各人の課税価格を計算
各人の課税価格とは、相続税の対象となる財産の価額から、債務や葬儀費用などの控除額を差し引いたものです。各人の課税価格は次の式で求められます。
課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税による贈与財産+相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与加算)-非課税財産-債務-葬儀費用
以下、各項目について詳しく見ていきましょう。
1️⃣本来の相続財産
本来の相続財産とは、相続や遺贈によって取得した財産のことです。例えば、不動産、預貯金、株式、自動車などが該当します。本来の相続財産の価額は、相続開始の時点での市場価格で評価します。不動産の評価方法については、こちらを参照してください。
2️⃣みなし相続財産
みなし相続財産とは、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産のことです。例えば、被相続人が支払った生命保険金や死亡退職金、被相続人が相続人に対して行った特別受益(相続人に不当に有利な取引や贈与)などが該当します。みなし相続財産の価額は、相続開始の時点での市場価格で評価します。生命保険金や死亡退職金については、非課税限度額がありますので、注意が必要です。非課税限度額については、後述します。
3️⃣相続時精算課税による贈与財産
相続時精算課税による贈与財産とは、相続時精算課税制度を適用した贈与によって取得した財産のことです。相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与税を納め、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税に相当する金額を控除した額をもって納める相続税額とする制度です。相続時精算課税による贈与財産の価額は、贈与の時点での市場価格で評価します。
4️⃣相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与加算)
相続開始前3年以内の贈与財産とは、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産のことです。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の課税価格に加算されます。これを生前贈与加算といいます。生前贈与加算の目的は、相続税を逃れるために相続開始前に贈与を行うことを防ぐためです。相続開始前3年以内の贈与財産の価額は、贈与の時点での市場価格で評価します。
5️⃣非課税財産
非課税財産とは、相続や遺贈によって取得した財産であっても相続税がかからない財産のことです。例えば、墓地、墓碑、仏壇、仏具などが該当します。非課税財産の価額は、相続開始の時点での市場価格で評価します。
1.生命保険金・死亡退職金のうち非課税額
生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、一定の限度額は非課税となります。非課税限度額は、次の式で求められます。
非課税限度額=(3,000万円+600万円×法定相続人の数)÷(相続人の数+被相続人が支払った生命保険金等の受取人の数)
法定相続人の数は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。養子の場合は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までを法定相続人に含めます。特別養子縁組や配偶者の実子などは、実子とみなされます。
2.弔慰金のうち非課税額
弔慰金とは、被相続人の死亡に伴って支払われる金銭のことです。例えば、会社や組合などから支払われるものが該当します。弔慰金は、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、一定の限度額は非課税となります。非課税限度額は、次の式で求められます。
非課税限度額=(3,000万円+600万円×法定相続人の数)÷(相続人の数+被相続人が支払った弔慰金の受取人の数)
法定相続人の数は、生命保険金・死亡退職金の場合と同じです。
3.法定相続人の数
法定相続人の数とは、相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。法定相続人の数は、非課税限度額の計算や基礎控除額の計算に必要です。法定相続人の数は、民法に定められた法定相続順位に従って決まります。法定相続順位は、次のとおりです。
兄弟姉妹(傍系血族)の相続順位は、直系卑属や直系尊属がいない場合に限られます。兄弟姉妹には、被相続人と同じ両親から生まれたもの(実兄弟姉妹)と、片親が同じもの(異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹)がありますが、相続順位は同じです。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(甥姪)が代わりに相続します。甥姪の相続順位は、その親である兄弟姉妹の相続順位に準じます。
6️⃣債務控除
債務控除とは、相続税の計算で、相続財産の価額から、被相続人が残した借入金や未払金などの債務と葬式費用を差し引くことです。債務控除をすることで、相続税の負担を軽減できます。
債務控除の対象となる債務は、相続開始時に現に存在するもので確実と認められるものに限られます。例えば、金融機関からの借入金や連帯債務、未払いの税金や医療費、事業上の未払金などが該当します。一方、保証債務や団体信用保険の付された住宅ローン、墓地や仏壇の購入費用などは、債務控除の対象となりません。
債務控除の対象となる葬式費用は、亡くなってから葬儀、納骨までの費用です。例えば、お通夜や告別式にかかった費用、火葬料や埋葬料、お布施や戒名料などが該当します。一方、香典返しや生花、位牌や仏壇の購入費用、法事に関する費用などは、葬式費用には含まれません。
債務控除ができる人は、その債務や葬式費用を負担することになる相続人や包括受遺者です。相続人や包括受遺者であっても、相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人は、債務控除の対象が限られます。
債務控除の計算方法は、次のようになります。
課税価格=相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税による贈与財産+相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与加算)-非課税財産-債務-葬式費用
3.Step2 相続税の総額を計算
1️⃣遺産に係る基礎控除
遺産に係る基礎控除とは、相続税の対象となる財産の価額にかかわらず、一律に控除される金額のことです。基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えたものです。
法定相続人の数とは、相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。法定相続人の数は、非課税限度額の計算や相続税の税率の計算にも必要です。法定相続人の数は、民法に定められた法定相続順位に従って決まります。
2️⃣相続税の税率
相続税の税率を確認するには、国税庁が公表している「相続税の速算表」を参照します。相続税の速算表は、次のようになっています。
表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
相続税の速算表では、左の列に「法定相続分に応ずる取得金額」、右の列に「税率」と「控除額」が示されています。法定相続分に応ずる取得金額とは、相続税の対象となる財産の価額から、基礎控除額を差し引いたものを、各相続人の法定相続分で案分したものです。法定相続分とは、民法に定められた相続人の相続する財産の割合のことです。基礎控除額とは、相続税の対象となる財産の価額にかかわらず、一律に控除される金額で、3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えたものです。
相続税の速算表の使い方は、次のようになります。
各相続人の法定相続分に応ずる取得金額を求める
取得金額に対応する税率と控除額を見つける
取得金額に税率を乗じて、控除額を差し引く
各相続人の税額を合計する
例えば、法定相続人が妻と子2人である場合、法定相続分は妻2分の1、子4分の1、子4分の1となります。課税遺産総額が1億5,200万円とすると、法定相続分に応ずる取得金額は、妻が7,600万円、子が3,800万円ずつとなります。これらの取得金額に対応する税率と控除額は、次のようになります。
表
相続人 取得金額 税率 控除額
妻 7,600万円 30% 700万円
子 3,800万円 20% 200万円
子 3,800万円 20% 200万円
これらの数値を使って、各相続人の税額を計算します。
表
相続人 取得金額 税率 控除額 税額
妻 7,600万円 30% 700万円 1,580万円
子 3,800万円 20% 200万円 560万円
子 3,800万円 20% 200万円 560万円
各相続人の税額を合計すると、相続税の総額は2,700万円になります。
4.Step3 各人の納付税額を計算
1️⃣各人の算出税額の計算
各人の納付税額とは、相続人や包括受遺者が実際に納めるべき相続税の額のことです。各人の納付税額は、次のように計算します。
各人の算出税額を求める
各人の算出税額とは、相続税の総額を、各人の相続財産の取得割合で案分した額のことです。
相続税の総額とは、相続人全員が納めるべき相続税の合計額のことです。相続税の総額の計算方法は、こちらを参照してください。
相続財産の取得割合とは、各人が相続や遺贈で取得した財産の価額を、相続税の対象となる財産の価額の合計額で割ったものです。
各人の算出税額は、次の式で求めます。
各人の算出税額=相続税の総額×各人の相続財産の価額/相続税の対象となる財産の価額の合計額
2️⃣相続税額の2割加算
相続税額の2割加算をする(対象者のみ)
相続税額の2割加算とは、相続人や包括受遺者が、被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合に、その算出税額に2割を加算することです。
2割加算の対象となる者は、次のとおりです。
被相続人の祖父母、孫、兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母、従兄弟姉妹などの親族
被相続人の養子である孫(被相続人の子供が死亡していない場合)
被相続人の配偶者の親族
被相続人と血縁関係や婚姻関係のない者
2割加算の対象とならない者は、次のとおりです。
被相続人の配偶者
被相続人の父母
被相続人の子供(養子を含む)
被相続人の養子である孫(被相続人の子供が死亡している場合)
2割加算後の税額は、次の式で求めます。
2割か産後の税額=各人の算出税額×1.2
3️⃣税額控除
税額控除をする(対象者のみ)
税額控除とは、各人の納付税額を軽減するために、2割加算後の税額から差し引くことができる金額のことです。
税額控除の種類と対象者は、次のとおりです。
配偶者の税額の軽減:相続人や包括受遺者が、被相続人の配偶者である場合
未成年者の税額控除:相続人や包括受遺者が、被相続人の死亡時に20歳未満である場合
障害者の税額控除:相続人や包括受遺者が、被相続人の死亡時に障害者である場合
相次相続控除:相続人や包括受遺者が、被相続人の死亡後3年以内に死亡した場合
医療法人持分税額控除:相続人や包括受遺者が、被相続人の死亡時に医療法人の持分を相続した場合
贈与財産の加算と税額控除:相続人や包括受遺者が、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた場合
税額控除の計算方法は、こちらを参照してください。
各人の納付税額は、次の式で求めます。
各人の納付税額=2割加算後の税額ー税額控除の合計額
5.相続税の申告と納付
相続税の申告と納付とは、相続人や包括受遺者が、相続や遺贈で取得した財産に対して、税務署に申告書を提出し、相続税を支払うことです。相続税の申告と納付は、次のように行います。
1️⃣相続税の申告
相続税の申告とは、相続人や包括受遺者が、相続や遺贈で取得した財産の内容や価額、相続税の計算方法や額などを、所定の様式に記入して税務署に提出することです。相続税の申告は、次のように行います。
申告期限を確認する
申告書を作成する
相続税の申告書とは、相続税の申告に必要な書類の総称で、次のようなものがあります。
相続税の申告書(様式第1号)
財産目録(様式第2号)
財産評価書(様式第3号)
財産評価計算書(様式第4号)
相続税の計算書(様式第5号)
相続税の納付書(様式第6号)
その他の添付書類(相続関係説明図、戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書など)
申告書を提出する
相続税の申告書の提出先とは、被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人や包括受遺者の住所地を所轄する税務署ではありません。申告書の提出方法は、次のようなものがあります。
窓口で直接提出する
郵送で提出する
電子申告で提出する(e-Taxを利用する場合)
2️⃣相続税の納付
相続税の納付とは、相続人や包括受遺者が、相続税の申告書に記載した相続税の額を、税務署や金融機関などに支払うことです。相続税の納付は、次のように行います。納付期限を確認する。
相続税の納付期限とは、相続税の申告期限と同じで、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内のことです。納付期限までに納付しない場合は、延滞税がかかります。
納付方法を選択する
相続税の納付方法とは、相続税を支払う方法のことで、次のようなものがあります。
一括納付:相続税を一度に全額支払う方法です。納付期限までに納付する必要があります。
分割納付:相続税を分割して支払う方法です。納付期限までに税務署に申請し、許可を受ける必要があります。分割回数は最大12回までで、分割納付には利息がかかります。
延納:相続税の納付を一定期間猶予する方法です。納付期限までに税務署に申請し、許可を受ける必要があります。延納期間は最大5年までで、延納には利息がかかります。
物納:相続税を金銭ではなく財産で支払う方法です。納付期限までに税務署に申請し、許可を受ける必要があります。物納には、国債や地方債、株式、不動産などが対象となります。
納付先を選択する
相続税の納付先とは、相続税を支払う場所のことで、次のようなものがあります。
税務署:相続税の申告書とともに納付する場合や、分割納付や延納の場合に利用します。
金融機関:銀行や信用金庫などの金融機関で納付する場合に利用します。納付書が必要です。
電子納付:インターネットバンキングやATMなどで納付する場合に利用します。納付書が必要です。
※FP3級試験練習問題
相続税の基本に関するFP3級の試験問題と回答を作成しました。😊
問題1. 次の相続における相続税の計算方法について、正しいものを選びなさい。
<相続の概要> 被相続人の死亡時における住所は東京都である。相続人は妻と子2人である。相続財産は次のとおりである。
現金:1,000万円
預貯金:2,000万円
株式:3,000万円
自宅(土地):4,000万円
自宅(建物):2,000万円
車:500万円
死亡保険金:1,000万円(契約者・被保険者=被相続人、受取人=妻)
<選択肢>
相続税の対象となる財産の価額は13,500万円である。相続税の課税価格の合計額は13,500万円から遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×3人=5,800万円)を差し引いた7,700万円である。相続税の総額は、7,700万円を法定相続分通りに分けた各相続人の取得金額に対応する税率と控除額を適用して計算し、合計すると2,050万円である。
相続税の対象となる財産の価額は14,000万円である。相続税の課税価格の合計額は14,000万円から遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×3人=5,800万円)を差し引いた8,200万円である。相続税の総額は、8,200万円を法定相続分通りに分けた各相続人の取得金額に対応する税率と控除額を適用して計算し、合計すると2,250万円である。
相続税の対象となる財産の価額は13,500万円である。相続税の課税価格の合計額は13,500万円から遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×3人=5,800万円)を差し引いた7,700万円である。相続税の総額は、7,700万円を法定相続分通りに分けた各相続人の取得金額に対応する税率と控除額を適用して計算し、合計すると2,150万円である。
相続税の対象となる財産の価額は14,000万円である。相続税の課税価格の合計額は14,000万円から遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×3人=5,800万円)を差し引いた8,200万円である。相続税の総額は、8,200万円を法定相続分通りに分けた各相続人の取得金額に対応する税率と控除額を適用して計算し、合計すると2,350万円である。
回答:3
解説: 相続税の対象となる財産の価額は、相続や遺贈で取得した財産の価額の合計額である。ただし、死亡保険金については、法定相続人の数×500万円まで非課税となる。よって、相続税の対象となる財産の価額は、13,500万円(14,000万円-500万円)である。
相続税の課税価格の合計額は、相続税の対象となる財産の価額から遺産に係る基礎控除額を差し引いたものである。遺産に係る基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えたものである。よって、相続税の課税価格の合計額は、7,700万円(13,500万円-5,800万円)である。
相続税の総額は、相続税の課税価格の合計額を法定相続分通りに分けた各相続人の取得金額に対応する税率と控除額を適用して計算し、合計したものである。法定相続分は、妻2分の1、子4分の1、子4分の1となる。よって、相続税の総額は、次のように計算できる。
表
相続人 取得金額 税率 控除額 税額
妻 3,850万円 20% 200万円 570万円
子 1,925万円 15% 50万円 240万円
子 1,925万円 15% 50万円 240万円
合計 7,700万円 1,050万円
相続税の総額は、1,050万円に相続税額の2割加算(210万円)を加えた2,150万円である。2割加算は、相続人や包括受遺者が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合に適用される。本問では、被相続人の母が相続人であるため、2割加算の対象となる。
以上の理由から、正しい答えは選択肢3である。
これらの内容がFP3級試験に役立つことを願っています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
