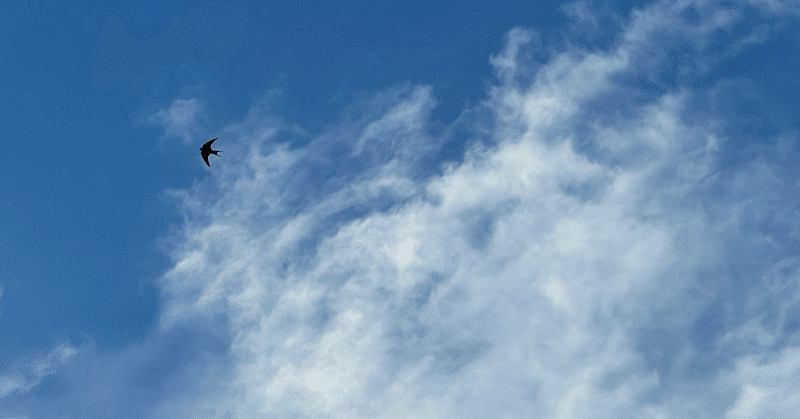
「冒険」がしたい大学生。 Vol. 2
第二章 机に向かって空を飛ぶ。15~18歳
机に向かいながら空を飛べるわけがない。というか人間は生身で空を飛べない。二年前の私は映画の物語世界に没頭しすぎるあまり、「人は空を飛べない」という事実をどうしても受け入れられなかった。
十代後半になると、私は自分の小説を書き始めた。しかし、最後まで書きあげたのは『メイリンと魔法の指輪』というタイトルの一作品だけだ。小説とは呼べないほどの、個人の偏見と欲求を詰め込んだ作品だ。とても読めたものじゃない。頭の中で想像した映像を無理やり言葉にしたようなものだ。指輪が人を惑わせるというアイデアは完全に『ホビット』に基づいている(この時はまだ『ロード・オブ・ザ・リング』を知らなかった)。裏紙に手書きで記し「穴あけパンチ」と毛糸で綴じた。古い書物に見えるよう、コーヒーや絵の具、うがい薬で紙を染めた。今も本棚からとり出すと、うがい薬の臭いがほのかに香る。
高校生になったころからほかにも2本くらいの小説のアイデアを書きはじめた。小説というよりは自分で妄想を膨らませて作り出した「世界」と呼ぶべきか。部屋でひとりその世界に陶酔していた。自分が作り出した世界だから当然理想的だ。理想的なトラブルが起きて理想的な人が現れ、理想的な冒険ができる。ところが、現実はそうはいかない。
毎日同じ通学路を歩いて毎日代わり映えのしない学校に通わなければならない。勉強はしなければならない。なんて味気ない日々。「冒険がしたい。『ありがたい』日常を捨て去りたい。人間関係も、今やっていることもすべて投げ出して自由気ままに空を飛べたらどんなにいいだろう。大学受験期に入るとその想いは加速した。どうして勉強してるんだろう?本当にやりたいことじゃないのに。どうして机に向かわなければいけないんだろう?大学には「行った方がいいから」行かないと就職できないから。じゃあ学歴社会のせいだ。日本の社会のせいだ」。
自分を縛る不自由を「網戸」にたとえたことがある。「外は見えるけど、網目が邪魔をする。風は入って来るけど、自分からそちらに行くことはできない。本物の『外』に手を触れることもできない。そして自分を阻むものは『壁』なんて大それたものではなく『網戸』という味気なくてダサいものだ」と考えていた。しかし、網戸を堅く閉めていたのは誰でもない、自分自身だった。「網戸は決して開けることはできない」と勝手にあきらめていたのだ。あの頃は毎日のようにトンビを眺めていた。風に身をまかせ悠々と舞う姿をとりつかれたように見つめていた。あんなふうになりたいと思った。これが高校時代。
大学に入学後一年間は新型コロナウイルス感染症のパンデミックに見舞われた。気がつくと家から一歩も出ない日がつづいていた。それでもベランダからトンビを眺めつづけた。毎日変わらない景色、日々だらしなくなっていく自分の外見。見かねた母が「野菜の収穫を手伝って」「散歩にでも行ったら?」としきりに声をかけてくれ、私は家の外に出た。これが転機となり、それまでの生活が一変した。
次回、「Home(故郷)について。19~20歳」お楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
