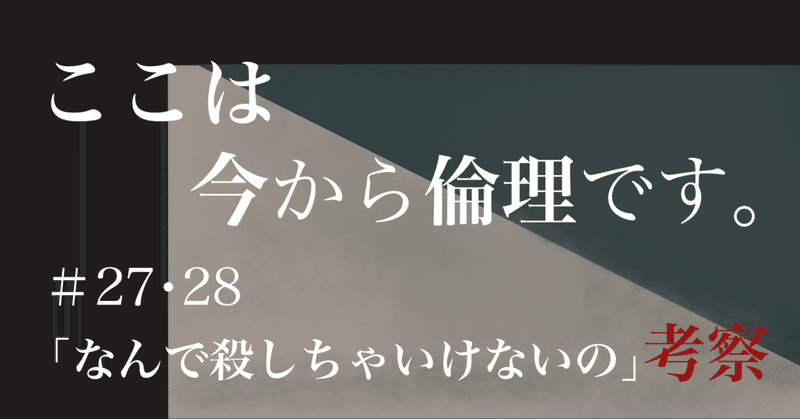
『ここは今から倫理です。』27・28話を読んで"今"私が何を考えているか
□鳥岡くんの問い「なんで殺しちゃいけないの?」
今回取り上げるのは『ここは今から倫理です。』6巻に収録されている、倫理の先生である高柳と素行不良な生徒である鳥岡との話である。
この記事はすでに話を一度読んだことがある人を読者として想定しているため、ネタバレが含まれる。
さて、鳥岡には幼いころから何かを殺したいという衝動があり、現在の高校生活では他生徒との喧嘩や性交を行う様子が描かれる。そんな鳥岡が高柳先生にぶつけたテーマは「なぜ人を殺してはいけないのか」である。
□鳥岡君の攻撃性ってどこからくるの?
鳥岡にとっての防衛反応もしくはコントロールできない苛立ちからきている。自分を攻撃してくる上級生に仕返しすることはもちろん、高柳先生を独占している六本という他生徒に苛立った時も攻撃的行動があらわれる。
周りの人間は自分を傷つけようとする敵としてとらえ、その相手の感情を考えることはしない姿勢が描かれる。
しかし、他者への無理解を徹底して貫き通している様子の鳥岡は、高柳先生に対して異なった行動をみせている。ある鳥岡の喧嘩後のシーンでは、高柳先生が鳥岡と女子生徒の対応順序に迷いそうな場面では、以下のような気づかいをみせている。
「今は外で先輩がブッ倒れてっから
せんせーはそっち優先したほーがいいと思う」
(『ここは今から倫理です。』6巻 p.70)
□なぜ鳥岡くんは高柳先生には違う態度をとるの?
きっかけは「なんで殺しちゃいけないの?」と鳥岡が高柳先生に聞いたことである。その場の高柳先生の対応は、問いに対して向き合う姿勢を十分に示すものである。
さらに、その後のやり取りにおいても、鳥岡の視点で描かれる高柳先生は”自分を優先してくれている”と感じさせるものである。
また、鳥岡は高柳先生に待たされ、後回しにされていると感じた時にはイライラする描写もある。
□ゲシュタルト療法ってどんな治療方法なの?
作中でカウンセラーの萱島(かやしま)は、鳥岡に対してゲシュタルト療法で治療にあたろうとする。
ゲシュタルト療法は人間学的心理学のひとつであり、人間学的心理学の主なテーマは以下の3つに代表される。
①自己本来の可能性の発見
②自分の存在意識への気づき
③責任と選択に基づく本位的な生き方
ゲシュタルト療法の治療メカニズムは感情そのものを発散することである。抑圧された感情を発散させ、自己認識の欠如に気づくことにより心身の恒常性と人格の統合を目指す。
患者は治療をとおして、「いま、この時点」の内臓的体験(体のどこかの感覚など)を象徴的にとらえ、外界ではなく人間の内部に自分を変える・支える力があることを体験する。
これを高柳先生は以下のような言葉で語っている。
「ゲシュタルト療法」はスクラップアンドビルドのカウンセリングと言われています
自分の考えをまずは徹底的に粉々に”破壊”して貰って…
その粉の中から新しい考え方を”再構築”して貰うというやり方
(『ここは今から倫理です。』6巻 p.100)
□ なぜ萱島とは話したのにスクールカウンセラーの前では口を開かないの?
スクールカウンセラーの「傾聴」に対して、鳥岡は心理的安心感がないと判断した。
スクールカウンセラーは学内の人間だという意識があり、話した内容が他の教師に漏れないという確証がないと感じていた。金銭のやり取りもなく、時間も制限が緩い学校側のサービスでしかない。
対照的に、萱島は学外にいるカウンセラーであり、萱島は仕事として鳥岡と話す。費用も発生するし、話せるのは営業時間内に限られる。
鳥岡は高柳先生を窓口として、学外に自分に適した答えの探し方を見出す。
□ 高校生にとって8800円って高くない?
萱島の提示するカウンセリング費用は8800円である。高校生にとって8800円は簡単に払える金額ではない。鳥岡がタバコをやめたとしても工面できる金額ではなさそうだ。
そこで鳥岡は父親にカウンセリングに行きたいと伝える。この場面は鳥岡の目線で描かれている。破れたふすまと暗い部屋、振り向く父親の目つきは粗く太い線で描かれている。鳥岡は犯行現場をみている第一発見者のようだ。
ともあれ、鳥岡はその後も萱島のもとでカウンセリングを受け続けている。その費用は父親が出していると推察できる。鳥岡の視点からは、家庭内は暗く描かれているが、父親の視点からみると異なるかもしれない。
□ 「なんで殺しちゃいけないの?」という問いは幼稚な質問なのか?
高柳先生もいっているが、この問いに答えを出すだけでは、鳥岡のこころのモヤモヤはなくならないと思われる。必要なのは自分の中の感覚に何故と問いを立てたときに、言語化して整理する力を身に着けることだろう。
□ なぜ人を殺してはいけないのか
作中ではこの問いに対して一時保留という展開だ。
しかし、このページでは少し触れようと思う。
最初のアプローチとして、ゲーム理論風に考えるならば、鳥岡の住む日本において多くの人々が選択している均衡状態は「人は互いに殺しあわない」状態であるといえる。
この選択の結果が、人を殺さないルールである。
そのため、一部のサンプルが殺人行動を選択し、状態にゆらぎが生じたとしても、やがて元の「人は互いに殺しあわない」均衡状態に戻る。
次に国家理論的なアプローチでは、『リヴァイアサン 』(トマス・ホッブズ)によると、作者のホッブズは、国家も法律もない自然状態において、人々は「万人の万人に対する闘争」と呼ばれる混乱状態にあるとした。
この闘争を停止させるためには、自然法というルールが必要であるとした。第一に「平和を手にする望みがある限り、平和へと進め。~」とあるように、人は互いに殺しあうことをやめることが国家の秩序となる。
しかしながら、環境や社会的死生観の変化といったきっかけがあれば、人々の選択する均衡状態が変わりプライド戦争が起こることもあるだろう。
ホッブズの唱えた第一の自然法の続きはこうだ。
「平和を手にする望みがある限り、平和へと進め。その望みがなければ戦争遂行のためあらゆる手段を使用せよ」
□ この出来事は鳥岡君にとって良いイベントだったのか?
後日談として、鳥岡が高柳先生に以下のように話しかける場面が描かれる。
「せんせーい、昨日もいったぁ偉いっしょ~」
(『ここは今から倫理です。』6巻 p.129)
これまでの放課後は、ストレスを何とか解消しているが、悩みや闘争の中で心を摩耗させながら過ごしていた。今回の出来事によって、この時間の一部が自尊心の向上につながる時間の過ごし方になっている。
これらの結果が生まれたのは、高柳先生に話しかけた場面、親にカウンセリング費用を出して貰う場面といった要所で、鳥岡自身が行動を起こしたからである。転換点を迎えるために、行動が重要であると再認識した。
□おわりに
『幽麗塔』(乃木坂太郎著)という作品で描かれる「人を殺したものは、殺す前と変わってしまう」というテーマを思い出した。
今回取り上げた作品でも、カブトムシの幼虫を殺した鳥岡は、死体の血液の色である黒色に、気持ち悪いという感覚を結び付けている。
もしも人間を殺してしまったら、もう殺す前と同様に人間を見ることができなくなるのかもしれない。鳥岡が一番ましだと思える”赤色”すら気持ち悪い色になってしまうだろう。
この色再感覚は人間性の比喩であるとも感じた。
そうなれば、殺人を犯して人間性が変化した場合、鳥岡に残された髪型はスキンヘッドしかない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
