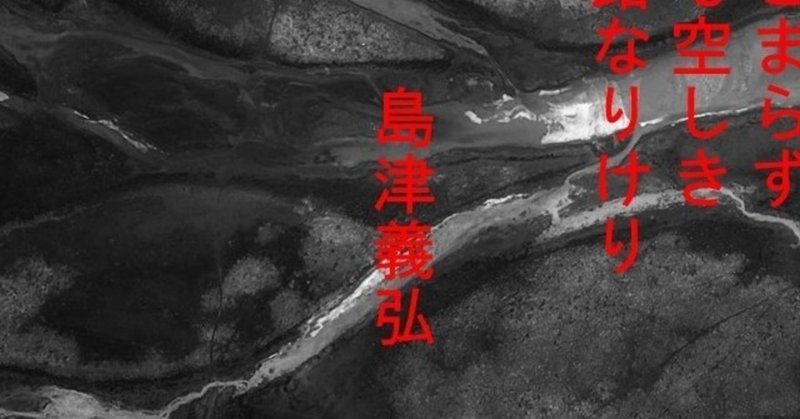
島津義弘の辞世 戦国百人一首⑬
島津義弘(1535-1619)は、⑫で紹介した島津日新斎(忠良)の孫だ。
「鬼島津」と呼ばれた猛将である。
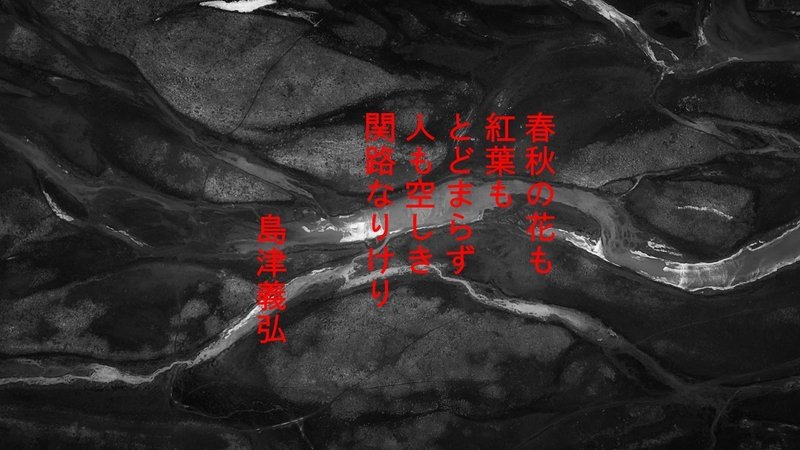
春秋の花も紅葉もとどまらず 人も空しき関路なりけり
春の桜や秋の紅葉が散っていくように、
人の一生も関路のようにはかないものだ
1597年から98年にかけての慶長の役(朝鮮出兵)のときに朝鮮水軍を震い上がらせ、1600年の関ヶ原の戦いで見せた決死の中央突破「島津の退き口」をやってのけた、猛将の辞世にしては少し弱々し気に聞こえるだろうか。
「関路」という言葉に注目して欲しい。
これは、「関ヶ原から続く道」という意味が込められている。
1619年、死に際の島津義弘は、まだあの関ヶ原の戦いで薩摩まで帰国した時の逃亡劇のことが忘れられなかったのだ。
関ヶ原の戦い。
西軍に与していた島津義弘は、西方の敗北が濃厚となったときに撤退を決意した。
生き残るためのその方法とは、目の前の東軍に突っ込み、中央突破して逃げるという思い切ったものだった。
東軍の福島正則軍を蹴散らし、井伊直政、本多忠勝などの追撃を受けながらも伊勢街道から難波の港へ向かった。
その時に島津軍が用いた凄まじい戦法が「捨てがまり」だ。
本隊が逃げる間に、何人かがその場に留まって死ぬまで敵の足止めする。
彼らが全滅すれば、また新しい足止め部隊が残って本隊が逃げる時間稼ぎをした。
難波の港から船で帰国し生きて薩摩に戻れたのは、300人中たった80人。
この撤退戦が「島津の退き口」として島津軍の勇猛さを世に知らしめた。
晩年になっても義弘はその撤退劇のことが忘れられなかった。
自分の死期にあたって、大将の自分を戦場から生きて帰すために、喜んで命をなげうち、犠牲になった忠義に篤い家臣たちの命のことを思ったのだろうか。
それが「関路」という言葉になって彼の辞世にも登場した。
彼にはもう一つの辞世がある。
天地(あめつち)の 開けぬ先の 我なれば 生くるにもなし 死するにもなし
じきにこの世から消えてなくなる自分は、それはただ元に戻るだけのこと。死ぬことでも生きることでもないのだ
島津義弘は、大隅の加治木の隠居先にて死没した。享年85。
義弘の後を追って13名の家臣が殉死している。
