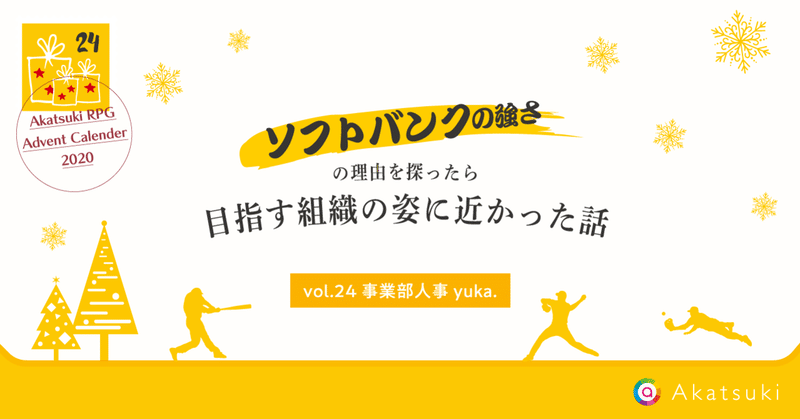
ソフトバンクの強さの理由を探ったら目指す組織の姿に近かった話
この記事は、『アカツキ人事がハートドリブンに書く Advent Calendar 2020』 の 24日目の記事です。 前回は鶴岡優子さんの、「広報」と「採用広報」の違いは何か?アカツキの採用広報3つの事例で考える でした。
こんにちは、yuka.です。昨年は丸選手みたいな人を採用したい話の記事を書かせていただきました。今回も好きな野球から学ぶ組織やチームづくりについて書きたいなと思っています。人事以外の方でも、野球のことはよくわからん〜という方でも(笑)組織やチームづくりに日々奮闘されている方に読んでもらえたら嬉しいです。
今年はなんと言ってもコロナ禍の影響で、プロ野球が無事に開幕できるのか、そもそも開幕していいのだろうか、開幕したとして(無観客試合で)野球を楽しめるだろうかなど、ファンとしても複雑な心境でした。ただいざ開幕を迎えてみると、野球が観れる喜びとこれまでの日常が戻ってきた安堵感が入り混じり、とにかく感動したことを覚えています。同時にスポーツ(もっと広義に捉えるとエンタメ)は人の心をこんなにも潤す力があることや日々の生活に根づいているのだと再認識させられました。
異例のシーズンもようやく先日終わりましたが、それにしてもソフトバンクは強かったですね。とても強かった。どのポジションの選手もレベルが高く、主力選手に若手がたくさんいます。CSと日本シリーズを見るにつれて、気がつくと試合展開そっちのけで強さの理由が気になっていました。「圧倒的な強さ」というキーワードに引き寄せられるように読んだ本がこちらです。
私の話を少しだけさせていただくと、今はゲーム事業部内の人事担当として働いています。具体的には事業部の戦略に紐づく人材定義や人員計画を行い、その計画にそって採用、配置、育成等で体制をつくっていく仕事です。事業戦略をどんな組織で実現していくかに向き合いながら、手探り感満載の日々です。そんな時にこの本を読みました。業界は全く違いますが、課題感が似ていて考えさせられる内容でした。前置きが少し長くなりましたが、その中身をご紹介させてください。
人材輩出に成功した3軍構想はどうできたのか?
2軍制が主流の日本の野球業界でソフトバンクが3軍制を導入したのは2011年のこと。3軍構想のコンセプトは大きく2つあります。
1つ目は「サバイバル思想」です。これはメジャー式をアレンジしています。人材の裾野を広く設け競わせるというやり方です。
- 抜粋 -
メジャー30球団はそれぞれ「8軍」まで抱えているわけだ。マイナー選手だけでも約6000人。独立リーグも各地で毎年のように発足したり、あるいは休止が繰り返されているが、毎年7〜8リーグが稼働している。
メジャーを頂点とする、米プロ野球界の「人材の裾野」の巨大さは明白だ。
これだけのマイナーリーガーがいれば、必然的に「メジャー」という小さなパイを巡っての争奪戦は激化する。ルーキーが、いきなりメジャーでデビューするケースは長いメジャーの歴史の中でも数例しかない。誰もが、下部組織からスタートする。試合の中で結果を出し、評価され、次の階段への上がっていく。
日本野球は2軍制で人材の裾野は狭く、生え抜き重視でトレードやFAもそれほど活発ではなく人材流動が少ないという課題があります。そこでメジャーのシステムを取り入れ、育成選手を増やし競争させ、人の回流を生み出そうという発想です。3軍の育成選手の給与は最低年俸240万円と低額で、かつ3年以内に芽が出ない場合は退団しなくてはなりません。そのため、なんとか生き残ろうとする必死さが1軍への足掛かりとなります。その下からの突き上げに1軍選手もうかうかできず、競争が生まれていくという構造です。競争がないところにはハングリーさは生まれない、それはつまり強さも生まれにくいという考えです。
2つ目はこの構想をつくった東大出身の元プロ野球選手小林至さんの原体験によるものでした。プロになったものの試合で投げる機会がとにかく少なく、1軍登板の機会がないままプロ生活は2年で終えたそうです。
- 抜粋 -
将来、1軍で戦うために鍛えなければならない選手たちに与えられる試合数が、1軍よりも少ないということは、どう考えても、合理的なシステムではない。これが育成を強化するべきだという自らの持論の「原体験です」と小林は明かす。とにかく、試合で投げる機会が少なすぎるのだ。
(中略)
シーズンのうち、1ヶ月に2イニングしか投げてない計算になる。
たたこれだけのチャンスでやり尽くしたなんて、とても言えない。
「試さずにクビ。燃え尽きていない。なんとなくクビですよ。悔しいだけ。それって球団にも選手にも損失ですよね」
投げる機会がない→成長しているかわからない→課題が生まれない→モチベーションが沸かない、この負のスパイラルを断つため生まれたのが、3軍制のコンセプトのひとつ「実戦主義」(=試合で投げないと結局うまくならないよねという考え)です。そのため3軍では練習だけでなく「たくさん試合をすること」に趣を置き、試合を通じて選手がPDCAを回せるシステムにしたのです。
①サバイバル思想
②実戦主義
この2つが3軍構想の肝となる思想です。これをいざ実現させるためには、試合ができる環境をつくり、低額給与とはいえ毎年十数名の選手たちを在籍させるコストはなかなかのものなので、内外からの反発や反対は相当あったようです。それでもやり遂げられたのは、フロント及び現場の布陣を固めたこと、信念を持って推進したことだと本書には書かれています。
アカツキの人材育成・輩出機能を担う"CAPSチーム"
ここからは弊社の話になりますが、アカツキはゲームを中心としたIPプロデュースをする会社です。昨今の国内ゲーム市場は成熟期に入っており、ゲームのリッチ化や新技術開発など、新規ゲームを市場に出すコストや時間はどんどん膨らんでいます。また、市場自体がある程度落ち着いていることもあって人の流動性も高いとは言えない状態です。つまり新しいゲームをつくるという打席に立てる機会が少なく、人材の流動が鈍いという点がまさに日本野球界の問題とシンクロしているなと思いました。
人材の裾野を広げることにおいては、弊社でも以前から取り組んでいることがあります。人材育成と人材輩出の役割を担うCAPSというチームの存在です。チーム名は「Customer And Product Satisfaction」からきていて、「顧客とプロダクトの満足度の最大化」を追求するチームです。製品の品質の担保とお客様のサポートをミッションに置きつつ、ゲーム業界を志す人の登竜門的な存在を目指し組織づくりをしているのです。将来ゲームプランナーやディレクター、プロデューサーになりたいという熱い想いがある未経験の方をアルバイトや契約社員で採用しています。「自分で考え、行動し、なりたいを形にする」これを体現できる人が採用基準です。このハングリーさは3軍選手に繋がるところがあるかもしれません。その中でゲーム製作の過程を学び、足腰を鍛え、ディレクターやプロジェクトのコアメンバーになっています。アカツキの未来をつくる重要なチームです。CAPSメンバーのインタビューがありますので、よかったらぜひご覧ください。
安納さんというリーダーの存在
私が入社した6年前、すでにCAPSという組織はありました。今も昔も安納さんというリーダーが率いています。当時から当たり前のようにゲーム事業を支えてくれていました。今では100名以上の大きな組織になっています。「最高の品質と感動体験をつくること」というミッションに置きながら、事業や組織の変化と共にCAPSの組織はどうあるべきなのか常に真摯に向き合い続けています。色々な葛藤の中で「人材育成、人材輩出の役割を担う」と決めた当時のことが以下のインタビューでも語られています。
決めたことをブレず体現していくことは簡単なことじゃありません。その安納さんの偉大さが年々身に染みます。強い信念で今も変わらずメンバー1人1人と向き合い続けている安納さん。本当に尊敬しています。
実戦をどう積んでいくのか
「実戦主義」においても大事な要素だと考えています。ここ数ヶ月、クリエイターのスキルや経験値の底上げのため何をするべきなのか、社内外のプロデューサーやディレクター、同業界の人事の方に聞いて回りました。(お話を聞かせて頂いた皆さまありがとうございましたm(_ _)m)その中でわかったのは「企画〜リリースするまでの経験」をいかに積めるか(野球でいう試合)が重要であることです。
ゲームディレクター育成に関するまとめ
・経験したタイトル数(リリースしてからのユーザーの反応を経験すること)とにかく場数。特に失敗の数が重要
・アウトプットを見せ合い比較できることが大事
・職人芸ではない。特にロジックの部分とやり方の型は教えられる
・こだわりを持ってやることが結局「その人じゃなきゃできないこと」
・ディレクターの領域は広域である。全部(エンタメマインド、教養、ロジック)が高いレベルである人は少ないという前提のもと、複数で補うことを視野にいれて育てる
※ここでいう教養の高さとは、物事の洞察、掘り下げ力があり、その知見が豊富であることを指す
・同じ系統の人ばかりだと補完ができないし、良し悪しの判断もできない
潜在能力を開花させるための環境とその先導者が必要。では実際にどう実戦を積む場をつくるのか。ここについてはまだまだ模索中です。ただ人材獲得の難易度が増す中で自社に人材育成のシステムがあることはきっと組織の強みになっていくはずです。更に大事なのは、小林さんや安納さんのような強い意思や信念を持って取り組むリーダーの存在だと思っています。自分に置き換えた時に、、私はそんな風になれるのだろうか。。。全く自信ないし、今の存在価値すらよくわかない、、、という具合に、理想と現実の間で大いに悩んでいるというのが本音だったりします。その中で自分を支えているものは、アカツキがずっと大事にしてきた「チームで勝つこと」を体現し続けたい気持ちとその思いを共有できる仲間の存在があるからです。
業界や職種は違えど同じようなことに向き合っている方がたくさんいらっしゃると思います。正解はわからないけど、自分の想いを絶やさず頑張っていきましょうというエールを込めて。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
人事アドベントカレンダー
【 クリスマス限定 】株式会社アカツキの人事広報部に所属するメンバーが、ハートドリブン&思いのままに綴った記事を毎日リレー形式で連載しています。
記事を読んでアカツキが気になった方は、ぜひこちらのHPへ遊びにきてください。▶︎ https://aktsk.jp/recruit/
