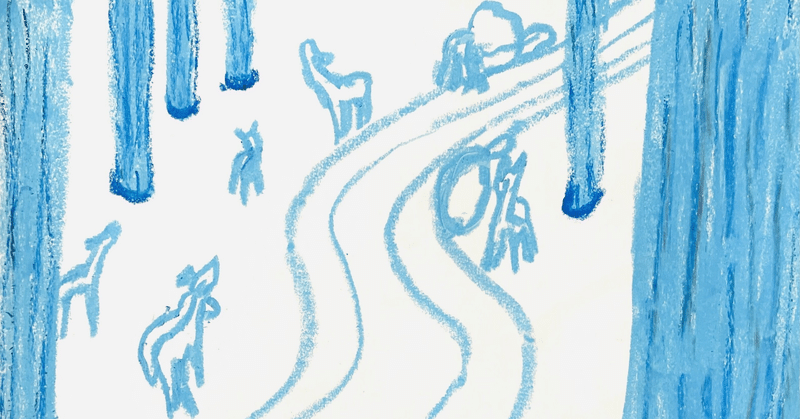
今月の一冊:宇佐美ゆくえ著『夷隅川』(港の人)
『夷隅川』は二〇一五年五月に発行された。作者は宇佐美ゆくえさん。かばんの会会員こずえユノ(現 ユノこずえ)さんのお母様である。残念ながら宇佐美ゆくえさんは、歌集が発行されたその年にお亡くなりになった。
『夷隅川』は、筆者が近年読んだ中で最も胸に迫ってきた歌集だ。その理由は、写実的な力が最大限に発揮され、作者の人生記ともいえる内容になっているからだ。境涯詠的な歌集は色々あるが、多くは短いスパンの内容である。本歌集ほど一人の人間の境涯が詰まったものは滅多にない。ゆくえさんの短歌を通読し、まるで古き良き邦画を観おわったような気分になった。
来嶋靖生著『中高年の短歌教室Ⅱ』(飯塚書店)によると、写実の基本とは、「具体的であること」「描写によって心のありさまを伝えること」だという。五感で知覚したことを〈具体的〉に〈描写〉することで〈心〉を示唆するのである。『夷隅川』から、五感に基づいた歌を一首ずつ挙げてみよう。太字がそれぞれの感覚に対応する箇所。
【視覚】 刈り終えしなだりの暮れて残したる山百合の花ほのかに白き 【聴覚】 そら豆の種選り分ける納屋のすみ間をおきながらこおろぎのなく【嗅覚】 藁を焼く中に落穂のまじるらしかぐわしき香の夕べ漂う
【味覚】 からすらの気付かぬうちにと味わいし山畑の枇杷いたく酸っぱし【触覚】 薪負いて届けてくれし母の背を思い出でつつ今はさするも
一首目だけ見てみたい。ここでは、刈らずに残しておいた山百合の花が暮れてもなお「ほのかに白」いと具体的に描写し、作者の受けた感動を暗に伝えている。さらに「白き」と連体形止めにすることで余情をかもし、山百合の存在・生命のかけがえのなさを看取しているように思う。ここに歌意の説明はいっさいなされていない。
では、なぜあえて説明を避けるのか。以下、一首目をもとに筆者なりの考えを示してみる。それが、ひいては写実の力を探ることになればと思う。
第一の理由として、三十一音字の短歌では、作者の感動を言い尽くすことができないからだ。一首目の感動をかりに既成の言葉で説明しようとすればどうなるか。〈うつくしい〉〈きよらかだ〉〈神々しい〉〈凛としている〉〈けなげだ〉と幾つもの言葉が必要になり、とても短歌の器におさまらない。
第二の理由。そのような多声的・重層的な感動は、既成の言葉で表現することができないからだ。短歌における写実表現とは、既成の言葉に変換できない感動を無理に説明するのではなく、具体描写に徹することで、出来るかぎり同じ感動を味わってもらおうという手法なのではないか。
そして第三の理由。短歌の写実とは、対象を理性によって認識し判断する以前の状態を描くことで、感動を伝えるものだからだ。作者が山百合のほの白さを見た時とは、〈うつくしい〉とか〈きよらかだ〉と理性が働く以前の状態である。一首目の内容は、作者が山百合のほの白い姿と出合い、山百合の趣そのものを感受した時間を描写している。〈うつくしい〉〈きよらかだ〉といった感想は、この歌で描かれた時間の後に出てくる認識や判断である。それを作者が叙述しないからこそ、読者の想像力が働く余白になっている。
以上の話は哲学が好きな人ならば、西田幾多郎の「純粋経験」論を想い出すかもしれないが、筆者がいいたいのはまさにそれである。
さて、ここまで短歌における写実というものを考えてみたが、本歌集で写実の力が最も発揮されているのは、夫のことを詠んだ歌だと思う。最後に、筆者の胸に迫ってきた歌を引用して終えたい。
雪げしき見むとのぼりし坂の道 夫のつけたる足あとをふむ
花の名が思い出せぬとたたずめる夫の傍にあじさい濡れて
詫びながらわが名きかるる淋しさを菜を間引きつつ思い出しおり
なごり惜しむ夫の思いか心音機とだえてはまた微かに鳴れり
初出「かばん」2016年2月号の「今月の一冊」
※一部加筆修正しました
