
ずっと食べたかったタルタルステーキを初食
9月6日、夜。突発的になんかあったものの、何とか仕事を切り上げてレストランにやってきた。

チェコ酒場Divadlo。見ての通り、店内は照明が弱めでいい雰囲気の店であった。自分もここに来るのは初めて。入ろう。もう予約時間より20分も遅れている。
「こんばんは!お一人ですか?」
「こんばんは。予約したUです」
「あっ、タルタルステーキをご予約した方ですね?席はどちらしましょうか?」
「そうですね……」
壁際の二人席に目を向けると、ワイングラスを片手に持っているエルフの王子がすでそこで座っていた。
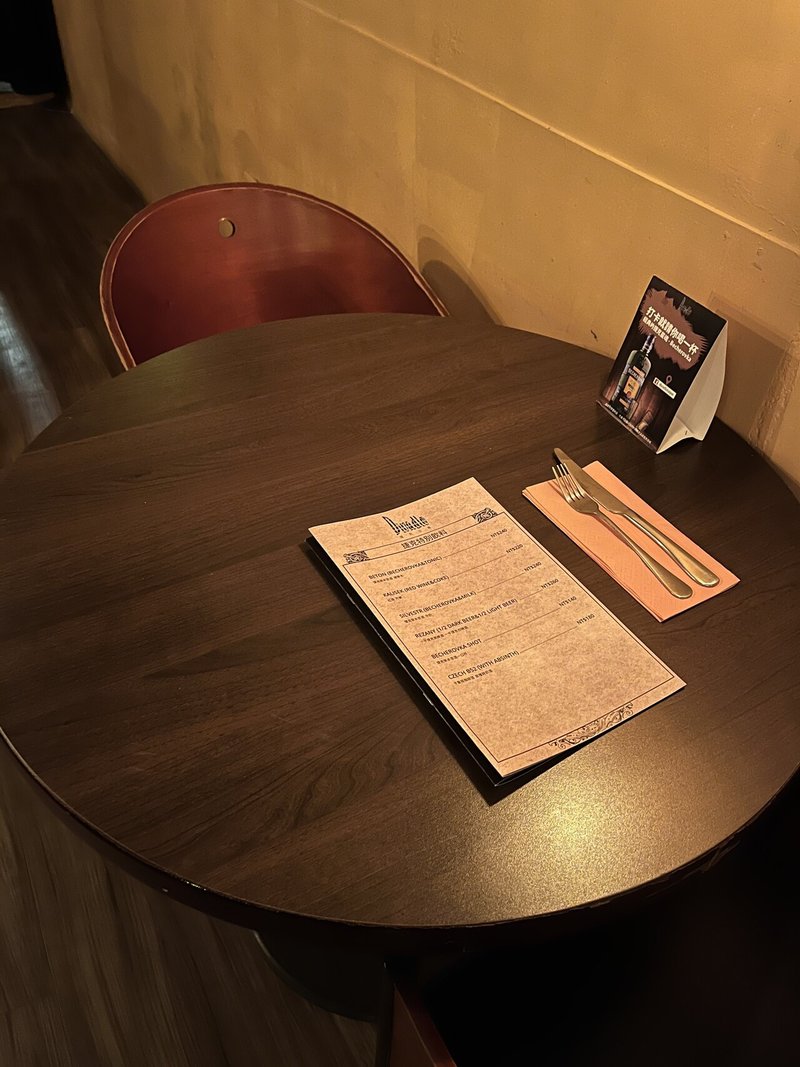
「この席にします」
「お飲み物やほかに料理も注文なさいますか?」
「はい、見てみます」
「決めたらまたお呼びください」
ウェイトレスがほかテーブルに向かった。俺は席に腰を掛けた。
「遅かったじゃないかアクズメ君」王子はワイングラスを揺らしながら言った。「もし私が先に来て席を取らなかったら、きみは今頃店のブラックリストに入れられてFacebookで携帯番号が晒されて大変なことになっていたぞ」
「なわけあるか。ちゃんと遅れますよと店に電話しておいた」
彼はエルフの王子、付き合いが一番ながいイマジナリーフレンドだ。彼の容姿は若き日のオーランドブルームと似たイケメンである。
「ってか、もう酒飲んでるし一人で楽しんでんじゃねえの」
「そうだ。私にこのままではひとり酒で溺れてしまう。きみも早く酒を注文せよ」
「ああ」
明日は休みを取ったので、とことん飲んでいくつもりだ。この店はメニューは事前にある程度把握した。

Rezanyというのは黒ビール半分と白ビール半分ずつ入れたアルコール飲料だ。チェコ名物らしい。
「すみませーん」
「はい、お注文は決まりましたか?」
「はい、このレー……なんて読むんですっけ?」
「すみません、実は私もよくわからないんです。で当店のおすすめってことは間違いないです」
ウェイトレスが苦笑。仕事なのにわからないんかい!ちょっと可愛い。
「じゃこれ一つ。あとチーズフレンチフライズも」
「はい、少々お待ちください」
ウェイトレスはタブレットで注文内容をキッチンに送った。飲み物の方は先に来た。

ただ2種類のビールをバーッと注ぐだけではなく、綺麗に層が分かれていて見た目もいい。
「酒が来たことでーー」
俺はジョッキを持ち上げた。ずっしりとしている。たまらねえ。
「34年目の人生、その始まりにーー」
王子もワイングラスを持ち上げた。
「困難に当てても乗り越えられる一年であると願いつつーー」
「「乾杯」」
キャン。ジョッキとワイングラスがぶつかった。俺はジョッキを口に運び、含んだ。黒ビールのコク深い味わいが口に広がる。なるほどそういうことか。このRezanyというのはBarにやってきた酒飲みが「今日は味が濃い黒ビールが飲みてえ~あっでも食事に合う白ビールも捨てがないなぁ~ねえマスター何とかならない?」とぬかして、「おう、できるぜ。待ってろ」とマスターそう言って即席に作った飲み物の感じだ。まず濃厚の黒ビールで仕上がらせて、そして料理が来てから白ビールを啜りながら食べるという楽しみ方。もしくは逆に白ビールでウォーミングアップして、最後は黒ビールでダッシュかけて酩酊の郷にゴールする。素晴らしい発想だ。
「うまいなぁ、今日は仕事がタフだったから余計美味しく感じるぜ」
「仕事のせいで遅れたか?」
「ああ」
「具体的になに言うと?」
「にあー、買い物したら金を払うという常識もインストールしていないお客様のケアとかさ」
「そんな些細なことで?私より仕事の方がどっち大事か?」
「何言ってんだ王子?まさかもう酔ってる?」
「……そうかもしれん」
あらま、弱気を見せるなんて王子にしても珍しい。
「タルタルステーキ入りまーす」
とウェイトレスが数枚の小皿を載せた木板を運んできた。

店のFacebookで予習したつもりだが、実物は迫力が違う。俺の脳裏に騎馬の軍隊が湾刀と弓を掲げて村に突撃するシーンがよぎった。タルタルステーキの起源としてモンゴル(タルタル)人が固い馬肉を乗用馬の鞍の下に挟んで、自分の体重と馬の運動で肉を柔らかくしてから生のままで食べるのが有名だが、単に肉の生食は蛮族連想させるため蛮族っぽい名前をつけたという説もある。
「では今から混ぜますね?」
「あっ、自分でやるんじゃなかったですか?」
「はい、私がやります」
「ちょっと撮影していいですか?」
「もちろんですよ」
「ありがとうございます。ちょっと……」
俺はスマホを録画モードに切り替えて、構えた。
「OKです」
「じゃ、始まりますね」
ウェイトレスは玉ねぎ、ケチャップ、マスタード、胡椒、岩塩、パプリカパウダーを順番に入れた後、2本のフォークで肉を混ぜていく。

べちゃ……びちゃ……粘質っぽい声を立てながら、ウェイトレスが巧妙なフォーク捌きでひき肉を潰し、攪拌している。何とも官能的感覚だ。
「食べ方も説明しますか?」
「はい、お願いします」
「では一枚作らせていただきますね。ここのパンがあります」


「パンを一枚とって、断面をにんにくで擦って汁を出させます」

「タルタルステーキをジャムのようにパンに広がります」

「最後はブラックペッパーを振りかければ完成です。問題ありますか?」
「いいえ、完全に把握しました。ありがとうございます」
「ではごゆっくりどうぞ」
ウェイトレスは去っていった。王子は彼女の背中を目で追いながら口を開いた。
「魅力的なレディだ。あとでLINEを尋ねようか?」
俺は王子の言葉を無視して食事に集中することにした。

とても赤くて、肉々しい。たまらねえ。俺は早速それを掴んで、齧りついた。
ぱり……もぎゅ……ぼり……
ふむ、なるほど、そういうことか。
一言で例えると、「とてもフレッシュなハンバーガー」が妥当でしょう。とてもFreshなFleshだ。よく見るとさっき挽肉に入れた玉ねぎ、ケチャップ、マスタードなど、全部ハンバーガーにもよく使われている材料だ。噛むごとに牛肉の旨みと玉ねぎ甘みが染み出て、生肉を頬張っている事実は心の野蛮的な部分を刺激して気持ちを昂らせる。脳内では騎馬の兵士が逃げ惑う村娘の背中に剣で切り裂き、鮮血が空高く舞い上がったシーンがよぎった。ちなみにハンバーグの起源はまさにこのタルタルステーキだと言われている。
「うん、うん、うまいぞこれ。王子も食ってみない?」
「遠慮する。私はきみに食される牛さんが広い牧場で不自由なく歩き回れて、おいしいエサを食べて育ち、そして人道的に苦痛なく屠殺されたことを願うよ」
「ああ、きっとそうだ。ありがとうな牛さん。美味しくいただくぜ」
雑談を混じりながら、俺は食事を進んだ。そしてパンの枚数が半分になったところで、ペースが著しく低下し始めた。
「苦しい……」
「なんだい?さっきまで旨い旨いと言っていたのではないか?」
「このパン、やばい。保存食のように乾くて硬い。咀嚼するだけで顎が疲れる。オリーブオイルを垂らしたのでとても油っぽく胃に負担がかかる。さらににんにくをおろせるぐらい繊維が荒いから、口の中の皮がもうザラザラだぜ……」
「でもここでギブアップしたら死んでくれた牛さんに申し訳ない」
「そうだな。頑張るよ」
「お待たせしました、チーズフレンチフライズです」
「ぶほっ!?」

「なんか、量がすごいですね。メニューの写真だと全然少なかったのに」
「はい、当店のフレンチフライズは多数人で楽しめるよう大盛にしています。タルタルステーキも二人前の量でセットしてます」
「それは有難いですねぇ。なぁ王子、芋なら食べても……」
「頑張れ」王子は真っ直ぐな目で俺を見つめるだけだった「きみならやれる」
王子の助力を得ず、孤独な闘いが幕を開けた。肉、肉、芋、酒、肉、芋、酒、肉、肉、トイレ、芋、肉、酒……
顎が疲弊してきた。口の中がモンゴル兵に蹂躙されたあと村みたいにめちゃくちゃになってるが、何とかパンと肉を完食できた。

「ふぅー……食ったなぁ」
「何を言っている、またフライズが残っているぞ」
「王子、俺が尊敬しているシェフのアンソニー・ボーディン氏がスペインロケの時こう言った。『おれはステーキに付け添えたポテトや野菜などを食わない。なぜなら付け添えは本当に付け添えただけで、そこに料理人の工夫が1ミリもこもっていないからだ。おれはステーキだけ食べる。だからたくさん食べれる』と」
「それで?これがフライズを完食しない理由になると?」
「うん」
「だめだ。チーズフレンチフライズは溶かしたチーズをかけたことで一品の料理として成立している、付け添えの範疇に入らない。よってアンソニーの理論が無効だ」
「わかったよもう、負けを認める。フードVS.ヒューマン、フードの勝利だったってことで」
重くなった腹を抱え、俺は会計を済ませて店を出た。
「来てくれてありがとうよ、王子。俺はしばらく散歩してから帰るけど、そっちはどう?」
「いつも通り、夜の街に飛び込んで私の温もりを必要としているレディを探しに征くぞ」
王子はプレイボーイの設定だった。
「そうか。あまり調子に乗りすぎて囲んで殴られないようにな」
「そちらこそ、あまりの孤独で心がやんで首を吊らないようにね」
「HAHA、笑えるぅ。じゃあな」
「良い夜を」
俺は帰路につき、王子は狩りに征った。
(終わり)
当アカウントは軽率送金をお勧めします。
