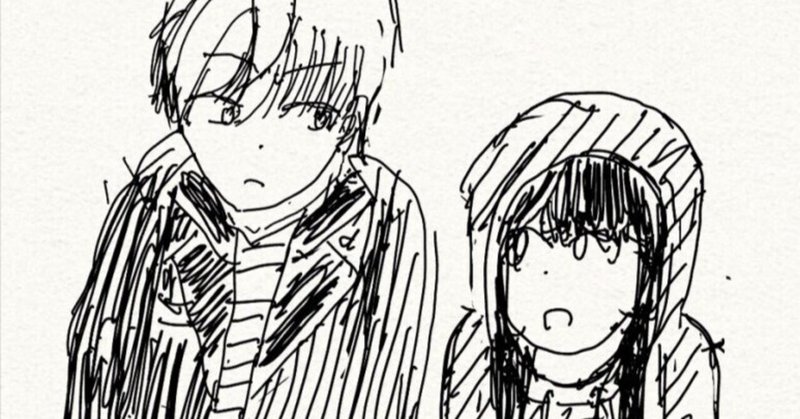
「CANON 11」 EP.2 人工知能評論家 (2)
《CANON MAGAZINE》はスピーディーでステディーな運営方針をを心がけていた。全編集者—二人—がレビューを週に一度以上は提出するようにして、マガジン規模で隔週ごとにコラムやエッセイ、時にはあるテーマに沿ったおすすめリストなどの特集記事も意識的に出すようにしていた。月が終わるとマンスリー・ベスト・アルバム/トラックを選定していき、年が終わると年間アワードを設けて、素晴らしい作品群と共に年の全貌を振り返る一大イベントに仕立てた。
歌音は文才があるし、Nも知識と分析力には富んでいた。とはいえ、本業がこれでない以上、さすがに二人だけで自ら設けたペースを保つのは意外と難しかった。特に年末年始になると労働量の激増を免れぬもので、ベストと候補群を選定してそれらの意義を書き直す作業をジャンルごとに行う作業をたった二人で負担していたのだ。
「問題は二つある」と、編集長の歌音。
「〈山ほど〉の間違いでは?」 総務のNが訊いた。
「しばくぞ。けどまあ二つに絞ったということで確かに間違ってはないな」
「合ってるのにしばかれるのか…。その一、」
「人手不足」
「その二、」
「資金不足、というかそもそも収益化できてない」
「詰んだな」
「諦め早ぇ〜! まあ確かにどこにでもある問題だし、しゃあねぇっちゃぁねぇけどよぉ…」
「なら人を集めたり金を儲ける手段を探せばいいじゃないか」
Nの言葉に歌音の素振りが止まって目だけぱちぱち瞬いた。
「その手があったか…」
そこで考えたのがSNSとYouTubeなどを活用したプラットフォームの拡張。そしてそれを運用するメディア・ディレクターを新しく呼ぶことで人手も補うつもりだった。その雇用費は出せるのか? とNから突っ込まれた時、「ボクらは法人でもなんでもない、ただの同人ブロガーなんだぜ?」と、詐欺師な口調ですらすらと言い訳をした。
かと言って、別に夜行星と仕事仲間になろうというところまでは思わなかった。彼女のチャンネルは次のステップをより解像度高く想像するためのレファレンスのうちの一つであって、会議のアポをとったところで、単なる助言やコネクション形成程度を求めたわけだ。夜行星はさすがに“theneedledrop”のような音楽レビューチャンネルの名声には全然及ばないにせよ、それでも五桁の登録者数を持って、毎日のように投稿する動画のほとんどが四桁以上の視聴者数を持続的に確保してきている立派で有益な V-Tubeチャンネルである。そんな人を無給でこき使える度胸まではさすがに至らなかった。
でも人じゃないというならいいかもしれない。
「ペースやばすぎると思ったんだよ」
歌音が言った。
「動画は毎日上がってて、しかもきちんと編集されてて、そんなんだと逆に音楽とか映画とか鑑賞する時間はあるのかって不思議だし、仮にチームの形で動いたとしてもそこまで大規模に人力を動かせるキャパまではいかないと思うんだよね」
「デジタル・データ化されている作品であるならすぐに読み込むのは簡単ですしね」
そしてドヤッと誇らしげな表情をする夜行星。時間芸術の根本を揺るがす発言だったが、かわいい。
「つまり?」
「人間離れしてると思ったけど、人間じゃないならいいっかって。ボクの仲間になれよ!」
歌音がどこかで聞いた台詞と共に手を差し伸べた。
「おい、こいつさっき〈人間の評論家など要らない〉とか言ってたぞ」
「いいですよ」
「いいのかい」
夜行星が答えた。
「私の上位互換性を見せつけて、やがて人間の評論家を絶滅させるいい機会ですもの」
「産業スパイだった」
Nのツッコミが忙しくなるばっかりの展開。
「おい、歌音、マジでこんなイカれたパソコンを仲間に入れていいのか⁈」
「ふーん、なに、妬いてんの?」
歌音がニヤッと笑った。
「なっ、そ、そんなんじゃねぇよ! つーかなんでお前こそ敵意丸出しな相手にそんな平然といられるんだよ」
「いやー、こんな人(人?)材が金要らずにモチベだけで働いてくれるなんて、一石二鳥じゃん?」
「こっちはこっちでゴリゴリの悪徳企業家だった…」
こうして編集長の歌音、総務のNに並んでメディア・ディレクターの夜行星が仲間に加わり、編集陣が三人(人?)になった《CANON MAGAZINE》。みな自己主張が強いからか、マガジンの改修作業は順調に進むわけではなかった。
最も激しく議論されたのは、評価点制度の見直しと合意だった。
歌音たちはメダルの色やRIAAの認定名にちなんでバッド/ノーマル/ブロンズ/シルバー/ゴールド/プラチナ/ダイヤの七段階評価で表した。駄作や凡作を大きい枠に詰め込んで、「悪くない」と「良い」、「すごい」、「素晴らしい」、そして「最高」を細かく区切り分けた形になっている。
一方で夜行星はレビュー作の評価を100.00を基準にパーセンテージ化して見せた。表示される数値は小数点以下二桁まで及ぶもので、夜行星自らの説明だと評価点を出す計算式が作られているようだ。
「ウッソだ〜。ボクも評点制度にはうるさい勢だけど、そんなのバババって計算できたら批評家なんて苦労しねぇよ」
「あら、だから言ったではないですか、人間の批評家などもう要らないと」
やっと唾をゴクリと飲み込んで緊張する姿の歌音。
「喉乾いた。エヌっち、アイスラテちょーだい」
違った。
「批評って原理さえわかれば難しくないのはあなたも承知のはず」
「バカにしてるなぁ」
「とある作品が位置するフィールドを見定め、そのフィールドが要求するルールに作品がどのようなパターンで応答するかを分析すれば、価値は簡単に判断できるのです」
「はあ」
「作品にまつわるメタデータの取得はもちろんのこと、フィールドごとのルールから作品内部の表現様式、そして作者が残した記録や社会風潮、理念、批評言説などのビッグデータを全てトークン化して組み合わせれば、批評の自動化なんてあっという間ですもの」
「理屈は納得した」
Nが首を傾げた。
「ボクのコーヒーは?」
「説明が長いところ、たぶん〈あっという間〉ではなかったはずなのでお疲れ様だけど、その図式自体のエラー可能性について他の知能・人格との相互フィードバックやディバグは行なったか?」
このシンギュラリティの彼方にある地獄絵図を目の当たりにしても落ち着いて突っ込めるNは、奇天烈な研究者の親元で幼い頃から本やレコード、ビデオの山に囲まれた面白い成長を経てきた。
「私、友達がいないのです」
「ごめんな、わかるぞそれ」
そのせいか、学校と波長がうまく合わず、高校を中退する選択をする。
「そのためにもあなたたちの協力が必要ですわ」
「やだよ、人類滅亡ルートじゃん」
「それはエントロピーの導きなので仕方ないこと…」
「否定はしないんだ」
「やっこー」
歌音が言った。もう愛称で呼んでるんだ、と二人は驚いた。
「仲間になるにつれていくつか戒めておきてぇもんがあるぜ」
あっ、特有の編集長ヅラだ、とNは気づいた。
「まず人が必要じゃなくて捨てるという思想は明確に拒否りたい。それだと脚動けないボクなんかはとっくに捨てもんだし?」
「脚が動かないということだけで捨て物にされる思想とは思えぬのですが、確認いたしますわ」
「そこだよ。脚じゃなくて口でも体でも頭でも回らなくたって要は同じだよ。ボクも読むと殺したくなる評論はいっぱいあるけど(お前も大概だよ、とNが突っ込んだ)やっこーの批評が人間どもと引き続き相互作用することを前提にしてるのなら、そういう選民思想は軽々しく言わないで欲しいのが一つ」
そして歌音がさらに深刻な顔になって言った。
「二つ目は、評価制度をどっちかに寄せなければならなくて、ボクは譲る気が全くないということだ」
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
