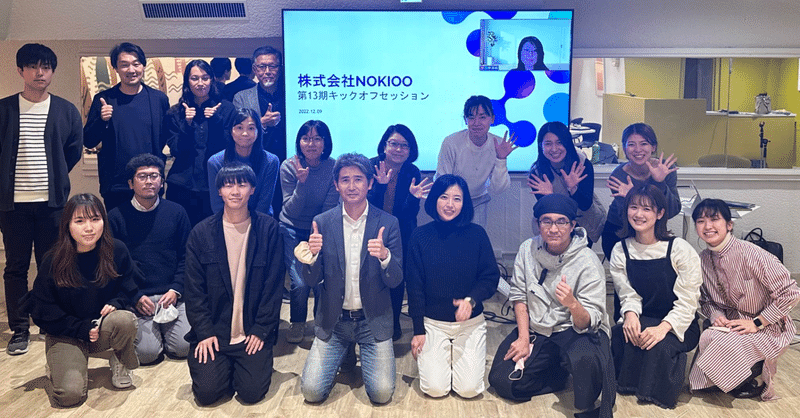
キックオフミーティングのススメ
1.NOKIOOのキックオフセッションに参加してきた
株式会社NOKIOO(ノキオ)の新しい期のキックオフセッションに参加してきました。
NOKIOOは僕の顧問先のうちの1社で、静岡県・浜松市に本社を置く従業員約20名の企業です。
フルリモートワークのメンバー(兵庫県、福岡県、大分県に在住)も多い会社ですが、この日はメンバーの多くが浜松に集合(オンライン参加のメンバーもいるためZoomを利用して配信もおこなっています)。このキックオフセッションで初めて顔を合わせる人もいます。

NOKIOOのキックオフセッションのプログラムの概要は以下の通りです。
・経営方針説明
・各事業部の事業計画共有
・グループワーク(組織の目指す姿、事業計画をディスカッションする)
・講義動画を視聴してのディスカッション
・懇親
会場は浜松市街のシェアオフィス・コワーキングスペース、Dexi(デクシィ)板屋に併設する、地下コラボレーションスペース "SOU"。

広く、明るく、そして暖かくて快適な空間で良いキックオフが出来ました。
2.キックオフミーティングの効果
NOKIOOのキックオフセッションに参加してみて、僕は率直にこう思いました。
「キックオフミーティング、おススメです。皆さんの会社や部署でも是非やってみてください!」
僕がNOKIOOのキックオフセッションに参加して感じたメリットは3つです。
(1)ビジョン、ミッション、バリューや事業計画の(初期)理解浸透を図ることができる
(2)メンバー同士の自己開示と相互理解が促進される
(3)意思決定への参画意識が醸成される
3.「有意義なキックオフミーティング」の特徴
「キックオフミーティング? 当社(当部署)でもやっていますが、どうも効果があるのかどうか分からなくてね……」
そうおっしゃる方もいらっしゃることでしょう。
盛り上がらない、チームビルディングに寄与しているのかどうかも不明。
そのような組織に共通して言えることがあります。それは……
一方通行である。
往々にして、盛り上がらないそして退屈な(失礼)キックオフミーティングは、経営トップや部門長が一方的に方針を語るだけの場になってしまっています。
(ちなみに、僕は日本の大企業に勤務していた頃、部門長の演説をただ聴かされるだけの部門のキックオフミーティングがほんとうに苦痛で、その日たまたま有給休暇取って摩周湖にいたこととかあります ←不良社員。良い子はマネしちゃダメです!)
今回のNOKIOOのキックオフセッションでは、経営陣による方針説明があった後に、テーマを決めたグループディスカッションを行いました。
「私たちはどんな顧客を理想の顧客ととらえるか?」
「私たちが顧客に提供する価値は?」
「私たちが顧客に価値を提供するために、どんな行動や体験を増やしていったら良いか?」
これらをテーマに、複数のグループに分けてディスカッション(僕はファシリテーターを務めました)。

このようなメンバー参加型のセッションは、メンバーが会社のビジョン・ミッション・バリューや、事業の方針を自分ごととして考えるきっかけになります。
メンバー参加型のディスカッションは、受け身ではなく会社の意思決定のプロセスに関与する(させる)意味もあります。
(僕は、エンパワーメントってそういう行動の積み重ねじゃないかなって日々思っています)
こういう「景色が変わる」場があるだけでも、メンバーの意識は徐々に組織のビジョン・ミッション・バリューに向きますし、ディスカッションを通じてメンバー同士の相互理解を図ることもできます。
「社員のコミュニケーションが良くない」
「テレワーク、ハイブリッドワークで職場の風通しが悪くなった」
「ビジョン・ミッション・バリューが社員に浸透しない」
そうお悩みの経営者、部門長、マネージャーの皆さん。キックオフミーティングに工夫を凝らしてみてはいかがでしょうか?景色を変えてみてはいかがでしょうか?
キックオフミーティングを有意義な場にするためのポイントは、新刊『話が進む仕切り方』にも散りばめています。宜しければご一読を。
こういうコミュニケーションの場を定期的に設けている効果もあってか、NOKIOOの社員はフルリモートワークのメンバーであってもオンボーディング(着任後にチームに順応すること)が早いです。
また、僕が一緒に仕事をしているメンバーも休暇後のキャッチアップがものすごく早い、素晴らしく早い、嘘みたいに早いです(驚きます)。そのポイントは、別の機会にお話しします。
「テレワークだとコミュニケーションがうまくいかない」
「ハイブリッドワークでは信頼関係構築ができない」
そう言っている経営者やマネージャーの皆さんには、是非NOKIOOのコミュニケーションの仕組みづくりを参考にしていただきたいです。
4.ワーケーションでのキックオフミーティングも有効
思い切って、キックオフミーティングを普段とは場所を変えて、ワーケーションでやってみるのも良いと思います。
(NOKIOOでも、事業部の業務合宿をワーケーションで開催することがあります)
NOKIOOのキックオフセッションの前日、僕は三島市のコラボレーションスペース「みしま未来研究所」に出張してワーケーションの講演と対談をしてきました。

この日はKDDIのグループ新会社『KDDIアジャイル開発センター株式会社』のメンバーがあつまり、チームビルディングと新規事業開発のアイディア出しを兼ねたワーケーション合宿が行われていました。そのワーケーション合宿のプログラムに、僕の講演が組み込まれていたのです。
(三菱地所で地方創生やワーケーションの活性に取り組む、神田主税さんと、KDDIでDX推進のミッションを担いつつ三島のコミュニティ作りを手掛ける大橋衛さんにお声がけいただきました)
発足したての新会社。普段はテレワーク併用、かつ出社していても異なるチーム間でのコミュニケーションがなかなか生まれにくい。
そんな中、オフィスでも普段のテレワーク場所でもない、三島市のコワーキングスペースで仕事をしてみる。講演を聞いて意見交換してみる。良いチームビルディングにの場になったようです。
キックオフミーティングを、普段とは景色を変えてワーケーションで行ってみる。それにより、コミュニケーションが生まれるようにする。
ワーケーションには、越境(普段とは違う環境に身を置いてみる行為)の効果が間違いなくあると実感しました。そして、ワーケーションは組織開発のための業務プロセスとして十分に機能し得ると確信しました。
越境のバリエーションと効果は、書籍『新時代を生き抜く越境思考』に詳しく書きましたので、宜しければ参考にしてみてください。
5.「場がある」こともきわめて重要
ところで、企業がいざキックオフミーティングやワーケーション合宿をやろうとしても、適切が場所がなければ意味がありません。
幸いなことに、浜松市にはDexiさんが運営するSOUのようなワークスペースが生まれ始めています。三島市には、加和太建設さんが運営するみしま未来研究所ほか、三島駅から徒歩圏内に複数のワークスペースやコミュニティスペースが増えています。
地域の建設会社やデザイン会社が、人々が交流する「場」を作り運営している。素晴らしいですね。
僕も企業の経営者や部門長によく聞かれます。
「沢渡さん、会社(部署)の業務合宿をやりたいのです。たまには郊外や地方でやりたいのですが、おススメの場所ありませんか?」
そんな時、企業のキックオフミーティングやワーケーション合宿に適する場がある町は喜んで紹介しやすくて助かります。

急なオンラインMTGにも対応でき、安心して出張できます

僕はこのような「場」を創造する企業がある地域はブランド価値(ファンを創り育む力)が高いと思います。新しいコトを誰かがその地域で起こそうとしても、「場」が地域にないことには始まりませんから。
ワーケーションにしても、どうもコンセプト先行でいざやろうとしても適する場がない。ゆえに単発のイベントやお祭り騒ぎで終わってしまう。そのような地域も散見されます。Dexiさんや加和太建設さんのような企業は素晴らしいと思いますし、地域に「場」を創り運営する企業が増えて欲しいと強く思います。
そして、「場」を活用してコト(変化)を起こす能力と行動は、これからの時代の組織およびビジネスパーソンに求められるものであると僕は感じています。
ちなみに、このレポート記事も僕は豊橋市内でワーケーションしながら綴りました。景色を変えると、発想と執筆も捗ります。
良い「場」を創っていきましょう。そして、「場」を良く活用していきましょう!
▼よい「場」づくり・ファシリテーションのための手引き。『話が進む仕切り方』
▼組織開発者のための越境学習プログラム『組織変革Lab』
▼組織変革、自分変革を目指すあなたのコミュニティ『沢渡あまねマネジメントクラブ』
