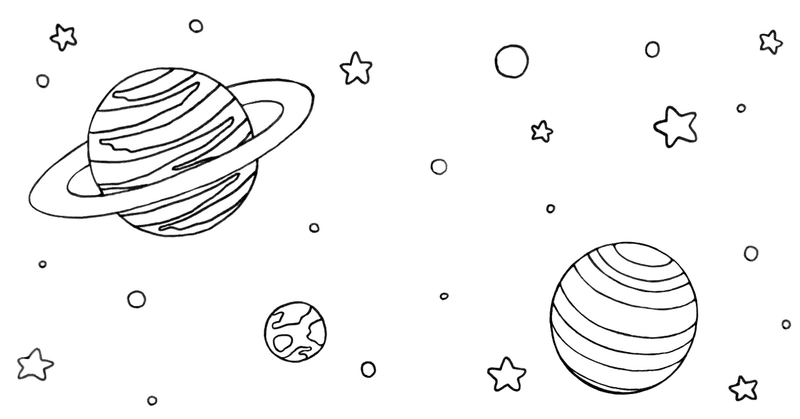
「惑星のメモリア」(短編小説)
遠くはなれた銀河の果てに、「F0168-エレ」という惑星がありました。
ここは、過去と未来が繋がりあう星。
空間に満ちる豊富なエネルギーと、それを動力にした巨大なコンピューター。
張り巡らされたネットワークには、毎日、宇宙からたくさんのアクセスがあります。
今日もまた、過去への手がかりを求めて、誰かがやって来たみたいです。
[……]
【こんにちは。初めていらっしゃる方ですね】
[……あ? これ、もう繋がってるのか。えーっと、『過去の自分と話せる星』っていうのは、この場所のことでいいのか?]
【ええ。間違っていませんよ。「過去」というのが、現在のあなたと深い繋がりを持つ、並行時空のことならば】
[並行……? あー、よく分かんないけどさ。間違ってないならいいんだ。それで、早速利用してみたいんだけど]
【かしこまりました。では、まず出身星と、お名前のほうをお教えいただけますか?】
[ネオレイラ星。アルテ・リード、26歳]
【アルテ様ですね。私はクレイス。このシステムの案内役を務めさせていただいております。疑問に思ったことや、質問などがございましたら、お気軽にお尋ねください】
[その「様」っていうのやめてもらえないか。なんか、むず痒くなる]
【では、アルテさん、でよろしいでしょうか】
[んー…本当は、呼び捨てのほうが気楽だけど、まあ、それでもいいよ]
【承知しました。私のことは、ご自由にお呼びくださって構いませんので】
[了解、クレイス]
【それでは、今から、あなたの過去の意識へと接続していきます。準備はよろしいですか?】
[え……必要な情報って、あれだけでよかったのか? もっと、いろいろ聞かれるかと思ったのに]
【いろいろ、とは?】
[なんかこう、あるだろ。職業とか、趣味とかさ]
【形としてのデータよりも、あなたの意識が今この場所にある、ということのほうが重要ですので】
[ふーん……そんなもんか]
【それに、あなたのことは存じております。アルテさん。先月リリースされた「水星の記憶」、とても良かったですよ】
[! 知ってるのか!?]
【はい。「ジオネル」と言えば、この惑星でも名前の知られたバンドですから】
[そっか。はは、なんか嬉しいね。……いや、こんなところで、俺たちを知ってるやつに出会えるなんて思ってなかったからさ]
【この星のネットワークには、毎日たくさんの情報が流れてきます。私はそこから、新たな知識や学びを得ることが好きです。「言葉」というのは、実に多くの世界を見せてくれます。ですが同時に、「音楽」というものの可能性にも興味を持っているんです。たとえ言葉が分からなくても、伝わるものがありますから】
あそこにある、四角い窓が見えますか?
そう言われて視線を向けると、白い空間の真ん中に、いつのまにか枠のようなものが出現していることに気がつきました。
【深層へと繋がる入り口です。どうやら、私たちを受け入れるための準備が整ったみたいですね】
クレイスに促されて、窓のような入り口が浮かぶ場所へと近づいていきます。
よく見ると、表面はガラスではなく、薄いスクリーンのようになっているのが分かりました。
【どの地点の過去へとアクセスしたいか。日時や場所など、ご要望があれば承りますが】
[……そうだな。俺の頭の中にある、一番古い記憶。確か、4歳か、5歳くらいの頃だったと思う。時期はいつでもいいけど、その頃の自分に会って、伝えたいことがあるんだ]
【わかりました。では、過去の自分をイメージしながら、窓の向こうがわを覗き込んでみてください】
言われた通りにすると、何も映っていなかった枠の中に、ぼんやりとした映像が浮かび上がってきました。
それは、次第にはっきりとした形を取り始め、やがて、一人の少年の姿へと変わりました。
白い部屋。
広い空間に置かれた、質のよさそうな調度品。
シンプルながら、手入れの行き届いたそれらの家具は、見る人が見れば、一目で高価なものだと分かります。
しかし、広すぎる室内に、少年以外の人の気配はありません。
部屋の隅っこの小さなスペース。
壁際に座って、絵本を眺めているその顔からは、何の表情も読み取ることはできません。
ただ、背中を丸めた小さな体だけが、この空間を、寂しげなものに見せていました。
【この時のことを、覚えていますか?】
クレイスに聞かれて、アルテは、ああ、と答えます。
[うろ覚えだけどね。この頃の俺は、いつも一人でいることが多かった。母親は、仕事漬けの毎日で、めったに家に帰らなかった。父親は、この2、3年ほど前に病気で死んで、そのストレスもあったんだと思う]
【他に、頼れる人はいなかったのですか?】
[週に何度か出入りする、通いの家政婦がいた。身の回りのことや、ちょっとした家事なんかは、その人がやってくれてたよ]
【大人からの愛情を必要とする時期ですから、さぞ寂しかったことでしょう】
[……そうだな。今思えば、すごく寂しかったし、苦しかったよ。でも、この時の俺は、その気持ちを誰かに話したり、ぶつけたりすることができなかった。したらいけないと思っていた。心のどこかで、諦めていたんだろうな]
【今のあなたの姿からは、想像もつきませんね】
[そうだろ? いくつになっても、人は変われるってことだよ]
アルテは、どこか得意そうな調子で、そう返しました。
[母親は、俺の星じゃ、結構名前が売れててさ。役者っていうの? 映画とか、舞台とか、そういう芸能系の仕事をメインにしてる。ジャンルは違うけど、今の俺も似たような所にいるからさ。気持ちはわかるんだよな。父親がいなくなって、幼い俺と二人きりで残されて。未来に対するプレッシャーとか、周囲からの同情とか。もともとそんなに強くはないし、演じるのが生きがいみたいな人だから、自分の心を保つのに必死だったんだと思う。幸い、お金に困ることはなかったし、そういう苦労をしなくて済んだことには感謝してるよ]
【アルテさんは、お母さまのことを尊敬しておられるのですね】
そう言われて、アルテは少しだけ、考え込むように間をおいてから答えました。
[……尊敬、か。そんなこと、今まで言われたことなかったな。あんたにはそう聞こえたのか?]
【はい】
[確かに、人間として、自分と同じ「表現者」として見るなら、そうかもしれない。親としては未熟だったし、決して理想的とは呼べなかったとしても。俺が本当に望んでいた世界を、与えてくれることがなかったとしても。母親なりに、その時の自分を、精いっぱい生きてただけなんだって。……そう思えるようになったのは、つい最近のことだけどね]
スクリーンの中の少年は、相変わらず、部屋の隅から動くことなく、静かに本を読み続けています。
未来の自分のことなんて知る由もないまま、ただ流れていく時間の中に、身をゆだねています。
【あの窓の向こう側に行く前に。まず、私たちの意識を、この空間に合わせて実体化させる必要があります。メイン画面の左端にある、人型のアイコンを押してみて下さい】
[えーと……これか?]
指示された通りに、ボタンを押します。
すると、軽い浮遊感とともに、突然、周囲の景色が淡い光の中に包まれました。
一瞬ののち、目を開けると、自分の足元にしっかりとした地面の感触があることに気がつきました。
画面越しのように感じていた先ほどまでとは違い、まるで自分が、本当にその場所にいるかのような現実感をともなっています。
ふと気配を感じて視線を移すと、すぐ近くに、品の良い格好をした、30代くらいの男性の姿がありました。
「もしかして、クレイスか?」
アルテが尋ねると、男性は、「はい」と答えます。
「へー。あんたって、そういう見た目だったのか。違和感が無さすぎて、一瞬、俺の頭の中から出てきたのかと思った」
「別の外見のほうがお好みでしたら、女性や動物の姿をとることもできますが」
「いや、別にいいよ。なんか話しづらいし……。それに、その姿がデフォルトなんだろ?」
「ええ。ですが私は、このシステムを案内するために生み出されたAIですから。特定の外見や性別、年齢といったものは持ち合わせておりません。ただ、ここを訪れる方たちの中には、いろいろな価値観や、経験を持っていらっしゃる方が多くおられます。なので、不安や、警戒心を少しでも軽くできるよう、ご要望があれば、応じることにしているんです」
クレイスがAIであるという可能性は、アルテの中でも、何となく予想していたことでした。なので、そこまで大きな驚きはありませんでした。
けれども、今目の前にいる相手が、別の誰かによって作られた存在だとは、どうしても思えませんでした。
ちなみに、と前置きしてから、クレイスは言いました。
「この外見は、私をデザインしてくれた博士の、若いころの姿がモデルとなっているんです。私はとても気に入っていますが、実際の姿よりも、ほんの少しだけ美化されているというのは、ここだけの話です」
そう話すクレイスの表情はどこか楽しそうで、こうしていると、自分と何一つ変わらないように思えてくるのが不思議でした。
少年との対面は、アルテが想像していたよりも、ずっとスムーズでした。
仮想空間上のこととはいえ、過去の自分に干渉する行為です。面倒な手続きやら、禁止事項なんかが存在するかもしれないと身構えていました。
しかし、クレイスによると、特に必要はないという話でした。
「あの少年は確かに、意識の上では、現在のあなたと深い繋がりがあります。『過去のあなた』と呼んでも差し支えがないくらいに。ですが、時空というのは無限に存在しています。あなたが実際に経験してきたことも、しなかったことも。今この瞬間、無数の宇宙の中で生まれ続けているんです」
「えーと……つまり、パラレルなんとかってやつか?」
「完全に切り離されているわけではないので、厳密には、少し異なりますが……しかし、そう考えていただいても構いません。あなたが、あの少年と関わることによって、新しい道が作られ、未来が生まれます。しかし、それによって、あなた自身の過去や現在が、直接的に書き換わるわけではありません。間接的な変化が生まれることはあったとしても」
クレイスの話を完全に理解したわけではありませんでしたが、少なくとも、今の自分に、何か悪い影響があるということはなさそうでした。
「要は、好きにしていいってことだな?」
「ええ。存分に」
アルテは教えられた通り、スクリーンの表面に手をかざしました。
すると、そこから白い光が生まれ、やがて水面のように小さな波紋が広がっていきます。次の瞬間、アルテの体は窓の向こう側へと吸い込まれ、気づくと、見慣れたあの部屋の中に立っていました。
先ほどまでここにいた少年の姿は、今はありません。
突然現れて、驚かせてしまわないよう、少年が部屋を出たのを確認したあと、こちら側にやって来たからです。
時計の針は、ちょうど15時の辺りを指し示していました。
この時間帯を見計らったのは、決まったタイミングで、キッチンに食べ物を取りに行くことを知っていたからでした。
しばらくして、お菓子の入った袋を抱えて戻ってきた少年は、部屋の中に人がいるのに気づいて、はっとしたように固まりました。
「よぉ。邪魔して悪いが、入らせてもらってるぜ」
ソファに座ってくつろぐアルテの手には、少年が先ほどまで眺めていた絵本が握られています。
「しっかし、懐かしいなあ、これ。昔好きで、よく読んでたやつ。確かシリーズもので、特に気に入ってた3巻だけ、表紙がボロボロになるまで読み込んだんだよな。今思えば、よく飽きなかったな~と思うよ」
楽しそうに語るアルテとは対照的に、少年は、おそるおそるといった様子で尋ねました。
「……誰? 新しいお手伝いの人?」
「そんなもんかな。家事は苦手だけど……まぁ、座れよ」
うながされて、少年は仕方なく、ソファの端っこのほうに腰を下ろします。
アルテは、少年がお菓子を置けるように、テーブル上に広げていた本をどかしてやりました。
「どう説明したらいいだろうな。俺が今、ここにいるのはな、お前の存在を許しに来たからだ。……つっても、わかるわけないか。つまり、だ。お前は今、この家にいて、居場所がないと思ってるかもしれない。でも、俺たちの住む、この宇宙は広い。お前の世界も、これからいくらだって広げていける。居場所はちゃんとある。それを伝えたくて、ここに来たんだ」
少年は、怪訝そうにアルテのことを見ています。
「その顔は、信じてないって顔だな。まぁ、いいや。これから時間あるか? それ、食い終わってからでいいからさ。お前の気に入りそうな所に連れてってやるよ」
「えっ」
アルテの言葉に、少年は戸惑ったようにつぶやきました。
「でも……知らない人には、ついてっちゃ駄目だって、マーシャが」
マーシャというのは、この家によく通っていた家政婦の名前です。
一人で過ごすことの多かったアルテのことを、人一倍、気にかけてくれていました。
「心配するな。マーシャは俺のことを知ってるし、俺もマーシャのことを知ってる。それに、俺とお前は、今こうしてソファに座って、同じ時間を共有してるだろ? つまり、もうとっくに知り合いってことだ」
不安そうにしていた少年を説き伏せて、連れてきたのは、家からそう遠くない場所にある音楽専門店でした。
8階建ての大型ビルで、懐かしのレトロミュージックから、最新のヒットチャートまで。
ありとあらゆる、宇宙中の音楽データが集められています。
各階ごとに様々なフロアに分かれており、中には、子供が楽しめるように工夫されたコーナーもありました。
ずらりと並んだディスクの数々や、モニターから流れてくる、色とりどりの音や映像たち。
それらに圧倒されたのか、少年は言葉を失った様子で辺りを見渡しました。
初めのうちは、ただ遠目に眺めているだけでしたが、次第に慣れてきたのでしょう。
目の前のラインナップを観察する余裕が生まれてきます。
その中に、大好きな絵本シリーズのテーマソングを発見し、少年の顔がぱっと明るくなりました。
アルテに教わりながら視聴するその目の奥は、キラキラと輝いていました。
「いいだろ、この店。俺が初めて入ったのは、今のお前より10個くらい上のころだったけど、もっと早くに出会えてたらって、悔しかったんだよな。まだ早いかと思ったけど、楽しめてるみたいで良かったよ」
二人はしばらくの間、自分の好きなジャンルの曲を、思い思いに楽しみました。
少年はその間に、いくつか新しいお気に入りを見つけたらしく、サビのフレーズを小さく口ずさんでは、満足そうにしていました。
次に向かったのは、同じ建物の3階にあるフロアでした。
ここでは色々な楽器が展示されており、自由に選んで、試し弾きすることができます。
その中の一つを手に取り、アルテが軽く弾いてみせます。
「すごい……」
少年は、感嘆したようにつぶやきました。
巧みに動く指先から、軽やかな旋律が生まれるのを、尊敬のまなざしで見つめます。
「お前も、弾いてみろ」
そう言われて手渡されたのは、アルテが手にしているものと同じ楽器でした。
簡単な手順を教わりながら、見よう見まねで何とか弾こうとします。
しかし、曲を奏でているとはとても言えず、ただ音を出すだけで精一杯でした。
眉間にしわを寄せ、躍起になっている姿を見て、アルテはおかしそうに笑いました。
「初めは誰だって、そんなもんだ。ちょっとずつ上達していく過程が面白いんだよ」
二人はこの後も、色々なフロアを見て回りました。
少年はそのたびに、驚いたり、感心したり、笑顔になったりしました。
見るもの全てが新鮮で、興味を引くものばかりです。
隣でわかりやすく解説してくれるアルテの話も面白く、気づけば、あっという間に時間が経っていました。
着いた頃は、明るかった外の景色も、いつのまにか深いオレンジ色に照らされています。
家へと向かう帰り道、アルテが言いました。
「普段と違う世界に触れてみるのも、たまには悪くないだろ」
少年は、こくりと頷いたあと、小さく「楽しかった」と付け加えました。
アルテは、少年の頭にポンと軽く手を乗せました。
「そう思った自分の感覚を、大事にしろよ。それは、お前にしか出来ないことなんだから」
そして、視線を前に戻しながら、こう続けます。
「そうやって「何か」を感じられるから、自分の中の喜びにも気づけるんだ。だから、これ以上、無理して気持ちを抑えこもうとするな。辛いときは、辛いって言っていいんだ。大人をまねして、物わかりのいい振りなんてしなくていいんだよ。たとえ、かっこ悪くても。弱くて、情けなく感じたとしても。そのままのお前がいいってやつに、きっと出会える。その時まで、自分でいることを諦めるなよ」
アルテの言葉を、少年がどれだけ理解したのかはわかりません。
ただ、手元に落ちてきたものを拾い集めるかのように、静かに耳を傾けていました。
二人で過ごした短い時間も、いよいよ終わりが近づいていました。
家の入り口で足を止めたアルテに、何かを感じ取ったのか、少年が尋ねました。
「もう、会えないの?」
「今日のことを、お前が忘れていなければ。そのうち、また会えるさ」
「僕、その時までに練習しておく。もっと、ちゃんと鳴らせるように。そしたら、また遊びにくる?」
「ああ。また一緒に弾けるのを、楽しみにしてるよ。俺の見る限り、お前には見込みがある。だから、俺のことなんて、あっという間に追い抜いちまうかもな」
アルテはそう言って、いたずらっぽく笑いました。
「じゃあな。幸せになれよ」
「うん」
二人は、最後に固い握手を交わしました。
少年が家に入ったのを見届けると、アルテの体が白い光に包まれました。
それは、こちら側にやってきた時と、同じ色をしていました。
光がおさまり目を開けると、そこは、窓に似た入り口のある、あの空間でした。
「お帰りなさい」
声をかけられて振り返った先には、クレイスが立っていました。
「伝えたかったことは、伝えられましたか?」
「おかげさまで。あんたには感謝してるよ」
「私はただ、入り口までの道をご案内しただけですから。実際に、あの世界と繋がるためには、あなたの意志が必要でした」
「正直なところ、ここに来るまでは、半信半疑な部分もあってさ。今さら、過去と繋がってなんになるんだって。でも、部屋の隅にしか居場所を見いだせなかった、あの頃の自分を見たとき、思ったんだ。ああ、こいつは確かに俺自身で、だからこそ今の俺がある。こいつの弱さを理解して、居場所を作ってやれるのは、俺しかいないんだって。あいつからしたら、余計なお節介だったかもしれないけどな」
「そんなことはありませんよ。こちらをご覧ください。ここにあるものが何だか分かりますか?」
クレイスが指し示したほうを見ると、そこにはいつのまにか、小さな丸いテーブルが出現していました。上には、綺麗な色をした四角い箱が乗せられています。
箱を手に取って開けてみると、中から出てきたのは、何かのデータが入ったディスクのようなものでした。
「音楽……?」
「ご名答。あなたがこちらへ戻ってきたのと同時に、届けられたものです。聞いてみますか?」
空間上に現れた半透明の機器にディスクを差し込むと、軽快なテンポの演奏が流れ出します。聞いたことのない曲でしたが、その後に聞こえてきた歌声を耳にした瞬間、はっとしました。
それは、まぎれもなく自分の声だったからです。
正確には、今のアルテよりも少し若い、10代後半くらいの声に聞こえました。
「彼はあの後、あなたとの約束を守り、数年かけて楽器の練習に励みました。その過程で、信頼できる仲間と出会い、居心地のいい世界を見つけられたようです。ちょうど、今のあなたと同じような流れですね。あなたがグループを結成したのは20代に入ってからなので、随分と早まりましたが」
クレイスはその言葉のあとに、こう続けました。
「この曲は、19歳になった彼が作った、『未来の自分への感謝の気持ち』を表現した歌だそうですよ」
そう言われて、あらためて歌詞を聞き返してみます。
すると、二人で過ごしたあの時間のことや、そこで出会った音楽のこと。
この日を境に、見える景色が変わったこと、などが、アルテだからこそ分かる表現で綴られていました。
そこに、つたなかったあの頃の面影はありません。
演奏や、曲の完成度から見ても、今のアルテに十分見劣りしないくらいの実力を感じさせるものでした。
「……あいつ、俺より上手く弾けるようになりやがって」
そう呟いたアルテの表情は、悔しげながら、どこか嬉しそうでもありました。
その時、ふとアルテの頭にひらめきが降りてきました。
「そうだ。次の新曲は、『過去の自分へのアンサーソング』なんてのは、どうだ?」
「素晴らしいアイデアだと思います。出来上がったら、ぜひ聞かせてください。私が責任をもって、彼の元までお送りしましょう」
そう言って笑う、二人の間に流れる空気は、心地よいリズムに包まれていました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
