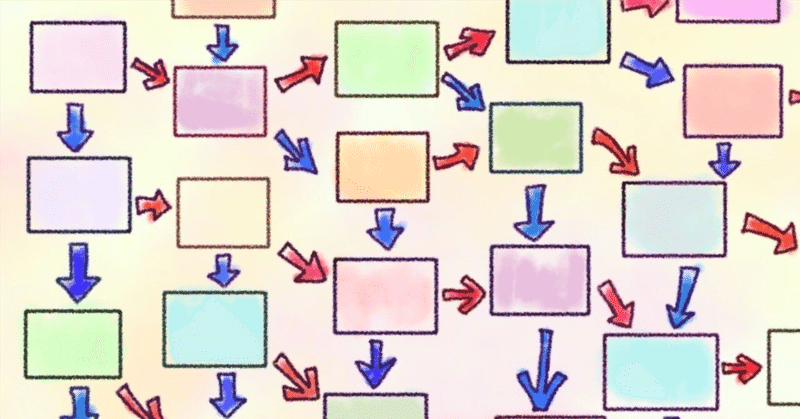
自立じゃなくて自己決定。
子どもの権利条約には、子どもの意見表明権としっかり書いてあり、それを最大限尊重することとされています。それを実行すると子どもと大人の信頼関係のパイプは太くなり、子どもの安心感は増していきます。人間(子ども)には安心感が生活の基盤です。安心なくして何も成り立たない。不安を感じるお子さんには特に安心感が必要ですね。
教育機会確保には、『安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られようにすること』規定されており、文科省の基本指針や、現在の学習指導要領にも不登校児童への配慮の項に明記されております。しっかり切り取って手帳とかスマホに貼っておきましょう。
いつでも示せるように。
(栃木県で長年不登校の活動をされてる方)
『安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られようにすること』
かぁ・・・
娘、久しぶりに学校に行ってみることで、学校の違和感を教えてくれるんだけど、どうしてあげることもできない母です。(多分そこまで娘は求めてはないかもしれないけど)
でも、変な連鎖があることは確か。
だから、なんか、悔しいんだよなぁ。
学校に行って友だちと会いたいのに、それができない娘。
学校に行くも行かないも自己決定ではあるけれど・・・
ちなみに人権って「自己決定」のひとつかなーと、最近つくづく思います。
だけど
学校が安心して行ける環境ならばいいけど・・・
娘の話を聴いていると、安心して行けないんだろうな・・・
行きたいけど、行けない・・・
これいかに。
・・・
教育機会確保法には
「社会的自立」
という言葉があって、無理に学校に行かなくてもいいけど、社会的自立が大事だよねってことなんですが
私が最近思うのは「社会的自立」という言い回しより
「質の高い自己決定」
がしっくりくるなと思っています。
一歩ずつ、小さなことでも、質の高い自己決定をと思います。
ただ、
シンプルに学校に行かない、というのは自己決定だけど、
学校に行きたいけど行けないってのは、自己決定でもなんでもない。
なのに「無理に学校に行かなくてもいいけど、社会的自立が大事」と言われてしまうのは、学校に行きたくても行けない多くの子どもたちにとって本当に酷なことです。
大人たち全然わかってねーな、って子どもは思うだろう。
学校に行きたいけど行けない時の次の選択肢がない。
大人たちはこぞって第三の居場所を、とやっているけど(必要は必要なんだけど)、本質はそこじゃない。
子どもたちが質の高い自己決定ができたら、可能性だらけ☆彡
イノベーション起こりまくりじゃないかと☆彡
そもそも大人たちもね、自己決定できてないからねー
あと社会的自立って言われても、私それも怪しいし。
とりあえず
大人子ども関係なく
レッツ自己決定☆彡
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
