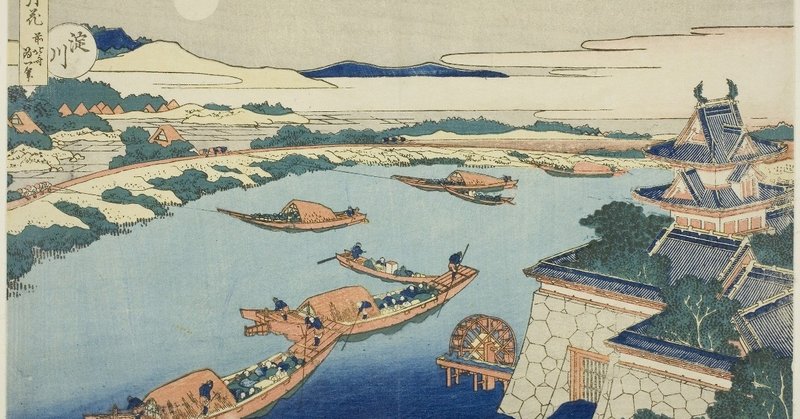
2019/03/18 NewsPicksオリジナル記事感想まとめ
このBlogでは、ニュース配信アプリ「NewsPicks」で読めるオリジナル記事について、個人の感想を綴っています。(1日1回)
◎注意事項
・あくまで「個人的な意見、感想」です
・記事の詳しい内容は省く方向で、その場の気分で書いてます
・興味がなかったり、時間が無かったりで読まない記事もあります
・問題があれば削除します
本日の内容はこちら
1、【新】「24時間営業」は必要か?みんなで考えるコンビニの未来
01の話を読んだ限り、セブン側が個人の裁量をもう少し認めればそれで収まった話なのでは?と感じてしまった。
しかし短い期間で方針を何度も変えたことで、会社対個人で収まる話では無くなってしまった。
これまでもちょいちょいこの不公平な話はニュースになっていたが、とうとう一線を越えてしまったのだろう。
自分の意見を書くなら、地域によって24時間の営業にしなくてもいいだろうし、場所によってはむしろ朝や昼の数時間を閉店するお店があってもいいと思う。
何事も運用のしやすさが長続きのコツではないだろうか?
ーーーーー
「セブンイレブンが常に業界の先駆者でいられるのは、小さな変化さえも見逃すことなく対応しつつ、組織も、社員たち自身も、柔軟に変わっているためです」(「変わる力」鈴木敏文 著より)
ーそして、コンビニの未来についてこう結ぶ。
「日本社会にはこれからもさまざまな変化が訪れることでしょう。それにいち早く気づき、対応策を見いだせるかどうかで、ビジネスの成否がわかれます。つまり、変化対応力がなければ生き残れない時代がやってくるのです」(同)
この言葉が有効に機能していたのは、数を増やし規模を拡大させる時期のことだけだったのか?
これからは、逆に今まで培ってきたものが無駄とされる時代になるかもしれない。(何もコンビニ業界だけに言えた話ではないだろうが)
同じ山道を登り続けようとすることを一旦諦め、新しい山道を探すタイミングにあると思える。
上記の言葉は、今後の時代の変化に対応する上でその真価が問われていると感じた。
2、役職・部署ゼロ。超フラットな組織改革で会社が復活した理由
ISAOという会社は初めて聞いたが、管理職0、階層0、チーム力∞(無限大)のバリフラットモデルによって組織管理をしているとのこと。
運営のやり方は、ティール組織のセルフマネジメントとミッション型経営に近いと思う。
ただこれってやり方を間違えれば現場はしっちゃかめっちゃかになり兼ねないので、協調性と「良い意味」でのスタンドプレーを両立させることのできる質の高いメンバーが必要になると考えている。
それで上手く行っているのなら良い職場なのだろう、羨ましい話。
※※※
上手く行かせたコツとして、組織のメンバーの意識を日々どう保つ(又は高める)かが肝心だと考えるが、情報をオープンにした上で機会を平等に持たせたのだろう。
だから不満が溜まっても早い内にガス抜きさせることができるし、同時にチャレンジに対する意欲も湧かせやすい環境を作っていったのではないかと思う。
こういう働き方は他の場所でもどんどん増えて欲しい。
それが全体の生きやすさに繋がるのではないかと考えている。
3、【驚異】年収5倍増を実現。「転職プログラム」の中身
「さしあたりどこかに就職先を見つければいいというだけのアプローチは、短絡的であり、間違っているとさえ、僕は思うのです」
自分が失業保険を受け取りにハローワークへ出向き、そこで感じた疑問はまさにこれであった。
人間が目的を持ち、行動を始めるにはいくつかの準備が整う必要があると感じている。
身体的には長時間働くための体力が必要だし、精神的には未来に希望を持てるだけの余裕を感じられていることが、物事を継続する上で大事だろう。
ハローワークに行った時点で本人がその状態を持ち合わせているのなら問題は無い。
しかし傷を負い、疲れた状態で訪れる人も多くいるだろう。
日々活力を持って生きていけるための継続力とは、手段を提示する以前に、本人が何を願っているのか本人自身に自覚させることでスタートするのではないかと感じている。
ーーーーー
パースートの債券システムは2016年にスタートした。プログラムの卒業生が年収6万ドル以上の仕事を得た場合、3年間にわたって収入の12%を出資者に還元するという契約だ。
インヘレントのトニー・デイビスCEOによると、今のところパースートの卒業生の就職成功率は予想を上回っており、「債券」の利回りは6.6%になるという。
「次世代の受講者がテック業界に進むのに貢献できることを嬉しく思います。払った分を引いても、昔よりずっと多く稼いでいるんですから」
年収6万ドル(=現在約700万)の内12%だから「84万円」となり、それを3年間払う(→合計252万)と考えると、それでも割に合うと考える人はどんどん応募するだろう。
本来は大学の奨学金もこのように運用されることが目的だったのだろうね。(今じゃ半分借金になっているけど)
社会的にも効果が出ると証明されるようなら、他の国でも同じような行いは増えていくと考えられる。
むしろ自分も、独立で苦しんだ若い時に利用できるならしてみたかったと感じさせられた。
何らかのアクションをいただけると、一人で記事を書いてるわけではないのだと感じられ、嬉しくて小躍りしちゃいます。
