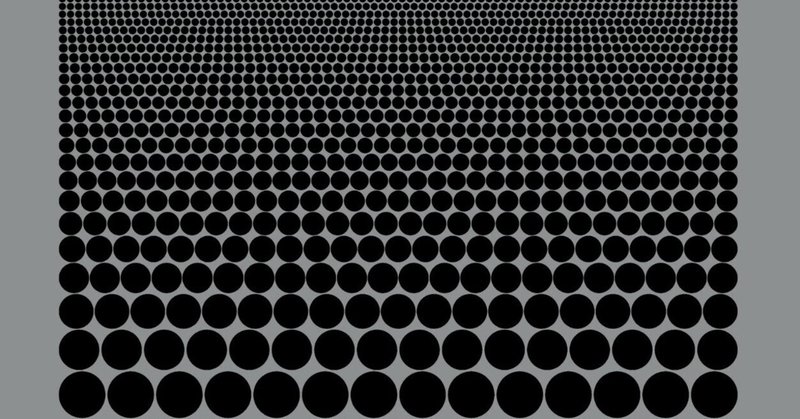
[後編] Boris Groys(ボリス・グロイス)『Philosophy of Care(ケアの哲学)』
近日邦訳が発行されるボリス・グロイスのPhilosophy of Careについて、英語版を読んだ際の読書メモをまとめて公開しておきます。12章構成、後編は7〜12章までをまとめました。
7 ケアテイカーとしての民衆
前半(1~6章)までの哲学者たちは、グロイスによれば世界の全体性、宇宙、存在に直接、無媒介にアクセスすることを求めていた。もし「私」が世界全体を支配する権力や力に直接、無媒介にアクセスすることができれば、私はケアの制度への依存をやめ、セルフケアを実践することができるのだ。「制度」というのは結局、宇宙のほんの一部にすぎず、宇宙そのものにアクセスするような態度をとることによって、例えば医療といった制度に対するメタ的な立場をとることができ、患者であるという非知識の立場から知識を判断することができるのだ。
ケアという制度の枠組みを超えることは、ケアのサイクルの「目的」である仕事から解放され、真に健康になれるという期待を抱かせる。ケア機関の中で生活するということは、そのために働くということでもある。それは疲れをもたらすことである。だからこそ、このメタ的な立場というものの探求は(本当の意味での)良い健康の探求と密接に関係している。仕事の切迫感は身体に悪い影響をもたらす。なので、逆説的にプラトン的な理性の存在論が私たちの健康に良いのだと、グロイスは述べている(ここで問題はプラトン主義や宗教は身体やその欲求を軽んじているのではないかということである。しかしながら、キリスト教徒や仏教徒は比較的健康であろうと、グロイスは考える)。
真理への観照が創造的仕事への動員へ取って代わるとき、状況は変化する。個人は制度的なルールを破り、根本的に新しい何かを創造することになる。ヘーゲルの弁証法的論理の枠組みでは、新しいものは古いものの否定の副次的効果として現れ、それ自体が目標になることはない。したがって、新しいものの生産は、否定の否定、すなわち歴史の終わりとともに終わらなければならなかった。
ニーチェは権力への意志を進歩の永遠の原動力とし、また権力への意志は否定ではなくむしろ差異であり、人間存在の新しい可能性を生み出すとした。この意志が創造しようとしている未来という観点から既知の歴史を判断することができるようになる。
しかし、権力への意志によって動員された結果、私たちの身体はどうなるのだろうか? 超人は「大いなる健康」を持っているかもしれないが、一般人としての私たちにとって未来は創造的な冒険ではなく、老いの病である。若々しい生命力あふれる肯定的な言説は、ある世代にインスピレーションを与えるが、次の世代に見捨てられ、忘れ去られてしまう。技術は刷新され、私たちはその技術の条件にライフスタイルを適合させているにすぎない。変化は個人の内部で生じるのではなく、技術的発展によって個人に課される。
こうした技術は仕事によって生み出されており、それを作り出し世界を変容させているのは主人ではなく奴隷のほうである。主人たちは、奴隷が自分たちのために築いた世界、つまり産業の世界によって完全に幽閉される。ニーチェの権力への意志は奴隷による精神と道徳の支配に対する主人たちの反乱の舞台を作り出すのである。主人はもはや現在を支配することはできない。よって、権力への意志は未来へと移行し、何千年も残る象徴的な身体を創造することを目指すのだ。
「大いなる健康」の原点は、太陽、古代魔法、恍惚の力などの付加的なエネルギーであり、こうした余剰エネルギーを必要とするからこそ「超人」が必要なのである。しかし、未来は国家機関や大企業による支配に満ちており、超人でもそれを支配することはできない。
バタイユとカイヨワはは未来の冒険を説くのではなく、歴史的変化を乗り越えて現代文化の中に存在し続ける古代の文化形成の名残と痕跡を賞賛している。カイヨワにとって祭りは、創造的エネルギーの爆発を模倣し、再現しているに過ぎない。主人公たちは死んだ祖先の仮面を持ち、模倣の模倣、再演の再演が繰り返されるからこそ、これらの儀式は参加者を活性化させるのだ。ここで、真の健康への探求は、生命力への信仰から、(未来ではなく)現在における過去の生存への関心へ移行する。そしてそのような生存を可能にするのは近代的な医療制度への関心だ。
カイヨワはゲーム理論を発展させ、競争・ゲームといった見世物についてドゥボールは受動的な観客を生むとし批判した。しかしこの批判は、私たちの現実の生活それ自体が競争によって搾取されている現実を見落としており、スペクタクルは私たちの現実の競争に関連して形而上学的な立場、安らぎを与えるのも事実である。
聖なるものと俗なるものの境界は、見世物と大衆の境界でもある。現代、スペクタクルを上演するのはケア施設なのである。ショーに参加するには超人のような努力は必要ない。古代の祝祭の観客は神であったが、現代は大衆に取って代わった。そして、ショーに登場する役者の身体を動員するのは他者の視線=大衆の視線である。
いまや名声、お金のためにあらゆる人が競争している。競争は、哲学者のための学問の場だけでなく、芸術やスポーツの場でも繰り広げられている。子ジェーヴは、成功は専門家ではなく一般の人々の認知に依存していると指摘している。真実と認められるためには大衆に受け入れられなければならない。
芸術や詩などあらゆる「非合理的な」欲望は生命力の現れであり、人間の知識や真善美の観念とは無縁で、生命力、力への意志は、善悪を超えたものだ。創造の力は永遠かつ普遍的であり、宇宙そのものと同じくらい永遠かつ普遍的なものである。しかし、創造性のイデオロギーはブルジョワ社会に受け入れられ、やがて消費社会にも受け入れられていった。なぜなら、合理的な観点からすれば、消費は非生産的なエネルギーの浪費だからである。だから、人間の身体の欲求、衝動、欲望を満たすものとして、容易に正当化することができる。
創造性のイデオロギーは芸術や文化を正当化するが、同時に「破壊」も正当化する。イデオロギーにとって必要なのは作品ではなく「創造性」であり、その芸術家が死ねば芸術活動のための別の体現を見出すだろう。欲求、衝動、欲望は動物や植物、あるいは無機物にも働くので、人類全体は無関係になる(重力を見よ!)。「誰が」というのは実は関係ないことなのだ。
そして本書の序盤で参照された洞窟の例えが再び登場する。洞窟の入り口で留まる我々は、永遠の光を観照する立場から、芸術批評家の立場へと移行する。美術評論家は、必ずしも壁を見ているわけではないが、洞窟の中で起こるすべてのことを見ることができる一般大衆に加わる。大衆が存続してこそ、見世物も存続するのだ。大衆に加わることは、ヘーゲルやニーチェが実践していることでもある。書物を遺すということは、象徴的な身体を手に入れると同時に、未来の名声を期待することなのである。コジェーヴが正しく予言したように、文化や政治のスペクタクルを刺激するのは、大衆に認められたいという欲求であり、それを世話する(care-take)のは大衆なのだ。
8 民衆とは誰か?
8章ではワーグナーが登場する。前章でスペクタクルと大衆の関係について掘り下げたところでワーグナー『未来の芸術作品』における見世物と民衆(Volk)の関係の問題提起が参照される。よると、民衆(Volk)とは集合的な欲求を感じる人間の縮図だという。ワーグナーは流行を批判し、当時の流行に支配された芸術に対して、偽りの共産主義でなく真の共産主義を発足させる「普遍的芸術作品」という独自のプロジェクトを提唱している。
ワーグナーはブルジョワではなく貧しい人々や虐げられた人々だけを真の民衆であるとした。ワーグナーの観客は、少なくとも革命が起こるまでは、想像上の観客であり続けなければならない。ワーグナーは、未来の芸術は、集団的な共同体芸術であると信じていた。そして、芸術家もまた、来るべき共同体の一員であると信じていた。そして、彼は死によってのみ、気まぐれや流行を拒否できると主張したのである。
スペクタクルとしての普遍的な芸術作品は、自由な芸術家たちによって生み出されるべきであり、死を演じる役者は刷新され続け、死は生者のためのスペクタクルになる。ヒーローは去るが、観客は劇場に残る。ワーグナーは観客をあらゆるスペクタクルの決定的な要因とし、観客こそがスペクタクルの、芸術の真の担い手なのだ。文化活動の真の原動力は、作家の健康やエネルギーではなく、観客の健康であると想定されるのである。
ワーグナーは人類が国家によって分裂していると述べているが、自分の普遍的な芸術作品を、全人類を統合するための方法であると宣言した。そして、ワーグナーは古いゲルマン神話への関心を強め(マルクスがそうしていたように)ていき、共同体は、貧民の共同体ではなく、民族の共同体として理解されるようになった。
ニーチェは、ワーグナーが革命家であることを喚起させつつも、こうしたゲルマン神話への関心ががワーグナー主義の堕落だと主張する。ワーグナーの観客は深遠なもの、圧倒的なものを求める」という、当時の退廃したヨーロッパブルジョアジーの典型的な代表の集まりだった。そうして、ワーグナーは、退廃的で、病的で、虚偽のスペクタクル、つまり大衆が彼に期待する芸術を生み出すようになったのである。
ワーグナーのケースのように、退廃的な聴衆は創造者を「退廃」に感染させ、退廃的な芸術を生み出させるのだ。これは、偉大な創作者であっても、ケアの社会を超えることはできないことを示している。彼が神聖な神話的祝祭を模倣したとしても、彼はケアの制度(ex. 近代劇場)の枠内にとどまり生政治的国家に家畜化された「退廃的」大衆に直面するのだ。
9 現存在としてのケア
タイトルからもわかるように、9章に登場するのはハイデガーである。彼の主著『存在と時間』では、哲学史上初めてケアという概念が中心的な位置を占めることとなった。グロイスは自己主張として理解されるセルフケアと、近代的な公的ケアの制度との間の対立が、ハイデガーの哲学的言説の中心にあると、ポストコロナ時代の哲学的解釈を加えている。師であるフッサールに従い、人間を動物やほかのものと同列に扱うことを否定している。人間は、動物や植物のような他の生物と同様に、生命的な欲求や衝動によって動かされる生物ではないのである。ハイデガーは人間を「世界-内-存在」としての「現存在(存在者)」として定義したのは有名であろう。
ここで、世界の中にいるということは「客体」としての世界に対して、「主体」としての現存在を考えることが不可能であることを意味している。世界は現存在と相関的であり、互いに切り離すことはできないのだ。現存在は、未来に向けて投企されており、ということは、私たちはさらに存在し続けることが前提にされている。だからこそ、私たちの存在に関心を持たなければならない。私たちの世界との関係は、ケア(sorge)の性格を持っており、実際、セルフケアの性格も持っている。セルフケアは、現存在の基本的な存在様式なのだ。現存在は自分自身を気にかけるからこそ存在するのであり、自分自身を気にかけるという様式で存在する。ここで、ケアは人間存在の中心的な存在論的様式となる。
ハイデガーによるケアは、現存在の世界に対するケアとして理解されている。そして、セルフケアは、世界における現存在の特定の存在様式のために、また、他者によって支配される世界のモノになることに反対する戦いを前提としている。世界はもともと現存在に、その特定の存在様式に属している。現存在は世界の中にいますが、世界を支配しているわけではない。現存在が技術的な手段によってその世界を支配しようとするときが、危険なのだ。
ハイデガーのエッセイ「技術への問い」の中で、ライン川の流れによる水力発電所が登場する。ヘルダーリンの賛美歌はライン川をドイツ世界の一部として讃えるのに対し、発電所はライン川を道具として、むしろ資源として使っている。こうした技術の発展の中で、現存在は自らを失い、技術的な処理のための原料として扱われる危険性に直面するようになるのだ。ハイデガーがそのような可能性を示すために選んだ例は、まさに医療制度である。医療行為は真の存在様式を殺し、彼らを医療産業のための原料に変えてしまうというのだ。
換言すると、現存在はもはやセルフケアというモードでは存在せず、したがってその本来の存在論的地位を失っている。現代の現存在は、テクノロジーによって幽閉され、コントロールされている。でも、ハイデガーには希望があった。それは真実を私たちが見つめ、真摯に存在をあらわにすることである。しかし、それが問題は私たちが存在のさなかにあるということを忘却する過程へと導いてしまうことであった。
存在の隠蔽解除は芸術を通して起こる。ハイデガーは「芸術作品の根源」で芸術作品が文明によって単なるモノとして扱われていると述べる。この論文の中でハイデガーは農夫の靴を例に出しているが、靴は、ゴッホとハイデガーもまた参加していた農民の生活の世界への視線を開くものであった。芸術作品は真実の作品である。真実とは、芸術家が生きている世界の隠蔽されていない姿なのだ。芸術家によって切り開かれた世界は、作品の物質性、物性によって、つまり作品が作られた大地へと還元されることによって閉ざされる。
現存在が死ぬと、ケアの世界は消滅し、物、死体だけが残り、土に吸収される。ここで、現存在と芸術作品の間のアナロジーが明らかになる。美術館では、作品ではなく、その死体を見ることになるのだ。芸術作品は、この作品の真の観衆となる人々が生存している場合にのみ、存続する。作品を保存するということは、その作品の生き方の保存であり、その意味で作品の創造と保存は一体なのだ。そして、作品は民衆に衝動、エネルギーの量塊を与えるのである。ハイデガーがニーチェの権力への意志を「形而上学的」なものとして否定したとしても、彼は「創造的な仕事」をエネルギー(個人ではなく、存在から与えられるエネルギー)の余剰によって生み出されるものと理解している。それゆえ、芸術はその本質において起源であり、真実が存在し歴史的になるための独特な方法なのだ。
10 日雇い清掃人女性のまなざしの下で
10章では日雇い清掃人女性(Charwoman:日本で言う家政婦のようなものかもしれないが、①日雇いの、②掃除婦という日本では聞き慣れない職業のようだ)が登場する。グロイスによると彼女たちは現実の埃を掃除する役目を負う世界から離れ、物質としての美術品の技術的ケア、メンテナンス、修復といったシステムの下で働くケアの主体なのだ。ゴッホは畑を耕す農婦の絵を描いたが、こうした絵はケアの主体にとっては地球のかけらのひとつにすぎない。農婦はゴッホの絵の中で畑を耕すが、日雇い清掃人女性はケアの実践においてゴッホの絵を耕す。
しかし、彼女らの仕事はケアのシステムの一部であり、彼女はケアの実践に関する決定において自律的な存在ではない。しかし、それは現存在を失ったわけではない。彼女たちは自分の責任の領域からケアの実践を行っているのだ(それに対して、ゴッホの絵の「中」の農民の女性は市民であり、自分の製品を売るために市場に依存しているといえる)。芸術作品にかかわるケアの様式の中で彼女は彼女の現存在を実践している。このケアの様式は「美術館」という制度に関わるものである。
美術館は伝統を存続させることを目的とし、世界の変化に合わせてケアの様式も変化させる。(過去の伝統を保存した)作品を観ることは美術館という制度のために作られているように見え、それは制度に寄り添った裏切りのように見えるかもしれないが、そうではない。伝統を大切にするということは、それを継承すること、つまり新しい作品を生み出すことになる、とグロイスは述べる。またこのように問う。ある芸術作品が芸術作品として、そして、ケアの対象に値する芸術の伝統を継承するように認められるための最低限の条件とは何なのか、と。
その答えは前衛芸術にある。これは日雇い清掃人女性の世界の啓示であったという。どういうことか。前衛芸術は創造性の現れであり、生命力あふれる創造力の爆発であったという見方が広まっている。しかし、実際には、この芸術は、ケアに対する反省と拡張の結果であった。アルベール・グライツとジャン・メッツィンガーはキュビズムについての本で絵画のポータブル性について言及し、さらに絵画のカタログ番号や額縁の底に書かれたタイトルの重要性を肯定している。つまり、絵画は積極的にそれが帰属すべき完了的システム(ex. 美術館)に流通する単なる「物」であると彼らは主張し、キュビズムの物質的対象としての個々の絵画の自律的な性格を主張した。つまり、絵画はある番号で登録された単なる物であり、その定義に従って自分たちの絵画をデザインするのである。
そしてデュシャン移行、「アートケア」は日常生活におけるあらゆる可能なものへと拡大した。アーティストたちはキュレーターの役割を担い、展覧会や出版物を企画するようになった。「キュレーター」という言葉は、実は同じ「cura」(ケア)という言葉から来ているのだ。展覧会は一時的なものであるが、そこに出展された作品は別の文脈で再び展示される可能性がある。アート作品と道具、アート作品と消費財の基本的な違いはこの反復性にある。消費財は使い尽くされ、破壊される。しかし、芸術作品は使用や消費のためではなく観賞のためだけに存在するため、永続性という保証を得るのだ。
もともと絵画は教会や貴族が道具として使用していたものだったのを変えたのがフランス革命だった。芸術は革命的な暴力によって生み出されたのだ。前近代はそれまでの文化的形態や態度に関わるものを物理的に破壊する、過激なイコノクラシスがあったのを、フランス革命は「美しい物質的な対象」への思慕として、破壊する代わりに、機能を停止させ、芸術として提示するという新しい対処法を提示した。道具ではない対象になることで、それはケアされるという保証を得たのである。
人間のモノ化がしばしばネガティブな響きを持つのは、それが奴隷制に結びついているからだ。しかし、モノになることは、必ずしも人間が道具になることを意味しない。それどころか、モノになるということは、ケアの対象になるということでもある。美術品の保護は、人体の医療的保護と比較することができる。奴隷制度を野蛮とみなすのは芸術を商品とすることが野蛮とみなすのと等価なのだ。19世紀のヒューマニズムは人間は自分が芸術品であることをよく自覚し、その地位を向上させ、安定させようと、幾度も試みている。
人体と芸術作品のアナロジーはロシア宇宙主義の草分け的存在、ニコライ・フョードロフによって19世紀末に先鋭化された。フェドロフにとって芸術とは、過去の保存と再生のための技術である。芸術は未来のよりよい社会を待つのではなく、今、ここで不滅のものとするのだ。また、美術館の存在そのものが19世紀の一般的な功利主義的、実用主義的精神と矛盾していると正論を述べているが、これまで生きてきたすべての人々が芸術作品として死からよみがえり、宇宙全体と同一である普遍的な美術館に保存されなければならないという。個々の美術品が腐敗する恐れがある場合には保存と修復を行うように、国家は各個人の復活と不滅の生命に責任を持たなければならない。
フーコーは生権力は単に部分的なものではなく、全体的なものにならなければならないと述べた。人口の生存が国家の目標の中心であるが、死は個人の私的な問題として扱われる。フーコーは博物館の空間を他者空間、ヘテロトピア(heterotopic)な空間として理解し、時間が蓄積される場所として「現実の生活」の空間から区別した。対してフョードロフは生活空間と美術館空間を一体化させ、その異質性を克服しようとした。これは生活の完全な美術館化であり、新しい権力の明確な目標はすべての人の地上での永遠の命であった。これがフーコーの部分的な生権力との違いであり、完全な生権力である。
技術革命や政治革命の最初の結果は、多くの人間の身体の脱機能化した。芸術革命の結果としての芸術作品の脱機能化に類似している。ケアというシステムを通して、人間の身体はレディメイドになるとも言える。それまでの職業という文脈から切り離され、脱機能化されるのだ。労働の日々を終えた後(老後)、ただ働く道具として使われてきた私たちの身体は貴重なケアの対象となる。ここで、既存の有用性の理論は無効化される。ケアのシステムは、実は仕事のシステムを超越していているという。なぜなら、ケアのシステムには、これまで働くことのできなかった、そしてこれからも働くことのできない身体も含まれているからだ。病院は私たちの存在が仕事よりも価値があるという、患者の生体そのものに価値を見いだす。
11 仕事と労働
ハンナ・アーレントは『人間の条件』のなかで、ケアワークは伝統的に生産的な仕事よりも評価が低いと論じている(しかし、古代ギリシャの伝統では、ケアの仕事は主人の身体をその対象としていたため「仕事」であると考えられていた)。生産的なプロセスとして理解される「仕事」と、ケアという非生産的な仕事として理解される「労働」。労働は何も残さないとハーレンとは述べているが、にもかかわらず、労働は大きな緊急性から生まれ、他の何よりも強力な原動力によって動機づけられている。
こうした仕事と労働の関係を逆転させたマルクスは、生産的な仕事を非生産的な労働に従属させたとアーレントは主張する。生産性とは人間の「力」であり、そこから生まれる「余剰」が労働の生産性を説明するのだ。すべての仕事は労働となり、世俗的な質ではなく生きている労働力の結果、そしてえ生命プロセスの機能として理解されるのだ。しかし労働の世俗的で物質的な痕跡がなくなってしまうとき、つまり仕事が労働として理解されるとき、世界は生命に完全に吸収されてしまう。ここでハイデガー的な世界の喪失が再び表面化する。現存在がセルフケアを行うとき、それはその世界をケアする。現存在はどのようにして生命になるのか。それは「痛み」においてである。生命は苦痛のうちに自己を明らかにする。マルクスが人類史を人類と自然との代謝として捉えたということは、マルクスが人類の痛みを見たということでもある。
人間の身体だけでなく、世界の物事もまたケアの労働を必要としている。アーレントは「出生」という概念を導入したが、人は自分の一生を越えて何かを保存することはできず、自然との代謝に関わるケアによってすべてが吸収される。「社会化された人間」の生が目標となったとアーレントは書いているが、同時に、動物労働者としての人間の勝利は、歴史的に必然であると宣言している。
また、人体のプライバシーについても言及している。公的・私的なケア機関の出現と、それと並行してケア労働者を含む労働運動の台頭は、プライバシーの喪失につながる。ケアのシステムは、社会化された身体と自然との代謝が行われる媒体であるが、この身体は身体的であると同時に政治的である。ブルジョワ社会が身体が道具化すると、身体は象徴的地位によっても分離され、またプライベートな身体(生命に関わる)はセックスと戦争によって経験されるものとなった。
こうして身体は公的なものと親密なものというアイデンティティを持ちはじめ、それは現代のSNSによく現れている。インターネットを通じて、私たちの象徴的な身体と物理的な身体がどんどん一致するようになった。SNSのアカウントは、象徴的な身体としてユーザーの肉体のほぼ延長線上にある。インターネットは鏡であるだけでなく、私たちの欲望する自己のイメージを作り出すカメラだ。これは私的で個人的な身体が象徴的なものになったということでもある。こうしたナルシシスティックな自己顕示が麻酔として機能すると、自分の身体が社会化・政治化されることで、その痛みを「私の」痛みとして経験することができなくなるのだ。
創造性はその背後に潜む弱い物理的な身体を守るための巧みな模倣(カイヨワ)なのであり、視線についての理論において、芸術、特に絵画は常に他者の視線にさらされるのではなく、さらされないように保護するための手段であるという指摘をカイヨワの著書を使って行った。他者の視線は常に悪の視線なのである。芸術家は作品を制作することで、他者の視線を自らの身体から作品の身体へと向け直そうとし、その結果、観客の邪悪で有害な視線を解除しようとするのである。
ここで新しいアイデアが残った。それは「創造性」が余剰エネルギーの効果としてではなく、他者の侵略に対する弱者の防衛ということだ。私的で親密な身体とその欲求を明らかにすることは、他者の邪悪な視線に耐えることのできる保護的な象徴的身体を作り出す最も経済的な方法である。現代人は生まれつきの容姿に頼るのではなく、セルフデザインを実践し、極めて異質な社会で好かれることを目標に、自分のイメージをプロデュースしていかなければならない。かつて宗教があった場所に、デザインが出現し、セルフデザインは自己防衛・自己管理の一形態となりはじめている。そして、人間の身体は芸術作品となり、博物館の展示品に例えられる。
12 革命的なケア
前章ではセルフデザインの必要性が説かれたが、12章ではそれを「革命的に」逃れる方向へ向かっていく。アレクサンドル・ボグダーノフは、革命のプロセスを「egression」と「degression」という概念で説明した。egressionは権威主義的な組織形態であり、不安定であるという。支配の連鎖が長くなり管理が困難になると、権力による侵攻型システムは溶解してしまうのだ。対して、ポスト侵攻型組織は、可塑性の原理に基づいているという。そしてボグダーノフは可塑的有機体はdegression=骨格的なもの(スケルトン)であるという。皮膚など、生物を保護するすべての形態を骨格的なものとして理解している。
「ここ(スケルトン)には、衣服ーー身体の付加的な外部骨格ーーと、住居ーーより高次の類似の骨格ーー、あらゆる種類の労働生産物の保存のためのケースや箱、液体用の容器などが属する」
ここに病院や博物館を加えることもできる。グロイスが象徴的な身体と呼ぶものは、ボグダーノフによって外部の骨格として理解されている。芸術作品もまたこの骨格に属している。ボグダーノフは非常に早くからその主要な保護機能を見抜いていた。コロイド状のタンパク質の生きた可塑的性質を固定することは、心的イメージの生きた可塑的組織の固定、保持、保護なのだ。ハイデガーもまた、Gestell(ドイツ語で「骨格」の意)という言葉を技術論の中心的存在として紹介している。この語には「装置」の意味もあるというが、ハイデガーは技術・社会的装置が私たちの世界観を枠付けると主張した。しかし、枠にはめるからこそGestellを見失うとも揶揄している。
egressionとdegressionの対立はセルフケアとケアの対立と読み替えることができる。ここでの骨格となるシステムはケアのシステムであり、患者は、退廃的な医療システムに対して比較的外部的で脱中心的な立場を利用して、このシステムを支配し、患者とその健康のためにそれを変革する運動を開始することができるのだ。ここでセルフケアがケアを支配し始める。
ボグダーノフは医師でありながら、ボルシェビキ、ロシア社会民主労働党内部の運動の指導者の一人で、また1912年には活動を放棄し「プロレトクリト」の主催者となった。プロレトクリトの主旨は、一般の労働者や農民が芸術を作る意欲を持つようにすることであり、検閲や選別はほとんどなかった。ある意味で、プロレトクリトは、マルクスの芸術の脱専門家化、つまり芸術市場による支配からの解放という考えを実現したものだった。しかし「プロレトクリト」は権威的運動の圧力により1920年には事実上廃止に追い込まれた。
その後、ボグダーノフは1924年から1928年まで「血液学・輸血研究所」を組織している。なんと、古い世代の代表者と若い世代の代表者の間で輸血を行えば、古い世代の若返りにつながると考えていたのだ。1928年、ボグダーノフは自分の血液と、結核とマラリアにかかった女子学生の血液を交換した。この輸血の結果、ボグダーノフは死亡し、学生は完全に回復した。ボグダーノフの輸血実験は、地球上に万人のための幸福な生活を建設するという共産主義的約束と、技術的手段によって不死と復活を実現するという革命後の傾向に合致するものだった。
こうしたバイオ宇宙主義運動における予感は、1912年に発表されたSF小説「不死の日」のテーマにも盛り込まれている。不老不死になる方法を発見した科学者が、1000年生きた結果、ニーチェ的な永劫回帰のテーマを体現し、自殺をするという物語だが、自殺の方法には一番苦しいとされる火あぶりが選ばれている。単に生きるだけでなく、自分が本当に生きていると感じたいという思いと、人は痛みの中でこそ真に生きている自分を発見することができるのだということが、この物語からうかがえる。極度の痛みの体験は、健康で不死身で永遠に退屈な存在とする制度的ケアによって未来の人間に課せられた、麻酔をかけられた機械のような存在様式からの逃避を提供するのだ。
(後編:了)
前編へ:イントロダクション+1〜6章
1 ケアからセルフ・ケアへ
2 セルフケアからケアへ
3 大いなる健康
4 ケアテイカーとしての賢者
5 主権的な動物
6 感染する聖なるもの
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
