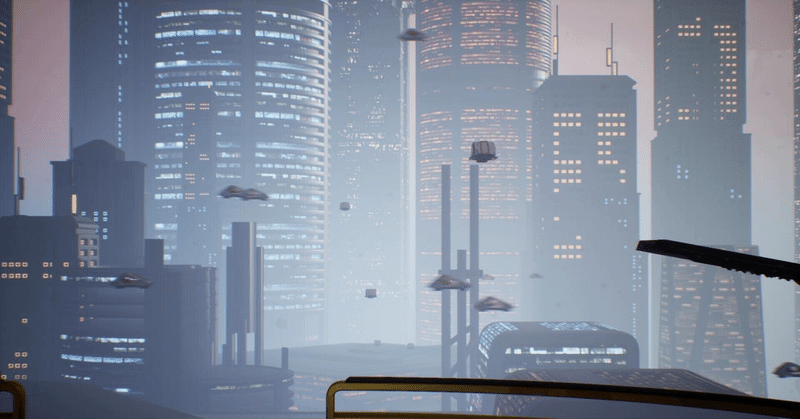
自動的に消滅する、を飲むと #ネムキリスペクト
誰にでも、消し去りたい過去はある。太宰でなくても、振り返れば恥の多い生涯を送ってきましたと言いたくなる。
取り返しのつかないこの過去が、なかったことになるのなら。
せめてこの記憶だけでも、自動的に消滅してしまえば。
忘れたいと苦しむこの痛みが、まるで魔法のように急になくなってくれたなら、どんなにいいだろうか。
***
その店は外観からして妙だった。だいたいどこにあるのかすらも定かではない。少年は煙が詰まって膨らんだような頭を載せた足を、でたらめに運んでいたのだから。
大通りからは既に何ブロックも離れ、薄汚れた建物が両側から迫ってくるような路地を歩いていた。するとどこかの換気扇からか、奇妙に芳しい白い靄が流れてきた。構わず歩き続けて視界が晴れた時、その店の前に立っていたというわけである。
一瞥しただけでは、それはただ緑の庭の中の洒落た洋館に過ぎなかった。先程の路地のむさくるしさは微塵もない。川のせせらぎと木々のざわめきが涼しかった。
そう、その店は川を背にして建っているのだが、その建ち方というのが奇妙であった。利休茶色の四角い積み木を三段に重ね、それをうっかり蹴飛ばしてしまったという風情に、ちぐはぐなのである。さらにはそのずれた所に、各階に赤煉瓦の煙突が付いていて、三階部分の切妻屋根には、鳥の巣のように雑草が繁茂している。極めつけは、その店には入り口がなかった。
彼は店のぐるりを回ってみた。正面と思しき壁面に、小さな細い文字で
喫茶店
とあった。各階に8個ずつ木枠のガラス窓があって、中を覗くと木の床が赤茶色の飴のようにつやつや光っている。チョコレート色の木製の丸テーブルと椅子のセットが幾つかひっそりと置いてあり、奥にはたくさんのグラスが銀色に光る戸棚。
突然ちりんちりんと鈴が聞こえた。灰色の木の扉が開いていて、燕尾服姿のすらりとした老人が品よく佇んでいた。
「ようこそ、このお暑い中いらっしゃいました。さあどうぞ、おあがりください」
忽然と扉が出現したことも、老紳士が音もなくそこに立っていたことも、超常としか言いようがなかった。彼は気の遠くなる思いがした。熱中症だろうかと思った。実際、灼熱の中をもう2時間も歩き回っているのだ。
老紳士に導かれて敷居を跨ぐと、芳香を含んだひんやりとした空気が、太陽に焼かれた肌を優しく包んだ。しかしその香りは珈琲のそれではない、嗅いだことのないような種類の芳しさであった。
老紳士は椅子を引いて少年を座らせ、革表紙のメニュー冊子を手渡す。彼はそれを開いてみて、
「これはどういうことですか」
と老紳士を見上げた。メニューにしては分厚い本だが、どこを開いても白紙のページが続いている。
「どうぞ、構わずにめくってください。あなたにぴったりのものが見つかります」
老紳士が穏やかにそう言うので、少年は白紙のページをめくり続けた。最後のほうになって初めて、柔らかな薄黄色の紙の上に、細い小さな文字がただ一行、こう並んでいた。
自動的に消滅する
「これは何ですか、この、自動的に消滅する、って」
彼は再び老紳士を見上げた。老紳士は微かに微笑んで、話し始めた。
「こんな御伽噺をご存じでしょうか。
昔、ある探検家が、地図にも載っていない小さな島に上陸しました。彼は丘の上に向かって伸びる一本の細い道を見つけて、それを辿って行きました。彼が通ったあとからその道が消えてゆくことに、彼は気が付きませんでした。やがて一軒の家に辿り着きました。そこには一人の男が住んでいました。彼はその男にお茶をご馳走になり、しばらく話をしました。男はこう言います。
僕には双子の弟がいる。弟は今もここにいるが、君には今は僕しか見えないだろう。しかし、君がここから立ち去れば、君はきっと僕のことは忘れて、かわりに弟のことを覚えているのだ。
男は悲しげにそう言いました。探検家は、何そんなことはあるはずがない、現に今僕には君しか見えていないのだからと請け合いました。
しばらくの後、探検家はその男に別れを告げ、元来た道を帰ろうとしました。ところが、来たはずの道はきれいさっぱり消えているのです。仕方がないので、彼は道なき森の中を、探検家らしく歩いて行きました。彼の通ったあとから、道ができてゆきます。そして彼が自分の船に戻ったとき、果たして、彼はさっきの悲しげな男のことは忘れて、かわりに陽気な男が言った冗談やそのひょうきんな仕草のことばかりを覚えているのです。彼は船から自分が先程丘を降りてきた道を見上げて、これを登って行って会った陽気な男のことを航海日誌に記しました」
老紳士は話し終えた。少年は彼を見上げたまま、三拍待った。
「…それで、それはどういうことなのでしょう」
老紳士はにっこりと微笑んだ。
「そういうことです。『自動的に消滅する』を召し上がると、こういった効果があります。忘れたい過去、なかったことにしたいことが記憶から消滅し、その穴は適当な物語に置き換わります。そのメニュー表は、あなたが一番欲するものを見せてくれる優れものです。それでは、今からそちらをお持ちいたしましょう」
彼は燕尾服の裾を翻して奥へと去った。少年は狐につままれたような心持でその後姿を見送る。とんでもない店へ入ったと腹の中で呟いた。しかし不思議と悪い気持ちはしない。それは彼が、忘れたい過去、なかったことにしたいこと、という言葉に、何か感じるものがあったからかもしれなかった。佐倉まこと、という名前が胸の裏側を抉った。
老紳士はほどなくして戻ってきた。お待たせいたしました、と彼は紫がかった透明な液体で満たされたグラスを置いた。
「どうぞ、お召し上がりください」
少年は恐る恐るそれに口をつけた。舌から染み通るように爽やかな冷たい甘い飲み物であった。しかしその香りは一風変わっていた。スパイスか、ハーブか、それにしても何のハーブなのか、およそ検討のつかない芳香であった。店内に満ちている香りと同じものだろうかと彼は思った。
液体が喉に落ちた瞬間に、鋭い頭痛が走った。それとともに包帯を巻いた細い腕の幻影が目の前をちらついた。彼は驚いて老紳士を見上げた。
「これを飲むと、忘れられるんですか」
老紳士は頷いた。
「先程の御伽噺を思い出してください。忘れるにはまずゆかなければ。道を辿ってこそ、通った後から道は消滅するのです。辛い思いをされるかもしれませんが、それは今だけ。今それを一杯飲み干せば、これからずっとその過去に煩わされることなく暮らしていけるのです」
老紳士は励ますように頷いて、ごゆっくり、と退いた。少年はグラスに向き直る。「これを飲み干せば」。飲み干さなければ。なぜなら過去は決して消えてくれないのだから。
彼はぐいとグラスを傾けた。割れるような頭痛がして、色彩と音声の奔流が彼を飲み込んだ…
夏だった。運動場の砂は目を射るように眩しかった。同級生たちがばらばらと集まり始めて、彼の目は自然と、よく馴染んだ顔を探し当てた。半袖の体操服を着た彼女の両腕に巻かれた包帯の白が、かえってそこに流れた血液の赤さを強く想起させた。
…おれは関係ない。
夏だった。狭い教室は夜に反抗して白々とした電灯を暴力のように掲げていて、汗と焦りの匂いに満ちていた。彼は早々に問題を解き終え、計算のやり直しを始めた。
「佐倉はまた欠席か。あいつもう駄目やな」
講師が呟くのが聞こえ、彼は思わず教室の最後列右隅を振り返った。彼女の席はがらんとしていて、それが白々した電灯の下でいかにも寂しかった。
「おい園田、テスト中やぞ」
講師に注意され、彼はまた俯いた。彼の席は最前列の左隅であった。
…おれは関係ない。
秋になった。昼休みの学校は混沌であった。彼は勉強場所を求めて図書室へ赴いた。この秋から難関N高校入試のための塾の特訓クラスに入ったのだ。途中通り過ぎた教室の後方の席で、一人で机に覆いかぶさるようにして何か描いている彼女の姿が見えた。長袖のシャツが腕を覆っていた。その白さと、彼女の周りの誰もいない空白が、冷たさを含んだ空気の寂寥の感を倍加していた。
…きっともうあんな馬鹿なことはやめている。それに、彼女のことはおれには関係ないんだ。
冬になった。学校でも、塾でも、家の近くでも、彼女の姿が見えなくなった。けれど彼はそんなことには構っていられなかった。入試は2月10日であった。
彼は震える手でグラスを置いた。氷も浮かべていないのに凛と冷たいそのグラスは、チョコレート色のテーブルの上でびっしりと汗をかいていた。
しばらく休憩しよう、と彼は思った。しかし今しがた見たものが頭を離れず、考えることは自然彼女のこととなった。
佐倉まことは彼の幼馴染だった。母親どうしが同じ病院の医師と臨床検査技師だったこと、誕生日が近かったこと、家が斜向かいにあったこともあって、二人はほとんど兄妹のように育った。まことはいつもりっくんりっくんと言って彼の後をついて回っていた。
小学校に上がってから二人とも別々に遊び友達ができた。彼はだんだん、妹のような彼女のことが分からなくなっていった。
まことは毎年のように絵で賞を貰っていた。彼女って絵が上手かったんだっけ。暇さえあればお絵描き帳に向かっていたのは覚えているが、彼女の作品を見て、これはまことのだと識別することは、彼にはできなかった。
小学四年生頃から、まことは塾に入った。彼女の母親の意向で、難関K中学を受験するのだそうだ。もともと利発な子供だったから、彼女はめきめき力をつけた。彼と遊ぶこともなくなった。彼はますます彼女のことが分からなくなった。まことは自分の知らない世界を知っていて、自分より何倍も偉大だという感じがした。
彼は公立中学校に進学した。同じクラスにまことを見つけて、彼は驚いた。さすがは難関とあって、K中学は容易には合格できないのだそうだ。高校でリベンジするのだと、まことは言って笑った。でも良かったかも、りっくんとまた一緒だから。
中学から、二人は同じ塾に入った。成績の良い順にAからIまで9クラスあって、彼らはAクラスになった。その中でも成績の順に最前列の左隅から最後列右隅まで席が決まり、まことは最前列の真ん中、彼はその真後ろにいた。
あの穏やかな頃のことなら、そんな些末な話まで覚えている。けれど何かがおかしなほうへと転がり始めた時、自分が何を言い、何をしたか、途端にぼんやりとしてくる。それはのしかかる罪の思いに苛まれた彼の防衛本能が、わざとその記憶に靄をかけたものに相違ない。だから彼は今、この過去に決着をつけるために、もう一度はっきりと、自分が何をしたのか確認する必要があるのだ。
彼は深呼吸して、再びグラスに口をつけた。
彼の父は実業家であった。とことん無駄を嫌い、人に何と思われようと気にしない、頭の切れるエリートだ。そして医者である妻にもひけをとらない科学の信奉者でもあった。
父が子供に対して欠けていた興味の分、母は彼を非常に大切に育てた。彼女は子供のカフェイン摂取は法律で禁じるべきだと信じていたから、彼は喫茶店とはオレンジジュースか牛乳を飲む店だと、中学に上がるまで本気で思っていたし、天下に最も特別な人間たれと、いつも聞かされて育った。だから、自分より優れているように見えたまことに対する思いには、どこか深いところで屈折したものがあったかもしれなかった。
小学生の頃は未知の領域にあり、微かな畏怖さえ抱いていたまことの実力を目の当たりにして、彼は猛勉強し始めた。ゴールが見えれば、人は踏ん張れるのだ。すぐに二人は並んで競い始めた。彼はその手応えが嬉しかった。科学的なメソッドで効率的に勉強した成果が、右肩上がりのグラフに見られて嬉しかった。塾でも彼は逸材だと言われた。母はもちろん、父も感心したようだった。彼はそれを誇った。
秋が忍びやかに鼻先を撫でていった。塾からの帰り道を二人は並んで歩いていた。
「最近はまってる歌い手さんのね、」
まことは嬉々として話し始める。
「ウタイテサンって何だ?」
彼はきょとんとして尋ねた。まったく、最近まことはずっとこうだ。最近はまってるアニメの、から始まって、今度ライブに行く音楽グループの、とか、最近ずっと聞いてるボカロの、とか、彼にはさっぱり分からない現代的趣味の話をつらつらと聞かせてくる。だいたい、アニメーションのアイドルたちがどうして3D空間でライブができるのか、理解不能だ。
「音楽を聞きながらの勉強は効率が落ちるよ。それに、昨日もそんなに夜更かしして、健康に悪いぞ」
彼はいつもうんざりしながら言い聞かせているのに、まことははーいと景気よく挨拶だけして、翌朝けろりと、今日も5時間睡眠だった、授業中寝ちゃうわと笑っていた。
まことが描く絵もアニメ色が濃くなった。確かに、彼女は絵が上手かった。そこらのアニメ以上だと、何も知らない彼でさえそう思った。彼女の線は脆くて繊細で、描き上げる図形は正確無比だった。
街路樹の葉が落ちて、手袋をしないと指が赤くなる季節になった。その頃には、彼は塾の帰りには最前列の左隅で、遥か後方のまことを待たなくてはならなくなっていた。
まことはもともと色が白くて雛人形みたいだと彼は思っていたが、最近はなんだか青白くなってきた。外に出ないせいだと彼は考えた。一日30分の日光浴は体内時計のリズムを整え、生産性を上げるのに非常に効果的だと、まことには教えてやったのに。
「最近ね、なんか眠れなくて」
彼女は疲れたように言った。
「寝る前にブルーライトを浴びるからだろ」
彼は素っ気なく答えた。
「眠ろうとするんだけど、その度に凄い頭痛がして。昨日も殆ど眠れなかった」
「そりゃ、急には体内時計は修正できないから。今日はもう寝て、お母さんに言って、学校休ませてもらったら」
「そんなことお母さんに言えないよ。今日もほんとは7度8分あったけど学校行きんさいって」
まことはぎゅっと目を閉じて白い息を吐いた。彼は驚いた。
「熱があったら休めよ!そんな体で何やったって効率悪いし」
「そんなこと、お母さんに言えない…」
彼女は繰り返した。彼は彼女のために少し怒った。
「いくらお母さんだって君と対等なんだよ。負けるな。説得するんだ」
まことは弱々しく笑って首を振った。
「成績下がってるし、今日返ってきたテストも見せらんないなあ…」
「そんなに悪かったの?」
「クラス落ちるかも」
彼女は笑いを残したまま言った。彼は衝撃を受けた。まことが?あの優秀な?有象無象の中に埋もれていってしまうのか?
「じゃ、勉強しないと」
「だよねー」
彼女はオリオン座に白い息を吐いた。
2年生になって、学校で二人はクラスが別れた。けれど相変わらず塾の帰り道は一緒だった。
まことは毎日のように体調不良を訴えるようになった。頭が痛い、眠れない、朝起きられない、眩暈がする…。彼はうんざりして苛立った。
「そんなにきついなら休めばいいじゃないか」
「睡眠はちゃんと取れ。そのために寝る2時間前にはブルーライトを浴びないようにしとけ」
「眩暈は血流を改善すればたいてい治るから、ストレッチしな」
いつも言っているのに、まことは一向に彼のアドバイスに従わなかった。それで毎日同じように、頭痛がする、眠れないと言い続けた。そして大好きなボーカロイドや歌い手やアニメやゲームのことを、まるで熱に浮かされたように語るのだった。
彼はそのためにサイバーカルチャーを憎んだ。時折露骨に、もうそんな下らない遊びはやめて、真面目に健康に勉強しろと諭した。まことは塾でも落ちこぼれ扱いされていて、講師が皆の前でおい佐倉もっと勉強しろと笑うたびに、彼はやるせない思いに歯を食いしばった。塾は学校じゃない。だからこんな前時代的仕打ちができるんだ。
何度目かに彼がまことの趣味をけなしたとき、彼女は彼を睨み上げて言った。
「どうしてそんなこと言えるわけ。人が好きなものに口出ししないでよ。あなたさ、あたしを見下してるんでしょ。馬鹿にしてるんだいつも。ほんと、人のこと何だと思ってるの?」
「馬鹿になんか…」
彼が驚いて言いかけたのを彼女は涙声で遮った。
「あたしのことどうしようもない馬鹿だと思ってるんでしょ?周りのみんなのことそう思ってるんでしょ?だって、園田璃空は天才だもんね。知ってるよあたし、自分が馬鹿で間抜けなことくらい。自分で自分のこと一番嫌いだよ。なんで生きてるんだろっていつも思ってるよ、こんな屑みたいな人間がさあ」
まことは話の脈絡を失い、呆然と立ち止まって空を見上げた。彼も立ち止まって3拍待った。
「…言いたいことはそれだけか」
「…うん」
まことは鼻声であらぬ方向を睨みながら答えた。
「ふうん」
彼は苛立っていた。一体こいつは何を言い始めるのか。しかしここで何か言うのはいかにも子供っぽくて嫌だった。
「君がそういう風なものの考え方をしてるんだってことが分かった。…じゃあな」
「ばいばい」
彼女は言って、鼻をすすった。
彼はまことを残して歩き始めた。家までは、まだ何百メートルもあった。
彼は店内の落ち着いた木目の壁を眺めて、変にそぐわない気持ちがした。幼い頃、自分はすぐに死ぬという根拠のない予感を信じていた時期があったが、日曜日の昼下がりなどにソファに寝転んで目を閉じ、このまま死ぬのだと自分に言い聞かせ、安らかな甘い気持ちに浸った後に、ふと目を開けて見る緑がかった尋常の景色、その感覚を思い出した。
そういうことだったのだ、と彼は思った。中2の6月頃から、二人は顔を合わせて話すことがなくなった。学校ではクラスが違うし、彼は自転車で塾に通うようになった。ばったり出くわしても何を話すでもなく、自然に目を逸らし合って。彼女には課題の分離ができていないんだ、目の前のことに囚われてしまい、自己管理ができない。父親の好きなそういう言葉を並べて、彼はまことから遠ざかった。おれにはやるべきことが沢山あるんだから。大きくなったら医者になって、困っている人たちを助けるんだ。それはおれの義務なんだ。彼女のことに関わってる場合じゃない…
「えー、なになに?園田くんって、佐倉さんと別れたの?」
学校で、隣の席の女子が興味津々に聞いてくる。公立中学には、信じられないくらい頭の悪い連中もいて、つくづく頭脳って遺伝だよなと彼はいつも思っていた。カタツムリが葉っぱを咀嚼するよりものろい進度の授業でも、ついていけない生徒はいるのである。現行の学校教育はまるで機能していない、と彼はことあるごとに友人に演説していた。
「いや、そもそも付き合ってないし」
彼は愛想笑いして答えた。女子は大袈裟にええーっ、嘘だあと驚いてみせて、でも佐倉さんかわいそっ、友達いないもん、園田くん救ってあげなよーと口ばかりよく動く。
「ほんとに友達いないのか」
彼は誰にともなく言った。
考えてみれば記憶の中のまことはいつもひとりだった。自分でも何度か、私コミュ障だから、友達いないんよねえ、とへらへら笑っていた。彼はそんなに深刻に考えたことがなくて、まことはそんなこと気にする奴じゃない、騒ぐよりひとりで絵を描くほうが好きな子だと納得していた。だからこの時も特に何とも思わなかった。まことには避けられていると思っていたし、自分からわざわざ何か言いに行くような気は起らなかった。やるべきことはごまんとあったのだ。そんな風に1年過ごすうちに、まことのことはほとんど忘れてしまった。
夏だった。運動場の砂は眩しくて、視界に捉えた彼女の腕には、目を射るように白い包帯が巻かれていた。
暴力的に白い電灯を夜にかざす狭い教室で、振り返って見た彼女の席はがらんとしていた。
秋になった。ひとりで机に向かう彼女は、秋の寂しい空気の中で何にも支えられていなかった。
冬になった。彼女の姿が、見えなくなった。
***
入試が終わった後、彼は憑き物が落ちたような心持がした。毎日心穏やかに趣味に打ち込んだ。しかし、暇ができたのに、彼はなんだか落ち着かなかった。佐倉まこと、という名前が、胸の裏側を微かに傷つながら去来した。
彼女の母親は厳しい人だった。父親の顔は、長い付き合いで2、3度しか見たことがない。
小学生の頃、家の外で泣いているまことを見たことがあった。庭にしゃがみこんで、ごめんなさいごめんなさいと繰り返していた。彼が近づいていくと、私が宿題しなかったから怒られちゃったと、言い訳のようにぐちゃぐちゃの顔で笑った。彼は一緒にいてあげるよ、と隣にしゃがみこんだ。
どうして同じことができなくなったのか。そうだ、劣等感だったのだ、すべての始まりは、小4の時まことに抱いた恐怖に近い劣等感。彼の腹の底であらゆる言動、思考を操っていた黒幕。それを彼は上手に畳み込んで、しまい込んで、そんなものは存在しないというふりをした。そして彼は存在しないはずの黒幕に知らぬ間に突き動かされ、なんとか自分が優位であることを証明しようとしていたのだった…
具合が悪くて弱っているとき、人が一番求めるのは慰めであって、決してああすれば治る、こうするから悪いのだという説教ではない。どうしておれは、そうか大変だね、頑張ってるんだね、でももう休みなと、言ってやれなかったのか。心が弱っているのに、どうして母親と戦えとけしかけたりしたのか。どうして、彼女が選んだ道を認められなかったのか。それもこれも、そうすることで自分の優位を示したいというだけだったんだ。
たったひとりで、両腕に包帯を巻いて、やつれた顔をしていた彼女…
彼は地獄のような暗闇を見る心持がした。それで家を飛び出して、佐倉家の呼び鈴を鳴らした。いくら待っても、応答はなかった。
自分の幼稚さゆえに深く傷ついた、ぐちゃぐちゃの心を臓物の間に押し込んで、彼はN高校の寮に入った。学校生活は充実していて、息つく暇もなかった。
夏休みに家へ帰ってきた時、彼は彼女の家に見知らぬ家族が出入りしているのを見た。新しく引っ越してきた人たちだと聞かされた。
彼女は死んだのだと、彼は突然そう思った。そして紛れもなくおれが殺したのだと、殆ど直感的にそう信じた。彼女を殺したのはおれだ。おれが、佐倉まことを死なせたんだ。
罪の奈落は彼の胸に巨大な口を開け、物凄い力で彼を飲み込んだ。おれが死なせたんだ、おれが…。
***
これがその過去であった。彼が夏休みの大半を苦しめられ、ぼんやりした頭であちこちと歩き回ったその原因であった。彼は空になったグラスを握りしめて泣いた。
思えば忘れようとしたこのこと自体が、自らの恥を上乗せする行為ではないか。いつか、そんな日が来ればだが、いつかこの過去も自分のものとして受け入れられるようになったかもしれなかった。しかし彼は逃げることを選んだのだ、永久に…
「やってしまったこと、やらないでしまったこと、その罪のすべては、誰も許してはくれません。一生消えない十字架を、あなたは既に背負っている」
いつの間にか老紳士がそばにいて、小さな微笑を浮かべていた。
「ご機嫌よう。また会うこともないでしょう。これからはあなたが自分で自分のことを許すのですよ」
***
「璃空ー、今度映画見に行こ」
京香は彼の腕を取って言った。
「来週ね、佐倉まことの新しい映画が公開なんだ。言ったっけ、私あの人の絵、超好きなのよー」
彼は答えなかった。口を開いたら、なぜか涙が零れそうになったのだ。
「え、どうしたの?大丈夫りっくん」
京香はぎょっとしたように彼を覗き込む。
昔自分のことをりっくんと呼んでいたあの人。おれは何か彼女のことで、えらく悩んだことがあったような気もするけど、あれは何だったっけ。今訳もなく泣きそうなのと、関係しているような気がする。
彼は空を見上げた。いつか彼女が見上げたオリオンが、彼を見つめ返していた。
完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
