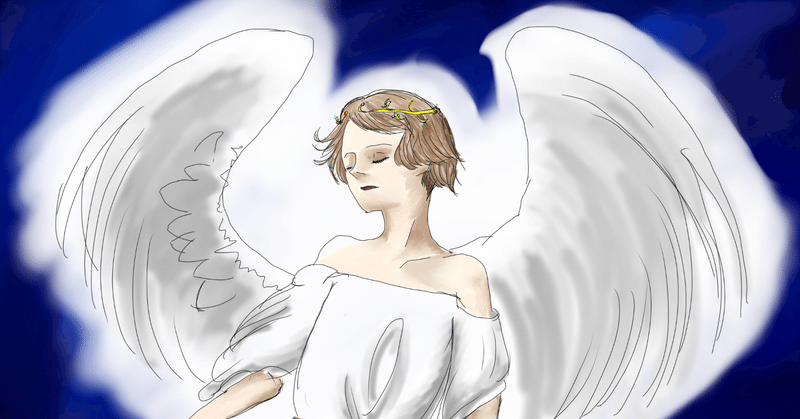
天使の去ったあと【ネムキリスペクト】
まぶたの裏にほのかな明かりがともった。胸の上をすんなりと覆う静かな布団の匂いが鼻腔に漂った。窓の外には森の朝の音が、蝶たちのようにはばたいていた。いつも通りの目ざめだった。
彼女は眼を閉じ、半分眠ったまま我が腕を抱いた。心地よく重い体のぬくみの楽園に、隙間風がしのびこんでくる。いつもある筈のぬくもりが、ひややかな裏切りをもって、彼女に布団の中で身体を縮めさせていた。
彼女はとうとう身体を起こした。昨夜いつものように隣に横たわったあのひとが、いなかった。そして窓からそそぐ朝の光が、ひとけのない小さな家を浮かび上がらせるように、もうあのひとは戻ってはこないのだという感じが、背をなぞるひややかな風を伴って、彼女の前途をぞうっと照らした。
彼女は寝台から滑り降り、キッチンに立ってやかんに湯を沸かした。ポットにいつもの茶葉をふたさじ入れて、沸かしたての湯を注ぎ、立ち昇る大好きな朝の香りの蒸気のなかに、こころもち鼻を持ち上げて、眼を閉じた顔を浸す。毎朝そうする彼女を、あのひとは笑って見ていた。あのひと。そんなよそよそしい呼び名で、そのひとのことを考えたことがなかった。しかし彼でも彼女でもない、あのひとを指すことばを彼女は持たない。だってあのひとは天使だったから。
あのひとに出会ったときの記憶は霧雨の靄がかかっていて、つまりそれほど幼い頃の記憶なのだが、ただ寒くてひもじくて、氷の針を刺されているようで、泥水をはねられながら道端で泣いていた。するとあのひとはどこからともなく現れて、あたたかいパンの匂いのする乾いた毛布に彼女を包んで、猫を拾うみたいに、ひょいと抱えていってしまった。背中に白くて大きな翼をはやして。彼女は眼をまるくしていた。
それからは、あのひとのいるあたたかい小さな家が、彼女の世界の中心だった。
ポットからカップへ、いつもの量のハーブティを注いでも、まだたっぷりと残っているのではじめて、彼女は自分が二人分の茶を淹れたことに気が付いた。気が付いてしまうと、いつもの朝の談笑が小さな家の空気を震わせないことも、キッチンで一緒に作業する天使の微笑が自分に向けられないことも、いつもは自分が茶を淹れる間に漂い始める朝食の匂いがしないことも、全部がいちどきに彼女を鷲掴みに揺すぶって、彼女は叫びだしたくなった。カップの中で湯気をたてる茶をそのままに、彼女は外に飛び出して、何かが彼女の心臓を掴んでひきずりまわすままに、走った。
脚が動かなくなって立ち止まっても、彼女は白い息を荒げて、まだまだ伸びる勢いを見せている自分の膝に手をついて、鼻をじくじくと刺す冷気をからからに乾いた喉が痛むくらい吸い込んで、わあーっと叫んだ。鳥たちが驚いて一斉に飛び立っていった。
「ねえ!…ねえ!どこへ行ったの?」
声を限りに叫んでみても、冬の森は閑静だった。ただ遠くに鳥の鳴く声がするだけだ。ねえ。彼女はあの天使のことを、いつもねえとかあなたとしか呼ばなかった。天使のほうでも、彼女をいつも二人称で呼んだ。それで事足りたのだ。たったふたりの世界だったから。彼女は天使の名を知らなかった。自分の名前すらも、知らなかった。
今天使がいなくなってみると、心にぽっかりとあいたその存在の空白はまったき虚無で、形なく崩れて、流れていってしまいそうで、それがとても、怖かった。こんなにあっさりと、失ってしまうなんて耐えられなかった。
「ねえやっぱり会いたいよ…あなたに会いたい」
ぼろぼろと転がる涙が、きんと冷えた頬をほんのいっときあたためた。
「いとしいあなた、私がいなくなった時の為に、贈り物を残しておきましょう」
天使は突然そう言った。彼女はどきっと肩を揺らして、自分の顔が不安に歪むのを感じながら、天使の眼を覗き込んだ。その眼はいつも通り優美で、慈しみ深く、どこか憂いをたたえていながら、奥のほうにぞっとするほど強い厳しさを備えていた。
「みっつの願いです。あなたの心の底からの願いをみっつ、神さまに言って、叶えてもらいましょう。ただ死んだ生き物をよみがえらせることと、ひとの心を変えることと、私が叶えたくないことは、叶えられませんけれども」
「…それじゃああなたが叶えたくなかったらなんにも意味がないじゃない」
彼女はわざと軽口を叩いた。天使は微笑した。
「大丈夫。私は天使だから」
そんなことが、あった。それからなんということもなく毎日が幸福に過ぎて、何でもない会話の一部に加えようとしてできなかった、その一場面。天使は、いつまでも私の隣にはいてくれない。いてはいけないのだ。彼女はそう考えて納得しようとした。
「寒いのに嫌な汗かいたな。お風呂に入らないと風邪ひいちゃう」
彼女は大きな声で自分に話しかけた。
風呂に入り、まごつきながら卵とパンを焼いて口に押し込み、一人分の洗濯物を干して、いつも来る四頭の鹿や栗鼠や小鳥たちにパンくずを投げて、ぼんやりしながら彼らのあたたかな毛皮を撫でた。菜園のブロッコリーをいくらか収穫して、花壇の手入れをして、庭から森へ続く木立の中を散歩した。編みかけの靴下を手に取って針を動かし始めてしばらくするとお腹が空いたので、パンを二切れとチーズをひとかけ切って食べた。また湯を沸かし、ポットに茶を淹れて、やっぱり二人分のハーブティを飲み干した。そうしていると再びやりきれない気分がぶり返してきた。
「ねえ会いたい。あなたに会いたい。置いて行かないで。私を置いて行くなんて酷い。私まだ子どもなのに」
涙の合間に、自分本位な言葉がとぎれとぎれに零れた。彼女は自分の耳に聞いた自分の言葉の、いやに芝居がかって滑稽なのを自覚して、悲しみの沼に腰まで埋まりながら、悔しくて歯を食いしばって泣いた。
「…結局、叶えてくれないんじゃない。私あなたに会いたいって、こんなに願ってるのに」
彼女は涙を乱暴に拭いながら呟いた。
「こんな重要なことが叶わないのなら、みっつ願いが叶うっていったってなんの意味もないわ」
誰にも届かない文句を言いながら、彼女はふと、天使が「私が叶えたくない願いは叶えられない」と言ったのは、ひとえにこのことを指していたのではないかと考えた。天使がいなくなって、彼女がまっさきに願うのは「戻ってきてほしい」に決まっている。それは叶わないのだ。
彼女はきゅっと唇を結ぶと、カップとポットを片付けようとテーブルを立った。
午後、彼女は一心不乱に靴下を編み上げ、洗濯物を取り込み、肩掛け鞄の綻びを繕った。以前天使と山歩きをするために村で買ってもらった、革のブーツを出してきて、丁寧に磨いて、履いて歩き回ってみた。パン生地を、額に汗をかきながらこねて、晩の食事をして、ひとりで布団を被って寝た。ひとりぼっちで入る床の冷たくてよそよそしいのに、また少しだけ涙を零して、彼女はぎゅっと眼を閉じ、あたたかな眠りが自分を抱いて攫っていくのを静かに待った。
翌朝彼女は決然とした面持ちをつくり、おへそにぐっと力を込めて起き上がった。昨日寝かせておいたパンを窯に入れて、いつも通りの朝の仕事を済ませ、家じゅうの毛布をかき集めてきて、綻びを繕ったり、天日に干したりした。革の水袋の強度と、食糧庫のチーズや燻製肉の残量を確かめた。パンが出来上がったので少し味見して、今度は菜園に出て行き、食べられるものはすべて収穫してしまった。それで昼食は野菜の大盤振る舞いだった。
午後は殆どを掃除に費やした。窓を開け放って天井から床まで、玄関から風呂場まで、ふたりで暮らした小さな家を、何かに取りつかれたように磨き込んだ。掃除がてら戸棚を探って、村でするたまの買い物のために持っている、いくらかの貨幣を掻き出してきた。
「どうしたものかしら、ってのは、この際考えないようにしよう」
彼女は何度もそう自分に呟いた。ともするといろいろな不安が彼女を襲って虜にしてしまいそうだった。なにしろこんなことは、彼女の過ごしてきた十回かそこらの冬の中で、はじめてのことだったからである。
彼女は夜明けとともに、ふたりのあたたかな家を去った。
「…い、…おい!生きてるなら返事しろ!」
彼女は乱暴に揺すぶられて、うっすらと眼を開けた。瞼の隙間からちらちらと漏れてくる緑がかった光の群れが、蜃気楼の星のように視界を泳いだ。身体じゅうが火のついたように痛かった。何日も冷たい土の上で、木の根元なんかで眠るからだわ、と彼女ははっきりしない頭で思った。
「…ったく…死んじまうぞ、こんなとこで…」
先程と同じ、乾いた無骨な声が、苛立たし気に降ってきた。二、三度瞬きをすると、やっと視界がはっきりした。目の前に、痩せて随分くたびれた様子の男が跪いて、少女を覗き込んでいた。彼女は一気に目が覚めて、ばねが付いているかのように跳ね起きた。
「おうおう、随分元気そうじゃないか。まったく、カワウソよ、余計な心配しちまったもんだな」
男は伸び放題の髪を掻き、「どうかしてるよ、まったく俺は」としきりに呟いた。彼女は何と言ったものか途方に暮れて黙ったままでいた。男の後ろの、真っ白に降り積もった雪の上に、ぽいと投げ出されたらしい旅行用の杖と、かなりかき乱れたような、大幅の足跡が付いていた。男が行く手に、毛布に包まれて身じろぎもしない小さな人影を認めて、どれほど慌てて駆け寄ってきたかが見て取れた。
「あのう…心配かけたみたいで、ごめんなさい」
彼女は消え入りそうな声をかけた。男は肩をすくめた。
「おまえ、親は」
問われて、すぐに浮かんだのは天使のことだった。けれど、あのひとは親とは違う。彼女は少し考えこみ、細い記憶の糸を手繰ろうと試みた。
「わからないわ。随分前に死んだと思う」
「ふうん。俺はてっきり、口減らしの為に親が捨てたのかと思ったが。でも口減らしならわざわざパンやらチーズやら持たせたりしないよな」
彼はちらりと、少女の肩掛け鞄に目をやった。
「あ、よかったら一緒に朝ごはんにしない?」
彼女はおずおずと男に微笑みかけた。彼は伸びすぎた髪の後ろで眼を瞬いた。
「…いや、俺はもう食った」
「そっかあ」
「追い出されたんじゃないなら、どうしてまたこんなところにいるんだ。旅人ってのは、冬には家へ帰れるように計らうもんだろう」
男は訝し気に言った。少女は返答に詰まった。しばらく眼を泳がせて考えた。別に、行きたいところがあるわけでも、天使を捜す当てがあるわけでもなかった。旅に出れば、何かに近づいて行けるわけでもなかった。ただ、旅に出よう、外へ出ようと思い立った時、彼女は驚くほどに生き生きした。何かの為に準備することが、彼女に活気をもたらしてくれた。
考え込む少女を、男はじっと辛抱強く見つめていた。
「…なんだか、家に、いたくなかったの」
「…そうかい」
彼はふっと息をついた。
「ねえ、だけどあなただって、こんな雪の中旅してるんじゃないの」
少女は再び、少し笑った。男はまた肩をすくめた。
「のっぴきならない事情があるのさ。ただ家にいたくないってだけでひとりでふらふらするのとはわけが違う。それに俺は大人だ。もう、おまえは家へ帰れ。気が済んだろ」
彼の口調は先程の苛立たし気な調子を取り戻していた。けれど少女のほうは一向に先程のような恐れすくむ気分が戻ってくる気配もなかった。簾のように被さった、ごわごわした髪の向こうの眼のまっすぐで優しいのが、はっきりと知れていたからだ。彼女はぴんと背筋を伸ばして、きっぱりと首を振った。
「帰らない」
「また俺みたいな奴に、余計な心配掛けるつもりだってか?それとも、そう、世の中にはとんでもない悪人もいるんだぞ。それに、冬の森では何に出会うかわかったもんじゃない。魔物やら、邪悪な生き物やら…黒い魔術師だって、この頃不穏な動きをしているとか。おまえがこれまで何日間か無事だったにしても、これからずっと無事とは限らんだろう」
「じゃ、あなたが私と一緒に行けばいいんだわ。そうしましょう、そうしましょう。私、まったく行くあてもないから、あなたについて行くわ」
「はあ?なに『名案!』とでも言わんばかりの顔してるんだ。俺はあんたみたいなちっさい子供を連れて行脚なんぞする趣味は持ち合わせちゃいねえよ。黙って聞いていれば、とんでもない無礼ものじゃないか。まったく、おまえが凍え死んじまうんじゃないかなんて、俺はほんとにどうかしてたよ」
押し問答は続いたが、少女はかなり面白がっていた。久し振りに人声を聞いたのが嬉しかったのかもしれない。誰かが自分を構ってくれるのが、この上なく愉快だった。散々堂々巡りの言い合いを繰り返した挙句、真面目に取り合うのが馬鹿らしくなったのか、男は降参だというように両手を挙げた。
「もう、勝手にしろ。だが俺は諦めたわけじゃないからな。機会さえあれば追い払う。他人の子供の面倒を見る義理はないんだから。まったくとんだ拾い物だ。さっきの俺は本当にどうかしてたぜ」
彼は杖を拾い、溜息をついて歩き出した。
男はカワウソと名乗った。彼の故郷では、動物や植物の名前を愛称として用いる習慣があるそうだ。それで彼は少女に名を尋ねたが、彼女は再び「わからない」としか答えなかった。男は返答に困ったように、しばらく黙りこくった。
「…俺はおまえがわからんよ」
彼はそう呟いた。
目的地はどこかという問いに対して、男はただ漠然と、西のほうだ、と言った。それで、少女は本当にこの男に振り落とされないように気をつけなければと決心を固めた。ふたりはどこまでも続くように思われる木立の中を、やわらかな浅い雪をさくさくと踏みながら歩いた。男は黙々と早足で歩いたので、少女は頬を真っ赤にして息を弾ませたが、彼女が何か言うと男は必ず短い返事をしたし、しばしば立ち止まって休憩させてくれた。
「目的地があるって素敵なことね。私、今までは途中で出会った鹿や栗鼠や鴉なんかの後をつけて歩いていたのよ。見つけてから、見失うまで。そしたらまた違うのを見つけて…その繰り返し。だけど私あなたに会えたから良かったわ」
「…俺がとんでもない悪人だったらどうするんだ。そんなふうに誰にでもひょいひょいついて行ってるんじゃ、先が思いやられるな」
後ろを歩く少女の明るい声に、カワウソは振り返りもせずに言った。
「誰にでもついていくわけじゃないわ」
彼女は相変わらず明るい調子で答えた。
その日の夕方、ふたりは森を抜けて、こぢんまりとした村に着いた。
「さて、ひさびさのあたたかい飯だ」
男は口元を歪めて笑った。
久しぶりにあたたかくやわらかな寝台で眠ったので、彼女はなかなか眼を覚ます気にならなかった。やっと身体を起こすと、こざっぱりとした宿の部屋の大きな窓から、既に高く昇った太陽の光が降り注いでいた。
彼女はあくびをし、伸びをして、それからやっと、カワウソが自分を置いて行っていやしないかと、急に目の覚める心地がした。大急ぎで着替えて部屋を飛び出し、隣の部屋の扉をがんがん叩く。返事がない。すっと胸の冷える感覚がした。すると通りかかった宿の使用人が、そちらのお客様なら外出なさったよと教えてくれたので、彼が続けて何か言おうとするのも聞かずに、少女は一目散に往来へ駆け出た。
小さな村は不自然なほど静かだった。誰もが眼を伏せ、足早に通り過ぎた。道端の商取引も、どこかひそめたような声で、まばらに行われるだけだ。彼女はその冷え冷えとした空気に思わず息をのんだ。焦燥と恐怖と疲労。昨夕この村に足を踏み入れた時から、この雰囲気は好きになれないと思っていたのだ。
ちょうどその時、捜していた男が二区画先の曲がり角から現れた。やはり長い杖を手に、彼はじっと俯いて、何かを探しているかのようだった。時折、建物の壁や生垣に注意深く手を触れながら、ゆっくりと、宿屋から遠ざかる方向へと歩いて行く。少女はいきおい、男の後をつけるかたちになった。しばらく様子を窺いながら尾行を続けると、カワウソは急に立ち止まった。
「これか」
ぼんやりしていると容易に見落としてしまうような、小さな荒れた小屋の前で、男が呟くのが聞こえた。彼は蔦を押し分けて中に入った。少女は爪先に弾みをつけて一思いにその前まで来ると、足音を立てずにそっと忍び込んだ。
中は薄暗く、かびと鉄と銀の臭いがした。死んだように静かで、とても寒かった。ぞっとするわ、と彼女は思った。そこには紛れもない、殺しの臭いがしたのである。
「だれか、来たね」
全身が凍り付いた。甲高くて甘ったるい、けれど恐ろしく冷たい、水銀のような毒のある声。彼女はその声が自分の喉に向かってひたと刃を向けてくるように思った。身体が小刻みに震えだして身動きもとれないでいると、別の声が答えた。
「おう、確かに来た。村の人間を喰っているのはおまえか」
昨日一日で散々聞いた、苛立ちの滲んだだるそうな、乾いた声だった。それでも、こんなにあたたかい、人間らしい声は聞いたことがないと少女には思われた。
「そうかもしれないわ。でも、あなたももうすぐ、殺された村人たちの仲間になるのじゃなくって?」
甘ったるい冷たい声が小屋の中に響いてくるばかりで、声の主は見えない。ことり、とカワウソのブーツが鳴った。彼も小屋を見まわしているらしかった。少女は小屋の隅の暗がりに、できうる限り縮こまっていた。
「ことによると、なるかもな」
そう言ったカワウソの声がいかにも投げやりで、少女は思わず息をのんだ。
「だが、俺は簡単には死なねえよ」
言った瞬間、まばゆい金色の光が稲妻のようにはしり、小屋がぐらぐらと頼りなく揺れた。物凄い悲鳴とうめき声が響き渡った。少女は邪悪なものが倒されたのかと喜んだ。
「あーら、あの馬鹿みたいに長い杖は、魔物退治の武器だったのね」
彼女は胸のうちで呟いた。
しかし一瞬間の後、彼女は自分がぬか喜びをしたことに気が付いた。カワウソが大きく舌打ちするのと同時に、小屋が突然銀色に光り出した。それは鏡だった。銀の鏡が、ぬらぬらと光る悪意のように、魔使いの男を取り囲んで、気味の悪いぎらぎらした光を放っている。
「おまえ、強いね。遊び甲斐がありそう」
さっきまでの甘さをかなぐり捨てた、毒々しい声が言う。小屋がとてつもなく大きくなったかのようだった。そそり立つ銀の鏡は小屋の天井まで覆い、少女は眩暈を起こして気を失いそうな気がした。どうしようもない身体の震えが戻ってきた。
と、銀の鏡の表面が、風の吹く湖面のように揺れ、像を結び始めた。それは小屋の中の像ではなかった。少女は眼を大きく見開いて、その鮮やかな映像に見入った…。
少年の顔が大きく映った。聡明そうな額に、やわらかい稲穂色の髪がかかっており、その下には優しくいたずらっぽくきらめく鳶色の瞳が笑っている。ひと目見れば、彼が神に愛された者であることがわかる、特別な人間だと感じる、そんなひとだ。
ふと様子が変わって、おどろおどろしい、黒々とした魔物に、少年が銀の刃を煌めかせて向かっていくところになった。血まみれで、口元から緑に光るどろどろしたものを垂らしているところにもなった。そういう切れ切れの場面が、いつも彼のすぐ隣にいるらしい人物の視点で、不明瞭で大音量の雑音とともに、ぎらぎら光る銀の鏡に、気味悪いほどはっきりと映っては消える。
少年はだんだん、瘦せ細っていくように見えた。視点人物の肩に頭をうずめて、泣いているような場面もあった。視点人物の手が、ぎゅっと、せつなげに、震える薄い背を抱きしめていた。それでも、少年ははれやかな瞳を煌めかせて笑った。
カワウソの動く音はもう、しなかった。
急に焦点があったように、場面がはっきりした。音がぶれなくなった。見渡す限りの雪だった。風はほとんどなかった。ほそぼそと雪片が舞う中で、荒く苦しい息遣いと嗚咽のような激しい声が、静かな銀世界に散らばった。乱れた足音とともに、視点が声のもとへと近づいていく。
少年のあのはれやかな様子は、もうなかった。腕や顔や脚についた深いひっかき傷から、だらだらと流れるものが、足元の雪を染めて静かに湯気を立てていた。彼は恐ろしい呻き声をあげながら、信じられないほど長く伸びた鉤爪で、自分の胸を引っ掻いた。深々と跡を残した傷は、どくどくと彼の命を吐き出している…。
彼は鳶色の瞳に涙を一杯にためて、こちらを振り向いた。息遣いの音が、心臓の鼓動が、うるさく響いた。
「僕を、殺してくれ」
彼ははっきりとそう言った。
「誰かを傷つける前に。僕はもう、…正気を保って…いられない…」
恐ろしい悲鳴と共に、彼は身体を折り曲げた。握った拳から血が滲んでいる。一瞬の間ののち、まばゆい金色の光が稲妻のように閃いて、どさりと重いものが崩れる音がした…
「…っだめっ!」
少女は叫び声をあげた。銀の鏡の奥から、鈍く嫌な色に光る刃が飛び出して、カワウソを突き刺しかけたからである。彼は呆然として、刃が腹を突き刺すのは避けたものの、握っていた杖を取り落とした。すかさず次の攻撃が来るので、少女は迷わず願いを叫んだ。
「この魔物に、もといた地獄へ永遠に帰ってほしい!」
ふっつりと何かが消える気配がした。瞬きひとつすると、何の変哲もない薄暗い小屋の床に座り込んでいた。彼女は自分の願いが聞き届けられたことを知った。
「…ったく、とんでもない子どもだな、おまえは」
カワウソは我が腕を抱きしめ、座り込んだまま言った。
「尾行して、盗み聞きして、魔物を倒しちまったわけだ」
「…ごめんなさい」
少女も小さくなって、ぼそぼそと呟いた。
「あの…怪我はない?」
遠慮がちに尋ねると、男は気を取り直したように少し笑って答えた。
「そりゃ、こっちがあんたにするべき質問だ」
そうして、彼は困ったように眉を寄せて、少女の小さな頭にそっと触れた。
「じゃあ、村長に、仕事は片付いたから小遣いをくれって言いに行かなくちゃな」
「あれは銀鏡魔だ。水銀の血を撒いて鏡をつくり、ひとに記憶の幻影を見せて気を散らせ、その隙に殺す。さっきのは動物に寄生する種類のものではなかったらしい。姿が見えなかったからな」
カワウソは独り言のように言った。ふたりは村長の屋敷を出て村を歩いていた。伝令の者が村人たちに、魔は倒されたから外出自粛令は解除するというお触れを出して回っているところだった。
「しかし銀鏡魔とは。てっきり絶滅したと思っていた。油断したな。おまえがいなかったら…」
彼は靴屋の前で足を止めた。
「さて、できるだけ上等なの選べ。でないと、俺がこの金飲んじまう」
少女が彼を見上げると、男は肩をすくめた。
「その靴窮屈なんだろう。歩き方でわかるさ。それに、足が霜焼けになってるだろ、そんなぺらぺらのブーツじゃ」
「なんで…」
「あたたかくてしっくりくるやつにしろよ。これはおまえの稼いだ金だ」
カワウソは簾のような髪の下でぎこちなく眼を細めた。少女の胸がぎゅっと苦しくなって、ついで喉が詰まって、眼が熱くなってきた。
「うん」
彼女はわざと明るい声で返事をして、棚にたくさん並んだ靴に向き直った。しかし真面目にブーツを見る気にはなれなかった。
彼女の今までの人生で、彼女の物語の主人公は彼女で、そのほかの人間も、彼女の世界の全部が、言うなれば壮大な舞台装置だった。家から町へ出れば、そこに暮らす人々がいて、いつも食料品を買う店には親切なおばさんがいて、日用品店には少し無愛想な店員がいて、しかし彼らは、少女が登場する舞台に一時的に出てきてひいていく、舞台装置とエキストラ。彼らには彼ら自身の生活があると、言われれば納得はする。けれど。
どうして今まで気が付かなかったのだろう。彼女は鉄板で殴られたような心持がした。
銀鏡魔の見せた幻影が忘れられなかった。いつも少年のそばにいた視点人物。一緒に笑って、一緒に泣いて、一緒に戦って、そうして、殺した。あの場でも、そうではないかと思ってはいた。そして今はっきりした。あれはカワウソの記憶だった。彼があれを見ていたときの、胸のはりさけるように悲痛な、無言の叫び。
彼のうしろに、そしてこの世界のすべての人々のうしろに、少女の知らない、長い長い物語があるのだと思うと、彼女は底なしの奈落を覗き込んだような、寒々とした恐怖を感じた。そうして彼女はふと思い至る、ずっと一緒にいて、彼女を深い愛情の中でまどろませてくれた天使のことをも、彼女は本当は、まったく知らないのではなかったか。
とてもやりきれない思いがした。彼女は自分がこの世界にひとりぼっちだと感じた。だれかに縋りつきたくなった。
つまり少女は、生まれてはじめて、「考え込んで」いたのだった。
「ところで、おまえはどうやって銀鏡魔を倒したんだ?」
村を出て街道を歩きながら、カワウソはふと尋ねた。少女は新しいブーツが石畳を叩く音に得意になっているところだった。
「お願いしたの」
「は?」
「だから、天使にお願いしたの」
「さっぱりわからん」
カワウソは苛立ちを通り越しておおいに呆れた様子だ。
「じゃあ、あなたはどうやって魔物を倒すの?」
「魔を吸い取る。で、次に魔を倒すときにそれをぶつける」
「さっぱりわからないわ」
「お願いよりはわかるさ」
「…ねえ、私あなたのこと知りたいの」
少女は急に男の手をとって言った。縋るようにぎゅっと握った。ひとりぼっちが怖かった。
「…銀鏡魔の幻影のことか」
彼は手を振りほどいて、素っ気なく言った。
「俺は、おもしろいお話じゃねえぞ」
「そんなこと思ってない」
少女が慌てて被せると、男は顔をしかめて空を睨んだ。
「…わかるよ。すまん」
それからふたりは黙って歩いた。
魔使いのカワウソはあちこちの村や町を訪れては魔物退治をして生計をたてていた。
「ただの日銭稼ぎだ」
彼は時折そう言って口元を歪めた。
男が銀鏡魔のときのように窮地に陥ることは二度となかった。実のところ、彼はとても強い魔使いだった。百戦錬磨の、とか、海千山千、とか人々は言った。
しかし、人々の魔使いを見る眼の冷たいことに、少女は間もなく気が付いた。左手に長い杖を携えた、草臥れた様子の痩身の男を見ると、人々は僅かに身を引いて俯き、彼が通り過ぎた途端に災いをよけるまじないを唱えた。
「みんな魔物は嫌いだからな」
カワウソは諦めたように言った。
「俺にもなんかついてると思ってるんだろ。まあ実際、魔を吸収しているわけだが」
ある城下町にて、ふたりがそばを通り過ぎた騎士たちがあからさまに魔除けの仕草をしたところだった。空はどんよりと灰色で、風がとても冷たかった。
「ついてないわよ。なにも」
少女はじっと騎士たちを見送って言った。
「あなたの身体の中で、魔が金色のエネルギーに変換されてるのがわかる」
カワウソは僅かに眼を見開いた。
「…魔喰らいという奴らもいてな」
彼は独り言のように言った。
「あいつらは生きるために魔を喰う。魔喰らいが受ける扱いに比べれば、こんなの屁でもないさ。ところで」
彼は急に言葉を切った。
「咬付魔だ」
少女は爪先立って彼の視線の先を見ようとしたが、カワウソのほうが速かった。彼はするりと人々の頭越しに杖を構えると、二、三軒先の露店を正確に撃ち抜く。魔物の断末魔の叫びが響き、広場が騒然となった。
「何も知らん奴らに一から説明せにゃならんから、人間に寄生する魔は面倒だ。逃げるが勝ちだな」
男が足早に立ち去るので、少女は慌てて走って後を追う。
「ねえあのひとを殺したの?」
少女は顔を真っ赤にして尋ねた。
「あ?いや、殺しはせん」
カワウソはどこか上の空だった。
「この街はなにかおかしい…あちこちから魔の臭いがするのに、まるで気配が霧にまかれたようだ…」
「どういうこと?それに、殺しはしないならじゃああのひとはどうなったの?なんでこんなに急いで逃げてるの?」
カワウソは見たこともないほど険しい表情で石畳を睨みつけている。
「いや、そうか…この街全体が…?だとしたら、とんでもないことになる…」
「ねえ…?」
少女が不安に駆られて尋ねると、彼は急に方向転換して足早に歩き始めた。
「確かめなければ。どうやら実態のほうが噂より酷かったらしい」
「ねえ何のこと?噂ってなに?どこへ行くの?」
少女は再び駆け足になって、必死について行きながら尋ねた。カワウソは振り返りもせず、背中一杯に苛立ちを滲ませて吐き捨てるように言った。
「俺が何か、おまえに説明責任を負うようなことをしたか?子供の質問にいちいち答える程俺は暇じゃない。そもそも、他人の子供の面倒まで見る義理はねえんだよ。だいたいおまえが勝手についてきたんじゃないか」
ことばは短刀のように投げつけられて、少女の胸に突き刺さった。彼女はぴたりと立ち止まった。男は振り返るそぶりもなく足早に歩き去った。少女ももう追わなかった。一歩たりとも、動く気にならなかった。
霧雨が降ってきた。氷の針を刺されているようだった。
泥水をはねられながら道端で泣いていた、あの時のように、パンの匂いのするあたたかい毛布でくるんでくれるひとは、もういない。
広場から町の人々が流れてきて、ひとり立ち尽くす少女を見つけた。騎士のひとりが、この少女が魔使いの男と一緒にいるのを見たと声高に叫ぶので、衛兵が呼ばれて彼女を城へと連れて行き始めた。少女はされるままになっていた。
きらびやかに着飾った男が玉座に座っていた。彼女はその城主らしい男の前に連れてこられてもまだ俯いたままだった。
「帝王様、こいつが服屋のギルバートを殺した男の連れです。悪魔の手下です」
「そうか、ご苦労だった。さがって良いぞ」
ゆったりとした、威厳のある声が答えた。少女は腕を縛った鎖の一端を持っている衛兵に無理やり顔をあげさせられ、城主の感じよさげに細められた赤い眼を見て総毛立った。
このひとは悪いひとだ。
玉座に座っている男は、若く麗しい見た目をしていた。白いなめらかな肌、人懐こそうで陽気な口元、優雅に組んだ脚はすらりと長い。巧妙に隠されていて、少女も眼を覗き込むまで気が付かなかった、この男の邪な企み。
黒の魔術師。
ふと記憶の底から浮上した、カワウソのことば。はじめて会ったときに、少女を家に帰そうとして出した名前だった。
《黒の魔術師だって、この頃不穏な動きをしているとか》
「街の城主が、帝王様とはねえ!」
彼女は心の中で呟いた。
「そうとも、私はこの世の帝王となる」
目の前の男が、美しい笑みをたたえて頷いた。少女は驚いて彼の赤い眼を覗き込んだ。その眼は何も感じない土の中の石のように冷たかった。
「私に隠しごとをしても無駄だよ。君は、魔使いがどこへ行ったか知っているかな?」
問われて、彼女は自分の心の中を無遠慮に踏み荒らされているような、胸糞悪い感覚を味わった。
「なるほど、こうやって心を読むわけね」
少女はそんな馬鹿みたいなことを考えた。ひたひたと感じる、玉座の男の冷酷さと絶大な力。銀鏡魔のときとは比べ物にならない。怖い。背中と脇から気持ちの悪い汗が滲み出ている。それでいて全身から血の気がひいて、震えが止まらない。考えがまとまらない。彼女は男の赤い眼だけをしっかりと睨み据えて、平衡感覚をなんとか保っていた。
「…ふむ、怯えているねえ。君がこれ程すばやく正確に私の正体を見抜くとは、誤算だったな。さすがは大魔使いのカワウソとだけはある。弟子をとったとは聞いていなかったが、君なら申し分なさそうだ」
男は愉快そうに言って、衛兵に向き直った。
「この小さなひとを客間へ。落ち着いたらまた話を聞くとしよう」
そうして少女はほとんど引きずられるようにして玉座の間を出た。ついに一言の口もきけないままだった。
客間にひとり取り残され、赤いびろうどの柔らかい肘掛椅子に殆ど埋もれるように座り込んで、彼女がまともにものを考えられるようになったのはしばらくあとだった。
「こんなとこにいて落ち着くわけないじゃない!」
彼女は小声で文句を言った。黒の魔術師のそばを離れられればどこだって素晴らしい楽園のように感ぜられるのも事実だったが、豪華すぎる調度品、一つしかない重厚な扉、おまけに部屋全体を魔術でふさがれており衛兵も見張っている明確な気配とあっては、落ち着けというほうが無理だ。
「さあ、これからどうするか考えなくちゃ」
彼女は自分に言い聞かせた。そうしないと、また底知れぬ恐怖の中へ引きずり込まれて腑抜けのようになってしまい、自分の首が落とされるのだって呆然と見ていかねないことになりそうな予感がしたのだ。
なるほど彼女には天使のくれたみっつの願いがあった。ひとつは使ったからあとふたつだ。黒の魔術師にいなくなってほしい、というのは、試す価値のありそうなことだった。そこでそう小さく祈りを口にしたが、何事も起こらないことをみるに、どうやらこの願いは通じないらしい。
「ほんっと、使えない願いだこと」
少女は勢いよく溜息を吐き出した。
「何なら叶えてくれるってのよ。この前カワウソと試したときだって」
少女は確かに天使をこの世で一番慕っていたが、みっつの願いについては、彼女の信頼は地に落ちていた。銀鏡魔の一件から数日後、焚火の準備をしながら、カワウソがふと面白半分といった感じで言った。
「おまえの言ってた天使にお願いっての、この世のすべての魔がいなくなりますように、って叶わないのか?」
そこで少女は眼を閉じ、一生懸命そう願ってみたが、駄目だった。
「まあ、叶ったら俺の仕事がなくなるからな」
カワウソはそう言って笑い飛ばしたが、少女に劣らずがっかりしていることは、彼女には手に取るようにわかった。彼にとっては自分が食っていく手段より世のひとの幸せのほうが大事なのだと、彼女は知っていたのだ。
「でもあなた、職には困らないんじゃない?いろんなことができるもの」
「それを器用貧乏と呼ぶんだよ」
彼はやれやれと首を振った。
「…あのひと、どこに行ったのかしら。早くあの化け物やっつけてくれるといいんだけど」
少女はびろうどの椅子から立ち上がり、広すぎる部屋をうろうろ歩き回りながら言った。
「それにしても、黒の魔術師は私の心を読んだ筈よね。私がカワウソの弟子なんかじゃなくて、どこに行ったかも知らないってこと、どうしてわからなかったのかしら。それとも、ほんとはそんなことどうでもいいのかな」
「あたりではずれだな」
突然真後ろから声がして、彼女の心臓が縮み上がるのに合わせて身体が飛び上がった。その一瞬後には、彼女は床に倒れてしまった。あまりに大きな驚きと、そして安堵のためである。
「びっ…くりした!一体どうしたの?あなたってカメレオンにもなれたの?」
左手に長い杖を持った、痩身の男だった。彼はにこりともせずに言った。
「随分陽気だな。この世で最も恐ろしい魔術師に捕まっているのに」
「ぶつぶつ言わないと、正気でいられないのよ」
少女が床から立ち上がるのを渋い顔で見下ろし、客間の様子をじろりと眺め渡して、カワウソはぼそりと呟く。
「わかってはいたが、やっぱりそういうことか」
魔使いの言葉と同時に、少女は自分の身体がぎゅるりと捻じれてかき消えていくような、気味の悪い感覚を味わった。そしてひとつ瞬きをすると、少女は再び玉座の間にいた。
「いらっしゃい、魔使いのカワウソ。お噂はかねがね伺っているよ」
ぞっとするほど美しい笑みをたたえた若い男が、ふたりの目の前に座っていた。空気が倍も重くなったようだった。全身の細胞が、今すぐこの場を離れろと言っている。
「美男に化けるのが好きなんだな」
カワウソはいつもの気だるい声で言った。
「この姿だとみんなが優しいんだよ。良いだろう?」
魔術師は首をかしげて両手を広げてみせた。魔使いは鼻にしわを寄せた。
「悪趣味だ」
「酷いや。酷いと言えば、君は僕の配下をことごとく殺してくれたねえ。忠実な、良い奴らだったのに」
「良い配下ってのは」
カワウソの声が険悪になった。
「町中にいた、ひとに憑りついた魔のことか?人殺しに間違われるのは慣れているが、あれだけいるとさすがにもみ消しに骨が折れたぜ。おまえみたいな畜生には聞いたって無駄だろうが一応聞いてやる。これだけ大きい城下町に人食い魔を集めたりして、おまえはひとの命をなんだと思っているんだ」
「この世で最も尊いものだよ」
魔術師はにっこりと微笑んだ。
「それに、あいつらには囚人を喰わせていたんだよ。…しかし、昔同じことを誰かに言われた気がするなあ。うん、そうだ、赤毛の女だったよ。ひとの命をなんだと思っているんだ…で、そのあと僕の首を吹っ飛ばしたんだ。酷いよねえ。その台詞、そっくり返してやりたいけど、もう死んだかな」
「それは」
カワウソは少し胸を張った。
「俺の師匠だ。あのひとはおまえを封じ、これまでにない平和な時代をつくった。しかし黒の魔術師はきっと戻ってくると、最後まで言っていた」
「その通りだよ。僕は諦めないからね」
どちらが先に動いたのか、少女には皆目わからなかった。ただまばゆい稲妻のような閃光がはしり、訳もわからぬまま眼を開けると、彼女は魔術師の足元に這いつくばっており、魔使いは床に走った亀裂の向こう側で杖を構えている。
「なんだよ話の途中だったのに…」
魔術師が至極残念そうに言うと同時に、再び金の光の柱が彼めがけて撃ち込まれる。彼は空中から黒い盾を出して防ぐ。すかさず毒々しい赤い閃光が魔使いへと飛び、カワウソは横っ飛びにかわしざま、一息に魔術師に迫り、杖を振り上げる。喉元に迫った仕込み刃を、魔術師は空気の膜ではじいた…。
「おいおい、最後まで話を聞けよ…おっと…」
魔術師は猛然と攻める魔使いに、赤い弾丸の嵐を浴びせた。カワウソは大部分を杖ではじいたが、よけきれずによろめく。
「ほうら、話を聞かないからこうなるんだぜ。おっと動くな、でないとこの子が痛い目に遭う」
少女は首根っこを掴まれて持ち上げられるような、奇妙な感覚を味わった。気が付けば何もない空中に浮いている。悲鳴をあげようとしたが声が出ない。ぞっとした。
「この子はもう、僕のものだ」
魔術師の甘い勝ち誇った声が、どこか遠くで聞こえる。自分の身体が自分の所有を離れていく。いや、本当はずっと前から、彼女は魔術師の術にかかっていたのだ。回らない頭に絶望感がたゆたう。いやだわ、もうおうちにかえれないのかしら。けれどそれも、何も考えることのない、漠然とした幸福感に飲み込まれていく…。
カワウソの渋い顔が霞んで見える。わたしいつもこのひとをおこらせているきがする。わからないけど、あやまるからもうおいていかないで。
「…服従の魔術。これを得るのに、おまえは何を売った?魂か」
カワウソの怒りに震える言葉に、魔術師は両腕を広げて笑った。
「僕の魂なんて何でもないよ、この世のひとたちみんなの命に比べればね。僕は平和な世の中の為に魂を売った英雄だよ」
「平和が聞いて呆れる」
「酷いなあ」
彼はすらりと長い指を振った。
「人々は自分がどうあるべきか、わからないんだ。一生不安でたまらない。だから小さな集団になって敵対しあって戦うのさ。僕はみんなを導いてあげるんだ。みんな、何も考えなくていいんだよ!何もせず、ただ幸せな気持ちだけを味わって、争うことも、殺すこともない。何もかも僕の思う通りにしていれば、さあ、なんて素敵な、平和な世界ができるだろう!」
「糞みてえな阿呆話だな。吐き気がする」
カワウソはこの上ないほどの冷ややかな侮蔑を込めて吐き捨てた。
「自惚れと思い上がりで膨らんだ、その頭切り落として永久凍土に突っ込んで冷やしてこい。まったくおまえみたいな思い上がりの考えそうなことだぜ、世界征服も、たかが魔使いひとり倒すためにこんな馬鹿みたいなことやってんのも」
「でもあんたは強いだろう?」
急に魔術師の眼が冷たく光った。周りのすべてが水中にいるようにぼやけて感じられる少女にも、その眼の冷たさだけは鮮烈に見えた。あら、なにかしら。やなかんじ。
「…なあ、アイハル」
アイハル、と彼が口にした途端、魔使いは固まった。眼を大きく見開いて、あらぬ方向を凝視している。魔術師はにんまりと口角を持ち上げた。
「君の名前を当てるのに、思ったより長くかかったよ。でも、これで僕の勝ちだね。君は一生僕の下僕だ」
からん、と、魔使いの手から杖が落ちた。玉座の間に、魔術師の高笑いが響く。
少女の耳の奥で、何かが聞こえてくる。音はだんだん大きくなっていく。
「…い、…おい!」
なに、かしら…まえもこんなこと、あったわよね…
「おい!生きてるなら返事しろ!」
途端に少女の中で何かがめざめた。彼女は再び、周りのものをはっきりと見ることができた。床や壁には縦横に亀裂がはしり、調度品は悉く倒れたりばらばらになったりした玉座の間。自分の隣に魔術師。目の前には血を流したまま取り落とした杖を拾おうともしない魔使い。
少女の後ろで、乾いた声が囁きかける。
「おまえには、術なんてかかってない。おまえの名前を、奴は知らない。これはただの催眠術だ。起きろ。そして天使に願って逃げろ。南のほうの、タルカン村にいる俺の仲間に助けを求めて、おまえはもう、家へ帰れ」
彼女はぎゅっと拳を握った。眼に涙が湧いてきた。軋む喉をこじ開けて大きく息を吸うと、腹の底が力強くあたたかくなって、目の前が急に金色の光で照らされるような気がした。今彼女は、天使の、そして神の息吹を全身に感じていた。
自分の成功に酔いしれ、ひとり興奮して喋っている魔術師には気づかれずに、彼女はそっと床に降り立った。カワウソと魔術師の間に立つと、少女は魔使いの杖を拾って魔術師の胸にまっすぐ突きつけた。
「おや、もう気が付いたのかい、おちびさ…」
「お黙りなさい」
少女は泣いていた。憐みの涙だった。
「天使の名にかけて、私は願う。黒の魔術師、おまえが救われますように」
魔術師は口を開きかけたが、何か言う前に驚きに眼を見開いた。彼の手が、足が、胸が、錆が剥がれるようにぼろぼろと崩れ落ちていく。全身が急速に黒い煤になって零れる。もの言いたげに少女を指した指も、華美な衣装も、美しい顔も、砂の城のように消えていく。
「あなたがどんな物語を持っていて、何を考えて、何をなしてきたのか、私は何も知らない。何も知らないし、どうせひとのことなんて全部は知りようがないんだから、私はそういうもの全部うっちゃって、ただ、あなたが救われてほしいと、願う」
最後にあがくように、黒い砂は醜く年老いた猿のような形を作って、消え去った。
「…あれが奴の本当の姿だったんだよ」
後ろから静かな声が言った。魔使いは立ち上がって、少女の隣に立った。彼女は年老いた魔術師の消えたあとをじっと眺めていた。
「さて、これからが面倒だな」
すべてが終わったのは三日後の昼過ぎだった。街の役人にすべての事情を話し、城の地下にあった魔を召喚する魔法陣を破壊したり(おそらくここから魔を呼び出して放っていたんだろう。これなら魔で世界を踏みつぶせるほどの軍勢が作れる)魔に憑りつかれていたひとたちの無事を証明して殺人の疑いを晴らしたり(だから言っただろうが、ちょっとの間意識が飛んで、そのあと一週間くらい腑抜けになるだけだって。俺は宿主を殺さずに魔を退治する方法を編み出すのに三年もかけたんだぞ)、取りこぼした魔を探し出して退治したり(服従の術が魔にも効くか試したかったんだろ。それで、ひとに憑りつかせてひとの中で生活させ、食欲を抑えられるかどうか実験した。胸糞悪い話だな)、ふたりは目の回るほど忙しかった。街の人々と関わるうちに、カワウソの正直で優しいことが人々に伝わり、魔使いを敬遠する者は次第に減っていった。人々は、魔術師がいかに巧妙に城を乗っ取ったか、次の城主はどうやって選ぶかを語って聞かせた。彼が街を出て旅を続けると言ったとき、ではいつかまた寄ってくれと、口々に依頼した。
「また『西のほう』へ行くの?」
少女が尋ねると、カワウソは少しきまり悪そうに眉をひそめてこう言った。
「ああ、墓参りだ」
「私も行ってもいいの?」
彼女が少し意地悪く畳みかけると、男は急にかしこまって頭を下げた。
「頼む。そこまででいいから、一緒に来てくれないか」
少女は少なからず驚いた。
「どうしてあなたが頼むの」
「おまえはいつか必ず、天使の娘と呼ばれ、世界中の哀れな者たちに慕われるだろう。おまえはおまえの翼でどこへでも飛んでゆけるんだ」
少女はしばらく男を見つめていたが、やがて笑い出した。
「勝手についてきたんだから、帰る時も勝手に帰っちゃうわよ。だけど私、まだ当分はあなたとの旅をやめる気にならないのよ」
街の教会には、魔に喰われた囚人たちのための墓ができていた。ふたりはそこに手をあわせてから、人々に見送られて街を出た。空気には微かに、春の匂いが混じってきている。
「いくつかわからないことがあるの」
少女が歩きながら切り出した。
「魔術師の城であなたが言った、あたりではずれって、どういうこと?」
男はゆったりと足を運びながら答える。
「時々おまえはひとの心が読めるのかと思うことがあるが、悪人の心理にはさっぱり通じていないらしいな。あいつは確かにおまえの心が読めなかった。神の加護が強い心には、あいつの邪悪な魔術は深入りできなかったんだ。それでも、あいつはそんなことはどうでもよかった。おまえを使って、俺を釣り込めばいいと考えたんだろう。読めないと認めることも癪だっただろうしな」
「私を使って釣り込む?」
少女が首を傾げたので、カワウソはやれやれと首を振る。
「人質だよ。悪人が使う常套手段だ。それにご丁寧にも、おまえのいた部屋だけ、外からの侵入を防ぐ魔術がかかっていなかった。俺が着いたらもろともに自分のところへ連れてきて、力自慢がしたかったんだろう」
「ふうん。ねえ、じゃあ、私が催眠術にかかってるだけだって、なんでわかったの?」
少女は魔術師の考えを理解するのを諦めて、話題を変えた。
「魔使いとか魔術師とか、そういうろくでもない商売の核は、いかに自分の本質を隠したまま、相手の本性を握るかなんだ。人間の魂についた識別符、俺の師匠は魂の名前と呼んでいたが、それを知り、正しい方法で呼びかければ、そいつの運命はこっちのものだ。で、俺も魔使いの端くれだからな、大抵の人間の名前は、ひと目見ればわかる(まあ俺たちはむやみに呼んだりしないから安心しろ)。でもおまえの名前はいくら一緒にいてもわからなかった。これは本当に名前がないんだなと、俺は思った。ことによると、天使に願い事ができるってのも、本当かもしれん、とな。だから、魔術師がおまえに、実効力のある術をかけられるはずがなかったんだ」
「で、私の記憶を揺すぶって起こして、俺を置いて逃げろと、そう指示したわけ?」
「逃げればよかったんだよ。そもそも、俺が城に来る前にさ、天使に頼んで」
カワウソはこころなしか怒気をはらんだ声で言った。
「なぜだか、そんな考えはちっとも浮かばなかったわ。ところで」
少女は踵を弾ませて街道を歩きながら男を見上げた。
「お墓参りって、誰のお墓?」
「俺の、…」
カワウソは言いかけて、言葉を探すように遠い眼をした。
「…ほら、おまえも見たことあるだろう、銀鏡魔の幻影で。魔喰らいだったんだ。生活活動のエネルギーを魔を喰って得る、天性の掃除屋だよ」
「ええ覚えてるわ」
少女は注意深く返事をした。
「魔喰らいに廿歳なしと言うが、あいつも、体内に魔が溜まって、自分が魔になって死んだ。まだ十七だったよ」
ふたりは黙って歩いた。
大陸の西の果てだった。大きな水が、のたりのたりと呼吸していた。なぜかとても懐かしい気持ちになって、少女は赤ん坊がおくるみの中でするように、すうっと眼を閉じて塩辛い風を吸い込んだ。
「海だ」
カワウソはそう言って、少し口元を歪めた。
眼下に海を臨む、崖の上の森の端に、白い大理石がぽつんと置いてあった。これが魔喰らいの墓らしい。石の表面は風にさらされて滑らかになっていた。それがちょうど、鏡の中に見たあの少年の、優しい晴れやかな笑顔に重なった。ふたりは跪いて手を合わせた。
「変な奴だよな。こんな人気のない吹きっさらしのとこに埋めてくれってせがむなんて」
カワウソはぼそぼそ呟いた。
「名前は何というの?」
少女はそっと尋ねた。
「死者の名前は、死んで七年経つまで呼んじゃいけないんだ。この地方の迷信だがな。あいつが戻ってくるかもしれないから」
「戻って来やしないわ」
少女は優しく言った。
「だって、あなたは大丈夫だって、知っているから」
ふと、カワウソの眼が曇ったように見えた。彼は深呼吸して、言った。
「クレオヴィネ」
さわさわと風が渡っていった。広大な海は、変わらぬリズムで時を呑み、生み出していた。
少女はカワウソに、短い身の上話を聞かせた。
「そりゃ…おまえ、難儀だったな」
男はそう言ってから、少し顔をしかめた。
「いや、俺が断定するのは失礼か。おまえはいつでも楽しそうで良い」
言いながら、彼はぎこちなく少女の頭を撫でた。
「ところで、願いはあとひとつ残っているんじゃないか」
「うーん、そのことなんだけど」
少女はにっこり笑った。
「もう、使い切っちゃったように思うの。はじめから叶っていたんだわ」
彼女は澄んだ青い空に向かって微笑みかけた。
「ねえ、あなた、私が最初の朝に会いたいって言ったときから、ずっとそばにいたんでしょ?」
少女の言葉はそっと風にのった。
「私は、ここにおりますよ」
天使の懐かしい声が、海の音に溶け合うように響いた。
完

※お詫び
魔使いは魔法使いとは違います。魔術師とか魔喰らいとかややこしい名前ばかりですみません。
ここまで読んでくださった優しいあなたが、素晴らしい聖夜を過ごされますように
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
